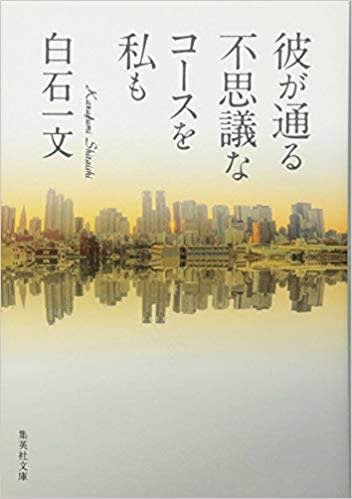
発達障害や学習障害、不適応障害などは
子どもの場合について語られることが多いけど
子どもはいつか大人になる。
つまりさまざまな障害を抱えたまま
親になる場合もあるってことだ。
本人が自覚しているならまだいいのだが、
そういう分野の研究が進んできたのは割と最近。
気づかないまま、結果虐待に陥る例もありそうだ。
そんなことを考えさせてくれる作品。
「学習障害だの、アスペルガーだのとラベリングしたって
認知に偏りがある子どもたちのための
具体的な教育プログラムを用意できなければ
単なるレッテル貼りでしかないし、子ども本人だって
『どうせ自分は障害者なんだから、できないのが当たり前なんだ』
とさっさと諦めるだけの話だよ。
現状では、僕は安易な診断は百害あって一利なしだと思ってる。
大切なことは、従来の学校教育に馴染めずに困っている
たくさんの子どもたちに、彼らひとりひとりに適した教育を
施すことなんだからね」
その通り、子どもたちは個性とみなして対応しなければ。
逆に大人は親としての自分を客観的に知らなければならないだろう。
「いまは学習障害だのなんだのとレッテルだけ貼られて
落ちこぼれ扱いを受けている子どもたちがたくさんいるけれど、
実は彼らにはものすごい可能性があると僕は思っている。
小さい頃から何でもそつなくこなして、
一流高校、名門大学へ進む子どもたちよりも
むしろ発達に偏りがある彼らの方によほど未来を感じるくらいなんだ。
この国は、そう言う可能性に満ちた子どもたちを、
旧態依然とした教育システムのせいでどんどん駄目にしてしまっている。
もうこれ以上、そんなことをつづけさせるわけにはいかないんだよ」
ある意味これも同感。
「出る杭」は平均的な人間からは生まれにくい。
そして本書で一番納得したのは以下のセリフ。
「自分が大事で大事でたまらないって思えれば、その子どもは絶対死なない。
それはそうだろう。
世界で一番大切なものを失いたいって思う人間はいないからね。
だからね、僕は、どんなことがあっても
子どもたちが自分のことを嫌いにならないように、
すごくすごく好きでいられるようにしてあげたいんだ。
そのためにどうすればいいか、そればっかり毎日考えてる。
そうするとね、いまの教育がどれほそ間違っているか
本当によく見えてくるんだよ。
誰かを負かすことでしか自信をつけられないような
こういう馬鹿馬鹿しい教育をやりつづけた結果、
負けた方だけでなくてね、買った方まで、
自分のことが好きでいられなくなってる」
自己肯定を失った時、ひとは命を軽んじる。
自分だけではなく、他人のことも。
小説を読んだのは本当に久しぶり。
得心するセリフは多かったけれど、ストーリー全体は不思議だった。
最後近くからはずいぶん走ったなぁ。
終わり方もイマイチ納得できないというか、よくわからなかった。
なんか狐につままれたような・・・
ところでこの著者は女性読者のファンが多いよね。
「彼が通る不思議なコースを私も」白石一文:著 集英社文庫















