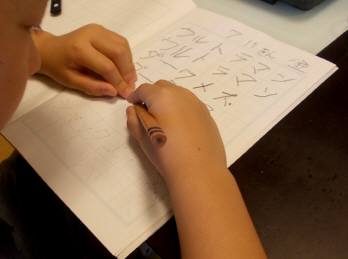7月24日(金)
連休明け、いよいよ夏本番という時に、東京の義兄の訃報が舞い込み、あわてて逗子に帰って来ました。
そんなわけで、「夏休み(2)」の記事のアップが少々遅れましたが、今回は21日の海の日の話題です。
兵庫の高校野球、今年は、「市立の明石商業に好投手あり」という声を耳にして、一度球場に足を運びました。
そんなに上背はありませんが、ストレートにキレがあり、地元のチームということもあって、この日も球場へ行こうかなと家を出ました。
駅に向かって歩いていると、海岸から太鼓の音や喚声が響いて来るので、少し潮風でも浴びてみようかと改札に入らず、海岸へ出る歩道橋へ向かいました。
この日は、花火大会歩道橋事故(2001年)の
命日でした

しばし頭を垂れて、海岸へ下りると、なんとまあ、この暑いのに鉄人レースをやっていました。
トライアスロンから自転車を除いた、スイミングとランニングのレースで、その名を「アクアスロン」と言います。
スイム200m、ラン3㎞の
中学生の部の表彰式

一般の部(スイム1㎞、ラン10㎞)の
スタート地点

いよいよスタート

250m先のブイで折り返します

暑中泳カモメが客の明石浦 弁人
戻ってきて、もう一往復

スイムを終えて
走り出したかと思うと、

そう、シューズを履かないと
走れません

2.5キロ先に折り返しがあって、
ここも都合二往復です

明石駅の南の、旧たこフェリーの港とその手前の市役所の間に折り返しがあるようです。ここから明石駅までは時々歩きますが、その4倍近くを走るなんて、今の私には考えられません。
炎天下猛者を励ます光る風 弁人
お疲れさまでした

これより何倍も過酷な「トライアスロン」も、やっぱり、こんな暑い時期にやるのでしょうか。
ところで、南西の島で遊んでいたKAZU君、夕方伊丹空港に帰ってくるというので、このあとお迎えに行きました。
やっぱり、海のきれいなこと、
あきれるほどですね

足もとにクマノミもいた夏休み 孫弁人
連休明け、いよいよ夏本番という時に、東京の義兄の訃報が舞い込み、あわてて逗子に帰って来ました。
そんなわけで、「夏休み(2)」の記事のアップが少々遅れましたが、今回は21日の海の日の話題です。
兵庫の高校野球、今年は、「市立の明石商業に好投手あり」という声を耳にして、一度球場に足を運びました。
そんなに上背はありませんが、ストレートにキレがあり、地元のチームということもあって、この日も球場へ行こうかなと家を出ました。
駅に向かって歩いていると、海岸から太鼓の音や喚声が響いて来るので、少し潮風でも浴びてみようかと改札に入らず、海岸へ出る歩道橋へ向かいました。
この日は、花火大会歩道橋事故(2001年)の
命日でした

しばし頭を垂れて、海岸へ下りると、なんとまあ、この暑いのに鉄人レースをやっていました。
トライアスロンから自転車を除いた、スイミングとランニングのレースで、その名を「アクアスロン」と言います。
スイム200m、ラン3㎞の
中学生の部の表彰式

一般の部(スイム1㎞、ラン10㎞)の
スタート地点

いよいよスタート

250m先のブイで折り返します

暑中泳カモメが客の明石浦 弁人
戻ってきて、もう一往復

スイムを終えて
走り出したかと思うと、

そう、シューズを履かないと
走れません

2.5キロ先に折り返しがあって、
ここも都合二往復です

明石駅の南の、旧たこフェリーの港とその手前の市役所の間に折り返しがあるようです。ここから明石駅までは時々歩きますが、その4倍近くを走るなんて、今の私には考えられません。
炎天下猛者を励ます光る風 弁人
お疲れさまでした

これより何倍も過酷な「トライアスロン」も、やっぱり、こんな暑い時期にやるのでしょうか。
ところで、南西の島で遊んでいたKAZU君、夕方伊丹空港に帰ってくるというので、このあとお迎えに行きました。
やっぱり、海のきれいなこと、
あきれるほどですね

足もとにクマノミもいた夏休み 孫弁人