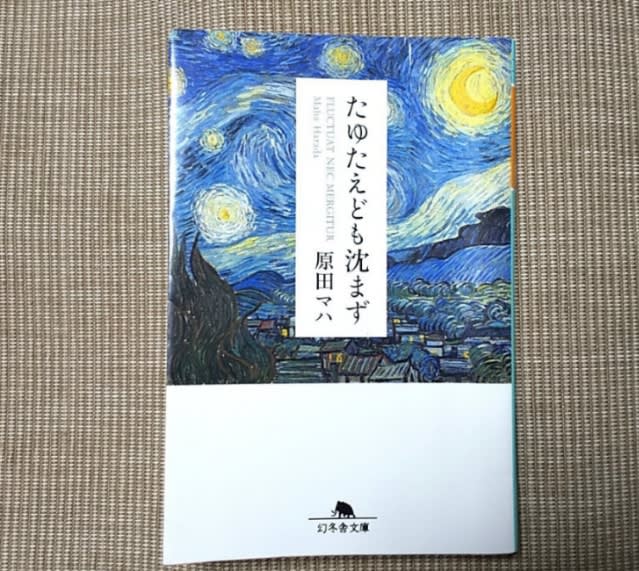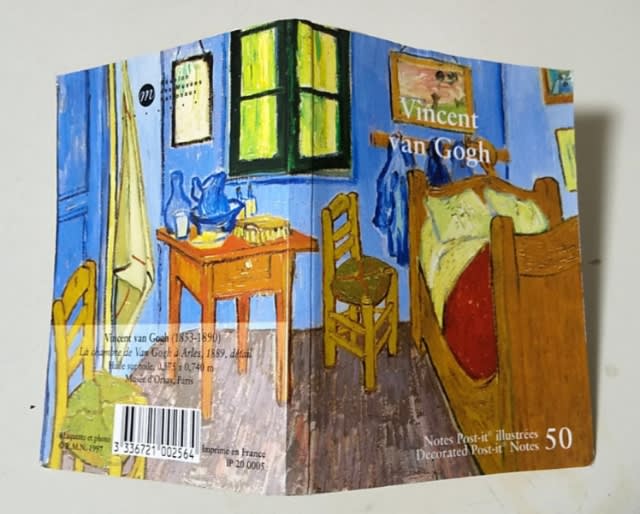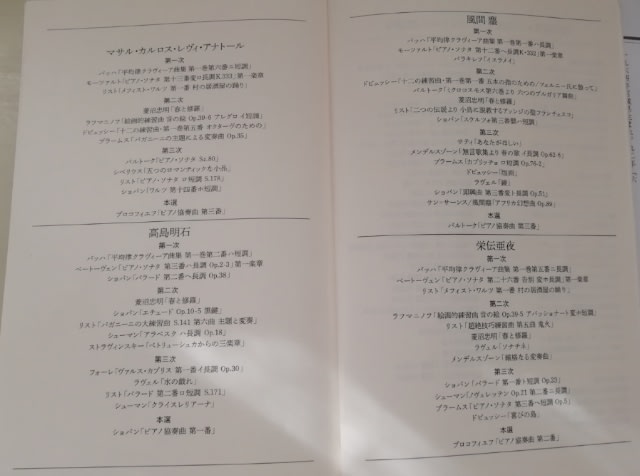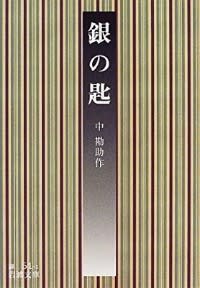2m以上もある皇帝ダリアは、茎の先端にびっしり蕾をつけるので頭が重たそう!花に気づかない人もいます。次々に開花して花は12月終わりまで咲き続けます。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
さて「ミチクサ先生」は78回を迎えどんどん面白くなってきました。
明治の新しい世の中は、『十年ひと昔というが、日本の歴史の中で、これほど目に見えて、街、市の風景、人々の姿が変わったのは初めてだった』というほどに目まぐるしく変わりました。
そのところを作者は市民の目で分かりやすく書いているので、政治史が先行しがちな明治の初期がとても身近に感じられます。明治の市井の生活、苦労のなかにもイキイキした息づかいが見えます。
政府の最重要課題、不平等条約の改正を念頭にキリスト教禁止の高札を下ろしたこと、太陰暦を採用したこととそれによる市民の混乱ぶりがあります。
日本でのキリスト教徒の弾圧は海外では野蛮人と非難され、また国際的な交渉の場では元号・陰暦では話が進まないという理由がありました。
武家社会が崩壊し生活に困窮した士族の反乱は西南の役に発展し、圧倒的な政府軍の勝利は軍備拡張と富国強兵の名実を与えてしまいました。
その間にさまざまな土地で、後の日本を代表する優秀な子供たちはきっちりと成長していました。
正岡子規。夏目漱石と同じ1867年、松山藩士の家に生まれた子規は6歳で父を亡くし、漢学者の祖父・大原観山から漢学を学び、祐筆だった叔父から書を習うという英才教育を受けます。松山中学に入学するも東京への憧れは絶ちがたく、中退して上京すると、持ち前の能力で直ぐ予備門に合格します。予備門は東京大学に入るための修業校なのです。旧藩主・久松家の給付生として奨学金を得て憧れの学生生活を始めました。
『皆が子規という若者の人柄に惚れ、何かにつけて子規のもとに集まった』と言われるほどの人物だったようです。
森鴎外。津和野藩の典医の家に生まれた鴎外は、6歳で論語・孟子を、7歳で四書を、8歳でオランダ語を学び『15歳以上の才能』と周囲を驚かせます。
西洋医学の重要性を考えた父は、10歳の鴎外を連れて上京し、鴎外は医学校本科に進みました。
夏目漱石。この小説の主人公・漱石は塩原家の養子になりますが、養父母不仲の冷たい空気の中で、蔵の中で掛け軸を見る密かな楽しみを見つけます。この経験は後の漱石の執筆に影響を与えます。
教育に熱心な実家の兄・大介はいち早く漱石の才能を見抜いて、学問の重要性を説きアドバイスしサポートしていきます。
漱石は20歳になる以前にさまざまな学校に入り「ミチクサ」しますが、これで色々な能力がついていきました。「夏目は英語ができる」と噂になるほどの力をつけて予備門の試験を一番で合格したのです。
優秀な若者が集まった予備門ではたくさんの出会いがありました。
漱石と子規の出会いは予備門の中です。漱石の寄席通いは実家の家風として子供の頃から。これが後の文学に大いに影響を与えました。
子規も、上方文化がいち早く入ってくる松山の風土でいろんなことに好奇心と興味を持ち、寄席にも馴染んでいました。漱石と寄席繋がりので出合いです。
子規の雑記帳には『夏目金之助君、秀才の人なり、その上、こころねやさしく、余のことを常に思ってくれる人である。余にとって金之助くんは、畏友なり』と記されています。お互いに相手の才能に敬意を払いながら、人間的にも評価していました。
子規はこの頃、日本に入ってきた野球に熱中しチームを作り毎日のようにグラウンドに出ていました。
予備門では同郷の親友秋山真之もいましたが、彼は後に経済事情で学問を断念し海軍兵学校へ入ります。
もうひとつの出合いは、漱石をして天下の秀才と言わしめた金沢出身の米山保三郎です。
漱石が建築科に進もうとしていたとき、米山は「君が言うような美的建築は今の我が国の技術では不可能だ。まったくもって無駄だ。それより文学をやりたまえ。文学なら何百年後、何千年後にも伝えられる大作もできる。それが新しい国家のためというものだ」という言葉に納得し深く感じるところがあり英文学に進むことになります。もし彼と出会わなかったら日本の文学界はかなり違っていたかも知れません。
子規は哲学科の米山の才能に恐れをなして、自分には無理だと哲学科に進むことを止めたというほどです。
今日から、明治論壇の雄・陸羯南の登場です。津軽の貧乏藩士の子で熱血漢。子規の叔父加藤恒忠(拓川)が羯南と親友の間柄で、子規の東京での後見人を頼んでいたのです。
やはり藩士の子弟は能力と横の繋がりに恵まれていた、根っからの庶民とは違うのだと実感しました。
連載が一年続くとして、まだまだ盛り上がってきそうです。「明治は遠くなりにけり」をぐいっと引っ張ってきた伊集院さん、分かりやすいストーリーを毎朝楽しみにしています。