


27日死去した三笠宮崇仁氏の葬儀・埋葬が4日行われました。「葬儀は宮家の私的行事として神道形式で」(10月29日付中国新聞=共同)行われました。
ところがその経費は、まるまる国費から支出されるのです。
「葬儀や墓所の建設に必要な費用は約2億8900万円に上る見込みとなり、うち約2億900万円が2016年度の国の予備費から支出されることが、1日の閣議で決まった。残りは16年度の宮内庁の予算や、来年度の予算要求でカバーする」(2日付中国新聞=共同)
皇室・皇族には毎年「私的生活」用の経費が税金から支出されています。「私的行事」である葬儀・埋葬の費用は当然その中から支払われるべきで、別途国費から出す道理はありません。
しかも、「神道形式」の葬儀はれっきとした宗教活動です。特定の宗教活動に国費を支出することが憲法第20条の「政教分離」(「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」)に反することは明白です。「大臣の玉ぐし料」の比ではありません。
皇室・皇族の葬儀に対する国費支出は今回だけではありません。
たとえば、三笠宮寛仁氏の葬儀(2012年6月18日)の際も、「宗教色が強い皇室行事だが、過去の葬儀や墓所建設には国費が使われた」(2012年6月7日付中国新聞=共同)と報じられたように、これは「慣例」化していることなのです。
政府が国費支出を閣議決定した言い分は、「国家的な弔意の対象となるとして、国費が充てられる」(同中国新聞=共同)というだけです。「国家的な弔意の対象」とは?そのようなあいまいな言葉で憲法違反を正当化することはできません。
問題は、この憲法違反行為を問題にし追及する政党、メディア、「学者・識者」が皆無だということです(新聞・テレビ報道の限りで)。
政府・自民党による憲法蹂躙は「9条」だけではありません。憲法上重大な疑義のある「私的行事としての神道形式の葬儀」への国費支出を、なぜ「革新政党」や「憲法学者」は追及しないのでしょうか。
先に新嘗祭という宮中祭祀に地方自治体から公費が支出されている問題を取り上げましたが(1日)、憲法に反することでも「天皇・皇族」に関することなら不問にされまかり通っているのが「日本社会」の実態です。
この問題も含め、「今日の天皇制」を抜本的に再検討することが求められています。
余談を2つ。
①4日TPP法案が強行採決された衆院の委員会で、民進党の議員が委員長席のどさくさの中で口走りました。「三笠宮さまのご葬儀の日になぜ…」。
②4日夕方のテレビ朝日「Jチャンネル」で、三笠宮の葬儀のニュースが終わった瞬間、男女2人のキャスターがともに頭を下げました。おそらく本人の意思ではなく局の指示でしょう。
「草の根天皇制(天皇教)」の根強さを見る思いです。



天皇が行う宮中祭祀の中で、最も重要とされるのが新嘗祭(にいなめさい。11月23日)ですが、それはたんに宮中での行事ではなく、全国の都道府県を巻き込んだものであり、しかもその宗教行事に公費が支出されていることが分かりました。
RCC中国放送のニュース(10月28日)が報じたもので、政教分離を定めた憲法(第20条)にも抵触するものです。
RCCニュースによれば(写真はすべて同ニュースより)、新嘗祭に向けて全国の都道府県で、指定された水田で収穫された新米が、「献上米」として天皇に納められます。その儀式(献納式)が行われる予定だったのが、今年は昨日(31日)でした。
広島県は「献上米」を納める費用の一部を公費から支出しています。県が負担しているのは、ホテルから皇居までのハイヤー代と、「献上米」を入れる絹製の巾着袋代(2万1000円)、それを入れる桐の箱代(1万4000円=使いまわし、写真右)です。
問題は金額ではありません。神道の宗教活動に公費が支出されている事実です。これははたして広島県だけでしょうか。「献上米」の存在自体あまり知られていませんが、それに都道府県がどうかかわっているのか、公費は支出されているのか、全国の都道府県で明らかにされる必要があります。
新嘗祭とは、天皇がその年の新穀を「神」に供え行事です。その起源は、「皇祖神・天照大御神が地上に降臨する皇孫(こうそん)に、斎庭(ゆにわ)の稲穂を授けたことにさかのぼる。神々が住まう高天原(たかまがはら)で育てられていた稲穂が、皇孫により初めて地上・葦原中つ国にもたらされたことで、わが国の農業が始まった。新嘗祭は、この恩恵に対し、皇孫にあたる天皇自らが、五穀豊穣の感謝を神々に奉告する祭り」(茂木貞純監修『神道としきたり事典』PHP研究所)とされています。
それは「神社神道の教祖としての天皇陛下」(菅田正昭氏『神道のすべて』日本文芸社)の姿を示すものです。「歴代の天皇は大嘗祭(だいじょうさい。天皇が即位後初めて行う新嘗祭ー引用者)のときニニギ(天照大神から米作りを命じられたとされる神・皇孫ー引用者)と同魂同体となられるので、ニニギである天皇は毎年、実際に米作りをして天照大神への復命、ご報告をされなければならない」(菅田氏、同)というわけです。
テレビや新聞にときどき天皇が田植えや稲刈りをする姿が出てきますが、あれは趣味ではなく農業振興を願うものでもなく、天照大神に従う天皇の重要な宗教活動なのです。
新嘗祭当日(11月23日)、天皇は夕方から翌24日午前1時ごろまで、神主の装束で、新穀を「神」に供えるとともに自ら食してこの行事を取り仕切ります(写真左)。
明仁天皇は即位以降、820件(6月末現在、宮内庁まとめ)の宮中祭祀を行っていますが、毎年の新嘗祭は「宮中恒例祭祀で最も重要な祭典」(三橋健氏『神道の本』西東社)です。
新嘗祭はじめ宮中祭祀は明白な神道行事であり、さすがに政府・宮内庁もこれを天皇の「公的行為」と言うわけにはいかず、「私的行為」とされています。
ところが新嘗祭の網の目は「献上米」という形で全国に張り巡らされ、農家は事実上強制的に動員され、自治体は(広島県のように)公費の支出までおこなう。
これでは「私的行為」といいながら、実際は事実上神社神道を国民に押し付け、天皇(「神社神道教祖」)の権威の維持を図るものと言わねばなりません。
「生前退位」の議論の前に、天皇の宮中祭祀の実態、その憲法上の問題を徹底的に洗い直す必要があります。



美智子皇后は20日の82歳の誕生日にあたり、宮内記者会の質問に答える形で、明仁天皇が意向を表明した「生前退位」に関してコメントしました。その中でこう述べました。
「新聞の一面に『生前退位』という大きな活字を見た時の衝撃は大きなものでした。それまで私は、歴史の書物の中でもこうした表現に接したことが一度もなかったので、一瞬驚きと共に痛みを覚えたのかもしれません」(宮内庁HPより)
今後波紋を広げかねない発言ですが、実はその前段もたいへん注目される発言でした。
「私は以前より、皇室の重大な決断が行われる場合、これに関わられるのは皇位の継承に連なる方々であり、その配偶者や親族であってはならないとの思いをずっと持ち続けておりましたので、皇太子や秋篠宮ともよく御相談の上でなされたこの度の陛下の御声明も、謹んでこれを承りました」(同)
皇后は今回の天皇の「生前退位」の意向表明の経過にはかかわっていない、「謹んで承った」だけだというのです。唐突にも思える〝釈明”をなぜしなければならなかったのでしょうか。
この発言は約1カ月半前に発売された「文芸春秋」十月号(以下「文春」)への事実上の反論だと考えられます。
「文春」は、「皇后は退位に反対した」の大見出しで「真相スクープ」なるものを掲載。その中で、天皇が初めて公に「退位」の意向を示したのは2010年7月22日の「参与会議」だとし、天皇が「私は譲位すべきだと思っている」と切り出し、参与会議のメンバー(羽毛田信吾宮内庁長官、川島裕侍従長、三谷太一郎東大名誉教授、栗山尚一元外務事務次官、湯浅利夫元宮内庁長官の5人)が「衝撃」を受け、そろって「摂政案」を提案した中で、皇后の態度はこうだったと書いています。
「皇后は、天皇の隣の席に座り、天皇とともに参与たちと向かい合っていた。その皇后も議論に加わって摂政案を支持し、退位に反対された。つまり天皇以外の出席者全員が、摂政案を支持したのである」(「文芸春秋」10月号)
その後「参与会議」で何度か「退位」について議論されたが、天皇の意向は変わらなかった。それで、「当初は摂政の設置で解決するべきだとしていた皇后も、天皇の固い意思を確認されて、やがて退位を支持するようになる。出席者の一人が、皇后の意外な一面を明かす。『皇后さまは議論にお強い方です。公の席での雰囲気とは全然違います。非常にシャープで、議論を厭わないのです』」(同)
「文春」は皇后が「退位」をめぐる議論に積極的に関わったというのです。皇后の「誕生日コメント」がこれに対する「反論」であることは明らかでしょう。
皇后のコメントより前、今月17日の第1回「有識者会議」を前後して、NHKや全国紙は「天皇の『生前退位』表明は6年前から」として2010年の「参与会議」について報じました(写真中)。「文春」の後追いです。しかし、「文春」が見出しで強調した「皇后の反対」についてはまったく触れませんでした。「参与会議」に出席していた三谷太一郎氏も、NHKのインタビューで皇后の言動については何も述べませんでした。
皇后の「コメント」によって、「文春」の記事は打ち消されたかにみえました。
ところが皇后誕生日の翌21日未明、日本テレビは「日テレNEWS24」で「宮内庁関係者」の話として、「参与会議」で皇后が「今は『譲位』の意向を明らかにすることはちょっと時期尚早ではないでしょうか」と述べ、「墓の見直しなどを先に検討すべきとの考えを示した」と報じました。
日テレは「文春」にはない「墓」の話まで持ち出して「文春」に同調し、皇后のコメントを再度打ち消したのです。
真相は分かりませんが、皇后の「参与会議」への出席(メンバー)は事実です。その場で「文春」や日テレが報じたような発言(関与)があったとしても不思議ではありません。そして、そうだとしても、それ自体別に問題ではないのではないでしょうか。なぜ皇后があえて「皇位継承権」を持ち出して自らの関与を否定しようとしたのか、その方が不可解です。それは逆に、女性・女系天皇や女性宮家に反対している安倍政権への「遠慮」ではないかとさえ思えます。
皇后が「参与会議」で天皇の「退位」(「譲位」)について意見を述べるのは当然でしょう。皇后に限らず、皇室・皇族が自分に関わる天皇・皇室制度の問題で自らの見解を持つことは、「皇位継承権」の有無にかかわらず、認められるべきでしょう。ただし、法改正を含む制度の改変は、あくまでも憲法に基づいて、国権の最高機関である国会の審議によって決定されるべきであることも言うまでもありません。
問題は、天皇(皇族)の意向を金科玉条のごとく扱い、超法規的措置(例えば「生前退位」の特別立法)をとろうとする政治権力(安倍政権)とそれを容認する「日本社会」にあるのではないでしょうか。
※次回は25日(火)に書きます。



明仁天皇が希望する「生前退位」について検討する有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)は17日の初会合で、「8つの論点」(①憲法における天皇の役割②公務のあり方③高齢の場合の負担軽減策④〝摂政”の設置⑤国事行為の委任⑥天皇の退位⑦退位の適用範囲⑧退位後の身分・活動)を示しました。
この論点設定は、安倍首相の意向に基づくきわめて政略的なものです。
問題は、論点をこの「8つ」に限定することにより、重要・肝心な論点がはじめから排除されていることです。
1つは、「女性・女系天皇」「女性宮家」創設問題です。
今井座長は会議後、「女性・女系天皇の実現や『女性宮家』創設は議題に含まれないとの認識を記者団に示し」(18日付共同)ました。
これが、日本会議や安倍首相の年来の主張に沿うものであることは言うまでもありません。しかも安倍首相には、「女系天皇や女性宮家創設などの課題にも拡大していけば、目指す憲法改正論議が遠のく懸念もある」(同、共同)といわれています。
安倍首相は17日の初会合に出席し、「予断を持つことなく十分審議していただきたい」と述べましたが、最初から「女性・女系天皇」「女性宮家」創設を排除するは「予断」の最たるものです。
もう1つ「論点」から排除された肝心な問題は、憲法の「象徴天皇制」そのものの是非です。
「8つ」の中の①②を論議することは否定しません。それが政府の誘導でなく公正に議論されれば、明仁天皇が自らの判断で拡大してきた「公的行為」なるものの憲法上の問題点も明らかになるはずです。
しかし、①②も含め、「8つの論点は」すべて現在の「象徴天皇制」の枠内です。議論をこの枠内に押しとどめようというのが政府(国家権力)の狙いですが、それを容認することはできません。なぜなら、問われているのは「象徴天皇制」そのものだからです。
たとえば、「生前退位」を認めるべきだという意見の中に、「天皇と皇族は生身の人間だ。人間は人権を有している」(田中優子法政大総長、8月9日付中国新聞)、「一人の人間としては、天皇にも言論の自由があろう」(小熊英二慶応大教授、8月25日付朝日新聞)などの論調があります。世論調査で「生前退位」に賛成する「世論」の中にもこうした天皇の「人権」「自由」を理由とする意見は少なくないでしょう。
しかし、憲法の象徴天皇制は、天皇や皇族に基本的人権を認めていません。職業選択の自由も、結婚の自由も、居住・移転の自由も、苦役からの自由も、政治的発言の自由も認めてはいないのです。
「天皇制は一人の人間に非人間的な生を要求するもので、『個人の尊厳』を核とする立憲主義とは原理的に矛盾します。生前退位の可否が論じられるということは、天皇制が抱えるこうした問題が国民に突きつけられる、ということを意味します」(西村裕一北海道大准教授、8月9日付朝日新聞)
「天皇や皇室を規律する皇室典範について、天皇自ら改正を働きかけるということは、天皇が法の上に立つ専制的な権力を持った存在になるという解釈も成り立つ。象徴天皇制下で許されるのかという疑問はぬぐえない。…皇室典範の改正にとどまらず、憲法と天皇制の関係についても再検討する必要があるだろう」(原武史放送大教授、8月23日付琉球新報)
「生前退位」の問題は必然的に、「天皇制と立憲主義の矛盾」「憲法と天皇制の関係」に行きつかざるをえません。憲法の「象徴天皇制」自体の是非を問い直すこと。それこそが私たち主権者・国民が議論しなければならない「論点」です。


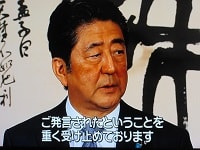
天皇明仁が「生前退位」の意向を事実上表明した「ビデオ・メッセージ」から、8日で1カ月になります。この間の政府やメディアの動向、さらに「識者」の論評をみると、問題の本質が隠ぺいされたまま、異常な違憲状況が放置され拡散されていると言わざるをえません。
★権力の手先となったNHKに新聞協会賞とは
驚いたのは、最初に天皇の「生前退位の意向」を「独自ネタ」として報道した(7月13日)NHKに新聞協会賞が与えられたことです(8日付各紙)。受賞の理由は、「国内外に与えた衝撃は大きく、皇室制度の転換点となりうるスクープ」とか。
確かに「衝撃」はありましたが、それは「だれが天皇の意向をメディアに伝えたのか、責任を負うべき内閣はどんな判断をしていたのか、全く明らかにされていません」(西村裕一北海道大准教授、8月9日付朝日新聞)という「衝撃」です。
NHKは権力の手先となって政府(おそらく宮内庁)のリークを垂れ流し、「生前退位」の露払いをしただけではありませんか。「スクープ」どころか、メディアにあるまじき行為と言わねばなりません。そんなNHKに協会賞とは、日本新聞協会も堕ちたものです。
★「特別措置法」という脱法行為
6日付の共同配信記事は、「政府内で天皇の生前退位を巡り、現在の天皇陛下一代に限り認める特別措置法の制定を先行させ、恒久的な退位制度や『女性宮家』創設などを含む皇室典範の抜本改正は、その後に議論する『2段階論』が浮上していることが分かった」と報じました。
「特措法が軸となるのは、首相の政権運営に絡む事情も背景にありそうだ。…自民党筋は生前退位に関し『自らが描く政治日程の足かせにならないよう、早めに仕上げたい』と首相の胸の内を推し量った」(同共同配信)といいます。
もともと安倍首相は、日本会議などとともに、「女系天皇」や「女性宮家」の創設を認める皇室典範改正には反対です。「特措法」ならその問題に手をつけずにすむという思惑もあるでしょう。いずれにしても安倍氏の狡猾な政治的思惑です。
しかし問題の本質はそこではありません。「特措法」は、天皇の「生前退位」という憲法や皇室典範の基本原則に反する行為を、一片の法律によって、天皇明仁だけに認めようとするものです。それは憲法や皇室典範を踏みにじる「超法規的」な脱法行為と言わねばなりません。
この「特措法」案に対し、批判がどこからも(誰からも)出ていない(報道されていない)ことは、きわめて重大です。
ところで、安倍首相に「特措法」を進言したのが田原総一朗氏であることは、「ジャーナリスト」のあり方を考えるうえで見過ごすことができません。
田原氏は8月31日午後、首相官邸に安倍氏を訪ね、会談しました。
「田原氏が会談で、陛下の生前退位への思いを踏まえ、特別法により対応すべきだと指摘したのに対し、首相は『それもある』と述べたという」(1日付中国新聞=共同配信)
憲法の基本にかかわる問題、政局を左右する焦点の問題で、首相に会って直接脱法行為を進言するとは、驚くべきことです。これが権力を監視するジャーナリストとはまったく無縁の姿であることは言うまでもありません。
★「リベラル派」も天皇の違憲行為に同調・賛美
琉球新報(8月30日、31日付文化面)に掲載された「『天皇メッセージ』をどう読むか」という論稿で梅田正己氏(高文研前代表)は、憲法第7条に定められている天皇の国事行為をあげたのに続けてこう述べています。
「(憲法7条が定めたー引用者)儀式的な役目を、内閣の助言を受けてこなすだけで、『日本国民統合の象徴』としての役割が果たせるものだろうか。答えは考えるまでもない」
「天皇はいかなる行為・行動によって『象徴』としての存在理由を確保できるのか。その『答え』を、天皇みずから国民に対して直接語ったのが、今回の『ビデオ・メッセージ』だったのである」
「『象徴』の意味と役割を、天皇みずから語った今回のメッセージは、私にはまさに〝歴史的”な出来事だったと思われる」
「ビデオ・メッセージ」、というより天皇明仁に対する全面賛美です。これで良いのでしょうか。
「ビデオ・メッセージ」は、天皇明仁が憲法の「象徴天皇」の意味を自分で勝手に解釈し、憲法にない「公的行為」なるものを勝手に拡大し、さらに憲法・皇室典範にない(したがって法改正に直結するきわめて政治的問題である)「生前退位」についての自分の意向を、「ビデオ・メッセージ」というこれまた天皇に認められていない手段(宮内庁はこれも「公的行為」と釈明)で一方的に国民に流したものです。その実態は何重にもわたる違憲行為です。
「リベラル派」とみられている梅田氏が、こうした天皇の違憲行為にまったく目をつむり、その行為を「歴史的な出来事」と賛美するのは、きわめて不可解で異常だと言わねばなりません。
梅田氏だけではありません。天皇明仁に対する美化・賛美が、いわゆる「リベラル派」といわれる人たちの間に広く見られます。
憲法の「象徴天皇制」とは何なのか。どうあるべきなのか。それを決めるのは(それ自体の是非を含め)、天皇ではなく、主権者である私たち「国民」です。
天皇も憲法下の存在であり、憲法や法律を遵守しなければならないことは、憲法99条を引くまでもなく、明白です。憲法・皇室典範無視の違憲行為は絶対に許されません。
天皇・天皇制をめぐる主張・議論は、憲法・民主主義に対する試金石です。



象徴天皇制の是非を考えるうえで、天皇が憲法に規定がないにもかかわらず「象徴的行為として」(8月8日の「ビデオメッセージ」)おこなっている、いわゆる「公的行為」の実態を明らかにする必要があります。
今月5日の新聞の「首相の動静」欄に次の記述がありました。
「午前10時9分、皇居。内奏」
「公的行為」の中でとりわけ見過ごせないのは、天皇への「内奏」です。これは父・裕仁天皇(昭和天皇)を引き継ぐもので、天皇の政治関与、あるいは政権による天皇の政治利用につながるもので、現憲法下では到底容認できるものではありません。
「内奏」とは、「上奏の前に、内閣などから人事・外交・議会関係などの重要案件を申し上げること」(後藤致人愛知学院大教授『内奏ー天皇と政治の近現代』中公新書)です。そして「上奏」(「近衛上奏」など)とは、「天皇大権に対応する形で国家法の枠組みのなかに正式に位置づけられたもの」(同)です。
つまり「内奏」と「上奏」はセットで明治憲法の天皇大権を支える制度でした。したがって国民主権の新憲法のもとでは当然両方廃止されるべきでした。ところがー。
「戦後、象徴天皇制になって上奏は消滅するが内奏は残る。昭和天皇が在位し続けたため、天皇がこの内奏という政治的慣習にこだわったことが大きかった。内奏は戦前以来、天皇の政治行為の重要な要素を構成しており、戦後象徴天皇制においても内奏が残ったことは、長期にわたる保守政権下、昭和天皇の政治力を残存させることになる」(後藤氏、前掲書)
「内奏」は政府から天皇に報告するだけではありません。その際、天皇からの発言(宮内庁は御下問といいます)があるのがふつうです。そのやりとりは当然秘密にされますが、かつてそれが明るみに出て大問題になったことがあります。防衛庁長官(当時)の内奏にあたり昭和天皇が「近隣諸国に比べ自衛力がそんなに大きいとは思えない」などと露骨な政治発言を行ったのです(いわゆる「増原防衛庁長官の内奏漏えい事件」1973年5月26日)。
問題は、昭和天皇がこだわったこの悪しき「政治的慣習」が、明仁天皇にも引き継がれていることです。
宮内庁HPの「天皇の日程」をくれば、「内奏」が出てきます。しかし公表されない「内奏」もあるといわれており、実態はベールの中です。
その宮内庁発表分だけを拾っても、第2次安倍内閣発足以来、2013年=5回、14年=5回、15年=6回、そして今年は8月上旬までですでに6回、「内閣総理大臣」による「内奏」が行われています。回数は徐々に増えています。また、安倍内閣以前の民主党政権時代は、2010 年=2回、11年=2回、12年=3回で、「内奏」は自民党政権下で2~3倍に増えていることが分かります。ここにも「内奏」の政治性が表れているといえるでしょう。
なぜ明仁天皇は昭和天皇の「内奏」を引き継いだのでしょうか。昭和天皇が皇太子・明仁に直接「帝王教育」を施し、明仁氏は父・昭和天皇をモデルに「天皇像」をつくりあげてきたからです(写真右は昭和天皇と皇太子時代の明仁氏)
「天皇のあり方については、(昭和天皇にー引用者)お接しした時に感じたことが大きな指針になっていると思います」(1989年8月4日、即位後の記者会見)
「私は、昭和天皇のお気持ちを引き継ぎ、国と社会の要請、国民の期待に応え、国民と心を共にするよう努めつつ、天皇の務めを果たしていきたいと考えています」(1998年12月18日、誕生日の記者会見)
とくに「内奏」については、「昭和天皇は、内奏の一部を皇太子明仁に見せることにより、戦後政治における天皇と内閣・行政機関の有り様を教えようとしていた」(後藤氏、前掲書)のです。
「知事の奏上(昭和天皇に対する内奏ー引用者)に毎年陪席しているわけですが…(昭和天皇が)よく知事にお聞きになっていらっしゃるのを、非常に印象深く感じたことがあります」(1978年12月21日、皇太子時代、45歳の誕生日の会見)
明仁天皇が「内奏」の際に政府(首相)とどういうやりとりをしているかは不明です。しかし、「『内奏』の慣行は、過去の上奏等を彷彿させ、天皇がいまなお統治の中枢にあるかのような印象を生み出している」(横田耕一九州大名誉教授『憲法と天皇制』岩波新書)ことは明らかです。
「国民主権」(憲法第1条)、「天皇の国政関与禁止」(第4条)に照らして、憲法違反の「内奏」は即刻やめさせなければなりません。


私たちは何を、どのように考えるべきでしょうか。
「ビデオメッセージ」の翌日の新聞に載った識者のコメントの中から、注目したものを2つ紹介します。
1つは、西村裕一北海道大准教授・憲法学の次の指摘です。
「今後この問題は国会などで議論されることになるでしょうが、そこでは、天皇の『お気持ち』を持ち出すことは厳に排除されなければなりません。それは、天皇の影響力を国政に及ぼさないためであると同時に、天皇の『お気持ち』が切り札となることによって、議論がショートカットされるのを許さないためでもあります。
生前退位を認めるのか。認めるとすればどんな条件をつけるのか。制度設計の議論にあたり、世論も含めた政治プロセスの中から天皇の『お気持ち』を切り離し、国民が自律的・理性的に判断をする。それによって国民主権原理が貫徹されることになるでしょう」(9日付朝日新聞)
「象徴天皇制」はあくまでも憲法にもとづく国の制度であり、そのあり方を議論し判断する際、天皇明仁の個人的「気持ち」に基づいたり、逆に天皇への個人的感情を介入させるのは誤りだということです。
共同通信の世論調査(10日付)によると、「生前退位をできるようにした方がよい」が86・6%にのぼっていますが、その理由の67・5%は「天皇の意向を尊重すべきだから」です。まさに「天皇の意向」で天皇制の根幹にかかわる問題を判断しようとする憂慮すべき現状があり、西村氏の指摘は重要です。
もう1つは、吉田裕一橋大教授・歴史学の指摘です。
「忘れてならないのは、『皇室に関心がない』という国民もいる事実だ。それを踏まえないと現実からかけ離れた議論になる」(9日付毎日新聞)
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」(憲法第1条)。これが「象徴天皇制」の基本原則です。しかし吉田氏が指摘するように、「皇室に関心がない」国民がいるのは事実であり、手元にデータはありませんが、日常生活感覚からその数は決して少なくないと思われます。
そうである以上、「日本国民の総意に基づく」という「象徴天皇制」の土台そのものを問い直す必要があるのではないでしょうか。
「ビデオメッセージ」をめぐり、「生前退位」や「皇室典範改正」の是非が中心課題のようにいわれていますが、それはいわば天皇制の枝葉です。それよりも幹の部分すなわち「象徴天皇制」の是非自体を抜本的に検討する必要があるのではないでしょうか。
今日は天皇裕仁(写真左)が「玉音放送」を流して71年目ですが、そもそも「象徴天皇制」は、「天皇の詔勅一つで数百万の日本軍がたいした抵抗もせずにあっさりと武装解除した」ことに注目した米国政府とマッカーサー司令部が、「天皇制は支持しないが利用する」という占領方針に基づいて、「天皇を含む統治機構を温存したうえで、間接統治をおこなう道を選択した」(中村政則氏『象徴天皇制への道』岩波新書)結果の産物です。
そしてこの71年間、「天皇制が議論の的にさえならないまま、重要視されてしまっている。まさに『慣性の天皇制』です」(奥平康弘氏『未完の憲法』潮出版)という状況ができ上がってしまいました。
「象徴天皇制」は「主権在民」に反しないのか、「生身の人間」として天皇の「人権」が保障されない制度が許されるのか、「政治利用」と無縁な「天皇制」などありえるのか、そもそも差別社会を固定化する世襲制の身分制度である「(象徴)天皇制」が今日のそしてこれからの社会に存在していいのか。
いまこそ「理性的判断」によって「慣性の天皇制」から脱却すべきときではないでしょうか。
※「ビデオメッセージ」に関する検討は一応今回でひと区切りとしますが、「(象徴)天皇制」に関しては引き続き考察していきます。



これまで「天皇のビデオメッセージ」がいかに日本国憲法に抵触するか見てきました。ここでは、焦点になっている天皇の「公的行為」(憲法に定められている「国事行為」以外の「公務」)が果たしている役割について検討します。
「天皇のメッセージ」を受けてメディアは、「こうした地道な活動(「慰霊の旅」や「被災地訪問」-引用者)に国民は感銘し、象徴天皇は陛下と国民の共同作業によって定着したといえる」(9日付毎日新聞社説)などと手放しで賛美しました。
はたして天皇の「公的行為」はそのように評価できるものでしょうか。代表的な2つの「公的行為」をみてみましょう。
★「被災地訪問」…強まる自衛隊との接近。被災者に求める「秩序ある対応」とは。
天皇は「即位以降、47都道府県の535余りの市区町村を訪れた。宮内庁によると、被災地への訪問は55回におよぶ」(9日付朝日新聞)といいます。天皇の「公的行為」の中で最も大きな比重を占め、「国民との接点」として重視されているのが、地方訪問(「行幸」)、とりわけ被災地訪問でしょう。
そもそも、被災者にとって「慰問」は歓迎すべきことであっても、それが「天皇・皇后」である必要はどこにあるのでしょうか。「天皇の被災地訪問」は、救援・復興活動に多忙な自治体にとって大きな負担であるばかりか、見過ごせない問題を含んでいます。
「3・11」直後、天皇は初めての「ビデオメッセージ」(2011年3月16日)を流し、それ以降再三にわたって東日本の被災地を訪れました。その「メッセージ」で天皇は、「日本人が取り乱すことなく助け合い、秩序ある対応を示している」ことを評価し、今後もそうやって「不幸な時期を乗り越える」ことを願っていると述べました。
「取り乱さない秩序ある対応」とは一般的には美徳のように思われますが、この場合は政府や自治体に不平・不満を言わないでおとなしくしておくように、という意味に通じるのではないでしょうか。
天皇の被災地訪問は、政府(国家権力)への反発・批判が被災者から沸き起こるのを抑える役割を果たしていると言えないでしょうか。「福島原発事故」はその典型でしょう。
「3・11」以降、天皇の被災地訪問には自衛隊機が使われることが一般的になってきました(写真左は自衛隊機による熊本地震被災地訪問)。先の「ビデオメッセージ」でも天皇は「警察、消防」より先に「自衛隊」の労をねぎらい、そのことに自衛隊幹部が感激したと報じられています(2014年4月28日付朝日新聞)。
歴代自民党政権が災害救助のための専門部隊・官庁をつくらず、自衛隊をそれにあたらせているのは、戦争のための軍隊であるという自衛隊の本質を隠し、「国民」との接近を図る狙いです。天皇の自衛隊機を使っての被災地訪問・自衛隊との接近は、客観的にそれに手を貸していると言えるのではないでしょうか。(3月14日~17日のブログ参照)
★「慰霊の旅」…侵略戦争・植民地主義の加害責任フタし、日米軍事同盟強化の地ならしも
天皇・皇后はいわゆる「慰霊の旅」として、米国サイパン島(2005年6月27、28日)、パラオ(2015年4月8、9日)、フィリピン(2016年1月26~30日、写真中・右)を訪問しました。これらは「平和への祈りをささげられた。…多くの関係者の胸を打った」(9日付読売新聞)などと賛美されています。
しかし、これらの「旅」の目的はあくまでも天皇制下の旧日本軍兵士の「慰霊」であり、日本の侵略戦争の犠牲になった「市民」の「慰霊」ではありません。
重要なのは、一連の「慰霊の旅」で、日本の侵略戦争・植民地主義の責任にはまったく触れていないことです。これは日本の加害責任にフタをしたまま、「戦後」を終わらせようとすることに通じます。
フィリピンでは天皇・皇后の訪問に合わせ、旧日本軍・政府による慰安婦制度の犠牲になった女性たちが抗議・要請行動を行いましたが、天皇はこれをまったく無視しました。日本軍による捕虜虐待として悪名高いマニラ近くの「バターン」にも訪れようとはしませんでした。
さらに重大なのは、天皇・皇后がフィリピンを訪れたのは、安倍首相とアキノ大統領(当時)が「共同宣言」(2015年6月4日)を発表して以降、軍事的連携を強めようとしていた時期と軌を一にしていたことです。日本とフィリピンの連携は、南シナ海におけるアメリカの対中国戦略により、米・日・比の軍事一体化を図るもので、今月11日にも岸田外相が訪比し対中国の連携強化を確認したばかりです。
客観的にみて、天皇・皇后のフィリピン訪問は、こうした米・日・比軍事連携強化の露払い役を果たしたといえるでしょう。(1月23日、2月1、2、4日のブログ参照)
「被災地訪問」にせよ「慰霊の旅」にせよ、上記のような「客観的役割」を、天皇自身がどれだけ意識・自覚していたかはわかりません。重要なのは、天皇自身の「思い」とは無関係に、天皇の行為は重大な政治的意味を持つということです。
それが「天皇の政治利用」であり、憲法にない天皇の「公的行為」はその危険な役割と無縁ではいられません。


「天皇の生前退位」あるいは「象徴天皇制」を考えるうえで、天皇と「人権」の関係は大きなポイントになります。
元最高裁判事の園部逸夫氏は、「天皇も自然人であり、一般的に人権をお持ちとされている。憲法や皇室典範に規定された公的な立場とともに、天皇という一人の『個人』と個人の思いは当然に存在する」とし、「人権を認め退位実現を」(9日付中国新聞)と述べています。
また、法政大総長の田中優子氏も、天皇の「メッセージ」は「政治介入」だとする指摘に対し、「天皇と皇族は生身の人間だ。人間は人権を有している。憲法は『国民』に対して基本的人権を保障している一方、天皇と皇族に基本的人権を保障しているのか。…政治介入とする論理は、天皇を生身の人間としない論理だ」(9日付中国新聞)と批判しています。
両氏の主張は、天皇・皇族にも人権はあり、それは保障されるべきだ、「退位」は人権の一種だから当然求められるべきであり、その意向を示すのも「政治介入」ではない、というものです。果たしてこの主張は妥当でしょうか。
確かに天皇に「生前退位」が認められていないのは、人権(「苦役からの自由」=憲法第18条、「職業選択の自由」=第22条)侵害です。しかし、天皇の基本的人権が保障されていないのはこの問題だけではありません。
天皇には「居住・移転の自由」(第22条)も、「表現の自由、集会・結社の自由」(第21条)も、「選挙権・被選挙権」(第15条)もありません。「労働基本権」(第28条)とも無縁です。
すなわち天皇・皇族は、憲法が「国民」に保障している「基本的人権」とは無縁、別次元の存在なのです。それが天皇制(象徴天皇制)というものです。
園部氏や田中氏の論理でいえば、「生前退位」だけでなく、現在保障されていない上記のような基本的人権はすべて保障すべきだということになります。「退位の自由」だけ認めてほかの人権はそのままでいいということにはならないでしょう。
しかし、「職業選択の自由」「居住・移転の自由」「選挙権・被選挙権」などを認める「天皇制」などありうるでしょうか。そもそも「世襲制」(憲法第2条「皇位は、世襲のものであって…」)の天皇・皇族に「職業選択の自由」など論理矛盾です。
天皇・皇族も「生身の人間」である以上、人権があり保障されるべきなのは当然です。しかしその人権を保障すれば、天皇制(現行の象徴天皇制)は存立しえません。ここに最大の問題があります。これをどういう方向で解決していくか。
「仮に天皇に退位の自由を認めるとしても、別の『誰か』の人権が制約されることに変わりはありません。天皇制は一人の人間に非人間的な生を要求するもので、『個人の尊厳』を核とする立憲主義とは原理的に矛盾します。生前退位の可否が論じられるということは、天皇制が抱えるこうした問題が国民に突きつけられる、ということを意味します」(西村裕一・北海道大准教授・憲法学、9日付朝日新聞)
問われているのは、主権者である私たち「国民」です。



前回は天皇が「ビデオメッセージ」を行ったこと自体の違憲性について考えました。今回は「メッセージ」の内容に即して問題点を検討します。
最初に確認する必要があるのは、以下の問題点は「生前退位」への賛否や、天皇明仁に対する個人的感情とは無関係だということです。
天皇制はあくまでも憲法に規定された国家制度です。その視点から、憲法に照らして、天皇が発した「メッセージ」内容を検討します。
憲法上、「メッセージ」には少なくとも5つの問題があります。
①「象徴的行為」(公的行為)の独自判断(憲法第4条、第7条に抵触)(写真中は自衛隊機による「公的行為」としての被災地訪問)
「(「日本の各地への旅」について)私は天皇の象徴的行為として大切なものと感じて来ました」「象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうかと思われます」(「メッセージ」から。以下同じ)
「象徴的行為」とはいわゆる「公的行為」のことです。ここは「メッセージ」の核心的部分ですが、その意味するものは、「象徴的行為(公的行為)」について、その内容も、量も、天皇が自分で考えて実行しているということです。「公的行為」についての天皇の独自判断です。
宮内庁はこれまで2度(2009年1月、今年5月)にわたって天皇の「公務」=「公的行為」の軽減案をまとめました。しかし天皇はこれに従わず、「公務」を減らすより「退位」の方を望んでいます。
こうした天皇の独自判断は、「公的行為」自体の憲法上の是非を無視し、「内閣の助言と承認」にも従わない「政治的言動」であり、憲法4条、7条に抵触することは明白です。
②宮中祭祀=宗教活動の公私混同(憲法第20条に抵触)(写真右は神武天皇式年祭に向かう天皇、皇后)
「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ました」
「天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務め」
「天皇の終焉に当たっては、重いもがりの行事が連日ほぼ二カ月にわたって続き…」
「祈る」とはけっして一般的な意味ではありません。「『国民の安寧と幸せを祈ること』は宮中祭祀を…意味している。祭祀(は)…憲法で規定されている行為ではない」「宗教的な『もがり』の行事への言及も注目される」(原武史・放送大教授、9日付読売新聞)
「祈る」も「もがりの行事」も、神道にもとづく宮中祭祀、宗教活動です。憲法にないのは当たり前です。政府・宮内庁もさすがに宮中祭祀は「公務」ではなく「私的行為」と位置付けています。天皇自身「メッセージ」で「もがり」は「これまでの皇室のしきたり」だと述べています。
ところがそう言いながら、天皇も政府・宮内庁も、「祈る」・「もがりの行事」を「天皇の務め」すなわち「公務」として扱っています。これは「私的な宗教活動(神道)」と「公務」の混合、公私混同であり、「政教分離」を規定した憲法20条に抵触します。
③「摂政」の否定(憲法第5条、皇室典範第3章に抵触)
「摂政を置くことも考えられます。しかし、この場合も…生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません」
これは事実上「摂政」制度を否定したものです。「摂政」は、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」(公室典範第4条)という天皇終身制において、皇室典範第3章(第16条~21条)と憲法第5条でその方法・性格が明記されています。
「摂政」制度を否定することは、憲法、皇室典範の規定を否定することにほかなりません。
④「万世一系」の天皇制の継続を意図(憲法第1条に抵触)
「日本の皇室が、いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えていくかを考えつつ、今日に至っています」
「我が国の長い天皇制の歴史を改めて振り返りつつ、…象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました」
「メッセージ」で天皇が一番言いたかったのはこの部分でしょう。天皇の念頭にあるのは、「長い天皇制の歴史」「伝統」を絶やさないこと、すなわち「天皇制」の「安定的継続」です。
明治憲法は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」としましたが、「統治」と「象徴」の決定的な違いはあるものの、天皇(制)を「万世一系」のものと考える皇国史観に変わりはありません。
憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と明記しています。天皇制はけっして未来永劫不変のものではありません。「象徴天皇制」が存続するかどうかはまさに主権者である国民の意思に基づくものです。天皇が自ら「万世一系」天皇制の安定的継続を口に出して望むことは、憲法第1条の精神に抵触すると言わねばなりません。
⑤天皇の憲法尊重擁護義務に反する(憲法第99条に抵触)
以上のように、「メッセージ」に盛られた天皇の発言は、たんに「政治的」であるだけでなく、直接間接に日本国憲法に反しあるいは抵触するものです。
憲法第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定めています。「メッセージ」が総体としてこの条文に反していることは明らかでしょう。
では「生前退位」「象徴天皇制」をどう考えればいいのか。次回検討します。













