











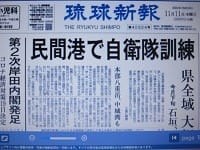


自衛隊のミサイル基地化・軍事要塞化が進行している沖縄で、自衛隊が民間の施設を使って軍事訓練する計画が進行しており、大きな問題になっています。
琉球新報(11日付)によると、防衛省は11月下旬に計画している自衛隊統合演習(実動演習)の一環として、民間の石垣港に自衛隊艦船を寄港させ、与那国島との間で人員・物資の輸送訓練を強行します(写真中は過去の実動演習、右は陸自演習、いずれも自衛隊HPより)。
また、本島・中城湾港でも、借り上げた民間の大型輸送船で県外から人員を輸送する計画です。
「自衛隊統合演習で県内の民間港使用するのは初めて」(同紙)です。
民間港のほか、沖縄戦の戦場になった本部町・八重岳では、「電子戦」の訓練が強行されます。
急速に進む自衛隊の民間施設使用。県民からは、「悲惨な戦場だった八重岳で戦争を想定した訓練をするのはありえない。…沖縄を再び捨て石にするつもりなのか」(12日付琉球新報)など、怒りの声が上がっています。
「統合演習で民間港を使用するのは、有事の際に民間地域を巻き込むことが避けられないことも示している。軍民混在の戦闘がどれだけ悲惨な結末をもたらすか、沖縄戦の体験を踏まえれば明白だ」(12日付琉球新報社説)
統合演習以外でも、陸上自衛隊は宮古島の演習場に物資を搬入する際、民間の平良港を使用することを宮古島市に要求。座喜味一幸市長は、これを許可しました(9日付琉球新報)。座喜味市長は「オール沖縄」の市長です。
自衛隊による民間施設の利用が加速しているのは、沖縄だけではありません。
朝日新聞デジタル(11日)によれば、防衛省は9月から11月末まで、陸自の全部隊が参加する「陸上自衛隊演習」を行っていますが、これに民間の輸送業者が大規模に取り込まれています。
「輸送には自衛隊や米軍に加え、防衛省が輸送業務を発注した民間業者が参加。日本通運のほかフェリー会社14社、航空会社1社の計16社で、日本通運はJR貨物など複数の下請けにも業務を発注した。…今回は業者の総数を含めて過去最大規模という。訓練は有事が迫る中で準備を整えるとの想定」(11日朝日新聞デジタル)
陸自幹部はこう言ってはばかりません。
「様々な意見があるのは当然だが、自衛隊だけでは国を守れないのも事実。今回の訓練が、民間の方に有事の協力のあり方を考える機会になれば」(同)
市民を戦争に巻き込む有事(戦時)体制づくりが、沖縄をはじめ、日本中で急速に進行しています。
しかもそれは、「国を守る」という方便とは逆の深刻な事態と同時進行です。 (明日へ続く)



菅義偉首相が防衛省・自衛隊に運営を担当させたワクチン大規模接種が24日、東京と大阪で始まりました。まったく場違いの自衛隊に担当させた狙い・効果については先に書きましたが(5月18日のブログ参照)、報道された初日の状況を見ると、案の定、と思わざるをえません。
会場案内、そして直行無料バスまで、表示されているのは防衛省のマークと「自衛隊東京(大阪)大規模接種センター」の文字です(写真)。
なぜ「自衛隊」とあえて表示する必要があるのでしょう。「ワクチン大規模接種センター」でいいはずです。書くなら「政府大規模接種センター」でしょう。主催は政府なのですから。あえて「自衛隊」と表記するのは、この場を自衛隊のアピールに使っていると言わざるをえません。
そもそも、メディアは「大規模接種センター」と大騒ぎしていますが、1日の接種は東京が最大1万人、大阪は5000人です(初日はその半分)。菅首相が公約した「1日100万人」の1・5%にすぎません。NHKでさえ「自治体接種の補完的役割にすぎない」(24日朝のニュース解説)というもので、報道は過大評価です。
さらに、「自衛隊によるワクチン接種」はとんでもない“副反応”を起こしています。それは防衛省でこれを担当している中山泰秀副大臣の相次ぐ暴言です(写真右は接種会場で自衛官に訓示する中山氏)。
中山氏は5日、先に日韓外相会談で韓国のチョン・ウィヨン(鄭義溶)外相が日本軍性奴隷(「慰安婦」)や強制連行問題で日本側に「正しい歴史認識」を求めたのに対し、「はあっ??本音は、解決したくないんとちゃうのん??」と言ったりチョン外相を揶揄するツイートを行いました。
これを21日の国会で追及された中山氏は、「韓国に責任を持って対応していただく必要があるという趣旨で発信した」と居直りました(23日付沖縄タイムス=共同)。
また中山氏は12日、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ攻撃の最中、「私たちの心はイスラエルと共にある」とツイート。パレスチナは外交ルートを通じて日本政府に抗議しました。中山氏は21日に削除しましたが、「中東に注目してもらえた。役割を十分果たせた」と開き直りました(24日付琉球新報=共同)。
中山氏はこのかん、5月13日の参院厚生労働委員会、20日の参院外交防衛委員会に相次いで遅刻もしています。まさに傍若無人の振る舞いです。
中山氏の相次ぐ暴言は、たんに低劣な自民党議員の愚行と片付けるわけにはいきません。なぜなら、「中山氏が削除したツイート内容を自信ありげに語る背景には、政府が「個人の見解」(官邸幹部)と位置付け、不問にした実情がある」(24日付琉球新報=共同)からです。中山氏の暴言は菅政権(官邸)のお墨付きなのです。
以上の中山氏の暴言・愚行は、いずれも菅首相が防衛省・自衛隊にワクチン接種を運営させると表明し、中山氏が責任者となり、メディアが連日それを大きく報道する中で起こったことです。
自衛隊という憲法違反の軍隊を社会で公然と活動させ、違和感、抵抗感を取り除き、歓迎さえする風潮をつくりだす。それが自民党政権の基本戦略であることを改めて銘記する必要があります。



20日、豪雨災害で未だに行方が分からない方々の大規模な捜索活動が、熊本県球磨川で行われました。テレビで流れたその映像に、目を疑いました。被災者を捜索するゴムボートに立てられているのは、なんと旭日旗ではありませんか!(写真左・中)
旭日旗は、明治以降の日本帝国の侵略・植民地支配を象徴する文字通りの旗印です。
「海外侵略の走りであった台湾出兵(1874年)や江華島事件(1875年)でも、『日の丸』(旭日旗―引用者)は日本の力の『誇示』に使われています。…日清戦争(写真右)から日露戦争、台湾割譲、南樺太割譲、そして韓国併合。日本はアジアへの膨張を進めていきますが、その先頭にはいつも『日の丸』がありました。…日中戦争に突入すると、またたく間に北京を占領。12月には南京を占領して『南京虐殺事件』を引き起こします。この南京城に立てた『日の丸』は虐殺のシンボルともなっています」(佐藤文明著『「日の丸」「君が代」「元号」考』緑風出版)
けっして遠い過去の話ではありません。この侵略・虐殺・植民地支配のシンボルである旭日旗を、現在の海上自衛隊、陸上自衛隊は「隊旗」としているのです。
そしてさらに、安倍政権はこの旭日旗を国際的イベントで政治的プロパガンダの道具として使おうとしています。「東京五輪」の客席でそれが打ち振られることをあえて公認したのです。
東京五輪を前に、韓国国会文化観光委員会は五輪組織委員会(森喜朗会長)に対し、「侵略と戦争の象徴である旭日旗が競技場に持ち込まれ、応援の道具として使われることがないよう求める」とする決議を採択しました(2019年8月29日)。
これに対し組織委は、競技会場への旭日旗の持ち込みは禁止しない(許可する)とする決定をあえて行い(9月3日)、安倍政権はそれを追認・擁護したのです(9月12日)。
旭日旗に対する批判はもちろん韓国政府・国会だけではありません。2018年10月、韓国主催の国際観艦式に自衛隊が旭日旗を掲げて参加しようとしたとき、韓国のハンギョレ新聞は次のような社説を掲載しました。
「1870年に日本陸軍が最初に使った旭日旗は、日本が太平洋戦争を起こしてアジア各国を侵略する際に全面に掲げた旗だ。それ自体が日本軍国主義の好戦性を象徴している。韓国や中国など周辺国が旭日旗掲揚に反発するのもこのような理由からだ。それでも海上自衛隊は16本の光の筋が描かれた旭日旗を、陸上自衛隊は8本の筋の旭日旗を使ってきた。『侵略国家』『戦犯国家』という事実を否定する処置だ。(中略)国際社会は旭日旗に固執する自衛隊と平和憲法改正を公言した安倍晋三総理を見つめて、日本の軍国主義復活を憂慮している。日本が真に平和を望むならば、自ら旭日旗を降ろすべきである」(2018年10月2日付ハンギョレ新聞社説)
その旭日旗が、豪雨災害の被災地に!被災者の捜索になぜ「隊旗」を立てる必要があるのか!
安倍政権が災害を利用して自衛隊の活動拡大・浸透を図ろうとし、「市民」も次第にそれに取り込まれつつあることの危険性について先日書きましたが(7月9日のブログ参照)、旭日旗の掲揚・誇示はたんに自衛隊の浸透にとどまらず、日本の侵略・植民地支配の歴史を隠ぺいし、国際社会の批判に対する居直りを図るものです。
それが被災者の深い悲しみと苦しみに乗じて行われていることに、身の震える怒りを禁じえません。


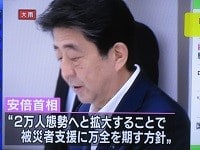
今回の大雨水害のテレビ報道で、自衛隊の映像、その活動に対するコメントがこれまで以上に多くなっていると感じるのは私だけでしょうか。
客観的データはありませんが、もしそうだとしたら、理由は2つ。1つは、自衛隊の活動(「災害派遣」)そのものがこれまでより広範になっていること。もう1つは、メディアの報道がより自衛隊に接近していることです。
安倍晋三首相は4日の関係閣僚会議で、今回の災害に対し「自衛隊1万人態勢で臨む」と早々に打ち出しました。さらに7日には、「自衛隊をさらに1万人増強し、2万人態勢に拡大する」と表明しました(写真右)。安倍首相が自衛隊の「災害派遣」を拡大しようとしていることは確かです。
テレビ報道は、自衛隊が画像に出る機会が多いだけでなく、キャスターが「自衛隊の手によって救出される人々」(7日、NHK)と解説したり、現場で取材にあたっている記者が被災者に「自衛隊が(救助に)来た時はどうでしたか」(7日、TBS系列)と自衛隊への感謝の言葉を引き出そうとしていました。
一方自衛隊は、救出・救援活動を自らビデオで撮影しています(写真左)。広報のためです。消防や警察では考えられないことです。そして防衛省はHPのトップページで「災害派遣」を写真とともにアピールしています。
災害が起こるたびに時の政権(自民党)は自衛隊を出動さ、大きく報道させます。その「災害と自衛隊」の関係が、固定化するばかりか、いっそう拡大し、それに対する疑問や批判の声がだんだん縮小・消滅していっているのではないしょうか。
これはきわめて危険な、自衛隊に対する感覚マヒであり、自民党政権(国家権力)の思惑通りと言わねばなりません。
これまで何度も書いてきたことですが、感覚マヒに抗うために、繰り返し強調しなければなりません。
自衛隊の「主たる任務」は、「我が国を防衛すること」(自衛隊法第3条)すなわち、武力行使・戦争です。自衛隊は憲法(前文、9条)違反の軍隊です。「災害派遣」は自衛隊法第83条に規定されている付随的な活動にすぎません。
にもかかわらず、災害のたびに自衛隊が人命救助・救援活動の主役であるかのように報道されます。これは軍隊としての自衛隊の本質、その違憲性を隠ぺいするものにほかなりません。
結果、日米軍事同盟(安保条約)による対米従属の軍隊の危険性、年間5兆円を上回る軍事費(多くは米国製兵器購入)の不正支出は覆い隠されます。そして、災害時の活動にあこがれて(惑わされて)自衛官の募集に応じる絶好の求人(求兵)活動になります。これが「災害」に乗じた政府(国家権力)の自衛隊認知・拡張戦略です。
被災者が救助する自衛隊に感謝するのは当然です。しかし、それは、本来災害救助・救援の専門組織が行うべきことを、自衛隊が代わりにやっているからにほかなりません。というより、本来あるべき組織をあえてつくらず、自衛隊に代行させて上記の目的を遂行しようとする、それが自民党政権の策略です。
憲法違反の自衛隊(日本軍)は直ちに解散しなければなりません。災害に対しては、防災・救助・救援・復旧に特化した組織(省庁)を創設すべきです。そして5兆円をこえる軍事費は医療・福祉・災害対策へ回すべきです。
災害という非常事態に乗じて自衛隊(日本軍)への感覚をマヒさせる国家権力の策略に陥ってはなりません。



心配していたことが現実になってしまいました。
3月25日~28日に陸上自衛隊宮古島駐屯地に熊本駐屯地から出張していた50代の男性隊員が、新型コロナウイルスに感染していたことが18日までに分かりました(写真左は19日付琉球新報)。
同隊員は3月28日に宮古島から熊本に帰任し、29日発熱。6日に入院し、7日に陽性が判明しました。
宮古島滞在中、「会話するなど接触があった」(陸自西部方面総監部)宮古島駐屯地の隊員が少なくとも4人おり、「7日から11日まで自室に隔離した」ものの、「発熱などの症状がないため、12日から業務に戻った」(19日付沖縄タイムス)といいます。
報道では、4人がPCR検査を受けたとはされていません。陰性を確認しないまま、「発熱など体調に異変がなかった」から職務に復帰させたといいます。驚くべきことです。
宮古島駐屯地では今月5日、地元住民・医師会の強い反対・抗議を押し切って、200人規模の式典(集会)を強行しました(写真右)。感染者と接触があった4人の隊員が隔離されたのは式典から2日後の7日からですから、感染の疑いが濃い4人の隊員は式典に参加していたことになります。
また、「(陸自は)隊員4人以外に接触者はいないとしている」(同沖縄タイムス)といいますが、4人以外にまったく接触がなかった(例えば2㍍の距離以内にいた隊員はいなかった)とはとうてい考えられません。接触者・感染の疑いが濃い隊員はもっと大勢いることが推測されます。
さらに、「(陸自は)男性(感染隊員)の島内での訪問先は明らかにしていない」(同沖縄タイムス)といいます。駐屯地以外(例えば飲食店など)で島民と接触した可能性は否定できません。
こうした事態に対し、「ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会」は18日、宮古島駐屯地を訪れて抗議し、要請書と質問状を手渡しました(写真中、琉球新報より)。
この中で、「(感染した)男性隊員の宮古島での行動歴、同隊員に接触した4人の健康状態など詳細について、22日までに文書で回答」(19日付琉球新報)するよう強く要求しました。
同連絡会の仲里成繁代表は、隊員の感染について「防衛相が会見で触れただけで、いまだ詳細が市民に伝えられていない」(琉球新報)、「1人でも感染者が出たら、島中がパニックになる」(沖縄タイムス)と怒りをあらわにしています。
感染の事実・経過を市民に知らせようとしないのは、軍隊としての自衛隊の本質、そして安倍政権の反民主性をはっきり示すものです。
5日の陸自式典は、安倍政権が全国の市民には「外出自粛」を要求する一方、自衛隊は200人規模の集会を、地元の強い反対を押し切って強行したものです。地元医師会は事前に、「宮古島は医療資源に乏しく、新型コロナ感染の不安が島内に広がっている。万が一、感染者が出たら大変なことになる」(宮古地区医師会・岸本邦弘副会長、4日付琉球新報)と強く中止を要求していました。
安倍政権はそうした地元の声を無視して式典を強行。それが、住民や医師会などが危惧した通り、感染の疑いが濃い隊員が複数参加し、クラスター(集団感染)の場になった可能性が判明したわけで、自衛隊の最高責任者でもある安倍首相の責任はきわめて重大です。



「可能な限り外出は自粛してほしい」。安倍晋三首相は緊急事態宣言を前にした6日夜、改めて国民に外出・イベントの「自粛」を要求しました。その安倍政権は5日、自ら200人規模の集会・イベントを行いました。地元自治体・医師会・住民の反対を押し切って。強行したのは陸上自衛隊の集会・行事、場所は沖縄・宮古島です。
「陸上自衛隊第15旅団は5日、宮古島市上野野原の宮古島駐屯地の編成完成行事を開いた。新型コロナウイルスの感染が全国で拡大していることを受け、市や宮古地区医師会が延期や自粛を要請する中、規模を当初の約700人から約200人に縮小したものの、行事を強行した」(6日付琉球新報、写真左も)
「宮古島駐屯地で地対艦・地対空ミサイル部隊の編成に伴う『編成完結行事』が開かれた5日、陸上自衛隊配備に反対する市民ら約30人が、同駐屯地周辺で抗議の声を上げた。…集会では宮古島地区医師会の岸本邦弘副会長(58)も声を上げた。『新型コロナウイルスがまん延する中での式典は延期するよう求めたが無視された。配慮してほしかったが残念だ』と怒りをあらわにした」(6日付沖縄タイムス、写真中も)
宮古地区医師会(竹井太会長)はすでに3日、コロナウイルス感染防止のため、自衛隊行事の延期を求める要請文を下地敏彦市長に手渡していました。これに対し、自衛隊基地推進派の下地市長でさえ、「市としてもすでに延期要請をしている」と答えていました(4日付琉球新報)。
市長に要請文を手渡した岸本副会長は、「宮古島は医療資源に乏しく、新型コロナ感染の不安が島内に広がっている。…国は国民にイベント開催の自粛を求めている。本来なら国が率先して延期するべきだ」と指摘していました(同琉球新報)。
安倍政権・防衛省・自衛隊は、こした地元自治体、医師会の切実な要請、住民の強い反対を無視して集会・行事を強行したのです。
宮古島駐屯地は、「島しょ防衛」を名目にした安倍政権の自衛隊拡張政策によって、2019年3月に住民の反対を押し切って新設され、約380人が配置されました。さらに今年3月、地対空誘導弾・地対艦誘導弾部隊(ミサイル部隊)として約240人が増員され、700人規模となりました。住民の逃げ場のない離島の宮古島が前線基地にされました。
地震や洪水などの自然災害に際し、自衛隊を出動させて存在をアピールし、軍備増強への批判をかわそうとするのが歴代自民党政府の一貫した政略です。安倍政権はそれを露骨に繰り返しています。
今回の新型コロナ感染に際しても、安倍首相、河野防衛相は機会あるごとに自衛隊を出動させてきました。先月28日には、地元自治体の要請がないにもかかわらず自衛隊を出動させるという一線を越えました(写真右)。
こうした策動はすべて、自衛隊がコロナ感染防止に尽力している、という姿を見せることによってその危険性をカムフラージュしてきました。しかし、今回の宮古島における集会・行事の強行は、自衛隊にとっては「感染防止」より部隊のセレモニー=戦力誇示が優先される、「感染防止」(災害出動)は擬態にすぎないことをはっきり示しました。
それは自衛隊が戦争を第1任務とする軍隊、憲法違反の軍隊であることを自ら証明したことにほかなりません。



新型肺炎に関連して安倍政権がことさら自衛隊を動かし、その存在を示そうとしているように、自衛隊の影は社会のさまざまな分野に広がろうとしています。大学の学問・研究分野もその1つです。
国立大学協会(国大協)の会長校でもある筑波大学(永田恭介学長)が、従来の基本方針を百八十度転換して軍事研究に着手しようとしており、学内外から批判の声が上がっています。国大協の会長校であることの影響も含め、これは筑波大だけの問題ではありません。
日本科学者会議茨城支部筑波大分会・安保法制に反対する筑波大有志の会などは今月13日、「筑波大学の防衛装備庁助成研究への応募・採択に抗議し、その中止を求めます」との声明を発表しました。
それによると、同大は2019年12月、防衛装備庁の「令和元年度・安全保障技術研究推進制度」に応募し、採択されました(5年間で最大20億円予算)。
同大は、2018年12月13日、「本学におけるあらゆる研究活動は、人道に反しないことを原則とし、学問の自由及び学術研究の健全な発展を図るため、研究者の自主性・自律性が尊重され、かつ研究の公開性が担保されるものでなければならない」としたうえで、「これらに反していることから、本学は軍事研究を行わない」と明記した「軍事研究に関する基本方針」を決定しています。それからわずか1年で、この方針を投げ捨てたわけです。
筑波大が応募し採択された「安全保障技術研究推進制度」について、防衛装備庁はこう説明しています。
「近年の技術革新の急速な進展は、防衛技術と民生技術のボーダレス化をもたらしており、防衛技術にも応用可能な先進的な民生技術、いわゆるデュアル・ユース技術を積極的に活用することが重要になっている」(同庁HP)
キーワードは「防衛技術と民生技術のボーダレス化」です。
日本学術会議はこの点に一貫して警鐘を鳴らしてきました。たとえば、2017年3月24日の「軍事的安全保障研究に関する声明」では、「近年、再び学術と軍事が接近しつつある中…軍事的な手段による国家の安全保障にかかわる研究が、学問の自由及び学術の健全な発展と緊張関係にある」と強調しています。
「軍事」と「民生」の「ボーダレス化」「接近」は技術・研究分野に限りません。災害救助・復旧分野でのそれは大災害のたびに可視化させられています。今回の新型肺炎では防疫・医療の分野でそれを見せつけています。自民党政権はこの「ボーダレス化」を利用して(口実にして)、軍事(自衛隊)の民生への侵出・支配を図ろうとしています。その策動は今後ますます強まるでしょう。
これにどう対抗すればいいか。いま筑波大学で有志らがたたかっているように、機敏な批判・反撃が重要であることは言うまでもありません。同時に根本的には、膨張・侵出する「軍事」分野そのものをなくすること、すなわち、憲法の前文・9条に忠実に従い、自衛隊という軍隊を解散することではないでしょうか。