


野党6党派は16日、丸山穂高衆院議員に対する「議員辞職勧告決議案」を衆議院に提出しました。「国会全体の権威と品位を著しく汚した」「わが国の国是である平和主義に反し」た、という理由です。
メディアも「平和国家・日本の国会議員として失格である。速やかに議員を辞職すべきだ」(15日付朝日新聞社説)、「議員として許容される範囲をあまりに逸脱した発言だ。もはや国会に籍を置くべきではなかろう」(15日付毎日新聞社説)などと、辞職を勧告しています。
これに対し丸山氏はツイッターで、「言論府が自らの首を絞める行為に等しい」(16日付共同配信記事)とし、議員を続けると表明しています。
丸山氏の「戦争しないとどうしようもなくないですか」(11日、国後島で元島民の訪問団長に)などの発言が、許すことのできない暴言であることは言うまでもありません。その責任は厳しく追及されなければなりません。
しかし、そのことと、それを理由にした議員辞職勧告は別の問題です。明確に区別して考えねばなりません。
辞職勧告に関しては、決議案を提出した6党派や「朝日」「毎日」などのメディアの論調よりも、丸山氏の主張の方に正当性があると言わざるをえません。なぜなら、今回の辞職勧告決議案は、国会議員の発言の内容を問題にし、それが議員として失格だと断じるものだからです。
これまで国会に提出された「辞職勧告決議案」はいずれも、贈収賄や政治資金規正法違反などで逮捕・起訴されたり有罪判決が下された場合に提出されました。刑事事件にかかわる実際の行為がその理由だったのです。しかし今回は、そうした行為ではなく、議員の発言(言論)の内容で議員を辞職させようとするものです。
これは議員の思想・信条の自由、言論の自由に対する重大な侵害であり弾圧です。戦後の憲政史上大きな汚点を残すものと言わねばなりません。
「国会全体の権威と品位を著しく汚した」とは抽象的ですが、その意味するところを、日本共産党の志位和夫委員長は16日の記者会見でこう述べています。
「志位氏は、丸山氏の発言は…戦争の放棄を定めた憲法9条と、閣僚や国会議員などの憲法擁護尊重義務を定めた憲法99条に反する『二重の憲法違反』の『最悪の発言』であり、『まったく国会議員の資格はない』と指摘しました」(17日付「しんぶん赤旗」
丸山氏の発言の内容が「二重の憲法違反」だから「国会議員の資格はない」というのです。これはきわめて重大で危険な主張です。
確かに丸山氏の発言は9条など憲法の「平和主義」に反しています。その低劣さ、荒唐無稽さは尋常ではありません。しかし、憲法の平和主義に反している国会議員は丸山氏だけではありません。
日米安保条約、自衛隊はともに9条などの憲法の「平和主義」違反です。9条に反する発言をする議員は国会議員の資格がないというなら、日米安保・自衛隊を容認・賛美する発言を行う国会議員はみんな国会議員の資格がないということになり、国会に議員はいなくなります。
憲法99条は確かに、「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定しています。
しかしその意味は、「権力行使者が憲法に違反する行為を行うときには、これに制裁を科するのは容易ではない。だからこそ、権力行使者の憲法尊重擁護義務を明文で宣言し、注意を喚起しておく必要があると考えられているのである」(高橋和之著『立憲主義と日本国憲法』有斐閣)と解されています。
また、「立法の担い手である国会議員は、憲法を尊重擁護することを前提として各種の法律を策定しなければならない」(志田陽子著『表現者のための憲法入門』武蔵野美術大学出版局)。さらに、「国会議員など国政上の実質的判断権限を認められている者は、その判断権限の行使に際して憲法に従うことが要求される」(安西文雄九州大教授『憲法学読本』共著・有斐閣)などの指摘(解釈)も合わせると、99条の憲法尊重擁護義務は、あくまでも国会議員の立法活動という権限行使の行為について課せられているものであり、けっして議員の思想・信条、言論を縛るものではありません。
仮に、国会議員の言論活動の内容がすべて憲法に沿うものでなければならないとするなら、「憲法改正」を毎年党大会で確認している自民党の国会議員は全員議員辞職すべきだということになります。
また、2004年の党大会で綱領を変えるまで憲法(第1章)に反する「天皇制廃止・共和政」を掲げていた日本共産党の国会議員も、「国会議員の資格」はなかったということになるではありませんか。
国会議員(政党)の思想・信条、言論活動を権力(「国会決議」もその一種)で縛ることはできません。縛ってはいけません。それはもちろん、現行憲法に対する批判、憲法改正の主張も含めてです。そうでなければ政治(憲法も含め)や社会の進歩・発展はありません。それが戦前・戦中の苦い教訓ではなかったでしょうか。
議員や政党の主張、政策の是非は自由で活発な言論活動の中で判断され淘汰されていくべきです。
繰り返しますが、丸山氏の暴言と、それを理由にした議員辞職勧告は別の問題です。暴言を吐いた人物だからといって、その正当な主張まで抹殺することは許されません。













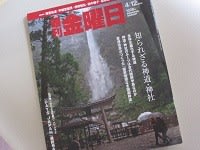
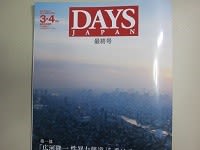














 東京MXテレビが「ニュース女子」で沖縄の基地反対運動をまったくのデマで中傷・攻撃した問題で、「扇動する黒幕」などと名指しされ右翼から標的にされている辛淑玉(シンスゴ)さん(在日コリアン3世、人権団体「のりこえねっと」共同代表)が、ヘイトクライムから身を守るため、ドイツに事実上亡命せざるをえなくなっていることが、4日の沖縄タイムスの報道(写真)で分かりました。
東京MXテレビが「ニュース女子」で沖縄の基地反対運動をまったくのデマで中傷・攻撃した問題で、「扇動する黒幕」などと名指しされ右翼から標的にされている辛淑玉(シンスゴ)さん(在日コリアン3世、人権団体「のりこえねっと」共同代表)が、ヘイトクライムから身を守るため、ドイツに事実上亡命せざるをえなくなっていることが、4日の沖縄タイムスの報道(写真)で分かりました。


