











「政府が「佐渡島の金山」(新潟)の世界文化遺産への推薦を2021年度は見送る方向で検討していることが20日、分かった」(21日付中国新聞=共同)と報じられて1週間。岸田文雄首相は28日、一転して「佐渡金山」のユネスコ世界文化遺産への推薦を表明しました(写真左)。
この急転換は、安倍晋三元首相、高市早苗自民党政調会長のゴリ押しの結果です。
1月19日 高市氏は記者会見で、「日本国の名誉に関わる問題だ」「政府には登録に向けて本気で頑張ってほしい」と主張。
20日 安倍氏は自民党安倍派の会合で、「論戦を避ける形で登録を申請しないというのは間違っている」「しっかりとファクトベースで(韓国政府に)反論していくことが最も大切だ」と政府をけん制(写真中)。
24日 高市氏は衆院予算委員会で、「国家の名誉に関わる。必ず今年度に推薦すべきだ」と政府に要求(写真右)。
26日 高市氏は記者会見で、「来年度の(ユネスコへの)推薦になると、今よりもはるかに状況が不利になることを心配して衆院予算委員会で質問した」「今年度に推薦できない理由というかハードルはない、と日本政府も考えていることが明らかになった」と発言。
安倍、高市両氏の発言は、彼らが「佐渡金山」の世界文化遺産登録に固執するのは、「日本国の名誉」にかけて韓国の反対に対抗するためだということを示しています。
韓国が「佐渡金山」の登録に反対しているのは、帝国日本の植民地支配によって多数の朝鮮人がそこで強制労働させられた歴史があるからです(1月11日のブログ参照)。
その韓国の反対に安倍氏や高市氏が対抗するのは、朝鮮人強制労働の歴史を隠ぺいしようとするからです。それは、高市氏が自民党の「来年度予算編成大綱」で強調した「歴史戦」の実行に他なりません(12月30日のブログ参照)。
今回の「佐渡金山」推薦の急転換は、岸田政権を操っているのが安倍晋三氏とそのグループの歴史修正主義者らであることを示しています。
韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」の報告書(2019年)では、「佐渡金山での朝鮮人強制動員は1939年2月に始まった。以後、1942年3月まで6回にわたって1005人を募集で連れて来るなど、計1200人を強制動員した」とされています。
一方、「佐渡金山」があった旧相川町(現・佐渡市)が1995年に発行した町史では、「当時の資料をもとに千人以上の朝鮮人労働者が佐渡鉱山(戦時中の名称―引用者)に移入したと見積もっている」(28日の朝日新聞デジタル)といいます。「佐渡金山」における朝鮮人の人数は韓国側の調査と地元の町史がほぼ一致しています。
朝鮮人強制動員・強制労働の歴史を隠ぺいしたまま、「佐渡金山」を世界文化遺産登録に推薦することは絶対に許されません。
それは韓国政府が反対しているからではありません。日本のメディアは「閣僚の靖国神社参拝」と同様に、この問題を日本政府と韓国政府の問題に矮小化していますが、問題の本質は、日本人が日本の植民地支配の歴史的とその責任にどう向き合うかにあります。
その視点に立って、安倍氏や高市氏らの歴史の隠ぺい、「佐渡金山」の世界文化遺産登録推薦は容認することができません。


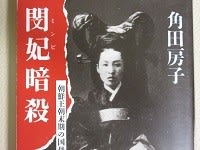
8月22日は、111年前の1910年、明治天皇制政府が朝鮮半島を名実ともに植民地化する「韓国併合条約」の調印を武力支配の下で強行した日です(公布は同8月29日)。
同条約は「明治維新」直後からの朝鮮半島侵略・植民地化の総仕上げで、そこに至るまでに日本政府は様々な無法・暴挙を行ってきました。主なものを挙げてみます。
1875・9 江華島事件(軍艦「雲揚」による一方的攻撃)
1876・2 日朝修好条規調印(治外法権など不平等条約)
1894・7 甲午(カボ)政変(日本軍による王宮占拠)
同・8 日清戦争(朝鮮半島の支配めぐり清に宣戦布告)
1895・4 日清講和条約(下関条約)調印
同・10 乙未(ウルミ)事変(公使・三浦梧楼を首謀とする閔妃=明成皇后暗殺)
1904・2 日露戦争(朝鮮半島支配をめぐりロシアに宣戦布告)
日韓議定書調印(系統的内政干渉の法的裏付け)
1905・9 日露講和条約(ポーツマス条約)調印
同・11 乙巳(ウルサあるいはイッシ)保護条約(第2次日韓協約)(伊藤博文による暴力的保護国化)
同・12 統監府設置。伊藤が初代統監=「武断統治」
1910・8 「韓国併合条約」(「大韓帝国を地上から消滅させ、形式上も完全な植民地にしてしまった」梶村秀樹氏『朝鮮史』講談社現代新書1977年)
こうした明治政府の暴挙を後押ししたのが、日本の社会(新聞、「識者」、市民)だったことを銘記する必要があります。
閔妃暗殺の首謀者・三浦梧楼は広島で裁判にかけられましたが「無罪」放免(後に枢密顧問官)。監獄から出てきた三浦は、「沿道到る処、多人数群して、万歳万歳の声を浴びせ掛け(られた)」(暗殺事件被告の一人の手記=海野福寿著『韓国併合』岩波新書1995年より)といいます。
「この間(「日韓併合」に至る過程で)、日本国民の大多数は、支配者のおごりにすっかり染まってしまい、日本が世界の一等国になったといって旗行列し、国を失って悲しみに沈む朝鮮人を、あからさまに侮蔑する状態であった」(梶村秀樹氏前掲書)
「併合直後の1910年8~10月の『東京朝日』『大阪朝日』『東京日日』『読売』『万潮報』の有力新聞社説と総合誌『太陽』『中央公論』『日本及日本人』掲載の論説を分析した姜東鎮氏の研究によると、すべての社説・論説が日本の韓国併合を美化し、こじつけの論理で正当化しているという」(海野福寿氏前掲書)
「自由主義者・植民政策学者として令名高く、現在(注・当時)の五千円札の肖像にもなっている新渡戸稲造でさえ例外ではなかった。1910年9月13日…校長演説でつぎのように述べた…「忘れることの出来ないのは朝鮮併合の事である。之は実に文字通り千載一遇である」」(海野福寿氏前掲書)
こうした日本社会の状況は、けっして過去の話ではありません。
朝鮮侵略・植民地化の主犯・伊藤博文、朝鮮を蔑視し侵略を鼓舞した福沢諭吉、上記の新渡戸稲造はいずれも日本紙幣の顔となりました。そして、伊藤と組んで経済的に朝鮮植民地化をリードした渋沢栄一(写真左)が、福沢に代わって1万円札の顔になることが決まり、渋沢を美化する大河ドラマが公共放送(NHK)の看板番組になり、渋沢本が書店にあふれている。これは日本の社会が111年前と本質的に変わっていないことを象徴的に示しているのではないでしょうか。



東電福島原発「事故」の汚染水を海に放出することについて、福島の人々は「これは福島だけの問題ではない」と言っています。県外の私たちに対し、この問題を「当事者」として、自分ごととして考えよ、という訴えです。
作家の高村薫氏は、「10年後の被災地を歩く」と題した「特別寄稿」で、「10年後の1F(福島第1原発)には死と隣合わせだった事故当時の阿鼻叫喚は、もう影もかたちもない。…1Fに関わっている東電社員も下請けの作業員も、余計な思考を停止して目の前の仕事を淡々とこなすことで、終わりのない不毛な時間に耐えることができているのかもしれない」としたうえで、こう述べています。
「この当事者性の消失は、東電や1Fを抱える自治体のみならず、ほかの原発立地自治体、電力業界、経産省、政府、そして電力の利用者である私たち国民も同様である」(3月13日付中国新聞=共同)
高校教師の経験をもつ札埜(ふだの)和男岡山理科大准教授は「平和教育」についてこう述べています。
「高校の現場にいる頃、文学教材による平和教育を実践してきた。最も工夫したのは「当事者性」である。「平和は大切」「戦争を繰り返してはいけない」といった飽き飽きするような感想ではなく、いかに「自分ごと」として考えさせることができるか」(3月16日付中国新聞)
「当事者性」が求められているのは、もちろん「原発」や「平和教育」だけではありません。沖縄の人々は「基地は沖縄だけの問題ではない」と訴え続けています。しかし多くの日本人は自分が「当事者」だとは思っていない、思えない。それはなぜでしょうか。
札埜氏が行きついたのは、宮田拓さんという高校地歴科教員の次の言葉です。「今の平和教育は…人間が見えなくなっている」「戦争が駄目なのは当たり前。祈るだけで平和は来ない。なぜ戦争が起きたのかを考えることが大事」
福島県の「いわきの初期被曝を追及するママの会」代表の千葉由美さんは、被曝の実態が情報公開されていない問題を指摘し、こう述べています。
「これは国が加害側にある公害問題だからです。国は実態を明らかにしないことで自らを守ろうとする。つまり十分な補償、賠償をしない。こういう中で…全国の消費者はそれを食べて自分も被ばくする可能性をどのくらい意識できるのかなと思います。当事者意識が持てないのは、加害側である国が、なるべく人々に伝えたくないという事情がある。それに流されないでほしい、飲み込まれないでほしいと思います」(季刊誌「アジェンダ」2021年春号所収のインタビュー)
千葉さんの言葉ですぐに想起されるのは、戦時性奴隷(「慰安婦」)や強制労働(「徴用工」)、そして高校無償化制度からの排除など在日コリアンに対する制度的差別の問題です。これらの問題を多くの日本人が「当事者性」をもって「自分ごと」として考えられないのは、やはり「加害側である国」が、「なるべく人々に伝えたくない」として歴史の事実を隠ぺいしてきたからではないでしょうか。沖縄の基地問題(軍事植民地政策)を「本土」の人間が「当事者」として考えられないのも、日米安保体制の実態、琉球併合(1879年)や沖縄戦の実相・歴史が国家権力によって隠されてきたからではないでしょうか。
日本の社会変革は、どれだけ多くの市民がさまざまな社会事象に対して「当事者性」を持つことができるか、そして「思考停止」から脱却することができるかにかかっていると思います。そのカギは、正確な情報と歴史の事実を国家権力から市民の側に取り戻すことではないでしょうか。
(写真は左から、福島原発汚染水の放出に抗議する韓国の市民、ミャンマーの市民弾圧に抗議する日本でのデモ、入管の人権侵害に抗議する人々。いずれも「当事者」としてたたかっている人たちです)



もうすぐ10年を迎える東北の被災地で、信じがたいことが起こっています。「語り部や訴訟遺族に中傷 宮城・石巻市 災害伝承に悪影響の恐れ」という見出しの記事は、こう伝えています。「東日本大震災で大切な家族を亡くし訴訟に踏み切った遺族や、教訓を伝えるため語り部活動を続ける被災者への誹謗中傷が相次いでいる」(2月21日付琉球新報)
石巻市立大川小学校で次女を失い、語り部活動を行っている紫桃隆洋さん(56)は、「昨年、被災した大川小校舎を訪れた観光客が「いつまで被災者気取っているんだ?」というような会話をしているのを聞いた。「語り部はみんな、すごくエネルギーを使い、傷つきながらやっている。それでも、一人でも多く命を救いたいという気持ちで続けている」と語った」(同紙)。紫桃さんには脅迫状もきているといいます。
許ししがたい人権侵害・人身攻撃ですが、これは誹謗中傷を受けている語り部・被災者・遺家族だけの問題でしょうか。
『記憶で書き直す歴史 「慰安婦」サバイバーの語りを聴く』(韓国挺身隊問題対策協議会・2000年女性国際戦犯法廷証言チーム、金富子・古橋綾編訳、岩波書店2020年12月)という本が最近出版されました。
帝国日本による戦時性奴隷(「慰安婦」)の被害者9人の証言集ですが、最大の特徴は、「問うから聴くへ」という「証言者中心主義」です。聞き手が聞きたいことを訊くのではなく、証言者の意思による語りが、言葉遣いはもちろん間合いも含め、忠実に再現されています。それによって、「慰安所」における暴力・残虐行為だけでなく、解放(日本の敗戦)後も続いた差別・貧困の苦しみが生々しく迫ってきます。
証言を聴取し文章化した証言チームの代表、梁鉉娥(ヤン・ヒョナ)さんが同書の中でこう言っています(太字は引用者)。
「被害者の証言は、被害の言語ではなく、すでにそれを「見つめる」言語であることに留意しなければならない。…経験を語る彼女たちは、被害者であり観察者であり、また再現者だ」「「聴く」とは無思考の空間ではなく…「聴く」の完成は究極的に、読者との交感から成し遂げられると考える。読者がサバイバーの肉声を「聴くことができる」とき、証言をめぐる対話が可能となり…共鳴できる。こうして証言研究は…サバイバーとしての個人のライフ・ヒストリーの叙述とアジアの歴史叙述の交差点に立っている」
意味深い言葉ですが、私はこう解釈しました。サバイバーの「証言」を「聴く(読む)」とは、たんに知識を得るだけの一方通行ではなく、証言者との「交感」であり、「対話」「共鳴」の双方向の行為である。それによって証言を「聴く(読む)」者も証言者とともに歴史の形成者となる―。
震災・原発被災者と戦時性奴隷の被害者を同列に置くことはもちろんできませんが、その証言を「聴く(読む)」ということにおいては、共通するものがあるのではないでしょうか。
語り部やサバイバーに対する攻撃は、重大な人権侵害であるだけでなく、証言の抑圧・封殺であり、それは「聴く(読む)」側の証言者との「交感」「対話」「共鳴」を奪い、歴史の形成者となることを妨げることではないでしょうか。
証言者に対するあからさまな攻撃はごく一部の者によるものでしょう。しかし、その背景には、この国の“証言文化”の貧困があると思えてなりません。
日本人は歴史の当事者の証言を「聴く(読む)」ことをどれだけ大切にしているでしょう。証言者にどれほど敬意を払っているでしょうか。歴史というもの、歴史を形成するということに対する私たちの向き合い方が問われているのだと思います。

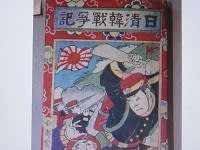

東京五輪・パラリンピック組織委員会(会長・森喜朗元首相、写真右の中央)が旭日旗の持ち込みを許可し、安倍政権(菅義偉官房長官ら)がそれを追認している問題については、以前書きましたが(9月14日のブログ参照)、政府はその後も「(旭日旗は)今の日本人にとっても大事な一種の伝統的なものという位置付けだ。いろいろクレームを付けられるべきではない」(18日、外務省・大鷹正人外務報道官記者会見)などと繰り返しています。
ところがその政府の言い分とは裏腹に、かつて日本政府自身が五輪の応援で旭日旗を使わないよう呼び掛けていた事実があります。
2008年7月31日、北京五輪を目前にして、在北京日本大使館は、「北京五輪期間中に訪れる日本人応援客への注意事項に関する説明会を開き、会場への横断幕やスローガンの持ち込みが禁止されることを明らかにした」(2008年8月1日付日経新聞)ということがありました。
その説明会は口頭での説明ではなく、「安全の手引き」という文書によるものでした。その「手引き」にはこう書かれていました。
「中国では競技場やイベント会場で政治・民族・宗教的なスローガンや侮辱的な内容を含む旗や横断幕等を掲げることは禁じられています。また、過去の歴史を容易に想起させるもの(例えば「旭日旗」)を掲げるとトラブルを生じる可能性があります」(9月19日付「しんぶん赤旗」より)
この「赤旗」の記事は、当時北京五輪を取材したスポーツ部記者の署名記事で、信頼がおけます。
北京五輪で旗や横断幕を規制したのは主催国の中国ですが、その説明にあたり「過去の歴史を容易に想起させるもの」の例として「旭日旗」を挙げたのは日本大使館(日本政府)です。「過去の歴史」が何を意味するか「手引き」」にはさすがに書かれていなかったようですが、日本による侵略戦争・植民地支配の歴史であることは自明でしょう(写真中)。
2008年北京五輪の時は旭日旗を「過去の歴史を容易に想起させるもの」の代表例として挙げながら、2020年東京五輪では「日本国内で広く使用されており、政治的宣伝とはならない」(組織委員会)、「伝統的なもの。クレームを付けられるべきではない」(大鷹外務報道官)と言って旭日旗の持ち込み・使用を容認する。二枚舌も甚だしいと言わねばなりません。
2008年当時の政権は、安倍晋三氏が突然政権を放り出したあとを継いだ福田康夫政権です。福田氏は安倍氏と同じ福田派(現町村派)で、安倍氏の先輩にあたります。安倍氏が福田政権のことは知らないという言い逃れは通用しません。安倍氏は11年前の福田政権のこの「手引き」についてどう釈明するつもりでしょうか。
安倍政権が東京五輪であくまでも旭日旗の持ち込み・使用許可を強行しようとしているのは、侵略戦争・植民地支配への無反省・開き直りの露骨な証明であるとともに、旭日旗を隊旗としている自衛隊(海上自衛艦旗、陸上自衛隊旗)、さらには天皇制を誇示し、改憲へつなげようとする意図があります。五輪への旭日旗の持ち込み・使用は絶対に容認することができません。



「東京五輪・パラリンピック組織委員会」(委員長・森喜朗元首相=写真右中央)が、競技会場への旭日旗の持ち込みを禁止しない(許可する)と決定(3日)し、菅偉義官房長官がそれを追認・擁護した(12日)ことは、安倍晋三首相や森元首相ら歴史修正主義者の本性をむき出しにしたものであると同時に、安倍政権が強行する「東京五輪」の正体を露呈したものと言えます。
この問題では韓国国会の文化観光委員会が、旭日旗の持ち込みを禁止する措置を東京五輪組織委に求める決議を採択(8月29日)していました。決議は旭日旗について「日本が帝国主義と軍国主義の象徴として使用した」ものであると指摘し、「侵略と戦争の象徴である旭日旗が競技場に持ち込まれ、応援の道具として使われることがないよう求める」としていました。
これに対し組織委員会は、「旭日旗は日本国内で広く使用されており、旗の掲示そのものが政治的宣伝とはならないと考えており、持ち込み禁止とすることは想定していない」(5日付琉球新報=共同電)として韓国国会委員会の申し入れを一蹴しました。
旭日旗が「日本国内で広く使用されている」とは驚いた言い分です。日本国内でも旭日旗を使っているのは、せいぜい陸・海自衛隊と右翼くらいです。森氏や安倍氏にはこれらの団体が大きく見えるとしても、それを一般化するのは無理な話です。
そもそも旭日旗とは何かを改めて確認しておく必要があります。
「海外侵略の走りであった台湾出兵(1874年)や江華島事件(1875年)でも、『日の丸』(旭日旗―引用者)は日本の力の『誇示』に使われています。…日清戦争から日露戦争、台湾割譲、南樺太割譲、そして韓国併合。日本はアジアへの膨張を進めていきますが、その先頭にはいつも『日の丸』がありました。…昭和天皇を大元帥に頂いた日本の『日の丸』は1937年7月『盧溝橋事件』を口実に、日中戦争に突入すると、またたく間に北京を占領。12月には南京を占領して『南京虐殺事件』を引き起こします。この南京城に立てた『日の丸』は虐殺のシンボルともなっています」(佐藤文明著『「日の丸」「君が代」「元号」考』緑風出版)(写真中は日露戦争の宣伝物=ソウルの植民地歴史博物館展示)
だから韓国のハンギョレ新聞は、昨年10月、韓国主催の国際観艦式に自衛隊が旭日旗を掲げて参加しようとした際、次のような社説を掲載しました。
「1870年に日本陸軍が最初に使った旭日旗は、日本が太平洋戦争を起こしてアジア各国を侵略する際に全面に掲げた旗だ。それ自体が日本軍国主義の好戦性を象徴している。韓国や中国など周辺国が旭日旗掲揚に反発するのもこのような理由からだ。それでも海上自衛隊は16本の光の筋が描かれた旭日旗を、陸上自衛隊は8本の筋の旭日旗を使ってきた。『侵略国家』『戦犯国家』という事実を否定する処置だ。(中略)国際社会は旭日旗に固執する自衛隊と平和憲法改正を公言した安倍晋三総理を見つめて、日本の軍国主義復活を憂慮している。日本が真に平和を望むならば、自ら旭日旗を降ろすべきである」(2018年10月2日付ハンギョレ新聞社説)
韓国国会の「禁止要求」をあえて拒否し、競技場への持ち込みを公認した組織委・安倍政権の意図が、侵略戦争・植民地支配の歴史を否定するとともに、旭日旗をシンボルとする自衛隊のアピールにあることは明白です。
それが9条への自衛隊明記を目論む安倍改憲策動と一体であることも言うまでもありません。
安倍首相は「東京五輪」をこうした改憲策動へ向けた国際的アピールに利用しようとしているのです。それが天皇徳仁のお披露目の場でもあることも無関係ではありません。天皇と自衛隊を一体化させて改憲へ弾みをつける。それが「安倍・東京五輪」の狙いです。
「旭日旗許可」はけっして韓国との外交問題ではありません。日本の侵略戦争・植民地支配責任にどう向き合うかという日本人自身の問題です。



参院選公示前日の3日に日本記者クラブで行われた党首討論会。司会陣(記者クラブ代表各社)の突っ込み不足もあり、興味の薄いものとなりましたが、その中で、最も注目されたのは、朝鮮半島の強制徴用(元徴用工)損害賠償をめぐる安倍首相の発言でした。
司会者の1人が、「政府は韓国の元徴用工らへの損害賠償判決問題で、事実上の対抗措置を取った。歴史認識問題を通商政策と絡めるのは両国にとって良くない」と質したのに対し、安倍首相はこう答えたのです。
「その認識ははっきり申し上げて間違いだ。歴史問題を通商問題に絡めたのではない。徴用工問題は歴史問題ではなく、国と国の約束を守るかどうかということだ。約束を守らない中で、今までの優遇措置はとれない」
今回の韓国に対する輸出規制強化が「元徴用工」問題での対抗措置であることは衆目の一致するところで、安倍氏の発言は言い訳にもなっていませんが、聞き捨てならないのはそこではなく、「徴用工問題は歴史問題ではない」と言い切ったことです。
安倍氏は続けて、戦時性奴隷(「日本軍慰安婦」)問題についても、「慰安婦合意は首脳間、外相間の合意だ。その合意が守られていない。国際約束が守られていない問題だ」と言いました。
いずれも「歴史問題」ではなく「国と国の約束の問題」だというのです。これこそ安倍首相(日本政府)の根本的誤謬であり、「元徴用工」「元慰安婦」問題の本質もここにあると言わねばなりません。
強制徴用、戦時性奴隷の根源は、言うまでもなく日本の朝鮮半島植民地支配です。それはまぎれもない歴史問題、日本の歴史的犯罪の問題です。
その被害者は「元徴用工」「元慰安婦」一人ひとりです。加害者である日本が賠償責任を負わねばならないのは「国」ではなく被害者個人です。それが日本の歴史的責任です。
それを日本政府は、「日韓請求権協定」(1965年)、「日韓慰安婦合意」(2015年)という「国と国の約束の問題」にすり替え、「解決済み」としているのです。両協定・合意とも、肝心の被害者個人(支援団体)の頭越しに行われたことがそれを証明しています。
「請求権協定」については日本政府自身、当初は「被害者個人の賠償請求権は消滅していない」と言明していましたが、安倍政権はそれをなし崩しにしてきました。
問題は、この根本的すり替え(歴史問題を「国家間合意」問題へ)が、安倍氏だけの問題ではないことです(歴史修正主義者の安倍氏がこうしたすり替えをするのはいわば自明)。
日本のメディアは、基本的にすべて安倍氏と同じ立場に立ち、いずれも「請求権協定」「慰安婦合意」という「国家間合意」の枠から出ていません。両問題を日本の植民地支配責任の問題ととらえきれていないのです。それが結局、安倍政権を擁護する論調につながっています。
メディアだけではありません。日本の政党も自民党だけでなく、基本的にすべて「国家間合意」に縛られています。両協定・合意に対する批判が皆無なことがそれを示しています(1965年の日韓条約・請求権協定にも2015年の「外相合意」にも日本の植民地支配の反省はありません)。
さらに問題なのは、そうしたメディアや政党の影響で、「日本国民」全体が結局安倍氏のすり替えにからめとられていることです。それが両問題の根源を見失い、安倍政権支持、対韓嫌悪の「世論」につながっていると言わねばなりません。
問題の核心は、主権者である「日本国民」が、強制徴用(元徴用工)、戦時性奴隷(元慰安婦)問題を、歴史問題、すなわち日本の植民地支配責任の問題ととらえ、心からの謝罪と被害者個人への損害賠償責任を果たす立場に立つかどうかです。



自民党内のポスト争いにすぎない総裁選で大騒ぎするメディアの愚についてはすでに書きましたが(8月5日のブログ参照)、8月26日に安倍晋三首相が鹿児島で行った総裁選出馬表明(写真左)とその直前の講演は、見過ごすことができない安倍氏の危険な”思想”と政治姿勢が表れていました。
第1に、皇国史観と天皇制の政治利用です。
安倍氏は出馬表明でこう述べました。
「来年は皇位の継承、日本初のG20サミットが開催され、さらにその先に東京オリンピック・パラリンピックが開催される。まさに日本は大きな歴史の転換点を迎える。…平成の先の時代に向け新たな国づくりを進める、その先頭に立つ決意だ」(写真)
絶対主義天皇制の大日本帝国憲法と違い、主権在民の現行憲法では天皇にはなんの政治的権限もありません。「内閣の助言と承認」によって憲法に定められた「国事行為」を行うだけです。その天皇が交代(皇位継承)するからといって、日本の政治・社会にはなんの変化もないはずです。あってはなりません。
それを「歴史の転換点」と言うのは、自民党の改憲草案にある「天皇元首化」と同様の皇国史観であり、それに乗じて自らの政権延命を図ろうとする天皇制の政治利用に他なりません。
第2に、「薩長藩閥政治」への回帰願望です。
出馬表明に先立ち安倍氏は鹿児島県鹿屋市内で講演し、「今年が明治維新から150年に当たることに触れ『しっかり薩摩(鹿児島県)と長州(山口県)で力を合わせ、新たな時代を切り開いていきたい』と述べ」(8月27日付沖縄タイムス=共同電)ました。
これを「地方重視」のリップサービスと片づけることはできません。なぜなら、明治の「薩長藩閥政治」への憧憬は安倍氏の“歴史・政治思想”の根幹だからです。
安倍氏は第1次政権時代も含め現在までに施政方針演説と所信表明演説を各7回ずつ行っていますが、その中で、「明治維新」のブレーンだった長州の吉田松陰と、薩長藩閥政治の理論的支柱となった福沢諭吉を、それぞれ2回合わせて4回も引用しています。
たとえば首相としての初の所信表明演説でこう力説しました。
「教育の目的は、志ある国民を育て、品格ある国家、社会をつくることです。吉田松陰は…若い長州藩士に志を持たせる教育を行い、有為な人材を多数輩出しました」(2006年9月29日)
さらにその翌年の初の施政方針演説ではこうです。
「福沢諭吉は…困難なことをひるまずに前向きに取り組む心(を強調)、この心こそ、明治維新から近代日本をつくっていったのではないでしょうか」(2007年1月26日)
このほか、2013年2月28日の施政方針演説で福沢諭吉、2015年2月12日の施政方針演説で吉田松陰を引用しています。
吉田松陰と福沢諭吉に共通しているのは、天皇主義と朝鮮・中国などアジア蔑視・侵略主義の結合です。福沢諭吉については先に検討たので(2月3日、3月1日のブログ参照)、吉田松陰について概観します。
松陰は「尊王攘夷」の旗頭でしたが、その思想の根底にあるのは、水戸学の影響を受けた「万世一系」の「国体」論でした。その皇国史観は、周辺諸国・他民族、とくに朝鮮への侵略と一体でした。
「松陰においては国体論によって朝鮮侵略が理念化され、それは皇国の構想全体のなかで中心的な位置を占めることになった。そして『幽因録』(1854年)ではいち早く、武備をととのえ、蝦夷・カムチャッカなどを奪い、琉球を諭して朝鮮をしたがえ、満州・台湾・ルソンに進取の勢いを示すべきだと、激しい海外雄飛の構想が打ち上げられた」(尹健次氏『日本国民論』筑摩書房)
この吉田松陰の導きを受け、福沢諭吉の「脱亜論」「帝室論」などの影響を受けた長州・薩摩出身者は、明治天皇と一体となり、朝鮮や琉球(沖縄)などへの侵略の先頭に立ちました。
「軍人集団をリードしていたのは、明治維新以来の薩摩・長州の出身者であった。軍人集団はこの二つの同郷集団によって支配されていたのである。大山巌、西郷従道、松方正義、黒田清隆、森有礼などは鹿児島県、伊藤博文、山県有朋、井上馨、桂太郎などは山口県の出身であった。…日露戦争の頃になると、これら薩長出身官僚は元老と呼ばれ、明治天皇としきりに接触する一方、閣外から内閣の政治に介入した。…日本軍国主義と天皇制は一体だと書いたが、それに藩閥政治を加える必要がある。…藩閥政府なくして明治天皇制はなく、明治天皇制なくして藩閥政治は存在しえなかった」(星野芳郎氏『日本軍国主義の源流を問う』日本評論社)
ここに名前があがった以外にも、「征韓論」の西郷隆盛、台湾侵略の大久保利通、朝鮮総督の寺内正毅(長州)も見落とせません。そもそも琉球を侵略したのは薩摩藩で、薩摩はそれによって財力を肥やしました。その琉球侵略を決定づけた「琉球処分」(1879年)で、処分官・松田道之を派遣したのは伊藤博文であり、手紙で松田を激励しアドバイスを与えたのは福沢諭吉でした。
こうした明治天皇制・藩閥政治の朝鮮、琉球侵略が今日の朝鮮半島、沖縄の現実につながっていることは言うまでもありません。
その鹿児島での安倍氏の総裁選出馬表明。皇国史観と薩長藩閥政治回帰願望が根っこでつながり、今日の朝鮮半島と沖縄に対する差別・強権姿勢を裏付けているといえるでしょう。