2012年6月25日(月) 〈続き〉
「駅からハイキング」のゴール、弘前市立観光館のそばに、県重宝の旧弘前市立図書
館がある。ルネッサンス様式の建物で、二つのドームや白壁の中に落ち着いた彩りの窓
枠が、建設当時のモダンさを感じさせる。

道路を隔てた西側は、弘前市役所。

市立観光館内部には、弘前ねぷたまつりの大きなねぷたが飾られていた。

ゴールの受付をしてもらい、館内にあったレストラン追手門で、ミニ丼ランチを注文
して昼食をする。
このあと、北側に広がる弘前公園と仲町伝統的建造物群保存地区を巡ることにして、
弘前公園の南側、追手門を入る。

弘前公園は、津軽統一を果たした津軽家初代藩主為信(ためのぶ)が慶長8年(1603)
に計画し、二代信枚(のぶひら)が慶長16年に完成した津軽氏の居城跡。広さ約49.2Ha、
東京ドーム10個分以上あり、三重の堀と土塁に囲まれていて、国指定史跡になっている。

公園内は、春の花どきに話題となる桜が多く、好天で気温が上がった今日はよい緑陰
になっている。
追手門を入ると、「弘前アイス組合」のミニ屋台でソフトアイスを販売していた。
100円だがたくさん盛ってくれ、さっぱりした味わいが暑さを和らげてくれる。公園
内の何か所かで販売していた。


レンガ積みの市立博物館横を進んで、朱塗りの「杉の大橋」を渡る。

隣接する県立弘前工業高校の向こうに、岩木山がほぼ全容を見せてくれた。


緑いっぱいの二の丸の下乗(げじよう)橋から、文化8年(1811)に再建という
天守閣を眺める。

時間が無いので観覧はせずに先に進む。


弘前市古木名木のソメイヨシノ↑や、県天然記念物王鹿石の巨岩↓、二の丸東門与力
番所などのそばを通過し、あふれるばかりの桜やモミジの新緑を眺め、北門を出た。

二の丸東門与力番所


ちなみに北門(亀甲門)は、5棟残る城門中で特に規模が大きく、形状も異なり最古
の形式だという。

弘前公園の北側一帯は、国の仲町伝統的建造物群保存地区になっている。北門を出て
亀甲橋を渡った向こうには、国重要文化財の石場家住宅がある。


城の北側の堀に沿って東へ。堀を埋めるコウホネが咲き出していた。城の東北端、交
差点際は川崎染工場の建物。「津軽天然藍染」と書かれたのぼりがゆれている。


交差点の斜前には、地元の新鮮な農産物などを販売する「ひろさき新撰組」があった。

川崎染工場の横を入って次の通りで右折して東へ。同じ針葉樹の生け垣の屋敷が続き、
独特の景観を見せる。

保存地区の東南端には、かやぶき屋根の武家住宅、旧岩田家が公開されていた。寛政
時代(1789~1801)末から文化年間(1804~18)に建てられたと推定さ
れるもの。

江戸時代後期の武士の生活を知る貴重な建築遺構の一つだという。

保存地区を離れ、駅に向かう。交差点のそばの亀甲町広場には、落ち着いた和風建築
の休憩所がある。

南進してNHKの角を曲がり、さらに進むと、東北最古のプロテスタント教会という、
クリーム色が美しい弘前教会の礼拝堂が目に入る。明治39年(1906)の建築で、
明治のゴシック式木造建築としては極めて貴重な建物と記されていた。

教会の角を曲がって南西へ。弘前郵便局前などを通過して、14時50分にJR弘前
駅に着いた。

(天気 晴後快晴、距離 12㎞、地図 「ひろさきガイドマップ」、歩行地 弘前市、
歩数 18,200)
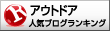 アウトドア ブログランキングへ
アウトドア ブログランキングへ
 にほんブログ村
にほんブログ村
「駅からハイキング」のゴール、弘前市立観光館のそばに、県重宝の旧弘前市立図書
館がある。ルネッサンス様式の建物で、二つのドームや白壁の中に落ち着いた彩りの窓
枠が、建設当時のモダンさを感じさせる。

道路を隔てた西側は、弘前市役所。

市立観光館内部には、弘前ねぷたまつりの大きなねぷたが飾られていた。

ゴールの受付をしてもらい、館内にあったレストラン追手門で、ミニ丼ランチを注文
して昼食をする。
このあと、北側に広がる弘前公園と仲町伝統的建造物群保存地区を巡ることにして、
弘前公園の南側、追手門を入る。

弘前公園は、津軽統一を果たした津軽家初代藩主為信(ためのぶ)が慶長8年(1603)
に計画し、二代信枚(のぶひら)が慶長16年に完成した津軽氏の居城跡。広さ約49.2Ha、
東京ドーム10個分以上あり、三重の堀と土塁に囲まれていて、国指定史跡になっている。

公園内は、春の花どきに話題となる桜が多く、好天で気温が上がった今日はよい緑陰
になっている。
追手門を入ると、「弘前アイス組合」のミニ屋台でソフトアイスを販売していた。
100円だがたくさん盛ってくれ、さっぱりした味わいが暑さを和らげてくれる。公園
内の何か所かで販売していた。


レンガ積みの市立博物館横を進んで、朱塗りの「杉の大橋」を渡る。

隣接する県立弘前工業高校の向こうに、岩木山がほぼ全容を見せてくれた。


緑いっぱいの二の丸の下乗(げじよう)橋から、文化8年(1811)に再建という
天守閣を眺める。

時間が無いので観覧はせずに先に進む。


弘前市古木名木のソメイヨシノ↑や、県天然記念物王鹿石の巨岩↓、二の丸東門与力
番所などのそばを通過し、あふれるばかりの桜やモミジの新緑を眺め、北門を出た。

二の丸東門与力番所


ちなみに北門(亀甲門)は、5棟残る城門中で特に規模が大きく、形状も異なり最古
の形式だという。

弘前公園の北側一帯は、国の仲町伝統的建造物群保存地区になっている。北門を出て
亀甲橋を渡った向こうには、国重要文化財の石場家住宅がある。


城の北側の堀に沿って東へ。堀を埋めるコウホネが咲き出していた。城の東北端、交
差点際は川崎染工場の建物。「津軽天然藍染」と書かれたのぼりがゆれている。


交差点の斜前には、地元の新鮮な農産物などを販売する「ひろさき新撰組」があった。

川崎染工場の横を入って次の通りで右折して東へ。同じ針葉樹の生け垣の屋敷が続き、
独特の景観を見せる。

保存地区の東南端には、かやぶき屋根の武家住宅、旧岩田家が公開されていた。寛政
時代(1789~1801)末から文化年間(1804~18)に建てられたと推定さ
れるもの。

江戸時代後期の武士の生活を知る貴重な建築遺構の一つだという。

保存地区を離れ、駅に向かう。交差点のそばの亀甲町広場には、落ち着いた和風建築
の休憩所がある。

南進してNHKの角を曲がり、さらに進むと、東北最古のプロテスタント教会という、
クリーム色が美しい弘前教会の礼拝堂が目に入る。明治39年(1906)の建築で、
明治のゴシック式木造建築としては極めて貴重な建物と記されていた。

教会の角を曲がって南西へ。弘前郵便局前などを通過して、14時50分にJR弘前
駅に着いた。

(天気 晴後快晴、距離 12㎞、地図 「ひろさきガイドマップ」、歩行地 弘前市、
歩数 18,200)













