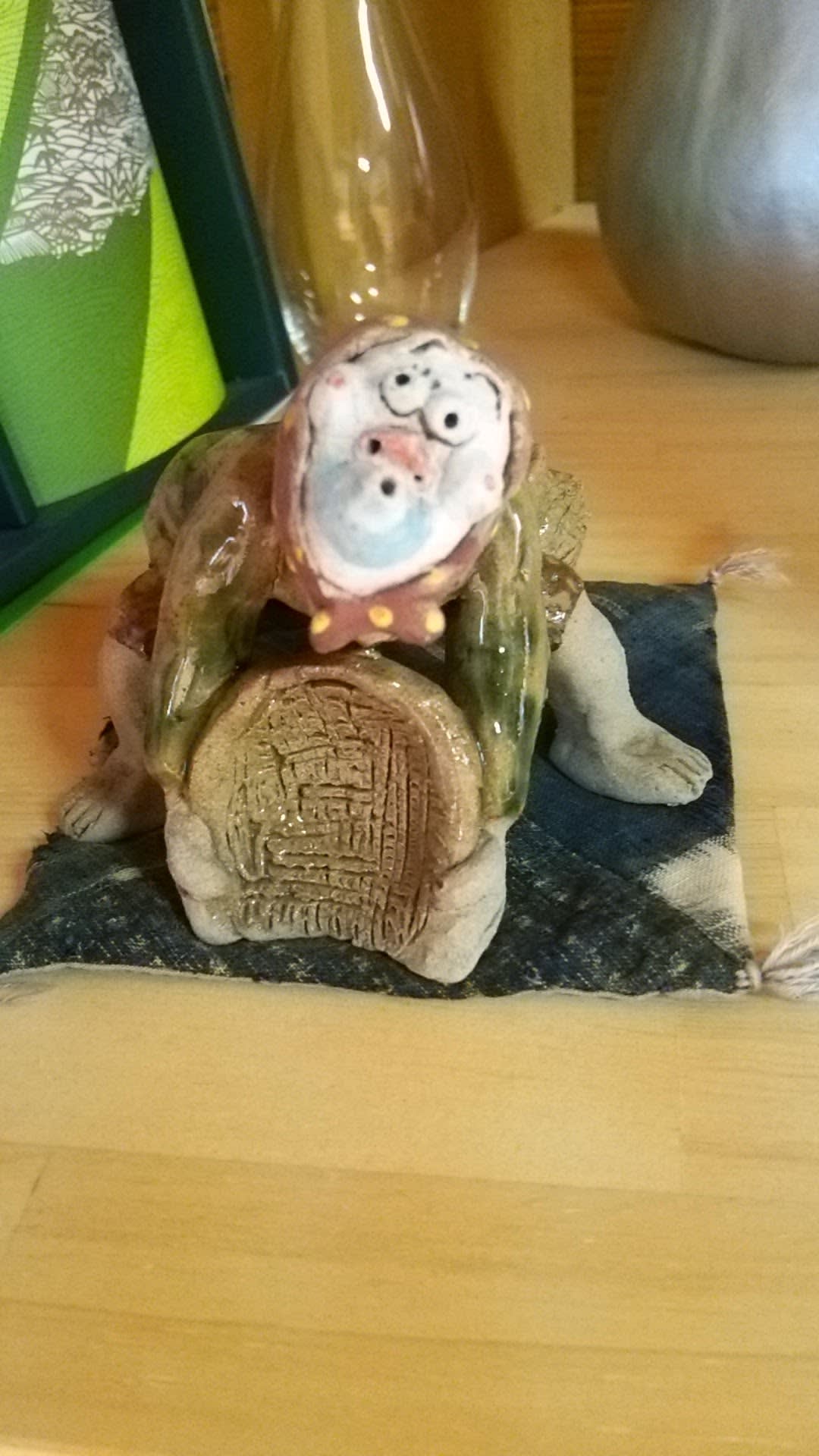本日は新暦ではあるが七夕である。梅雨で残念そうなのでこれは旧暦で再度再会を果たしてもらうこととして、さて、本日は(午後5時頃だというが)地球が太陽から一番遠いところである遠日点を通過する。地球と太陽との距離の平均は1億4960万㎞で、今日は1億5210万㎞まで遠くなるそうだ。その差は250万㎞。地球一周(場所で違う)が約4万㎞といわれるから、なんだかずいぶん遠いところまで来ていることは間違いない。太陽から遠くなるので、その分少しくらい涼しくなってもよさそうだが、はて、そんなに違いがあるのかは疑問だ。もともと1億5000万㎞あまりもの距離があることから、250万㎞の違いは2%にも満たない差でしかないからだ。改めて宇宙は広いというか、太陽はあんがい遠いというか、それでも夏は暑いので勘弁してくれというか、ともあれ地球人の実感としてはいい加減なものなのである。
本日は新暦ではあるが七夕である。梅雨で残念そうなのでこれは旧暦で再度再会を果たしてもらうこととして、さて、本日は(午後5時頃だというが)地球が太陽から一番遠いところである遠日点を通過する。地球と太陽との距離の平均は1億4960万㎞で、今日は1億5210万㎞まで遠くなるそうだ。その差は250万㎞。地球一周(場所で違う)が約4万㎞といわれるから、なんだかずいぶん遠いところまで来ていることは間違いない。太陽から遠くなるので、その分少しくらい涼しくなってもよさそうだが、はて、そんなに違いがあるのかは疑問だ。もともと1億5000万㎞あまりもの距離があることから、250万㎞の違いは2%にも満たない差でしかないからだ。改めて宇宙は広いというか、太陽はあんがい遠いというか、それでも夏は暑いので勘弁してくれというか、ともあれ地球人の実感としてはいい加減なものなのである。
スペイン人のテニス指導者が、日本の子供にテニスのコーチをするドキュメンタリーを見た。基本的に楽しんでプレーする工夫をする訳だが、その理由としては、テニスを続けてやっていくためには、楽しんでやった方が苦しみに耐えられるから。要するに長く練習に耐えられる精神力を作るためになるということかもしれない。恐らく日本の練習とは真逆の発想なのだが、これは大人にもためになる話ではないかと思った。
テニスの練習ではたくさんのボールを使う。ボールを使い切ったら、皆で散らばってしまった玉ひろいをしなくてはならない。子供たちは蜘蛛の子を散らしたように走り回って素早くボールを集めようとする。恐らく日本人のコーチからは、ぐずぐずするな、とか、急げとか怒られながら、これまで玉集めをしていたのではないか。それなのにこのスペイン人コーチは、玉集めするときに「走るな」というのだ。それぞれに歩いて集めるように指示する。これに子供たちは面食らってしまって「おいおい、走るなだって…」というように、全員動揺して戸惑ってしまう。まったく訳が分からない。いったいこの人は何を言っているのだろう。
真意としては、メリハリのようなことらしい。いつも集中してかえってその集中力を切らすより、テニスのゲームがそうであるように、長時間の戦いにおいても対応できるように、集中と弛緩をうまく利用して、精神力を鍛えるというか、そういう考え方を学ばせようとしているらしい。
また、親に対しては、試合から帰ってきた子供たちに、勝ち負けの結果を最初に聞くなとお願いする。子供たちがどういう考えで試合に臨み、そうしてそれが上手くいったかどうかが大切で、ゲームの勝ち負けはあえて重要ではないという。きっぱりと結果はどうでもいいことと言い切るのだ。親たちはあんぐり、という感じ。試合に勝つために練習しているのではないのか。試合に勝つことはいいことではないのか。
また、いわゆるチャンスボールというのがあって、確実に点を取りにいけるようなボールが来たら、今までなら確実に慎重に万全を期してミスをしない、という指導を受けていたようだ。まず、どのボールが自分にとってチャンスなのかという見極め方もあるが、その後自分がそうだと思うに至ったチャンスボールに対して、ミスをしていいから思い切りいくように指導する。これにはまた子供たちが目をぱちくり。もっともミスが許されない場面が、もっとも自分に自由がある場面なのだ。まったく真逆の教えと言っていいだろうが、その意味は確かに理解できるものではなかろうか。勝負というのは、自分が見つけるもので、そうして冒険して掴むものなのだ。
他にもテクニック的にはいろいろあったが、変わっているというより、日本人というのを今一度考えさせられる思いだった。強い人間を育てるというのは、単純な厳しさなのではないのかもしれない。たった一週間のコーチで、本当にがらりと変わるものなのかは分からない。しかし、やはり子供たちは自発的に練習をしているように見えたし、楽しんでいる。きつい練習がつらくなくなったのだ。そうして何より、これを見ていた日本人の若いコーチがショックを受けているのがよく分かった。ある意味で一番価値観が崩されたのはこの人ではなかっただろうか。これまでもいい人だっただろうけれど、これまで以上にいい指導者になって欲しいものだ。
育友会の役割を終えられた。PTAの役員をやりだしたのは、二十歳になる長男が小学2年生の頃からだから、13年ということになる。最初は青年会議所の現役でもあったし、監事だから何にもしなくていいといわれて始めたものだ。しかしながら副会長になり会長をと、段階的にハードルが高くなった。結局切れ目は作らず、副会長・会長は小・中学、高校とそれぞれやることになった。大変だったといえばそういう面もあったから、素直に卒業ということで、うれしい。青年会議所の卒業の次に嬉しい。それとやっぱり解放感。本来的にがらじゃないというのがあったから、そんなに化けの皮をはがされることなく終えられたのが良かった。いや、一度同級生の今はお母さんになっている友人から、ひとこと「(僕が会長なんて)ウケル~」といわれたことがあったくらいだった。ま、そうだよな。僕は本格的な不良とは言えないまでも、学校生活はちゃんと一貫してアウトローだったわけで、学校に関わるなんてもってのほかだったはずなんである。ま、子供のおかげで学校に写真なんかも飾ってあったりして、ウケない方がおかしい話である。
時々直接的にはあんまり言われないまでも、こういうのが好きでやる人がいるんだ、というようなことを漏れ伝わって聞こえてくると、なんとなく面白くない気分にならないこともなかったが、まあ、聞こえなきゃ平気なんだから、やることさえやればいいんだと自分に言い聞かせたりはしていた。それに役を受けるというのは、やはり人に頼まれたのを断れなかったというのが一番大きくて、要するに気が小さいだけのことである。しかしながら最初の方で、役を受けてほしいという電話をしてきたお母さんから、「基本的にはお母さん方が仕事の大半は引き受けるんで、男の人が役のところに名前があるだけでもいいんだ」ということをおっしゃった。要は表だって飾りでいいということで、そういう社会で僕の名前が役に立つのなら、人助けとしてやるしかないのかな、と思った。まあ、しかしそれでもそれなりに仕事はあったりしたわけだが…。
そういう役割ではあるけれど、小学生の頃が一番大変で、中学生は少しだけ、高校はそんなに大変ということまでは無かった。その理由としてははっきりしていて、順に先生の対応が良くなっていくからだ。小学生の先生というのは、言っちゃ悪いがかなり無責任な人たちがたくさんいる。夜の話し合いで、あんまり私語の声が大きいので注意したら先生だった、ということはざらだった。行事も教頭・校長を除くとかなり非協力的で、おれたちはいったい何をやってるんだろうな、という気分になったものだ。まあ、親なんかが学校に来ることが、素直に迷惑だったのだろうけど…。
とまあ、そういうことだが、それはそれでいいだろう。高校になると先生たちも生き生きとして頑張っている感じで、素晴らしいな、と思いましたからね。結局そういうやる気というのは、ある程度の選抜がないと湧いてこないものかもしれない。いろんな人が混ざっている義務教育下にあって先生方が疲弊するというのは、あながち考えられないことではない。そうして学校が嫌いになった人が、先生として生きていかなくてはならないなんて、それはそれでお気の毒なことである。
実をいうとブログにおいては、ほとんどPTA関係のことは書いてこなかった。ちょっと生々しい感じが好ましくなかったからだけど、距離がもてると、ちょっとくらいは考えていることくらいは書いてもいいかもしれない。ともかく、楽しいこともたくさんあったのは事実で、おかげさまでありがとうございました。
追伸:つれあいから指摘があり、長男が3年生の時からと判明しましたので、12年間ということになりそうです。謹んで訂正致します。
主人公の男は、ちょっと内気で好きな女の子に告白ができない。ただ、自分がピアノを弾いているときにピアノに寄りかかって歌う彼女が好きなのだ。時は流れて紆余曲折あって、男にも性行を伴う程度の付き合いのある女性などとの経験は経る。それでも離れている間にあっても、高校時代の彼女のことは思い続けている。彼女の父親は弁護士で、代理結婚のバイトを彼女とその友人である男にさせている。日本ではそういうことは無いからわかりにくいかもしれないが、米国の州によっては、離れている者同士が結婚しようとしてもそれが制度的に認められないということがある。たとえば戦争などで片方が遠方にいても結婚できるようなこと。しかしやはり宗教的に神の前で誓いを立てなければならないので、そういうカップルのために、代理の人間が誓いの宣言をして神に婚姻を認められるという儀式を行うわけだ。そういう関係で本当に時折彼女とは自然に出会う機会があるわけだ。しかしやはり告白はできず、そうこうする間、彼女は他の男と結婚し、そして離婚する。そうして久しぶりに以前のような代理結婚の役割をやってくれないかと持ちかけられることになる。今の流行のスカイプで、その状況を依頼人に中継することになる。今まではあくまで代理だから、誓いの言葉を交わして終わっていたのだが、代理人からせっかくだから結ばれるキスまでして欲しいといわれる。そうして二人はキスを交わす。男の方はいまだに彼女のことが好きだから、そのことで耳が真っ赤になってしまう。そこで初めて本当の気持ちが彼女にもわかるわけだ。どのみち気持ちがばれてしまったのだから、そうしてやっと踏ん切りがついて告白することができたということだ。
実は今もそうなんだけれど、この短編小説を読んでいて、本当にもうなんだかわけがわからないくらい涙があふれてしまう。泣けて泣けて仕方がないのだ。涙が止まらなくて困ってしまうのだ。本当にいじらしいくらいストレートな恋の物語なんだけど、これはもう身につまされるということなんだろう。まあ、僕は特に内気な人間じゃないから、いつまでも告白できないということは無かったのだけど、気持ちの上ではよくわかるということですね。内気な男の人がこれを読んでいるかわからないけど、ある程度思い続けられたのであれば、やはり気持ちは言った方がいいんじゃないかな。
演技のことはよく分からないのだけど、泣き方の上手な人というのはやはりいる。人間には共感があるから、泣いている人をみると泣ける。泣くのが上手だと演技が上手そうに思えることもある。見事な泣きっぷりで株をあげる人もいるのではないか。
子役はこれがなかなか上手い。瞬間湯沸かし器というのは聞いたことがあるが、瞬時に泣けてしまうような子役がいる様だ。子供は泣くのが商売のようなところがあるから、これはそれなりに備わった機能なのかもしれない。むしろその後だんだん泣き方をセーブするような生き方を選択していくのではないか。もっともむっつり泣かない子というのもいるから、しかしそういう子は可愛げがないというような評価を受けそうだ。そんなことを思われるという事自体がなんだか可哀そうだが。
泣く秘訣として、飼っていたペットが死んだことを思いだして泣く、というのは若い女優さんなどには定番だ。確かにそれで僕でも泣けそうだ。僕はすぐに泣くので演技が上手いのかというとそんなことは無いが、演技として泣いたことは無いからよく分からない。ためしに今歴代ペットが死んだことを思いだしてみたが、特に涙は出ない。悲しいが、しかしこういう実験ではなかなかうまくいかない。女優さんたちはある程度の緊張感の中それが出来るという事だから、やはりある程度の鍛錬を積んでいるという事かもしれない。
しかしながらテレビかなんかで見た気がするが、泣く場面というのはほとんど目薬を使っているという事だった。その場面だけだったら目薬してすぐにカメラを回せば、ポロリと頬を伝わる涙、という展開になる。インタビューなんかでは、本当に嘘ばかりとは言えないが、自分は泣けますというアピールもあるのかもしれない。撮影には撮り直しなんてものもあるから、何回も何回も撮り直しみたいなことになると、いい加減うんざりして涙が枯れてしまうとか、それとも怒りが爆発するようにことになってしまうのではあるまいか。怒りでも涙が出る場合があるから、そうなると一石二鳥だが。
それにしても演技で泣けたら、それは褒められることになるが、実生活で嘘泣きがばれたら、それなりに怒られるだろう。ちょっと前にそういうような地方の政治家がいたわけだが、あれは実際泣いてたんだろうか。僕にはちょっとよく分からないのだが、あれが出来るような人というのは、実はやはりそれなりの才能のある人ではないかとは思った。今はどうしているんだろうね。まあ、どうでもいいんですけど。
僕は無駄が多い割にせっかちなところがある。野球や相撲などのスポーツ観戦は大好きで、テレビでやっているとついつい熱中して観てしまう。見ているときに話しかけられても内容を理解できないことがある。そうやって熱中して見終わると、なんだかその時間が浪費されたような気分になる。熱中してしまうから、その時間がすっぽりと無くなるような、いわばいつの間にか時間が経過したように感じるのかもしれない。
働き出した頃、夕方に相撲があると、配達の車から降りられなくなったりした。ただ、相撲なら勝負が早いので何とかなるが、日本シリーズのように昼間に野球の試合をやられると困ることになる。気になるんだから仕方がないが、仕事に支障をきたすわけにはいかない。相手もあることだから、自分のわがままは通るものでは無い。
それで、いっそのこと見ないことにした。時々気持ちが揺れたが、一定期間我慢するとそれなりに慣れる。その上シーズンオフだってあるんだし、本場所だって二か月に一回だ。
しかしながらそういうことになって新聞で試合を確認するだけになると、あんがい選手たちの名前を本当に音で知らないという事ある。四股名は読みにくいものが多いし、野球選手というのは、どういう訳か変わった名前も多いものだ。時々本当に時間があるときに、たまに何かの間違いでテレビをみると、そのように知らない音としての名前を聞いて、ちょっとさびしい気持ちになる。もうずいぶん僕は知らないことを増やしてしまったな、と思うのである。
ところでしかし、駅伝やマラソンは録画してでもとにかく全部見る。早送りすることも無いではないが、これは流れを見ないことには面白くないからだ。野球や相撲は慣れがあって、試合結果だけでもなんとなく我慢できるようになったのに、マラソンはそういう訳にはいかない。苦しんで何度も駆け引きがあって、そうしてギリギリのところで勝負がつく。誰だって人より早く前に行こうとしているが、苦しいのでそれが出来ない。そういうことがわかるから、いや、そういうことは見ていないとわからないから、流れを見ないことには面白くない。
僕は特に意識はしてなかったが、サドかマゾっ気というのがあるのかもしれないな、と思う。その苦しんでいる人達の姿を見て、時々涙を流す。ほとんど馬鹿みたいだけど、本当に泣ける。
不思議なことにフラフラになって倒れそうな選手では、特に泣けない。お気の毒だとは思うけど、頑張ってくれとは思うけど、泣けるという事には少し違うようだ。
本当に泣けるのは、苦しんで粘ったけれど結局は勝負に負けて、そうしてインタビューなどで、さばさば話しているような選手なんかだと特に涙腺が緩む。そういう言葉の中に実は悔しさがあるはずで、悔しがって無いように見えても、さらに泣けてしまう。こういうのは、どういう共感なんだろうね。僕にもよく分からんです。
最近は猫のことをFBにおいてシリーズで書いている。猫本を読んで驚いたところを再編集して、私見などちょっと入れたりする。身近にいる猫だが、あんがい知らないことも多くて、改めて身近な動物と言えども知らないものなんだな、と思う。
ところで、短い言葉ではなかなか伝えにくいことがある。犬猫は人間に愛されて広くペットとして飼われている訳だが、多くの人が知っている通り、多くのペットたちは、公然と捨てられ、一部保護されるにしても、実にたくさんの命が捨てられ殺処分されている。推定ではざっと犬が10万弱、猫が20万以上といわれている。数十年前には100万頭以上殺処分されていたといわれ、その数は確かに減ってきているとはいえ、実に恐るべき数字である。家畜で人間が食べるために殺しているのではない。生まれてきたものを単に殺している事実を前に、何も考えない人が果たしているものなのだろうか。
犬の場合も問題が無いではないが、特にポイントを絞って考えるべきなのは、やはり猫である。もっとはっきり言うと野良猫問題だ。犬は事実上人間社会では、もしくは都市社会では、野犬としては生存が許されていない。特に日本では野犬は徹底的に殺処分され、事実上絶滅した。
ところが猫の場合は、少しあいまいな立場がある為、野良猫は相当数存在する。猫は特に人間に危害を加える恐れが少ないために、ある程度ではあるが、放置されるためだ。また猫は野良でもあいまいな立場で、半野生で生きていくものもそれなりに多いとはみられる。
しかしである。実際の野良猫の生存率というのは、実は結構厳しいものがある。一定数は野生下では生き延びられず、均衡を保って、地域で生き延びているということだ。その数がどの程度が適当かは人間も決められないことだろうが、自然下という考えでは、極力介入せずに保護する考えが必要になるだろう。
すべて前置きだが、しかし野良猫にも人間がやはり色濃く関与している実態があるわけだ。
猫がかわいくて餌をやる行為については、単純に咎めることは確かに難しい。野良ながらになんだかなついて、寄って来れば餌をやるくらいに、目をとがらせるべきことでは無いかもしれない。人間にも事情があって、例えば一人暮らしのお年寄りが、庭に遊びに来る猫の姿だけを心のよりどころにしているというような人に、何かをいう事が果たしてできるかという事も考えないわけではない。
ところが猫というのは、栄養状態が良くなれば、途端に繁殖能力が増すことがわかっている。普通、発情期は年に一度で、さらに生存率から考えて、そのうち3匹も生き残ることは稀といわれている。ところが人間から定期的に餌やりを受けて栄養状態が飼い猫並みに改善されると、発情期は年に2回、3回と増えるらしい。また生まれる個体も増える。生存率も上がり、さらに倍々で爆発的に増えることがある。最初はやせ細った野良猫が一匹遊びに来ていたものが、続々と仔猫を引き連れて現れるようになるはずだ。そうなると一気に近所から苦情が寄せられるようになり、結局は保健所が出動して捕獲・殺処分という流れになる。人間の介入による自然界の秩序というのは、実に簡単に崩れるものなのだ。
さらに問題だと思われるのは、それでもそういう原因の意識を持つ人というのは、実に稀だという事だ。誰も悪くないのに、猫の死体だけは増えていく。それは本当に不毛なことでは無いか。
もっともっと悲劇は続く。実際に殺処分にあたっている人間にも、感情があるという事だ。多くの獣医を含め動物関係に携わっている人間というのは、実は子供のころから動物が好きで、少しでも多くの動物にふれ、さらに少しでも多くの動物の命を守りたいという思いを抱いてこの世界に入ってくるのだ。しかし現実は主に動物の死刑執行人である。これほどの悲劇というのはそうそうあることでは無い。そのような人を救済することは、人間社会としても必要なことになるのではないか。
野良で生きる猫たちの可愛さに、ほんの少しだけふれているという感覚が、実は裾では大変に大きな、そして解決の難しい問題とつながっている。大げさな話なのではない。それは、単純な想像力があるかないかの問題なのだ。そして人間には、自分で考える力があるはずなのだ。
悲劇の連鎖を断ち切るのは、実は小さな行動一つだという事を、やはり啓蒙して知ってもらわなければならないのである。
尋常でない仕事を残した完全主義者の手塚治虫だが、激しい嫉妬心をあらわにしたことでも有名である。次々に現れる新しい才能に嫉妬し、時にはその嫉妬ゆえに過当に批判し、人々を困惑させた。偉大な手塚の負の側面、ダークサイドとして語られることの多い手塚の性格であるし、手塚の生前には知る人ぞ知るという話であったため、死後しばらくたってぼつぼつとあらわれてきたこれらの逸話について、驚いた人も多かったのではなかろうか。明るい笑顔を絶やさず、しかしすさまじく忙しく仕事をこなした超人手塚と、そのイメージはあまりにもかけ離れていると感じる人も多いのかもしれない。また、世界に誇るマンガの神様としての手塚という、誰も異論を唱えることのない人物像に、影を落としていると感じる人もいるのかもしれない。
しかしながら僕の感じる手塚像として、これはさらに手塚の人間的な偉大さの土台のような気がしてならない。激しい嫉妬心は、自分の自尊心の表れでもあろうし、さらに成長したいという願望でもあったろう。あくなき探究心と、そうして自分自身に対する素直な評価と葛藤、そうして誰よりも先んじて前を歩いていたいという焦燥感もあったであろう。そういう人間的な部分を持っているからこそ、本当に人間的なドラマを生み出すことが出来たわけだし、自分の殻を破る挑戦の繰り返しにも、自分自身を変革させうる柔軟性にもつながったのではないだろうか。
さらに手塚が偉大なのは、嫉妬心に駆られて、心無い手紙などを書いてしまった後に、相手に詫びに出向いたり、内省することを書いたりしていることである。衝動的に抑えられないほどに感情を露出してしまった後に、開き直ることなく、そういう自分に向き合い、反省する勇気を持っていたということなのである。これこそが、普通の人間にはなかなかできない素晴らしさだという気がする。嫉妬心というのは誰でも抱く感情であるし、人々はそのために時折ひどく失敗もする。しかし内省するにおいて、そのことに素直に向き合えることは、あんがいに難しいことだったのではなかろうか。そういう自分と向き合う前に、逃げ出しくなる方が自然なのではないか。ましてや既に名声を手にしている立場の人間が、謝罪したりする行動までとれるものではない。子供っぽい感情と行動をとりながら、しかし理性的にも自分を眺める力を持っていたということが人間手塚の偉大なところで、そういうところが作品に反映されなかったはずは無いのである。手塚治虫の人間的な嫉妬心とその克服があったというのが、手塚の真に偉大な勇気の持ち主だった証であると思うのであった。
白鵬があの大鵬とならぶ32回目の優勝を果たした。まさに偉大な記録であるし、本当に歴史的な大横綱が生まれたと言っていいと思う。その時の事情はたいして知らないが、大鵬が32回の優勝を果たしたときは、怪我に悩まされた後に復活して成し遂げられたというし、その後ほどなくして引退したということであるから、いまだに全盛を極めている白鵬とはまるで状況が違う。取り口を見れば歴然とわかることだが、力が強いというだけでなく、相撲の上手さや切り口の速さは素晴らしいものがあり、間違いなく角界では現在でも最強である。年齢はいまだに30前ということで、ひょっとするとまだ相撲自体は上手くなる可能性さえある。休場もほとんど無く、金星の配給も少ない。優勝する力があるままどれくらい土俵に立てるのかということだけが課題と言え、それが少なくとも数年、もしくは5年以上続く可能性すらあるかもしれない。本人の美学で引退するという可能性のみということもいえ(もしくは大けが)、大記録は今後伸びると考えるほうが自然だし、おそらくそうなっていくだろう。まったく偉大というか凄すぎという大横綱なのである。
この状況を、周りの力士の不甲斐なさと批判する向きもあるようだが、まったくの見当違いだろう。歴史的なタイムリーさということもあるが、歴代の名横綱が揃っていたとしても、白鵬の強さには揺るぎのないものがあっただろう。もちろん強くなりだしたころに朝青龍がいたということも大きいだろうし、朝青龍がまだまだ相撲が取れたのにかかわらず世論の圧力に敗れ事実上引退追放になったということも大きいとは思われる。白鵬が大横綱になったことは間違いなかろうが、少なくとも優勝回数においては、後数年は遅れて達成されるということになったかもしれない。
白鵬が強いのは間違いないが、今の他の二人の横綱についても、強いことには間違いが無い。大型化する角界にあって、特に軽量でありながら上り詰めた相撲の上手さがあり、力強さもある。白鵬が強すぎるということは言えても、彼らが特に弱い横綱だということは言えない。
また、日本人力士が居なくて寂しいという感情は、少しは分からないではないが、入門制限があってもともと数が少ないにもかかわらず、ちゃんと確実に強くなるモンゴル人勢力の事を思うと、差別を受けながらも各界の圧倒的な存在感を示しているわけで、ふがいないどころか、何とか政治的配慮で生き残っている日本人がいるということが正しい認識と言えて、寂しいどころの話なのではない。
もっとも相撲というものを極めているモンゴル人力士という偉大さもあって、まさに今こそ相撲という素晴らしさを見ることのできるしあわせを普通の相撲ファンは感じているものと思う。このような時代にこそ次の新しい強さが生まれえるわけで、今後もさらに楽しみは増えている。事実、これ以上の強さが無ければ、角界ではのし上がれない。今の時代に生きていることは、そのような真の意味での高みをタイムリーで体験できることに他ならない。偉大な横綱が生まれたことは、同じ時代に生きた人間に、そのような体験を共有させるということも意味するのである。
子供を褒めて伸ばそう、という話は実に一般的で、共感の強い方針という気がする。しかしながら現実は…、というのが実情なのではないか。褒めて伸ばすのが難しいから、もしくは本当に信じられてはいないから、実際には褒めて伸ばされている子供は少ないのではあるまいか。
さらにスポーツ界の実情というものがある。クラブ活動などで強豪といわれるチームでは、指導者の力量で左右される要素は強そうだ。また、強い子は(親は)、そういう指導者を求めてチームを移動したりする。まあ、それについては合理的行動といえるが、そのような強豪チームの練習は、当然ながらそれなりに厳しい。まったく褒めていないとは言えないが、強豪チームの指導者というのは、教育の名のもとに、実に素晴らしい指導のできる人が多いように思う。僕はもともと体育会系出身だから実情としても知らないわけではないが、優れた指導者の多くは、やくざだって近づきたくない迫力の人が実在する。そういう人に喜んで子供を預けているんだから、親は不安ではないかと思うのだが、やはり結果がすべて。実際にそういうチームは、全国的に常勝だったりするんである。
まあ、考えてみると、成長期の子供で、運動能力の高い子が、多少やんちゃな性格であるほうが自然といえる。力を持て余しているような子というのは本当にいて、実際そういう子と言うのは、指導がよかろうが悪かろうが、実にぐんぐん才能を伸ばすものである。僕なんかは後輩からどんどん抜かれる体験が多いからよく分かっているが、やはり運動能力や性格の悪さというのは、スポーツが強くなる必須の条件のように思う。また、疲れても食欲が落ちないような強靭さがあるから、厳しさにも耐えられるわけである。
要するに、子供だってまともに付き合うと、それなりのパワーを必要とする。厳しい指導でそれにあたるのは、当然といえば当然。合理的といえばそのようなものである。時々行き過ぎた指導で叩かれる指導者がいるが、誤解を恐れずいうと、単に周りが隠し切れなかった氷山の一角に過ぎないだろう。
という前提が長すぎたが、僕はあるドキュメンタリーを見て、正直かなり驚いた。本当に褒めて伸ばしているのである。そういう人がいたのである。そうしてそうすることで、本当にぐんぐん子供たちが上手くなったのである。それも実に競争の激しい、少年サッカーの話なのだ。
結構前に見たNHKの番組で恐縮だが、BSで「奇跡のレッスン」というものだった。その指導者はスペイン出身のフットサル日本代表監督のミゲル・ロドリコさん。子供の指導は一日2時間、それを一週間だけなのだ。
最初は練習を眺めるだけ、もちろん今までの練習を見て瞬時に問題を把握し、一週間の残りの時間を自分の指導通りにするだけのことなのだ。
驚くのは、実にすぐに変化が現れたことだ。課題をどんどん出して、変化を付けて、外国人としての大袈裟さはあるが、ポンポン褒める言葉を発しながら、まさに子供と一緒に遊んでいるようにさえ見える。そうして求めているのは、素早く自分で考えて、自分なりに答えを出すこと一点なのだ。今まで指導で禁止されていたような法則めいたやり方は一切ない。サッカーのセオリーと思われるような行動も、ことごとく否定してしまう。今まで指導してたコーチたちも、まさにあんぐり、という感じ。でもそれは否定される怒りや呆れではない。子供達がぐんぐん力を付けるその姿に、衝撃を受け感動しているのだ。
テレビ放送ということもあるかもしれないが、そういう子どもたちの練習を見に、親たちも駆けつけるようになっていく。お父さんたちまで、仕事を早く切り上げて、練習を見ようとするのだ。そうしてミゲルさんは、そういう親たちを集めて、家でも褒めるやり方を伝授する。子供を叱らなくてはならない場面においても、どのように接するか細かく質問にも答えていく。親として本当にそういうことが出来るか半信半疑の人もいたことだろう。しかし、やはりのびのびとサッカーに打ち込む子供が、目の前に証明としているのだ。
いろいろエピソードはあるのだが、なんと指導を受ける期間中に家族旅行を計画していた親子がいたのだが、そのサッカー少年だけはどうしても練習に出たくて旅行をキャンセルしてしまうのだ。ミゲルさんの指導が楽しくて仕方がない。そうしてもっとサッカーが上手くなりたいに違いないのだ。
自信の無かった子供は自信をつけ、横柄で自己中心な少年は献身的なプレーに目覚める。相手のプレッシャーにも平気になり、予想もできないトリッキーなプレーまでできるようになっていく。
一週間後に地元の同レベルのライバルチームとの試合をする。ここまで書いて結果がわからない人がいるはずがないと思うが、これこそがまさに奇跡の試合なのだ。
このドキュメンタリーは、絶対に再放送すべきだと思う。僕はミゲルさんに会いたいと思う。そして、そういう指導者に若い頃に出会いたかった。僕は過去に戻りたいと思うよう人間ではない。そういう僕が、少年に戻りたいと思ったのである。もちろん、ミゲルさんに会うためである。なんだか混乱して訳が分からないだろうが、これが真の「褒めて伸ばす」素晴らしさの、生きた証明だろう。
朝の連ドラも終わっているので少し間抜けな話題かもしれない。それに本当に僕は熱心に注目して見ていたわけでもない。というか、ほとんど見てない。花子と村岡との恋愛のところだけマンガみたいに面白がってみたくらいで、正直言ってたいしてスジを知っているわけでもない。
そうではあるが、村岡花子に興味が無いわけではない。本当はそんなに前から知っていたわけではなかったが、ちょっと変わった翻訳家だという話は聞き及んでいたような記憶がある。おそらく誰かのエッセイに紹介されていたのだろう。そうしてやはりこのドラマが始まってから、関連するお話を、また時々目にするようになった。当然だけれど、原作になっているお話と、ドラマの花子はかなり違う人物になっているとは聞いていた。そういうものなのだから、それはそれでいいだろう。もとにするというのは、もとにした創作だということに過ぎない。しかしやはり、実際はどんな人かな、という興味の方があるにはあって、それはほかならぬ「赤毛のアン」の所為だろう。
僕はなぜか独身時代に、赤毛のアンのアニメに見はまって、毎日のように泣いていた。こんなにも泣ける物語があるとは本当に知らなかった。そうして実はあとから村岡訳の赤毛のアンは手に取ったのである。しかしなんというか、ちょっとだけ読んでもピンとこなかった。それで後に知ったが、このアニメの底本となった訳は神山妙子という人のものと知る。それでというか、村岡花子という人は、あえて赤毛のアンについて、妙な飛ばし訳をしているということも知ったのである。いろいろ事情はあろうけれど、日本の子供に読んでもらうためには、その方が良いという考え方があったためらしい。
村岡花子の生涯の、おそらくかなりの影響力があったらしいのは、父の存在であるように感じられる。かなり変わった人のようだが、それもやはりキリスト教の影響があるものと思われる。外に子はたくさんいたが、長女である花子に特に目をかけて、教育を受けさせる。東京に移り住み家族は貧困に苦しみ続けるが、それでも何とか花子にだけは最後まで期待を寄せていたようだ。花子としてもその期待に応えたいという思いもあったろうし、西洋教育とキリスト教の影響も、やはり強く受けただろう。そうして世の中は戦争に突入し、様々な思惑がありながらも翻訳を続ける強さがあったことも間違い無いようだ。
村岡花子という人は、キリスト教的な強さを持った面(信じる物を曲げない)も持ちながら、しかし同時に当時の理想との乖離のある日本の女性像や子供についても、ある程度の理解のある人だったようだ。だからこそ、その当時の人間にちょうど合うように、翻訳を試みたのではなかろうか。それは正確な翻訳というものでは必ずしも無いのだが、しかしだからこそ、その当時の人々の心も捉えることが出来た。さらに結局は、日本においてもこの物語が長く受け継がれるものになったのではなかろうか。
赤毛のアンは、確かに子供の物語である。それも純粋に子供の持っているすさまじい能力が、何気なく発揮されている物語だ。大人ではその能力がすっかり失われてしまうわけだが、しかし、だからこそマリラやマシューは、アンに影響を受けてしあわせな気分になれるのだ。それを読む多くの人は子供なのかもしれないが、しかしやはりマリラやマシューのごとく、大人になって読んだ人の方が、その影響力を強く受けるのではないか。それを翻訳の力で、やはり日本の子供に最も伝えやすくするにはどうするか。村岡花子の考えと訳は、そのようにして生まれたものなのではあるまいか。
結局僕は、村岡花子のよき理解者ではないが、村岡花子が開拓した後の社会で、長く生きながらえたアンの姿に感動させられているわけだ。不思議な縁だけれど、もう少しさらに年を取ったとき、また影響を受ける可能性もあるように思える。それが大人の失う力であるからだ。アンに出会えた人間は、影響を受けざるを得ない。そのことを、やはり知っていた人物だったことは間違い無いのである。
なんだかワールドカップが開催されていたこと自体が、かなり遠い過去のような気分になっているのだが、総集編などをビデオ録画などしてあって、ちゃんとふり返ることができると、それなりに冷静に過去を俯瞰することができるようになった。終わった後は寂しさとともに、日本やブラジルの負け方などに影響されて、なんとなく後味の悪いものを残したような感じもあったものだったが、今になって見るとそれなりに順当に強いものが勝ち、さらに優勝においても一番予想通りドイツのものになったということもあり、やはりこの世界はこの世界だったというようなものになっているのが不思議である。こうして日常を取り戻し祭りの終わりを眺めると、人々は少しだけ肌の脱皮したような感慨にふけるものなのかもしれない。
さて、試合のほうはそうだったのだが、実はワールドカップで一番印象に残ったのは、他でもなくドイツの優勝後にグランドになだれ込んできたような美女集団の姿だったかもしれない。他ならぬドイツ代表選手たちの奥さんや恋人たちということだったのだろうけれど、皆選手にぴったりと寄り添い、恐らく愛を語り合い、喜びを分かち合っている様子だった。勝った瞬間は文字通りチームと観客と一体化して喜びを爆発させていた人達が、いっせいに個別に散らばって個人の喜びを一番親しいものと分かち合うという姿に変貌した。それを見せられている僕らは、なんともいえない違和感と衝撃を受けたという感じだった。それが悪いとはいえないのだが、日本にサッカー文化がどうだとか言う前に、決定的に何か違う文化圏のものの中でやっていたという現実を突きつけられたということになるのだろう。もちろん日本だって優勝するようなことになると、同じように美しい女性をピッチに上げるに違いないのだが、しかしながらそれは完全に日本文化ではなかろう。真似をしているだけのことに違いなくて、若い選手が多いからそれなりに絵になることだろうけれど、日本というチームの勝利感とは違うものになるのではなかろうか。いや、それは夢のようなことで、現実になるにはそれなりに文化が馴染んでいるのかもしれないが…。
さらに気になったのは、恐らくアルゼンチンの恋人たちも、ひそかに待機していただろうことかもしれない。無駄になってしまったけれど、十分準備は怠っていなかっただろうことを思うと、悲しいというより少し恐ろしい。南米の場合だったら、もっと飛び跳ねたりして大変だったかもしれないが、それはそれで楽しいものだっただろうに…。
しかしながらサッカー選手はもてるだろうからいらぬ心配だが、そういう人がいない人やちょうど喧嘩してる人なんかは肩身が狭い思いをするんだろうか? こういう習慣は自然なようで、かえって不自然な憶測をたくさん呼ぶという感じもする。なんだかみんな大変だなあ、という気がするんだけれど、これでいいのでしょうかね。まあ、ほんとにこんなものなのか、四年後も楽しみにいたしましょう。
スーダンからの盲目の留学生でアブディンさんという人がいる。詳しくはググッて欲しいのだが、日本語も完璧で非常に聡明な方のようなのだが、何よりその境遇もあってか、面白い人なのだった。ところが、そんな風に見ていると、「面白い障害者」という風に見られていることに、なんとなく不満のようなものを持っているらしいことも分かって、少しドッキリした。要するに、面白い障害者という視点が無いと、僕らは興味を抱かないということなのかもしれない。反省すべきとも思うが、まあ、ジャーナリズム的に表に出ると、そうならざるを得ないわけだ。そうした点は考えさせられるわけだが、しかしそれでも繰り返すが、面白い人なのだ。
既に日本に16年くらいいるらしい。スーダンで法学を学ぶ学生だったようだが、奨学金などをつてに来日し、現在は東京外語大で研究者として学んでいるらしい。ドキュメンタリーでは高学歴でも就職が決まらずにピンチに陥っていた。これだけの人ならどこかの学校が採用すべき人材だと思うのだが、壁は高いということなのだろう。
目が見えないので音でいろんなことを捉えているわけだが、まちの様子だとか人の感情だとか、実にたくみに物事を見ているものだという感じがする。日本人がどんな人たちなのかということも、批評性に満ちていて面白い。冗談も頻繁に言うし、基本的に楽観主義者のようだが、しかし、現実に不満が無いわけではなかろう。なんと日本でスーダンから女性を呼び寄せて結婚し、ふたりの娘がいる。助成を受けながらの生活で、いろいろあるとは思うが、このままでは卒業後スーダンに帰らなければならないかもしれないらしい。日本で就職が無ければどうにもならない崖っぷちだが、スーダンに帰っても職があるものなんだろうか。いや、ともかく大変に努力している風でもあり、何とか日本に留まって生活できる道が開けることを祈るばかりだ。
本も出版しているようだし、ツイッターでも人気である。ざっと見る限り文才もなかなかで、この分野でも幾分の活路があるのではないか。
録画していた放送を見て気になって仕方ないのだけど、その後どうなっているのかは不明だ。ツイートでは最近は広島カープの話題だった。確かにタイムリーだが、将来は分からない。
いろいろ苦労しているだろうことと、やはり障害があるということで僕に同情の気持ちがあることは間違いあるまい。しかしながらその努力もさることながら、スーダンからの盲目の博士でダジャレも上手いとなると、それはそれで十分キャラが立っているという印象もある。それでも就職したり、タレントとして生きていけるかは、本当に微妙な問題になってしまう。
しかしながら、それでもアブディンさんが本当に偉いなと思うところは、やはり自分の勉強した専門分野で勝負したいという思いが強いことかもしれない。葛藤があることも分かるし、現状の苦しさに負けそうな気分というのも伝わっては来る。本当に厳しいということは恐らく本人が一番分かっていることなのだろう。そうではあっても、自分の専門を生かしていきたいという姿勢を崩さない姿こそが、本当に感動の人という気がする。もちろん、適当に肩の力も抜いているように見えるが、たぶんそういう人なのだろうと思うのだ。僕にとって、今もっとも日本にいて欲しい人材なのであるが、本当に将来が心配なことなのである。
僕は普段はテレビは批判ばかりしている。じゃあなんで見るの? 問題はあるが、テレビは見るものなのである。で、やはり録画して見る。
その録画する番組の9割9分はNHKなのである。報道は最悪の偏った思想が癪に障る放送局だが、いいものは、というより見たいものは、これに集中しているためだ。
で、コウケンテツを見る。よく泣く人だよ。でもそれで、もらい泣き。よく分かるんだよね。今は以前のアジアの旅の焼き増しだけど、コウテンケツは素晴らしい。いや、現地の料理が素晴らしいのだが、コウケンテツの涙で、その素晴らしい味が分かるのだ。本当は日本人の口に合うようなものではあるまい。でも、この味は、涙が出るような人でないとわからない味なのだ。本当に素晴らしい旅とは何なのか。そういうことを考えながら見ている自分がいるのである。
ほかに欠かさず見ているのは数多いが、「デザインあ」も素晴らしい。
僕は見ていて時々やはり泣きたくなる。それで思い出すのはコウケンテツ。通じるものがあると思う。それが何かは良くわからない。でも、その視点の多くは似ているものがあると思う。こういう番組を、いわば面白がって作っている現場がある。そういうこと自体が、いいなあ、と思う。そして泣きたくなるのかもしれない。
それは、やはり本当には王道ではないかもしれない。でも、ちゃんと同じようにいいと思っている人が多いからこそ成り立つ世界ではないだろうか。そういうものを信用できるから、何とか僕もバランスをとって、生きていこうかな、という勇気がわく。大げさだけど、そんなような感じが僕のテレビの時間ということなのかもしれない。
箱根が終わった。終わってみるとおおかた戦前の予想通りのようにも見えるが、東洋の圧倒的な強さが目立ったということも出来る。実際ここまで強いとは予想できた人は少ないだろう。駒沢は4枚看板の3枚を最初に使って逃げ切りを図ったが、思うようには伸びなかった。それが最後までということは確かに言える。言えるがそれでもやはり底力があってかなり高いレベルの記録での2位。普通なら完全優勝なのに東洋が強すぎたのだ。
レベルが高いというのは確かに言えて、昨年優勝した日本体育大学の優勝タイムは11時間13分26秒だったわけで、今年9位の拓殖大学でも11時間13分06秒であることからもそれは見て取れる。考えようによっては多くの大学がこのレベルまで持ってくることが可能になっているということで、東洋・駒澤という双頭の龍(プラスα)がいるとはいえ、完全に次の段階にきているという感覚は各大学の関係者は感じていることだろう。現実的に考えて、留学生の大砲を持たずにトップがいるのだから、まだ伸びしろがあるのは確実だ。
しかしながら山の神様というような存在がいなくても、どの大学もかなり山に対しての強さが見られたこともあるように感じる。一昔前なら皆素晴らしい記録が並んでいるが、飛びぬけているように見えないからだ。柏原というのは歴史的に凄過ぎる訳で、そう簡単には次は現れないかもしれない。そうすると、今のレベルまで近づけば(それも簡単ではないが)、面白い組み立てが十分できるということだ。山のみ制すれば済む問題ではもちろんないが、そのウェイトにおいては、少し対応可能な手ごたえを感じているところも多いのではなかろうか。
それにしても一昔前のことを考えると、その水準は格段にあがっている。そういう練習の方法が確立されてきたこともあるだろうし、逸材がこのような注目されるレースに出られるようになったことも大きいのだろう。そのままマラソンに必ずしもつながっていない懸念は残っているが、これだけの関心が高まったことが、本当に底上げにつながっていることは間違いなさそうである。お正月にローカルだけどこのようなビッグレースがあるというのは、若い長距離ランナーにとっては、オリンピックなどの様に超一流しか駄目な世界を目指すより、より現実的で素晴らしい体験なのかもしれない。