
相変わらずデジカメ散歩だけは続けているのである。今日は渋谷から歩き始めた。青山通りを表参道から左折して神宮外苑まで足を伸ばした。明治公園では恒例のフリーマーケットが開催されていた。神宮球場では六大学野球が、となりの第二球場では高校野球の春の都大会の準々決勝が行われていた。第二球場に入った。帝京高校対専修大学付属高校の試合が始まるところで、3回の攻防まで見て帰ってきた。もちろん、帰りも渋谷まで歩いた。強風が吹き荒れる一日で、歩道の脇に置かれた自転車が、あちこちでなぎ倒されていた。

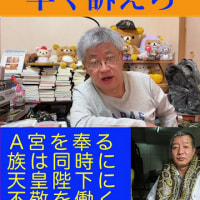 ▼てぇへんだ てぇへんだ 嫁のふんどし尻に巻きつけ
3週間前
▼てぇへんだ てぇへんだ 嫁のふんどし尻に巻きつけ
3週間前
 ▼てぇへんだ てぇへんだ 嫁のふんどし尻に巻きつけ
3週間前
▼てぇへんだ てぇへんだ 嫁のふんどし尻に巻きつけ
3週間前
 ▼団塊の梅雨の晴れ間のごま塩頭
3週間前
▼団塊の梅雨の晴れ間のごま塩頭
3週間前
 ▼団塊の梅雨の晴れ間のごま塩頭
3週間前
▼団塊の梅雨の晴れ間のごま塩頭
3週間前
 ▼団塊の梅雨の晴れ間のごま塩頭
3週間前
▼団塊の梅雨の晴れ間のごま塩頭
3週間前
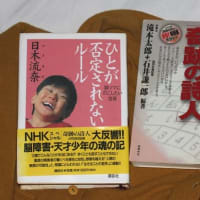 ▼専門ブタとアンポンタンPTA
1ヶ月前
▼専門ブタとアンポンタンPTA
1ヶ月前
 ▼意外に短気な老小児科医
1ヶ月前
▼意外に短気な老小児科医
1ヶ月前
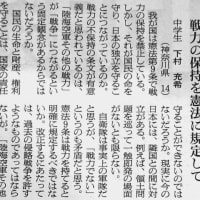 ▼ぜひ、皆さんに考えていただきたい・・・中学生の正論
2ヶ月前
▼ぜひ、皆さんに考えていただきたい・・・中学生の正論
2ヶ月前
 ▼ところで 九条を守れとは憲法違反であるやなしや?
3ヶ月前
▼ところで 九条を守れとは憲法違反であるやなしや?
3ヶ月前
 ▼ヴォーカル大好き<早春賦>
3ヶ月前
▼ヴォーカル大好き<早春賦>
3ヶ月前
姪は息子と同じ年に生まれ「可愛い女の子」でした。
彼女は早く結婚するのじゃないかと思われていた。
外国に旅行したり、車を乗り廻していたり
結構のん気に楽しく人生を謳歌していたようですが、
やはり この度 結婚と相成ったようです。
叔父として「まぁお幸せに」と願うばかりです。
近所に「研修所(たまり場)」のようなところがあって、
一ヶ月ぐらい通った。
私は「体験」が欲しかった。
だが、信者達は私の入会を欲していた。
だから両者が噛み合うはずもなく、やがて彼らは、
私に「もう来られなくて結構」と宣告。
私が何故、一ヶ月も通ったかといえば、その「体験」が
強烈だったからだ。
誤解されてもいけないと思い、私の体験は
彼らにまったく伝えなかった。
ひとりの幹部から、手かざしを受けていたときのこと、
(私は彼女から非接触で手をひたいに当てられていた)
強烈な熱と光を感じるという体験をした。
もうひとつは翌日の排便が黄金色となったこと。
別の日、有力幹部から同様の手かざしを受けても
何らの反応もなかったときもあった。
彼らの説明によると手かざしによる個人差は存在せず
「盟主様」だか「大神様」だか何だか知らないけれど
手かざしは、こうした神様から賜った救いの光であり、
太古からの霊術なのだとのことだった。
私には個々に手かざししてもらったひとによって
だいぶ反応が異なっていたので「相性」とか「感応」の
程度の差ということで説明がつくのじゃないか、
そういうふうに認識していた具合だ。
まぁ、結局
ひとが集まったり、「エネルギー場」が形成されたりとか
あるいは「気」が満ちてくるとか
その場の雰囲気、興奮状態とか
さまざま微妙、絶妙にして、
おかれた環境・周囲のバランスなどによっても
「感応」現象には格差があるというのが私の結論。
長兄「自分は小学四年生のときからアルバイトをやっていた」
三男「初めて知ったよ」 注:三男=私
長兄「子どもが三人も四人もいたし、家がひどく貧乏だった」
三男「うん。それは俺も分かっていたよ」
長兄「弁当も麦ばかりで米はほとんど入っていなかった」
三男「小学生の途中から給食が始まったのでそれほどひどいという記憶がない」
長兄「バイト代は全部家に入れてたので小遣いはなかった」
三男「俺も小遣いはもらえなかったけれどやがて次兄からもらったよ」
長兄「みんな貧乏だったけどよく生きてきたな」
三男「うん。アニキも長男だからスゴク大変だったと思う」
我が家の場合、父親は働いていたし、両親ともに健康だった。
家族一同、特別の差別や偏見にさらされず、
そして当時としてはごく普通の貧乏状態だった。
しかしながら我が家族にあっては
「絶対的貧困」と呼称されるような状態でもなかったようだ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E7%9A%84%E8%B2%A7%E5%9B%B0
現在兄弟で楽しく回顧できるというのはとても有り難いことであり幸いである。
[この世に存在するあらゆる物理的存在は、私たち人間を含めて生まれたときから消費に向かって劣化し続ける。これを物理学で定式化したのが「エントロピー増大の法則」である。
ただし、人は十分な休息と栄養を与えられれば労働力の再生産ができるし、維持管理を徹底することでモノの劣化を遅らせることができる。
しかし、これには費用がかかる。このような追加的なコストを「持越費用」という。
ところがお金は自動的に劣化することもなければ、所有者が無視できる程度にしか持越費用が発生しない。
お金はほかのモノと違って「劣化」という時間の支配を逃れているのだ。このことが、お金にすべてのモノに優越した存在として君臨できる特別な地位を与え、人々に「お金がすべて」という考えを植えつけることにつながっている。
かつてこのお金の持つ優越性に真っ向から異を唱えた人物がいた。その人の名をシルビオ・ゲゼルという。ブエノスアイレスに渡って成功したドイツ人実業家であったが、1880年代にアルゼンチンを襲った深刻な恐慌を経験していた。この経験が動機となってお金の問題を追及したゲゼルは、最終的に「交換手段としての貨幣を改革したいならば、われわれは商品よりも貨幣を劣化させなければならない」という結論に達する。
そしてその実際的方法として、週に1000分の1、つまり年間通して5.2%「減価」する通貨、「自由貨幣」の発行を提唱したのであった。
マイナス金利が課されて自動的に減価し最後には消えてなくなるというようなお金は、プラス金利の世界しか経験していない私たちにとって容易に想像がおよぶものではない。
現時点では荒唐無稽に思われるだろう。]
「お金」崩壊 青木秀和 集英社新書より
http://books.shueisha.co.jp/CGI/search/syousai_put.cgi?isbn_cd=978-4-08-720437-7
「お金」は劣化すべし、まったく同感である。
ゲゼルが提唱しているように、もし人びとが「想像力」を働かせることができれば、私は可能だと信じたい。
「所有していると、どんどん価値の減るお金」に強い関心を持ち、 実現のためのさまざまな運動をしていた。
NHKでそのドキュメント番組「エンデの遺言」(鎌仲ひとみ)が放送され、話題となった。
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=566233
公開されているのでぜひ覗いてください。