以下、「鉄から読む日本の歴史」(窪田蔵郎著 講談社学術文庫)より
-------------------------------
「諸国百姓刀狩りの令」(天正十六年 1588年 秀吉治世時)
(一)百姓が武器を持つ必要はない。よって所持をいっさい禁止する。これらを持つことは一揆の原因となり、やがてみずからを滅ぼすもととなる。
(二)武具類は没収しても、それらは無駄にはしない。鋳潰して寺の大仏殿を建立する釘などに再生し、百姓たちはその功徳で現世来世とも救われるであろう。
(三)百姓は刀や鉄砲のことなど考えず農耕に専心していれば、子孫繁盛はまちがいなのだ。
-------------------------------
さて、わたしが、なして、かような五百年も前のふるい文書を引っ張り出してきたのかといえば、現代のわが国の憲法に、その主旨たる処が実によく似ていると思ったからだ。もしや、マッカーサーは、秀吉による「刀狩り令」を知っていたのではないか。
それはともかく「刀狩り令」は、当時の為政者秀吉が、全国の百姓にたいして命じた。比して現行憲法は、日本を占領していた米軍が日本国民に対して施行してきたものである。いずれの場合も、戦勝者が、敗北した民人に対して、最終的な武装解除の思想を念押ししてきたのである。元来、「武装解除」とは、現状に不平不満を持つ世直し派にとっては、敗北を決定的に認めたことであり、以後、武器がなければ二度と抵抗することはできがたい。
よって、民人にとっては、その文言からして屁理屈以外のなにものでもないのだが、モノは言い様というように、支配者側からの飴と鞭が、巧妙に使い分けられている。このあたりの方便が、現行憲法の、とりわけ前文と9条に酷似しているように思った次第だ。










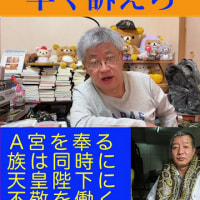




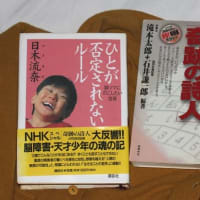

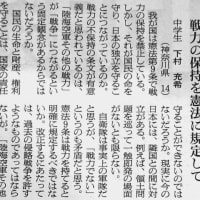








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます