
ああ、いやだ、いやだ、いやだ。どうしたなら人の声も聞こえない物の音もしない静かな、静かな、自分の心も何もぼうっとして物思いのないところへ行かれるであろう。つまらぬ、くだらぬ、面白くない、情けない悲しい心細い中に、いつまでも私は止められているのかしら。これが一生か、一生がこれか、ああいやだ、いやだ・・・仕方ない、やはり私も丸木橋を渡らずばなるまい。父さんも踏みかえして落ちてお仕舞いになされ、お祖父さんも同じことであったという。
「にごりえ」より・・・樋口一葉
「にごりえ」より・・・樋口一葉










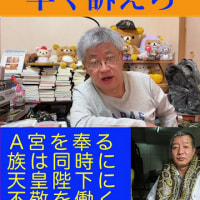




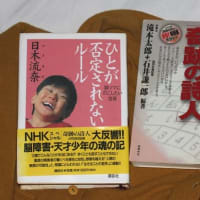

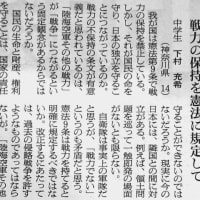








ハガキには「仕事からようやく解放。」
「通勤ラッシュを再度体験してます。」
「年金受給まで辛抱です。耐えて夢を追えということですか・・・。」とも添え書きされていた。
私の場合、思い返してみると、私は辛抱という世界とは無縁のとてもラッキーな環境にあった。そういうこともあって、「自己形成史の会=カウンセリング」を学んだり10数年にわたる「住民運動」や映画サークルの活動に20年以上参加できたり、また(ヨガ)気功を学べたり、陶芸教室にも通うことができた。細々ながら「市民運動」にも参加できた。
やりたいことは今までそれなりにやってこれたという実感がある。
「団塊の世代にとっては好きな生き方を選べる機会、これからが人生の黄金期でもあります。」とのS君のコメント。
S君は若い頃、官舎で「ビラ配り」を上司に見つけられ、「仕方ないけれど俺の将来も危ない」なんて愚痴をこぼしていた。しかしその後の彼は一級建築技師の資格も生かされてか「静岡地下街ガス爆発」の究明チームの一員として派遣されたり(国立)T大学大学院で「(関東)大震災プログラム」チームの一員として参画したり「東京都庁ビル」建設の際の防災担当に選ばれたりなどかなりの活躍の日々だったことが推察される。数年前からは東京消防庁の「消防署長」として転任していた。
6月には中学時代の同窓会が企画されている。
私はその会の準備委員のひとりだが、私のクラスではすでに8名が没している。
友人からのハガキによりあらためて「やりたいことは 先延ばし するのではなく、そのときが やれるとき」との強い思いに駆られた。
元々、兄弟の関係って難しいのだが、その傾向は増加しているのではないだろうか。
古い話だが、「旧約聖書」によると
アダムとイブから生まれた人類最初の兄弟=兄のカイン・弟のアベル。この兄弟はもし他人同士だったなら殺人まではゆかなかっただろうが、兄が(弟の神へのささげ物の方が神に喜ばれたことで激しく怒り)弟を殺害とのこと。兄弟は、殺人までのあい争う関係に。
身近なところに話を具体的に置き換えてみても
たとえば、兄の方がお菓子が一個多い、姉のハンバーグの方がちょっと大きい、なんて場合、兄弟は(まことにそんな些細なことで)大げんかをする。
親から見れば、そんな程度のことでケンカするなんて情けない。
しかしこれは、「親の愛の奪い合い」かも知れないのだ。
つまりお菓子の数が少ない、おかずの量が少ないということは、「自分よりも兄(姉)の方が好きってことなんだな」と子どもは感じてしまう。だから、激しく争ってしまう。(だから)子どもはこんなつまらないことでもゆずれないのだ。
だいいち上の子にとっては、今まで親の愛情も、おもちゃもお菓子も全部独り占めだったのに、ある日、突然あらわれた弟とか妹という名の「よそ者に」に、すべてが奪われてしまいそうになる。
子どもは苦しみ、愛を切望し、退行現象(赤ちゃんがえり)を起こすこともある。今までできていたことができなくなり、親に甘えてしまうのだ。
上の子は、少なくとも最初の頃は王子様、お姫様のように遇されていたのだ。下の子の方は、物心ついたときにはすでに自分より大きなライバルがいるのだ。つまり双方ともに「心に荷物を背負っている」というふうな見方が必要だろう。
すでに「兄弟は日常生活で張り合うライバル」という関係が成立しているのだ。
近年ますます学校の成績が子どもの評価の基準となっているような家庭も多い。
たとえば兄弟どちらか一方が学校の成績が優れていれば、一方は内心穏やかではない。
ますます(学校の成績というような)単一の価値判断=尺度が家庭のなかで幅をきかせるようになってくると、(子どもの成長そして)兄弟の関係に悪影響を与えてしまう可能性を我々は充分に知っておかなければならない。
私は20数年前、約一年ほど「自己形成史の会」でセルフ・カウンセリングを受講した。
両親、兄弟、先生、友達、周囲の環境(→思想・イデオロギー→その他諸々)を記憶のかぎり思い返し、それを記述してゆく過程で、やがてそのほとんどが「自分」とそれまで「思っていたモノ」を知ることになった。
丁寧に一枚づつ殻をはがして自分の頭の内部世界を見つめてゆく作業過程が「自分というモノの存在が作られてきたもうひとつの真実」に接近してくるような感じだった。
もし「ひとつの気づき」というものがあったとしたら、そのときおぼろげながら見えてきた「もうひとつの自分」というものが「この世に自分が生まれてきてもよかった」というようなことだったかも知れない。
世界が違って見える→世界の景色が明るくなったというような感覚もあった。
つい先日、次兄の子どもの結婚式・披露宴があった。
そこで子どもの頃、(今まで私が知らなかった)長兄の辛さ、苦しさ、悩みを長兄から初めて聞いた私は、長兄に対する感覚(感情)が変化した。気がつくのが遅かったといえばそれまでのことだが、一生知らなかったよりはよかった。
寅さん映画で有名な「男はつらいよ」ってホントは「長男(長女)はつらいよ」じゃなかったのかとあらためて思った。