*ナガイヒデミ作 兒玉庸策演出 公式サイトはこちら 紀伊国屋サザンシアターTAKASHIMAYA 23日まで これまでの民藝公演ナガイ作品の記事は→『送り火』
東京オリンピックの余韻冷めやらぬ昭和42年、四国の山あいの村。柚木百合(中地美佐子)と父徹男(杉本孝次)が暮らす家が舞台である。母は百合の7歳下の妹文(あや/飯野遠)を産んでまもなく亡くなり、頼りの兄は戦死した。来年数えで不惑になろうとする百合はいまだ独り身だ。かつて言い交した俊満(天津民生)という恋人がいたものの、父を置いて家を出る決心ができず、その伝言を文に頼んだところ、何と文が俊満と駆け落ちしてしまった。10年の月日が流れ、文と俊満が突然帰郷する。1月26日に逝去した兒玉庸策のあとを受けて、丹野郁弓が演出を担う2幕の物語である。
母方の叔母麦(別府康子)は、百合の縁談ばかりか、徹男の後添いまで辟易するほど世話を焼き、徹男の幼なじみで、地元の寺の住職佐倉(千葉茂則)も、実家に帰れない文と俊満と連絡を取り、親たちとの和解の場をセッティングする「仕切りたがり屋」である。今ではあまり見られない濃厚な人間関係の様相は温かく、ユーモラスだ。それが重荷になって村を出た者が結局戻ってくるという皮肉な展開であるが、家族の確執が解け、よい方向に進みそうなことを素直に喜びたくなる気持ちの良い物語である。
千葉茂則の住職の造形がおもしろい。読経のあと出されたおしぼりで顔から頭から脇の下まで拭いたり、かつては徹男の恋敵だったりなど生臭な面をこれでもかと見せながら、少々強引ではあるが、拗れた家族関係を解きほぐす手腕は、この人がいてくれて良かったと思わせる。別府康子の麦叔母も同様で、鬱陶しいほどのお節介ぶりも愛情あってこそ。声や表情、しぐさの一つひとつに味わいがあり、舞台を弾ませ、客席をなごませる。
公演パンフレット掲載の作者ナガイヒデミの寄稿は、本作に結実させた作者自身の感慨が淡々と記された味わい深いものだ。これを確と共有するに至らなかったのだが、「半世紀前の話を今舞台にする意義は?」などの疑問を持つのがいささか野暮と躊躇わせるのは、前述の俳優陣の魅力的な演技であり、初日の客席に満ちた温かな空気のためだろう。
性格の異なる姉妹の確執、それも姉の恋人を妹が奪ったというと、内館牧子ばりの愛憎劇になりかねないが、むしろ本作の軸は、娘たちそれぞれが父親と向き合うまでの過程だと思う。衝突を繰り返した文は、夫婦して故郷での新しい人生へ踏み出すが、百合は父に対し、最後になって幼子のような振舞いをする。もしかしたらここからがほんとうに重要な物語になるのではないか。ラストシーンの舞台美術が美しく、ほのぼのとした心持で帰路につきながら、百合はこれからどうするつもりなのかが心配で、百合がやってみたいというふたつのことを、「頑張ってみれば」と背中を押したくなるのである。




















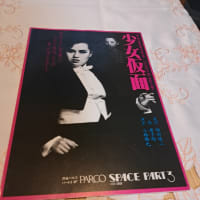





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます