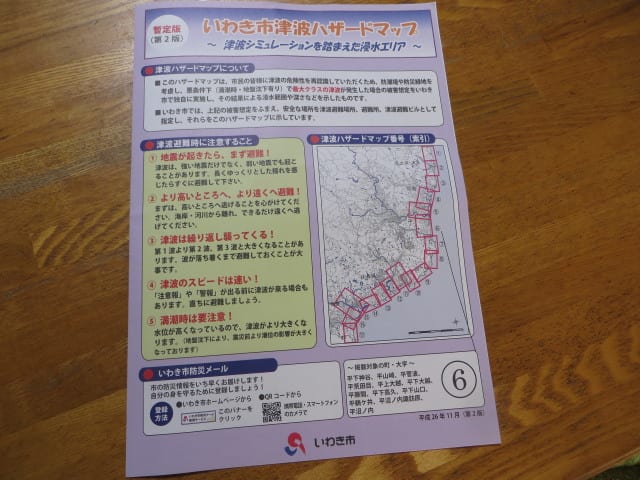大震災から今日で6年、長かったのか?短かったのか?
当地区の堤防の嵩上げ工事も終わりました。

河口に逆流防止の水門工事が行われています。

緑地帯の整備も行われています。

当地区をまもった防災林の松も半数程度が枯れ、植樹されました。
役に立つまで2~30年はかかるでしょう。

震災と原発事故は同時でした。
原発事故後3週間程度から緊急の事態に対処するため
連日避難区域に入り職務をこなしていました。
最初の一ヶ月程度は休日もありませんでした。

最近の旧避難区域です。
除染で出た廃棄物がいたるところに集積されています。

震災直後、最も苦労したのが水の確保でした。
現在では家族が10日程度で必要とされる約100リットルを備蓄しています。
食料も10日程度分を備蓄し、年に1~2回程度更新する、回転備蓄を行っています。

簡易トイレと処理剤も備蓄しています。

大震災で最も役に立ったのがキャンプ用品です。
ラップやペーパータオル、ウエットティシュ、トレペーにガスボンベ等々
そのとき使ってしまった消耗品をコンテナ2つに備蓄しています。
大震災ではスーパーやコンビニが再開(最小限で)されるまで2週間程度かかりました。
関東や関西など物流拠点が大きな被害を受けなかったにもかかわらずです。
水道などのライフラインの復旧には1ヶ月程度かかりました。
人口の少ない東北で、全国からの多くの応援を受けてもこれだけの日数がかかりました。
これが関東直下地震や東南海地震が起きたならどうなるのでしょうか?
人口が極端に多く、物流拠点が集中し、周りのバックアップ体制は脆弱です。
関東直下や東南海地震は、何時起きてもおかしくは無いと言われています。
自分や家族を守れるのは自分だけです。
最低でも1週間は援助に頼らなくても生活できるだけの備えが必要です。
大都会ですと2週間は援助が行き渡らないと考えた方が妥当でしょう。
過去記事はカテゴリー(東日本大震災)をご覧ください。