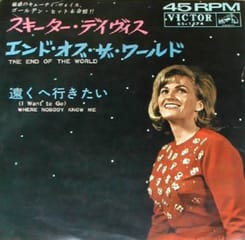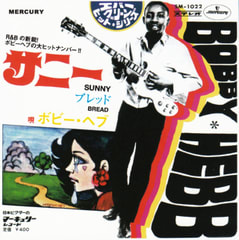今日は年末恒例の “阪神百貨店 中古廃盤レコードCDセール” に行ってきた。先週末に案内ハガキが届いた時はいまいちテンションが上がらず今回はパスするつもりだったのだが、一昨日 plinco さんからお誘いの電話を頂き “忘年会のノリでどうよ?” と言われ、すっかりその気になって参加を決めた。特に今 “コレが欲しいっ!!!” という盤は無いが、行けば行ったで何か面白い盤に巡り合えるかもしれないし、何よりも会場を出た後 plinco さんや 901 さんと茶をシバキながらそれぞれの獲物を肴にウダウダやるのが最高に楽しい。
頑張って早起きして大阪に向かう。最近はレコード・CD・DVD の99%をネットで買っており、レコ屋巡りも年に2・3回というテイタラクなのでちょっと歩くだけで息が上がってしまう。毎週大阪京都を歩き回っても平気だった数年前とはエライ違いだ。人間一旦ラクを覚えたらあきまへんな(>_<)
苦手な人混みをかき分けフーフー言いながら午後1時に会場に到着すると予想通りの暖房地獄... いつも思うのだが冬になると何故どこの店もまるで親の仇でも取るようにガンガン暖房するのだろう?客は厚着をして外出してきてるわけだから、店内に入ると暑くてたまらない。店員は薄着でちょーどエエかもしれないが、こっちは脱いだ分厚い上着を抱えながら買い物しなくてはならず、鬱陶しくてたまらない。これまでも真冬に汗だくで買い物するハメに陥ったことが何度もあったので、今回はエサ箱に向かう前にセーターも脱いで準備万端だ(^.^)。
どこから取り掛かろうかと会場を見渡してみて気付いたのは前回までとは違い、“ジャズ”、“ロック”、“ソウル”、“クラシック”、“J-Pops”、“演歌”という風に完全にジャンル別にコーナーが分かれていたこと。これまでは参加している店ごとに商品が並べられていたので不便で仕方がなかったのだが、今回はキッチリと棲み分けが出来ていて非常に見やすい。クラシックは当然問題外として、ソウルやJ-Popsにはあまり興味がないし、ジャズも欲しい盤は殆ど入手済みなので、今回は “ロック” と “演歌”(というか “歌謡曲” ですわ...)がメイン・ターゲットだ。まずは買いそびれているうちに廃盤になってしまってそれ以降滅多に見かけなくなってしまったジョージ・ハリスンの「ダーク・ホース」CD(2000年ヴァージョン)を1,470円でゲット、これでようやくジョージの公式盤 CD のコンプリート達成だ。そうこうしているうちに 901 さんから “こんなんあるでぇ~” と会場の一角の書籍コーナーにある「フェラーリ・サウンド DVD & CD BOX」を教えてもらい即決!定価880円のところを新品で330円だ。一言で言えばカーグラ TV の DVD 版みたいなモンだが、DVD-VIDEO では “激走する美しいエンジン音が堪能できる迫力の映像” が楽しめ、DVD-ROM には “パソコンで使えるフェラーリの高画質画像” を収録、更に CD にはフェラーリ各車種のエンジン・サウンドが入っており、私のようなティフォシには堪えられない。ドライヴの BGM には最高だろう(笑)。
再び音楽コーナーに戻ってエサ箱を引っかき回してエルヴィス・プレスリーの「エルヴィス '56」DVD を発見、昔NHKで放送されたものを録画したビデオ・テープは持っているが、やはり DVD で欲しかったので迷わずゲット、1,800円也。エルヴィスの DVD と言えば映画にもなった「エルヴィス・オン・ステージ」や NBC の「'68 カムバック・スペシャル」が好きでよく取り出して見ているのだが、やはり彼の全盛期は1950年代。そんな彼の若き日々の映像がモノクロながら存分に楽しめるのがこの「エルヴィス '56」なのだ。腰を振りながら歌う彼のスタイルが全米の保守的な大人たちの間で物議を醸し、スティーヴ・アレン・ショーで無理やりタキシードを着せられ、腰も振らず爪先立ちもせず、ただ悲しそうな目で本物の犬に向って「ハウンド・ドッグ」を歌いかけるシーン(下に貼り付けた YouTube では2分50秒あたりから)なんか何度見ても笑えると同時にエルヴィスが気の毒で仕方がない。エド・サリヴァン・ショーでも腰から下は映してもらえなかったという。要はそういう時代だったということだろうが、そういった諸々の事情を含めて実に見事な構成のドキュメンタリー作品であり、エルヴィス・ファンだけでなく全ロック・ファン必見の DVD だと思う。
Elvis '56 Part 4
頑張って早起きして大阪に向かう。最近はレコード・CD・DVD の99%をネットで買っており、レコ屋巡りも年に2・3回というテイタラクなのでちょっと歩くだけで息が上がってしまう。毎週大阪京都を歩き回っても平気だった数年前とはエライ違いだ。人間一旦ラクを覚えたらあきまへんな(>_<)
苦手な人混みをかき分けフーフー言いながら午後1時に会場に到着すると予想通りの暖房地獄... いつも思うのだが冬になると何故どこの店もまるで親の仇でも取るようにガンガン暖房するのだろう?客は厚着をして外出してきてるわけだから、店内に入ると暑くてたまらない。店員は薄着でちょーどエエかもしれないが、こっちは脱いだ分厚い上着を抱えながら買い物しなくてはならず、鬱陶しくてたまらない。これまでも真冬に汗だくで買い物するハメに陥ったことが何度もあったので、今回はエサ箱に向かう前にセーターも脱いで準備万端だ(^.^)。
どこから取り掛かろうかと会場を見渡してみて気付いたのは前回までとは違い、“ジャズ”、“ロック”、“ソウル”、“クラシック”、“J-Pops”、“演歌”という風に完全にジャンル別にコーナーが分かれていたこと。これまでは参加している店ごとに商品が並べられていたので不便で仕方がなかったのだが、今回はキッチリと棲み分けが出来ていて非常に見やすい。クラシックは当然問題外として、ソウルやJ-Popsにはあまり興味がないし、ジャズも欲しい盤は殆ど入手済みなので、今回は “ロック” と “演歌”(というか “歌謡曲” ですわ...)がメイン・ターゲットだ。まずは買いそびれているうちに廃盤になってしまってそれ以降滅多に見かけなくなってしまったジョージ・ハリスンの「ダーク・ホース」CD(2000年ヴァージョン)を1,470円でゲット、これでようやくジョージの公式盤 CD のコンプリート達成だ。そうこうしているうちに 901 さんから “こんなんあるでぇ~” と会場の一角の書籍コーナーにある「フェラーリ・サウンド DVD & CD BOX」を教えてもらい即決!定価880円のところを新品で330円だ。一言で言えばカーグラ TV の DVD 版みたいなモンだが、DVD-VIDEO では “激走する美しいエンジン音が堪能できる迫力の映像” が楽しめ、DVD-ROM には “パソコンで使えるフェラーリの高画質画像” を収録、更に CD にはフェラーリ各車種のエンジン・サウンドが入っており、私のようなティフォシには堪えられない。ドライヴの BGM には最高だろう(笑)。
再び音楽コーナーに戻ってエサ箱を引っかき回してエルヴィス・プレスリーの「エルヴィス '56」DVD を発見、昔NHKで放送されたものを録画したビデオ・テープは持っているが、やはり DVD で欲しかったので迷わずゲット、1,800円也。エルヴィスの DVD と言えば映画にもなった「エルヴィス・オン・ステージ」や NBC の「'68 カムバック・スペシャル」が好きでよく取り出して見ているのだが、やはり彼の全盛期は1950年代。そんな彼の若き日々の映像がモノクロながら存分に楽しめるのがこの「エルヴィス '56」なのだ。腰を振りながら歌う彼のスタイルが全米の保守的な大人たちの間で物議を醸し、スティーヴ・アレン・ショーで無理やりタキシードを着せられ、腰も振らず爪先立ちもせず、ただ悲しそうな目で本物の犬に向って「ハウンド・ドッグ」を歌いかけるシーン(下に貼り付けた YouTube では2分50秒あたりから)なんか何度見ても笑えると同時にエルヴィスが気の毒で仕方がない。エド・サリヴァン・ショーでも腰から下は映してもらえなかったという。要はそういう時代だったということだろうが、そういった諸々の事情を含めて実に見事な構成のドキュメンタリー作品であり、エルヴィス・ファンだけでなく全ロック・ファン必見の DVD だと思う。
Elvis '56 Part 4