


11日夕、高江の民有地で炎上した米軍大型ヘリCH53Eは「不時着」とされていますが、元運輸安全委員会航空事故調査官の楠原利行第一工業大教授は、「機体の壊れ方をみると、不時着以上の、墜落に近い『ハードランディング』だったのではないか。…米軍が『墜落』と言わないのは、沖縄の県民感情を考慮しているのだろう」(13日付中国新聞)と指摘しています。
沖縄県民の不安・怒りをさらにかきたてているのが、炎上したヘリの機材に放射性物質が使われていたことです。
「在沖米海兵隊は13日、本紙取材に『CH53Eのインジゲーター(指示器)の一つに放射性の材料が使われている』と認めた」(14日付琉球新報)
「炎上事故があった東村高江では放射能測定器とみられる機器を持った米兵が現場に入った」(同)(写真左はそのもようと思われます)
2004年8月13日にも同じCH53Eが沖縄国際大学に墜落しましたが、その時米軍は機体に放射性物質「ストロンチウム90」が含まれていたと発表しました。
放射性物質に詳しい矢ケ崎克馬琉球大学名誉教授は、ストロンチウム90はプロペラローターにダメージが入った時にいち早く感知するためのものだとしたうえで、「一番激しく燃えたところにストロンチウム90の装置が搭載されている可能性が非常に大きい。沖縄国際大に墜落したときは6本のローターの1本だけが燃え上がったが、今回は6本全部燃え上がっている可能性が大きく、大変危惧している」(13日の報道ステーション)と警鐘を鳴らしています。
米軍は放射性物質は「健康を害するのに十分な量ではない」(14日付琉球新報)としていますが、沖縄国際大に墜落した時は、消火活動にあたった米軍の消防隊員は消火活動の直後に放射能検査を行っています(日本の消防隊員には行われませんでした)。
ストロンチウム90は、「骨の中に入ると内部被ばくとしてベータ線を浴び続ける危険性がある」(勝田忠広明治大学准教授・原子力規制委員会審査会委員、13日報道ステーション)という恐ろしい物質です。
米軍機には放射性物質が使われており、事故で炎上すればそれが飛散し、住民が内部被ばくする危険性がある。それが現実のものとなりました。
これはもちろん沖縄だけの問題ではありません。米軍機が傍若無人に飛び回る日本全土が直面している恐怖です(日米安保条約の「全土基地方式」)。
時を同じくして、13日夕、RCC(中国放送)が重大なニュースを流しました。広島県北広島町の複数の視聴者から、11日、米軍機(F18か)から〝火の玉”がいくつも落ちてきた、という情報が寄せられたというのです(写真右)。
軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏によれば、この”火の玉”は「フレア」というもので、ミサイルを回避するためのおとりの熱源。黒井氏は、「フレアは通常海上の訓練空域で発射される。民家の上空で発射されたことは聞いた記憶がない」(13日RCCニュース)と驚きを隠しませんでした。
「ストロンチウム90」も「フレア」も、住民が暮らしている地域(上空)に、米軍がばらまいたものです。日本の領土領空をわがもの顔で飛び回り、住民を危険にさらす。
これが在日米軍の姿、それを許している日米安保条約の実態です。



アメリカのペンス副大統領は18日の安倍首相との会談で、北朝鮮に対する軍事圧力に関連して、「平和は力によってのみ初めて達成される」と述べました。これに対し安倍首相は、「(アメリカが)全ての選択肢があるとの考えで対処しようとしていることを日本は評価する」と賛辞を送りました。
日米同盟とは「力による平和」を共通基盤にしたものであることを白日の下にさらした会談でしたが、これを過小評価したり見逃したりすることは絶対にできません。
なぜなら「力による平和」は、日本国憲法はもちろん、国連憲章の基本理念にさえ反し、大戦の歴史的教訓を踏みにじるものだからです。
国連憲章は前文でこううたっています。
「われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し…共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保(する)」
そのうえで憲章第2条第3項は、「すべて加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない」と規定しています。
国連憲章がこう定めているのは、「紛争の平和的解決つまり非軍事的解決こそは、国連憲章の最も基本的な精神である。これは、第二次大戦の苦い教訓の上に立っている」(渡辺洋三氏『憲法と国連憲章』岩波書店)からです。
さらに、憲章第2条第4項は、「すべて加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなければならない」と規定しています。
「ここで特に注目されるのは、単に武力行使のみならず、武力による威嚇もまた禁止されていることである。これは、戦争を禁止しても、すでに戦争(武力行使)に入ってからでは手おくれとなるので、戦争になる以前に武力による威嚇そのものを禁止しなければならないという趣旨である」(渡辺洋三氏、前掲書)
こうした国連憲章の基本理念をさらに徹底させたのが、いうまでもなく日本国憲法です。
憲法は前文で、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言しています。
そして第9条第1項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と、「武力の行使」だけでなく「武力による威嚇」の放棄を明言し、第2項で「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と戦力不保持を明記しています。
日本国憲法の平和主義は、欧米の憲法や国連憲章とくらべても傑出しています。
「立憲主義を生み出した西欧の文明は、『最終的には力によって擁護される正義』という思想と分かちがたく結びついてきた。…ほかならぬ国際連合憲章も、『戦争』の違法化を前提としながらも、最終的には、軍事力による制裁によって平和を回復するという考え方のうえに組み立てられている。…それに対し、日本国憲法は、九条によって、二一世紀にむけての人類社会に対し、あえて、もうひとつの別の選択を提示したものである」(樋口陽一氏『憲法入門』勁草書房)
トランプ政権による北朝鮮への軍事圧力が、国連憲章が禁じている「武力による威嚇」にあたり、「力による平和」が日本国憲法の基本原則に反していることは明白です。
そして実態的にも、米軍と憲法違反の軍隊(戦力)である自衛隊の一体化が急速に進行しています。海自は朝鮮半島沖で米原子力空母カール・ビンソンと共同「訓練」を行う計画です。ペンス副大統領が19日に横須賀の米原子力空母ロナルド・レーガンで行った北朝鮮をけん制する演説には自衛隊も参加していました=写真右。
これが日米安保条約による憲法違反の「日米同盟」の実態です。
ところがこの憲法違反の「日米同盟」を擁護しているのが日本のメディアです。
ペンス副大統領の「力による平和」発言とそれを「評価」した安倍首相を社説で批判した新聞は1つもありません。
「北朝鮮への圧力は、外交、軍事両面で戦略的に高めるべきだ。…厳しい懲罰行動も辞さない姿勢を示すことが欠かせない」(19日付社説)と「武力による威嚇」をたきつけている読売新聞は論外として、「平和解決へ日米連携を」という東京新聞でも、「対話を呼び掛けるだけで北朝鮮が核、ミサイル開発の断念に応じるようなことはないだろう。残念ながら軍事力の存在がなければ、交渉のテーブルに着けることすらできないというのが、国際政治の現実ではある」(19日付社説)と、「武力による威嚇」を肯定しています。
憲法違反の「日米同盟」(日米安保体制)を擁護・肯定してはばからないこうした日本のメディアが、「安倍内閣の高支持率」を作り出している要因の1つであることは明らかです。



トランプ大統領が北朝鮮への軍事圧力を強める中、朝鮮半島・東アジアで軍事衝突(戦争)を回避するために、日本は何をすべきでしょうか。
朝日新聞は「北朝鮮と日本 軍事より対話の道描け」と題した12日の社説で、「安倍政権が米国の『力の誇示』を評価する姿勢を示していることに疑問を禁じ得ない。大事なのは、対話による危機回避の道筋を描くことだ」と指摘し、「軍事に偏らない選択肢をトランプ政権に説く。それこそが、日本がいま果たすべき喫緊の使命だ」と主張しています。
また、16日放送の「サンデーモーニング」(TBS、写真右)で、寺島実郎氏は、「アメリカの単独行動を許してはいけない」とし、「問題を国連に持ち込む。その中で日本の役割も出てくる。アメリカの単独行動に日本がついて行くことだけはやってはならない」と強調しました。
日本政府(安倍政権)に対する批判がきわめて乏しい日本のメディアの中で、いずれも注目される主張ですが、共通した問題を指摘せざるをえません。それは、日米安保=日米軍事同盟について一言も触れていないことです。
もちろん両者に限ったことではなく、今回の事態に関連して新聞の社説やテレビのコメンテーターで、日米安保・軍事同盟の問題に言及したものは(私が見た限り)皆無です。日本のメディア(社会)にまん延する「安保タブー」が浮き彫りになっています。
現実はどうでしょうか。
安倍首相はトランプ大統領のシリア攻撃を真っ先に「理解・支持」した談話の中でこう述べました。
「東アジアでも…同盟国と世界の平和と安全に対するトランプ米大統領の強いコミットメントを日本は高く評価する」(7日)
一方、トランプ大統領は米中首脳会談の直後、ツイッターにこう書きました。
「中国がやらないなら、アメリカと同盟国がやる」(13日)
安倍首相がトランプ大統領に追随し、米軍と自衛隊の一体化を強めているのは、日米安保条約によって日本がアメリカの従属的軍事同盟国になっているからにほかなりません。この同盟関係を見直さない限り、「軍事に偏らない選択肢をトランプ政権に説く」ことも「アメリカの単独行動について行かない」ことも夢物語です。
朝鮮半島・東アジアでの武力衝突(戦争)を避けるために、日本は、日本国民は何をすべきか。それが私たちにとっての最大課題であり、日米安保=軍事同盟の見直し・解消を抜きにそれは考えられません。「安保タブー」をいまこそ打ち破るときです。
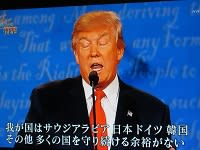


「米軍基地負担」など「日米同盟」に関するトランプ氏の発言が今後どう修正・変化するかは不透明です。しかし確かなことは、今回の米大統領選を契機に日本の私たちが考えるべき最大の問題は、今後の日米関係のあり方、言い換えれば日米軍事同盟(日米安保条約体制)の再検討ではないでしょうか。
「世界の警察官になるべきではない」という米大統領が誕生することは、たとえそれが今後撤回・修正されるとしても、日米軍事同盟にとっては最大の「危機」でしょう。
安倍首相が電話でトランプ氏に直ちに、「日米同盟は普遍的価値で結ばれたゆるぎない同盟だ。さらに強固にしていきたい」(9日)と述べたのは、その「ゆるぎ」を恐れたからにほかなりません。
では、日本のメディアは、「トランプ勝利」を受けて日米(軍事)同盟をどう再検討しようとしているでしょうか。10日の各紙の社説を見てみましょう。
朝日新聞…「米国の役割とは何か。同盟国や世界との協働がいかに米国と世界の利益になるか。…日本など同盟国は次期政権と緊密な関係づくりを急ぎ、ねばり強く国際協調の重みを説明していく必要がある」
毎日新聞…「第二次世界大戦後の世界は冷戦とソ連崩壊を経て米一極支配の時代に入り、米国の理念に基づいて国際秩序が形成されてきた。…『米国を再び偉大な国に』をスローガンにするのはいいが、同盟国との関係や国際協調を粗末にして『偉大な国』であり続けることはできない」
読売新聞…「何よりも懸念されるのは、同盟国を軽視するトランプ氏の不安定な外交・安保政策だ。…米主導の国際秩序をこれ以上揺るがしてはならないだろう。…日本は、新政権の方針を慎重に見極めながら、同盟の新たな在り方を検討すべきである」
日経新聞…「日本の安全保障が米軍に依存しているのは事実であり、ある程度の負担増はやむを得ない。…日本の防衛力強化も避けて通れない道だ。…国連平和維持活動(PKO)など世界平和への協力に日本も汗を流すなどして日米の絆を深めるのが現実的だ」
産経新聞…「より重要なのは、東シナ海の尖閣諸島の危機を抱える日本として、自らの防衛努力を強める覚悟を持つことである。(安倍首相の言葉を引いてー引用者)決意のみならず、具体的な防衛力の強化策を講じることが不可欠といえよう」
読売、日経、産経はいかにも率直に安倍政権の考えを代弁しています。稲田防衛相も述べたように、彼らはトランプの発言を奇貨として、日本の軍事力(自衛隊)の一層の強化を図り日米軍事同盟をさらに強固にしようとしています。
朝日、毎日はさすがにそうストレートには言いませんが、共通しているのは、「アメリカ中心の世界秩序」の維持(「世界の警察官」の継続)であり、そのための同盟国・日本との「協働」です。
こうして日本の主要メディアはすべて、強弱の差はあっても、トランプ政権下での日米軍事同盟の維持・強化を主張しています。その点で安倍首相との違いはありません。
メディアだけではありません。新聞やテレビに登場するいわゆる「学者・識者」も、「日米関係を見直す好機」(田岡俊次氏、14日付沖縄タイムス)とは言っても、日米軍事同盟を廃棄すべきだと主張する人は、私が見た限り、1人もいません。逆に、リベラルと見られている学者からも、「国際関係を維持していくには…これまで日本は米国依存だったが、今後は責任ある同盟国として対応していくべきだ」(西崎文子東大教授、10日付中国新聞=共同)などの論調が出ています。
政党はどうでしょうか。
民進党の蓮舫代表は「トランプ勝利」で、「日米関係の重要性は不変だ」「安定した日米同盟を引き続き維持し、経済関係の連携を図りたい」(10日付共同)との「談話」を発表しました。
政党で唯一日米安保条約に「反対」の日本共産党はどうでしょうか。志位和夫委員長は「談話」(10日付「赤旗」)で、「アメリカ社会の矛盾と行き詰まり」や「グローバル資本主義の深い矛盾」を指摘しながら、「新大統領として、今後どのような政策を提示するのか、注視していきたい」と言うだけで、「日米(軍事)同盟」の言葉(まして見直し・廃棄)は一言もありません。
こうして日本は、メディアも「学者・識者」も政党も、日米軍事同盟(安保条約体制)を維持・推進・黙認する点で、すべて1つの傘の中にすっぽり入っています。「トランプ政権誕生」でもそれは変わりません。変えようとしていません。
それでいいのでしょうか。
「日米同盟の普遍的価値」とは何ですか。日米軍事同盟に縛られていて、中国、北朝鮮と良好な関係が築けますか。「軍事同盟」で平和がつくれるでしょうか。
いま必要なのは、日本を覆っている「日米軍事同盟(安保条約体制)タブー」を打ち破って、「非同盟・中立の日本」を構想し議論することではないでしょうか。



米大統領選でのトランプ氏の勝利についは、これからもさまざまな報道・論説があるでしょう。トランプ氏自身の言明・政策にも変化が予想され、まったく流動的です。
そんな中で、今の段階で思うことを何回かに分けて書きます。
トランプ氏が勝った要因はいくつか指摘されていますが、私がもっとも大きいと考えるのは、格差社会における「貧困層」(広い意味で)の既成政治(政権)への反発です。それが予想以上に大きかったということではないでしょうか。
「白人労働者」をはじめトランプ氏を支持した人々が異口同音に「変化」を求めていたことにそれが示されています。背景に、人口の3%の層が富の54%を独占しているアメリカの超格差社会があることは言うまでもありません。
私も含め「トランプ勝利」を予測できなかったのは、この格差社会の中でいかに労働者・市民が厳しい生活・状態におかれているかがよくわかっていなかったからではないでしょうか。メディアの、そして私自身の「立ち位置」が改めて問われます。
労働者・市民は「二大政党制」という時代遅れの政治制度の中でとりうる限られた手段で、現状変革を求めて立ち上がったと言えるのではないでしょうか。いわば格差社会における労働者・市民の〝反乱”(革命)だったのではないでしょうか。
開票1日目はそう肯定的に考えました。しかし、その後全米各地で起こっている「反トランプデモ」を見て、こうも考えました。
たとえそれが労働者・市民の〝反乱”(革命)だったとしても、それでもやはり、トランプに投票すべきではなかった、と。
核兵器容認(使用を含め)、国境の「壁」建設、移民の排斥、女性蔑視(というより強制わいせつの居直り)…トランプ氏は政治的信条や政策以前の問題として、大統領はおろか政治家、人間として失格です。たとえ「既成政治」に不満があって「変化」を望んだとしても、そんな人物に1票を投じる(彼の暴言を許し容認する)ことが、有権者として、人間として、果たして正しい行為でしょうか。
どんなに生活が苦しくても、人には曲げてはいけないものがある。認めてはいけないことがある。カネよりも尊いもの(こと)がある。
そう思うにつけ、日本における「米大統領選報道」には絶望的な思いを禁じ得ません。
「トランプ勝利」が株価や為替にどう反映し「日本経済」にどう影響するか、すなわち自分たちにとって得か損かの一辺倒ではありませんか(メディアも市民の反応も)。
「一般市民」にも株や投機が浸透している「カジノ資本主義」の病理現象です。世界情勢にとって重要な出来事も、株や為替の動き、得か損かを最優先で考える。これこそ本当の「貧困」ではないでしょうか。
日本の私たちは、「トランプ勝利」にどう向き合うべきか。次回はそれを考えます。
※当ブログは基本的に月、火、木、土に書きます。ただ、介護している母の状況により、今回のように不規則になることが今後もありうると思います。どうかご了承ください。



田中角栄元首相がロッキード疑獄事件で逮捕されて、7月27日で40年になります。
24日のNHKスペシャルは、「日米の巨大な闇 40年目のスクープ」と題してロッキード事件の「新たな事実」を報じました。
田中が逮捕・起訴されたのは、米ロッキード社製の民間航空機トライスターの全日空への売り込みをめぐる5億円の授受(受託収賄、外為法違反)だった。しかしロッキード事件の本丸は実はそこではなく、ロ社製の軍用機・P3C対潜哨戒機の売り込みだった。
当時、対潜哨戒機は国産化の計画が進んでいたが、田中とニクソン米大統領(当時)のハワイ会談(1972年8月、写真中)の直後、国産化計画は白紙になり、ロ社からの購入(輸入)が決定した。ロ社から黒幕・児玉誉士夫に22億円の工作資金が渡されたが、その流れも未解明のまま、捜査は終結し、P3C疑惑は封印された。
当時キッシンジャー大統領補佐官の側近だったリチャード・アレン氏(写真右)は、ロ社の対日工作の本命はP3Cだったと証言している。ロ社からのP3C購入は今日までに100機(約1兆円)にのぼっている。
以上がNスぺの要旨です。
ロッキード事件の本丸がP3Cであり、それはのちのダグラス・グラマン事件(E2C早期警戒機売り込み)にもつながる、というのは、なにも目新しいことではありません。
しかし、日米間の兵器購入をめぐる闇は、今に至るも解明されることなく、米兵器産業からの購入は増え続け、日本の軍事費は膨張を続けています。ロッキード事件の闇はけっして過去の話ではありません。
たとえば、今年2月9日に公表された米議会調査局報告「日米同盟」は、「日本への米国の武器セールス」の項目で、「日本は米国製の防衛装備品の主要な購入者であり、『NATOプラス5カ国』という地位を保有している」として、以下の表を添付しています(『日本の軍事費Ⅱ』安保破棄中央実行委員会より)
兵器名 機・隻数 金額
F35戦闘機 42 100億ドル(1兆2000億円)
RQグローバル・ホーク無人偵察機 3 12億ドル(1440億円)
MV22オスプレイ 17 30億ドル(3600億円)
KC46A空中給油機 3 5.18億ドル(621億円)
E2Dホークアイ早期警戒機 4 17億ドル(2040億円)
最新鋭イージス艦 2 15億ドル(1800億円)
さらに問題なのは、日米相互防衛援助協定によって、米国からの兵器購入はFMS(Foreign Military Sales)というシステムで行われていることです。
「FMS調達は、一般的な商取引による契約とはまったく違います。もっとも大きな違いは、価格や取引条件などをすべて『アメリカいいなり』にすることが、アメリカの法律(武器輸出管理法)で決まっていることです」(『日本の軍事費Ⅱ』)
今年度5兆円を超える日本の軍事費(「防衛予算」)の多くは、こうして対米従属システムによって、アメリカの兵器産業を潤し、米政府の軍事政策に奉仕するために注ぎ込まれています。その原資は言うまでもなく私たちの血税です。
これが日米安保体制(軍事同盟)の実態です。
米兵器産業・米政界と日本の「防衛予算」・政界の闇にメスを入れ、軍事費を大幅に削減することは、平和にとっても財政にとっても、今日の喫緊の課題です。



安倍政権と自民、公明両党が、昨年末憲法(53条)を踏みにじって臨時国会召集要求を握りつぶしたのに続き、今度は野党が提出している戦争(安保)法制廃止法案を審議すらしないというのは、多数のおごり、国民無視も甚だしく、絶対に許されるものではありません。
29日施行された戦争法制は、あらためて国民的議論を巻き起こし、廃止しなければなりません。
その際、見過ごすことができないのは、「戦争法制反対」や「安倍政権批判」の論調の中に、自衛隊や日米軍事同盟(日米安保条約)を肯定するものが少なくないことです。
例えば、「『違憲』の法制、正す論議を」と題した29日付の朝日新聞社説は、「幅広い国民の合意を欠く『違憲』法制は正さねばならない」としながら、「法制の中身を仕分けし、少なくとも違憲の部分は廃止する必要がある」「問題は…自衛隊の海外活動に一定の歯止めをかけてきた『9条の縛り』を緩めてしまったことだ」といいます。これは自衛隊・安保条約自体を肯定したうえで、憲法9条は「自衛隊の海外活動」の「一定の歯止め」にすぎず、安保法制の「違憲」性も部分的なものだという立場です。
「安保法施行 思考停止せずに議論を」という29日付の毎日新聞社説はもっと露骨に、「日米同盟は重要だ」と言い切ったうえで、日米防衛協力の新ガイドラインも評価し、「だが、同盟強化一辺倒では、国際秩序の大きな構造変化に対応できないだろう」として、「外交と防衛のバランス」を点検する「議論」を求めているにすぎません。
しかし、戦争法制は「国民の合意を欠く」から違憲なのではなく、また従来の「政府見解」を変えたから「立憲主義」に反するのでもありません。憲法の9条や前文に照らせば、自衛隊という軍隊そのもの、他国との軍事同盟である日米安保条約自体が違憲です。戦争法制は「違憲の部分」があるのではなく、丸ごと違憲なのです。
憲法学者の横田耕一氏は、「『安保法制』に反対する運動に関していくつかの『違和感』を持たざるをえない」として、こう述べています。
「現在の反対運動のなかでは…反対論の依拠する出発点は『72年内閣法制局見解』にあるようで、それからの逸脱が『立憲主義に反する』として問題視されている。したがって、そこでは自衛隊や日米安保条約は合憲であることが前提とされている。過去の『解釈改憲』は『立憲主義に反しない』ようである。
けれども、『72年見解』等は、憲法前文の趣旨が示す『武力によらない安全保障』から『(個別的自衛権の行使を含む)武装による平和保障』への質的転換を意味するものであるから、『安保法制』は『72年見解』の延長線上にある量的変化と見做すべきものである(『周辺事態』から『重要影響事態』への改変が量的変化であるように)」(「靖国・天皇制問題情報センター通信」2015年11月号)
違憲性は「量的変化」(「安保法制」「重要影響事態」)ではなく「質的転換」(「72年法制局見解」「周辺事態」)に表れ、そこにこそ着目すべきだという指摘です。
憲法違反の自衛隊・日米安保を肯定しながら、「日米同盟の強化」を前面に出してくる安倍政権の戦争法制や米軍基地強化と正面からたたかうことができるでしょうか。
戦争法制廃止へ向けた議論・運動の中で、いまあらためて、自衛隊・日米安保自体の違憲性を問い直す必要があるのではないでしょうか。
そんな中、「シールズ琉球」の元山仁士郎さんの記事(写真右)が目を引きました。
「元山さんは…自衛隊配備に多額の予算が付けられていることを批判した上で『沖縄は3人に1人が貧困状態だと言われる。防衛予算額をより多く貧困家庭や待機児童、福祉などの予算に充てるようにするべきではないか』と語った」(29日付琉球新報)
「防衛予算を福祉に」。いまや日本共産党からも聞かれることが少なくなったこの言葉が、若い元山さんから聞かれたことがうれしく、そして頼もしくてなりません。
軍事費タブー、安保条約・自衛隊タブーを打ち破って、その違憲性を根本から問い直す学習・議論が、若い人たちの間で広がることを願ってやみません。



北朝鮮のロケット発射(7日)で、安倍政権が沖縄にPAC3を配備した狙い、さらにメディアと一体になって根拠のない「ミサイル」キャンペーンを展開する危険について、6日と8日のブログで述べました(http://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20160206
http://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20160208)。その後の経過はそれを実証するものとなっています。
今回北朝鮮が打ち上げたものは、「ミサイル」ではなく「人工衛星」だったことがはっきりしました。
「米戦略軍は7日・・・『二つの物体』が周回軌道に乗ったことを確認した。北朝鮮が『人工衛星』と主張する物体とミサイル3段目の残骸とみられる。今回、弾道部分を海上などに落とす『再突入体』実験は行わなかったことを意味し、ミサイル実用化へは道半ばといえそうだ」(9日付中国新聞=共同)
8日夜の「報道ステーション」でも、若松義男北海道情報大教授(元JAXAエンジニア)はパネル(写真左)を使って、北朝鮮が発射したロケットは「最終的に人工衛星になった」と解説しました。
にもかかわらず、日米韓政府だけでなく日本の国会(全政党)、メディアが頑として「人工衛星」と認めず「ミサイル」と強弁するのは極めて異様・異常です。
成澤宗男氏(「週刊金曜日」記者)によると、「ある軍事評論家がTV出演の依頼を受け承諾したが、事前にこのこと(北朝鮮が打ち上げたものを『ミサイル』などとは呼べない)を指摘したら、急に出演をキャンセルされた」といいます(「ピース・フィロソフィ・センター」ブログ http://peacephilosophy.blogspot.ca/2016/02/blog-post.html)。驚くべきことです。
発射当日(7日)のNHKテレビでもこんなことがありました。アナウンサーが「北朝鮮が人工衛星に成功・・・」と言いかけたいったとろで突然音声途切れ、数秒後に「事実上の弾道ミサイル」と言い換えたのです。なんとしても「人工衛星」ではなく「ミサイル」にしたいようです。
メディアと一体となった異常な「ミサイル」キャンペーンの狙いは何か。
「機能しない」PAC3の沖縄配備は、自衛隊のイメージアップとともに、アメリカの「ミサイル防衛システム」(MD)への参加・一体化を図る狙いがあると先に述べましたが、そのシナリオが急展開しています。
「米韓両国は7日、米軍の最新鋭地上配備型迎撃システム『高高度防衛ミサイル(THAAD)』の韓国配備を検討する協議を始めると発表した。韓国は北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、日米との軍事協力を拡大する一方、中国の反対を押し切り米軍の迎撃システムを配備する姿勢を鮮明にした。・・・韓国国防省高官は、協議入りはスカパロッティ在韓米軍司令官の提案を受けて決めたとし、早期配備を模索すると表明した」(8日付中国新聞=共同)(写真中は10日TBS系「ひるおび」より)
これにいち早く呼応したのが菅官房長官です。
「菅義偉官房長官は八日の記者会見で、米軍の地上配備型迎撃システム『高高度防衛ミサイル(THAAD)』の国内配備を検討する考えを表明した。・・・菅氏は・・・THAAD配備について・・・『国民を守るため、米国の先進的な取り組みや装備品を研究しつつ検討を加速したい』と述べた」(9日付東京新聞)
さらに安倍首相は9日、朴韓国大統領との電話会談で直接言及しました。
「日韓会談で首相は、米軍の最新鋭地上配備型迎撃システム『高高度防衛ミサイル(THAAD)』の韓国配備に向けた米韓協議を支持した上で『日米韓3カ国の安保協力をぜひ前に進めたい』と意欲を示した」(10日付中国新聞=共同)
そしてまたまたNHKです。NHKは11日朝のニュースで、安倍政権が「THAAD導入へ向け、その効果などの調査・分析を加速させる方針」だと安倍政権の意向を代弁しました(写真右)
THAAD(サード)導入によるMD参画が、アメリカの戦略補完にほかならないことは先に述べました。加えて、サード導入には自衛隊幹部からも、「THAADを導入するとなると莫大な金が必要になり、現実的ではない。それでほかの予算までを削られたらたまらない」(8日付中国新聞=共同)との声が漏れています。それほど「莫大な金」がかかり、5兆円を超えた軍事費をさらに膨張させるのは必至です。
NHKをはじめとするメディアと一体になって北朝鮮の「脅威」を煽り、巨額の軍事費を投じてアメリカの兵器産業からTHAADを購入し、日米韓の軍事一体化を急速に進めようとしている安倍政権の暴走を、絶対に容認することはできません。













