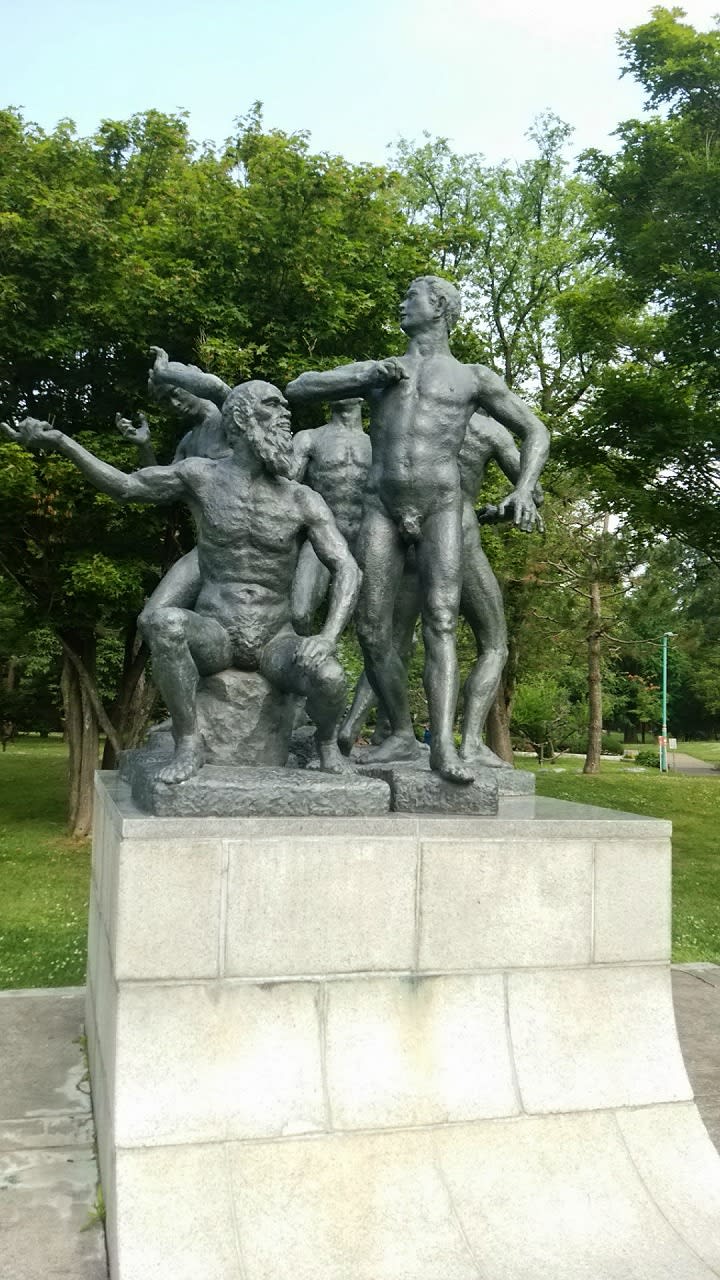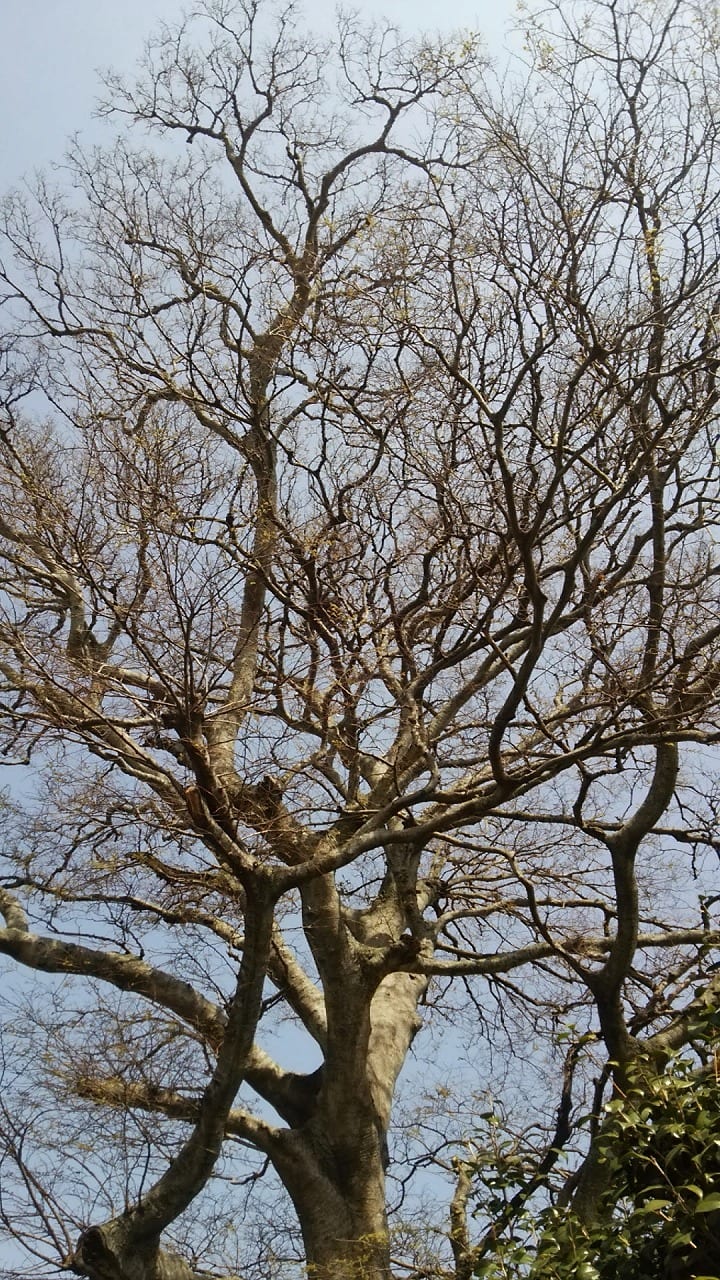古い話になるが、ツイッターでスガシカオがダウンロードよりCD買ってくれ、というような呟きが話題になったことがある。音楽家の現状としてCDが売れた方がいい(つまり儲かる)、さらに厳しいということのようだ。そりゃそうだろうな、とは普通の人なら思うのだが、しかしスガシカオのようなビッグネームでもそうなのか、という衝撃はあるのかもしれない。それでも消費者としてはCDなんか買わないよ、ということかもしれないし、業界何とかしろよ、なのかもしれない。ただ、この図式で少し問題点となりそうなことは、好きな音楽家の活動支援としてCDのようなパッケージを買ったりする意味ということについても言説が及んだようだ。好きだから聞き続けていたい音楽家であっても、食えなくなってやめてしまうのならば、結果的に消費者だって不利益なんじゃないか問題、という考えすぎな人がそれなりに居るらしい。多くの音楽家が食えないというのは過去から連綿と続く現実だとは思うが、その破壊として現在のダウンロードを含むネット環境の価格破壊の話になっているのかもしれない。
それは確かに由々しきこともかもしれないし、音楽以外のネット上の製作者側の都合問題、もしくは生きていく切実さということかもしれない。たとえばニュースだって以前と変わらない、いやむしろもっと多様で広いニーズがありながら、もとを辿れば一番金のかかっている取材本などがちゃんと利益を得られるシステムは崩壊している。大本の資本が巨大だから何とかいまだに生き延びているだけのことで、これが転んだら、無料で配信しながら少なからず利益を得ている末端まで広く崩壊することは間違いなかろう。また、そのような維持が不能になった後、報道の質をどこまで保てるのかという議論は既にかなり問題視されているところである。
音楽の話に戻ると、そもそも問題としては、食える人は少数だ。しかしながらネット上に情報が増えることにより、実際にはビッグネームといわれる人には、以前より多くの金が流れている現実もあるという。米国などは特に顕著なようだが、楽曲は流失しても、リアルにミュージシャンと接するコンサートなどの収入は相対的に増えているらしい。より興味を助長し、音楽家を助けているということだ。また、今までは簡単に宣伝に乗らなかった無名の人であっても、ちょっとしたきっかけで、多くの人の興味を瞬時に得ることも可能になってくる。巨大な資本の傘下に入らずとも、草の根的にビッグネームにのし上がるチャンスは増えたと考えられ、またその課金のやり方しだいでは、より多様に資金の回収の仕方も可能になっているのではないかという話なのだ。
考えてみると日本でもAKBのように握手会のようなイベントでも集客課金が出来るという話題もある。CDで支えられなくなっている現状にスポットを当てすぎることで、そのほかの可能性を見えなくしているとしたら、そもそもの議論として、やはりバランスに欠けたものになるのではないか。またはっきり言ってしまうならば、いくら問題視したとしても、その現状が政治的に変えられる方が弊害が大きいのではないか。CDが売れなくなって困るのは、そのパッケージに頼って商売しているだけの人間にとって不利益になっているということはあっても、だからその現実が元に戻ることの方が不自然になっているのではなかろうか。
もちろんスガシカオの真意としては、そう聞かれたからそう答えたというだけの話だったようだ。彼だって音楽で食う切実さはプロとして分かっているはずなのだ。受け取る側の責任転嫁して発言されているのではなく、恐らく他の食えないかもしれない恐怖の連鎖の方が、過剰にこの発言の重みに屈しているという図式ではなかろうか。それでもやるかやらないか、ひょっとすると馬鹿になれるかどうか。そういう世界の面白さとしては、今も昔もそんなに変わらない事なんじゃなかろうか。