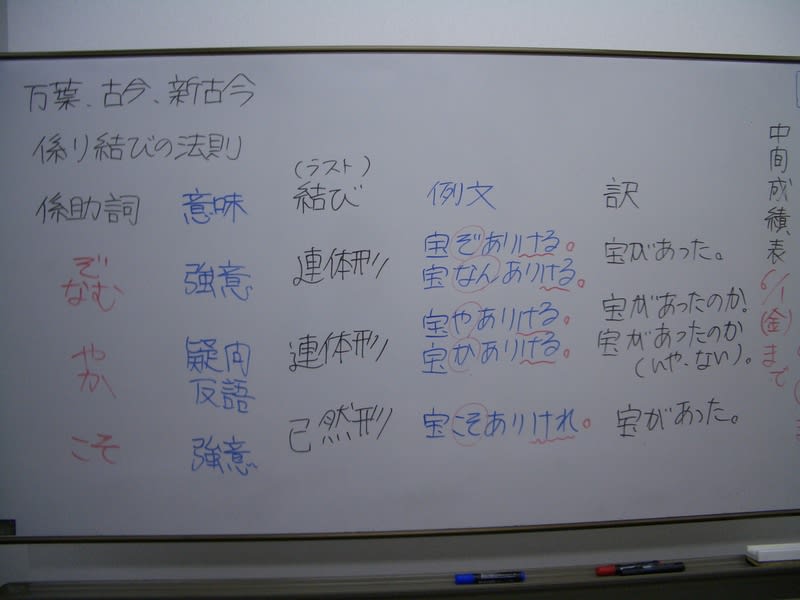写真は、070529、中3国語の授業です。
アビットの普段の国語は、実力養成の読解問題を勉強しています。
あと漢字(語彙)ですね。
そのほうが、北辰会場テスト、入試に必要な力がつくからです。
ただし、定期テスト前は、テスト範囲の教科書内容を勉強します。
また、古典や漢文は、学校の教科書内容を優先に勉強します。
学校で教わっただけでは、なかなか身につかないところですからね~。
アビットでも、全力でフォローしますよ♪
今日は、新古今和歌集の西行法師(さいぎょう ほうし)の和歌を中心に。
「道の辺に 清水流るる 柳陰 しばしとてこそ 立ちどまり( )」
( )には、何が入るか?という問題がありました。
ここで覚えておくことが「係り結びの法則」です。
とにかく「ぞなむやか連体、こそ已然」です!
呪文のように唱えましょう♪
文中に「ぞ」「なむ」「や」があれば、文末は連体形で終わる。
文中に「こそ」があれば、文末は已然形で終わる。
そいいうルールがあります。
上の問題の選択肢は、「けり」「ける」「つる」「つれ」です。
この問題を解答するために必要なので・・・。
古文の助動詞の活用も、少しだけ勉強しましたよ~。
中学校では、ほとんど勉強しないと思いますが・・・。
連体形と已然形がわからないと、問題が解けませんからね(難しいな~)。
まず「けり」。
未然形→連用形→終止形→連体形→已然形→命令形で・・・。
けら→○(なし)→けり→ける→けれ→○(なし)・・・と活用します。
意味は、過去(伝聞)「~たという」、気づき「~たのだ」、詠嘆「~たことよ」。
また「つ」「ぬ」。
未然形→連用形→終止形→連体形→已然形→命令形で・・・。
て→て→つ→つる→つれ→てよ
な→に→ぬ→ぬる→ぬれ→ね
意味は、完了「~た」、強意「~てしまう」。
テキストの問題は・・・。
「道の辺に 清水流るる 柳陰 しばしとてこそ 立ちどまり( )」
文中に、「こそ」がありますよね。
だから、係り結びの法則より、文末は已然形で終わります。
上の問題の選択肢は、「けり」「ける」「つる」「つれ」ですから・・・。
この中では「つれ」だけが已然形です。
答えは「つれ」となります。
まあ、ここまでは中学生では、ほとんどやらないはずです。
とにかく「ぞなむやか連体、こそ已然」だけでも覚えていれば、なんとかなります。
ところで、この和歌の解釈は・・・。
「道のほとりに清水が湧き出して流れている柳の陰、しばらく休もうと思って立ち止まってしまった」
・・・こんな感じです。
中学校の国語の授業では、国語の教科書をあまり使いませんが・・・。
おそらく古典や漢文は、教科書に掲載されているものを使います(去年はそう)。
少し先取りして、わかりやすく勉強していますよ☆