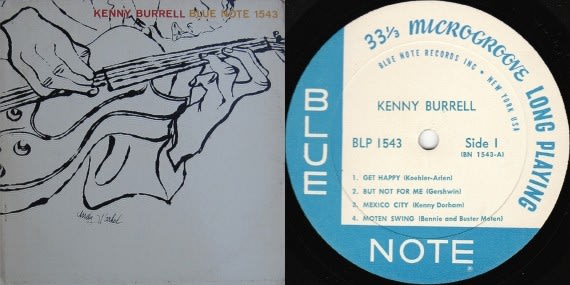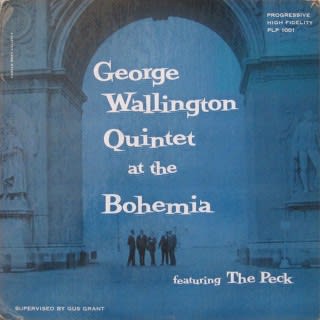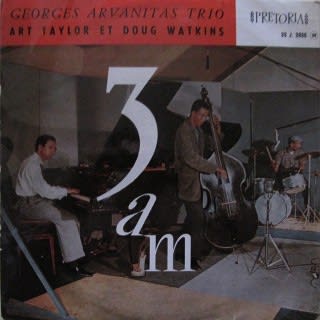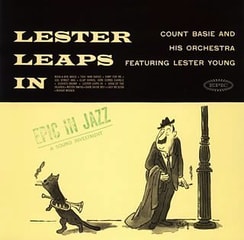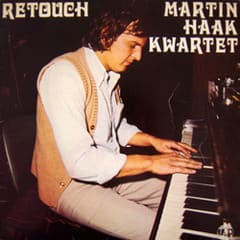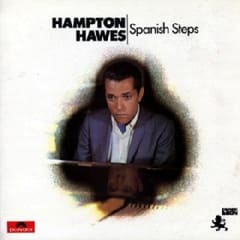前々から欲しかったAnalogue Productions社製「Art Pepper Meets The Rhythm Section」の45回転盤2枚組LP(AJAZ 7532)を手に入れた。このアルバムは星の数ほどあるジャズ・レコードの中でも5指に入るほどの愛聴盤で、コンテンポラリー・レーベルから出たオリジナル盤に加えて1992年にAnalogue Productions社が復刻した180g重量盤(APJ 010)も持っているのだが、巨匠バーニー・グランドマンによる真空管マスタリングが生み出す厚みのあるサウンドがめちゃくちゃ気に入って、それ以来 Analogue Productions という名前には全幅の信頼を置くようになった。
とにかくこの復刻盤の音があまりにも良かったので、このアルバムに関してはこれで十分と思って過ごしてきたのだが、同社が2003年にAcousTech Masteringと銘打って45回転盤2枚組復刻シリーズとして再びこのレコードを出していたということを3年ほど前に知り(←遅っ!!!)、もうこれ以上は望めないんじゃないかと思えるあの音を更に磨き上げたという45回転サウンドをどうしても聴いてみたくなった。私は手を尽くして中古市場を探し回ったのだが時すでに遅しで、運良く見つけても発売時には$50だったものが$300オーバーという鬼のようなプレミア付きの値段が付いており戦意喪失。半ば諦めモードながら一応 Discogsの「ほしい物リスト」に登録しておいた。
そして11月半ばのある日のこと、Discogsから “ほしい物リストのアイテム1点が出品されています” というメールが来た。どうせまた$300~$400やろ... と思いながら見てみると、何と$120という良心的な値付けである。しかも盤質を見るとNMとなっているのだ。違う盤を間違えて出している可能性もあるので一応セラーにメールして確認したが、どうやら本物っぽい。しかもUSセラーにもかかわらず送料は$20だという。私は小躍りしながら「注文する」をクリックした。
USPS(United States Postal Service)を使ったアメリカからの郵便物はトラッキング№で追跡ができるので、私は毎日ネットでUSPSのトラッキング・サービスをチェックしながら到着を心待ちにしていた。このレコードは購入翌日に発送され、カリフォルニアから4日で大阪に着いたので、“この調子やったら明日か明後日には来そうやな...” とウキウキワクワクだったのだが、何とそれから5日間ずっと ‟Held in Customs”(税関で止められてます) 状態が続いたのだ。〝何でやねん?” と不審に思いながら大阪での6日目(!)を迎えた日、“今日もこのままやったら大阪国際郵便局へ直接電話して抗議したろ...” と心を決めてトラッキングのページを開くとステータスが “Customs Clearance Processing Complete”(通関手続き完了)に代わっており、私は安堵の胸をなでおろしたのだった。
しかし話はこれで終わらない。その翌日のお昼頃、家にいる母親から職場のパソコンに(←スマホは大嫌いなので持ってない...)メールが来た。曰く、“今レコードが届いてんけど、国際郵便物課税と消費税で1,400円払わされたで。” とのこと。私は何のことかサッパリ分からなかったので、その “国際郵便物課税” とやらをググってみたところ、個人輸入の場合にかけられるものらしい。えぇ~っ、今まで何千枚というレコードを海外から買ってきたのに何で今回だけ関税がかけられたんやろ??? 税金に疎い私にはまったく納得がいかないが、払わな受け取れへんのならしゃあない。でも税金の上に更に消費税をかけるシステムってホンマにムカつくわ...
納得いかないので更に調べてみたところ、“価格が1万円を超える輸入郵便物については、個人使用の物品や贈与品(GIFT)であっても関税と消費税が課税される。” とある。もしやと思い、帰ってパッケージに貼り付けられた送付状を確認すると、案の定 value 欄にはバカ正直に$120と書いてあって、ようやく状況が呑み込めてきた。
因みに「国際郵便物課税通知書」「領収証書」の他に「不服申し立て等について」という書面が入っており、“この処分(←何でレコード買うて「処分」されなあかんのや?)について不服がある時は(←めっちゃ不服やぞ!)大阪税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に係る処分(←つまり消費税分200円のことか...)については国税不服審判所長(←そんな役職あったんかwww)に対して審査請求をすることができます。” と書いてあった。税金をむしり取られるのはめちゃくちゃ腹立たしいが、だからと言ってたかだか1,400円のために裁判するほどヒマではない。
とまぁこのようにスッタモンダの末に手に入れたこのレコードだが、音質の方はさすがにAnalogue Productions だけあって文句ナシだ。マスタリング・エンジニアは手持ちの92年盤がバーニー・グランドマンだったのに対し、今回手に入れた03年盤の方はスティーヴ・ホフマン... どちらも真空管を使ったマスタリングにかけては超の付く一流エンジニアである。
聴き比べしてみた結果は実に興味深いもので、ざっくり言うとコクの92年盤 vs キレの03年盤、という感じで、92年盤の方がナチュラルな音場感で勝り、03年盤の方が各楽器のディテールの鮮明さで一日の長があった。バーニー・グランドマンはさすがロイ・デュナンの愛弟子だけあってペッパーのアルトが実にナチュラルにふっくらと鳴るし、スティーヴ・ホフマンの方はとにかく各楽器本来の音が再現されており、結論としては “オリジナルLPの音を更にブラッシュアップして現代に蘇えらせた92年盤” と “当時の録音現場で実際に鳴っていた音の忠実な再現を極めた03盤” というのが私なりの感想で、このアルバムが好きなら両方持っていて損はないスーパーウルトラ高音質盤だと思う。まぁこれだけ良い音が楽しめたのだから、1,400円の関税など安いものだと笑い飛ばすことにしよう。
Art Pepper Quartet - You'd Be So Nice to Come Home To
とにかくこの復刻盤の音があまりにも良かったので、このアルバムに関してはこれで十分と思って過ごしてきたのだが、同社が2003年にAcousTech Masteringと銘打って45回転盤2枚組復刻シリーズとして再びこのレコードを出していたということを3年ほど前に知り(←遅っ!!!)、もうこれ以上は望めないんじゃないかと思えるあの音を更に磨き上げたという45回転サウンドをどうしても聴いてみたくなった。私は手を尽くして中古市場を探し回ったのだが時すでに遅しで、運良く見つけても発売時には$50だったものが$300オーバーという鬼のようなプレミア付きの値段が付いており戦意喪失。半ば諦めモードながら一応 Discogsの「ほしい物リスト」に登録しておいた。
そして11月半ばのある日のこと、Discogsから “ほしい物リストのアイテム1点が出品されています” というメールが来た。どうせまた$300~$400やろ... と思いながら見てみると、何と$120という良心的な値付けである。しかも盤質を見るとNMとなっているのだ。違う盤を間違えて出している可能性もあるので一応セラーにメールして確認したが、どうやら本物っぽい。しかもUSセラーにもかかわらず送料は$20だという。私は小躍りしながら「注文する」をクリックした。
USPS(United States Postal Service)を使ったアメリカからの郵便物はトラッキング№で追跡ができるので、私は毎日ネットでUSPSのトラッキング・サービスをチェックしながら到着を心待ちにしていた。このレコードは購入翌日に発送され、カリフォルニアから4日で大阪に着いたので、“この調子やったら明日か明後日には来そうやな...” とウキウキワクワクだったのだが、何とそれから5日間ずっと ‟Held in Customs”(税関で止められてます) 状態が続いたのだ。〝何でやねん?” と不審に思いながら大阪での6日目(!)を迎えた日、“今日もこのままやったら大阪国際郵便局へ直接電話して抗議したろ...” と心を決めてトラッキングのページを開くとステータスが “Customs Clearance Processing Complete”(通関手続き完了)に代わっており、私は安堵の胸をなでおろしたのだった。
しかし話はこれで終わらない。その翌日のお昼頃、家にいる母親から職場のパソコンに(←スマホは大嫌いなので持ってない...)メールが来た。曰く、“今レコードが届いてんけど、国際郵便物課税と消費税で1,400円払わされたで。” とのこと。私は何のことかサッパリ分からなかったので、その “国際郵便物課税” とやらをググってみたところ、個人輸入の場合にかけられるものらしい。えぇ~っ、今まで何千枚というレコードを海外から買ってきたのに何で今回だけ関税がかけられたんやろ??? 税金に疎い私にはまったく納得がいかないが、払わな受け取れへんのならしゃあない。でも税金の上に更に消費税をかけるシステムってホンマにムカつくわ...
納得いかないので更に調べてみたところ、“価格が1万円を超える輸入郵便物については、個人使用の物品や贈与品(GIFT)であっても関税と消費税が課税される。” とある。もしやと思い、帰ってパッケージに貼り付けられた送付状を確認すると、案の定 value 欄にはバカ正直に$120と書いてあって、ようやく状況が呑み込めてきた。
因みに「国際郵便物課税通知書」「領収証書」の他に「不服申し立て等について」という書面が入っており、“この処分(←何でレコード買うて「処分」されなあかんのや?)について不服がある時は(←めっちゃ不服やぞ!)大阪税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に係る処分(←つまり消費税分200円のことか...)については国税不服審判所長(←そんな役職あったんかwww)に対して審査請求をすることができます。” と書いてあった。税金をむしり取られるのはめちゃくちゃ腹立たしいが、だからと言ってたかだか1,400円のために裁判するほどヒマではない。
とまぁこのようにスッタモンダの末に手に入れたこのレコードだが、音質の方はさすがにAnalogue Productions だけあって文句ナシだ。マスタリング・エンジニアは手持ちの92年盤がバーニー・グランドマンだったのに対し、今回手に入れた03年盤の方はスティーヴ・ホフマン... どちらも真空管を使ったマスタリングにかけては超の付く一流エンジニアである。
聴き比べしてみた結果は実に興味深いもので、ざっくり言うとコクの92年盤 vs キレの03年盤、という感じで、92年盤の方がナチュラルな音場感で勝り、03年盤の方が各楽器のディテールの鮮明さで一日の長があった。バーニー・グランドマンはさすがロイ・デュナンの愛弟子だけあってペッパーのアルトが実にナチュラルにふっくらと鳴るし、スティーヴ・ホフマンの方はとにかく各楽器本来の音が再現されており、結論としては “オリジナルLPの音を更にブラッシュアップして現代に蘇えらせた92年盤” と “当時の録音現場で実際に鳴っていた音の忠実な再現を極めた03盤” というのが私なりの感想で、このアルバムが好きなら両方持っていて損はないスーパーウルトラ高音質盤だと思う。まぁこれだけ良い音が楽しめたのだから、1,400円の関税など安いものだと笑い飛ばすことにしよう。
Art Pepper Quartet - You'd Be So Nice to Come Home To