現代農業9月号の主張として、「新自由主義的復興論を批判する。」が掲載されている。震災のどさくさにまぎれての、火事場泥棒的経団連「復興・創生」プランを徹底批判している。批判としても的を得ているうえに、後半部分の今農村で起きている構造的変化の分析が興味深い。いくつかの論文を引用をしながら、農村の生の状況を深くとらえている。現代の農村の状況は、そこに暮らす者にもとらえきれない多面的な問題が、混在して現われている。部外者の評論的分析が、的外れな物言いが多く失望を重ねている。農文協らしく農業者に密着した、正確な見解を主張している。現代日本社会の矛盾のすべてが農村に集約されているともいえる。国際競争力の強化の為に、山間地の小さな集落なら犠牲に成っても構わないという構造である。矛盾が集中している分野としての、農業農村を考察すると言うことは、世界経済の動向を充分考慮しながら、「むら」のこれからを考えなくてはならない状況、と言うことに成る。
一つ残念なことは、農文協の主張では土地所有制度には論究していない。この点が物足りない。私有財産制の呪縛が、純粋な食糧生産と言う農業本来の目的を歪めている現実に、踏み込んでいないという点である。資産としての農地。資産を管理するという農業の側面。ここから抜け出ない限り次の段階を考察することは難しいのではないだろうか。食糧と言うものを他の生産品と明確に分けて考える必要がある。食糧は水と同等の生活の基本要素である。国が等しく国民全体に保証する義務を負って居るものである。すべての生産品が生活必需品であると言えないこともないのだが、農産物については別枠で考えるべきものではないか。その食糧を生産する場である農地とは、どういう性格のもんであるか。食糧生産の担い手が不足している現実がある。この主張では単純にそうとも言えない実態を示して、正論である。しかし、農地の担い手は年々不足が深刻化している事実は認識せざる得ない。この点は、複雑な社会的矛盾の中に絡み合った問題であるので、単純な判断は危険がある。
「農地をむらから切り離してはならない。」この主張の中心である。むらとは何か。このことと向かい合わなくてはならない。「むら」というものが、封建制の象徴として、農業離れのひとつの要素になった。それは大資本が望む戦略でもあったが、村が精神的に自由な空間で無かったことも確かである。個人の自主性を尊重すべきとする、近代主義的な生き様と、むらという集合としての制約をどこで調和できるのかである。一人ひとりの生き方が保証された形で、しかも、むらと言う暮らしの最小単位が、集合した生命体として、もう一度自由に動き出す仕組みを作り出せるのか。農の会が目指している「新しいむら」は、今までにない組織なのだと思う。地域の中での、例えば集落営農集団としてのテーマコミュニテ―の再編。その集落営農がどこまでも個人の生き方を尊重できるのかが、具体的にはイメージできないでいる。生き方としての農業論が論議されない限り、経営としてだけの営農集団は、経済競争の中でその意義を歪められてゆくことになる。
引用―――かくして農地管理は、「農地の権利移動のみを意味するのではなく、地域にとって望ましい農地利用一般の実現を課題とする。農地の作付協定、農作業の効率化、合理化のための利用調整等、多様な内容を地域の状況に応じて、地域の自律的な取組みを前提として実現する」ものであり、「農地流動化の加速、流動化率の向上といった、国が設定した目標達成にのみ還元されるものではない」のである。―――
主張は以上を結論として終わっているが、実はこの部分が肝心であるにかかわらず、その意味が分かりにくい。地域経済と農業に連関が薄くなるなか、どのような村の思想でこれをつなげるかがカダではないか。地域と薄い関係の中で、実際の農作業を行う多くの農業者との感覚のづれ。農地の作付協定。と一言で書けるが、その過程が血に成っていない。農作業の効率化。これも同様である。むらの目的が同じであれば効率化も、作付協定もできるが、生きる目的の共有化が出来ていない関係の中での話し合いは、経済性に偏ることに成りがちである。少なくとも経済的合理性の主張を、乗り越えることは難しい。そこにも農地の個人所有を越える思想の提起が必要になると思えるのだが。
一つ残念なことは、農文協の主張では土地所有制度には論究していない。この点が物足りない。私有財産制の呪縛が、純粋な食糧生産と言う農業本来の目的を歪めている現実に、踏み込んでいないという点である。資産としての農地。資産を管理するという農業の側面。ここから抜け出ない限り次の段階を考察することは難しいのではないだろうか。食糧と言うものを他の生産品と明確に分けて考える必要がある。食糧は水と同等の生活の基本要素である。国が等しく国民全体に保証する義務を負って居るものである。すべての生産品が生活必需品であると言えないこともないのだが、農産物については別枠で考えるべきものではないか。その食糧を生産する場である農地とは、どういう性格のもんであるか。食糧生産の担い手が不足している現実がある。この主張では単純にそうとも言えない実態を示して、正論である。しかし、農地の担い手は年々不足が深刻化している事実は認識せざる得ない。この点は、複雑な社会的矛盾の中に絡み合った問題であるので、単純な判断は危険がある。
「農地をむらから切り離してはならない。」この主張の中心である。むらとは何か。このことと向かい合わなくてはならない。「むら」というものが、封建制の象徴として、農業離れのひとつの要素になった。それは大資本が望む戦略でもあったが、村が精神的に自由な空間で無かったことも確かである。個人の自主性を尊重すべきとする、近代主義的な生き様と、むらという集合としての制約をどこで調和できるのかである。一人ひとりの生き方が保証された形で、しかも、むらと言う暮らしの最小単位が、集合した生命体として、もう一度自由に動き出す仕組みを作り出せるのか。農の会が目指している「新しいむら」は、今までにない組織なのだと思う。地域の中での、例えば集落営農集団としてのテーマコミュニテ―の再編。その集落営農がどこまでも個人の生き方を尊重できるのかが、具体的にはイメージできないでいる。生き方としての農業論が論議されない限り、経営としてだけの営農集団は、経済競争の中でその意義を歪められてゆくことになる。
引用―――かくして農地管理は、「農地の権利移動のみを意味するのではなく、地域にとって望ましい農地利用一般の実現を課題とする。農地の作付協定、農作業の効率化、合理化のための利用調整等、多様な内容を地域の状況に応じて、地域の自律的な取組みを前提として実現する」ものであり、「農地流動化の加速、流動化率の向上といった、国が設定した目標達成にのみ還元されるものではない」のである。―――
主張は以上を結論として終わっているが、実はこの部分が肝心であるにかかわらず、その意味が分かりにくい。地域経済と農業に連関が薄くなるなか、どのような村の思想でこれをつなげるかがカダではないか。地域と薄い関係の中で、実際の農作業を行う多くの農業者との感覚のづれ。農地の作付協定。と一言で書けるが、その過程が血に成っていない。農作業の効率化。これも同様である。むらの目的が同じであれば効率化も、作付協定もできるが、生きる目的の共有化が出来ていない関係の中での話し合いは、経済性に偏ることに成りがちである。少なくとも経済的合理性の主張を、乗り越えることは難しい。そこにも農地の個人所有を越える思想の提起が必要になると思えるのだが。












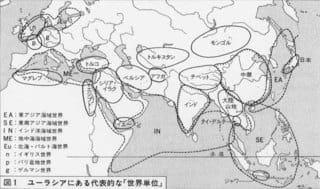
 『タッズよ、ありがとう』玉那覇 葉音著が送られてきた。手に取るや否や、一気に最後まで読んでしまった。涙が流れて止まらなかった。タッズはアメリカン・ピット・ブルテリアのショードッグのチャンピオン犬である。あえて、ショードックとつけなければならないのは、ピットと名前にあるように、アメリカン・ピット・ブルテリアは闘犬用犬種として一般には見られているからである。この不幸な犬種は、最強の犬と呼ばれる不幸を負っている。かつてのブルバイキングに使われていた、ブルドックと同じ運命である。高校生当時、ラブラドルリトリバーとブルドックを飼っていた。それは父も子供の頃ブルドックを飼っていて、その叔父は明治末期に横須賀で大津ブルドックケンネルという、犬舎をやっていたと、何度も聞いていたからである。ブルドックほど魅力がある犬は居ないと、刷り込まれていた。本気で飼ったブルドックはとても病弱だった。夏の花火の音に驚いて死んでしまった。
『タッズよ、ありがとう』玉那覇 葉音著が送られてきた。手に取るや否や、一気に最後まで読んでしまった。涙が流れて止まらなかった。タッズはアメリカン・ピット・ブルテリアのショードッグのチャンピオン犬である。あえて、ショードックとつけなければならないのは、ピットと名前にあるように、アメリカン・ピット・ブルテリアは闘犬用犬種として一般には見られているからである。この不幸な犬種は、最強の犬と呼ばれる不幸を負っている。かつてのブルバイキングに使われていた、ブルドックと同じ運命である。高校生当時、ラブラドルリトリバーとブルドックを飼っていた。それは父も子供の頃ブルドックを飼っていて、その叔父は明治末期に横須賀で大津ブルドックケンネルという、犬舎をやっていたと、何度も聞いていたからである。ブルドックほど魅力がある犬は居ないと、刷り込まれていた。本気で飼ったブルドックはとても病弱だった。夏の花火の音に驚いて死んでしまった。 タッズ犬舎から来た犬を飼う全ての人から、タッズ父として慕われている人である。この本にあるように、タッズという名犬に人生を変えてもらった人である。そして、この不幸な運命を負った犬種を、認知してもらうために生きている人である。タッズファミリーとしての同意書に判を押さなければ、譲れない。京都まで来てもらわなければ譲れない。部屋飼いが出来ない人には譲らない。我が家にも、どんな飼い方をしているか確認に見えた。京都の犬舎に伺うと、初対面の私に対し、タッズは堂々と近づいてきて、その大きな舌で顔をぺろぺろ舐めて親愛の情を示してくれた。博愛主義である。警戒心というものがない。じゃれているのではなく、受け入れてくれている事がわかる。本当の強い心を持った犬種だと言う事がわかった。こんな犬に育てなくてはいけないと、考えた。雷田を連れてかえる私たちを駅まで送ってくれた、タッズ母は別れが辛くて泣き続けていた。
タッズ犬舎から来た犬を飼う全ての人から、タッズ父として慕われている人である。この本にあるように、タッズという名犬に人生を変えてもらった人である。そして、この不幸な運命を負った犬種を、認知してもらうために生きている人である。タッズファミリーとしての同意書に判を押さなければ、譲れない。京都まで来てもらわなければ譲れない。部屋飼いが出来ない人には譲らない。我が家にも、どんな飼い方をしているか確認に見えた。京都の犬舎に伺うと、初対面の私に対し、タッズは堂々と近づいてきて、その大きな舌で顔をぺろぺろ舐めて親愛の情を示してくれた。博愛主義である。警戒心というものがない。じゃれているのではなく、受け入れてくれている事がわかる。本当の強い心を持った犬種だと言う事がわかった。こんな犬に育てなくてはいけないと、考えた。雷田を連れてかえる私たちを駅まで送ってくれた、タッズ母は別れが辛くて泣き続けていた。




