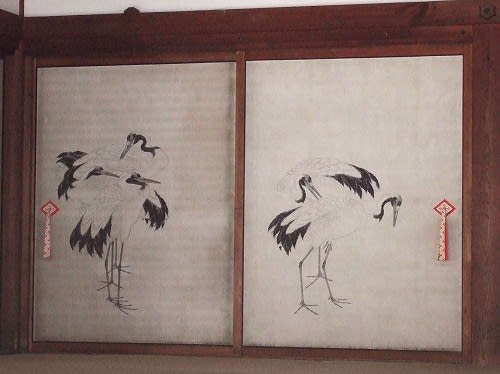2010年4月20日(火)
この日は11時から、京都市街の中心、京都御苑の一角にある仙洞御所(せん
とうごしょ)の拝観を申し込んであったので、その前に、近くの相国寺(しょうこくじ)
と京都御苑を回りました。
相国寺は、京都御苑の北側にあり、足利義満が創建した禅宗五山のひとつで、
下の図のように広い境内に、多くの堂塔が並んでいます。

これは宝塔。

背の高いアカマツの向こうの大きな建物は、本堂に当たる法堂。

東北の隅にある飛天閣と呼ぶ美術館に向かう両側は、みずみずしいモミジの新緑
が続いていました。

モミジの下は、やわらかなコケに覆われています。


秋のような彩りのモミジも。

飛天閣の入口左手には、大きなソテツもありました。

法堂の北側に回りました。法堂は、慶長10年(1605)、豊臣秀頼の寄進による
ものです。

法堂の東側にある鐘楼。

南側に並ぶ同志社大の、幾つかのレンガ造りの建物の間を南進し、京都御苑
に入ります。
京都御苑は、京都御所や、このあと拝観する仙洞御所を含む約65haの、緑が
いっぱいの国民公園。明治2年(1869)に御所が東京に移るまで、約200軒の
公家屋敷や宮家があったところです。

園内北側に、シダレザクラが咲き残っていました。
東の方に回ると、皇女和宮誕生の地といわれる橋本家跡の表示がありました。

和宮は、弘化3年(1846)にこの地で生まれ、14歳までここで育ったとか。
有栖川宮との婚約を破棄され、14代将軍・徳川家茂(いえもち)に降嫁したことは
よく知られたとおりです。
近くには、学習院跡の表示もあります。

学習院というと、東京・目白がすぐ浮かんできますが、この地は、安永8年(1779)
に皇位を継いだ光格天皇が公家の教育振興に取り組もうと考たのが発端で、弘化4
年(1847)に開講したとのことです。
京都御所の周囲は、高い土塀に囲まれていますが、ここは内部に入る門のひとつ。

普段は閉ざされたままのようです。
こちらは、このあと拝観する仙洞御所の長い土塀。

塀の中にある八重桜が、花を見せていました。

この日は11時から、京都市街の中心、京都御苑の一角にある仙洞御所(せん
とうごしょ)の拝観を申し込んであったので、その前に、近くの相国寺(しょうこくじ)
と京都御苑を回りました。
相国寺は、京都御苑の北側にあり、足利義満が創建した禅宗五山のひとつで、
下の図のように広い境内に、多くの堂塔が並んでいます。

これは宝塔。

背の高いアカマツの向こうの大きな建物は、本堂に当たる法堂。

東北の隅にある飛天閣と呼ぶ美術館に向かう両側は、みずみずしいモミジの新緑
が続いていました。

モミジの下は、やわらかなコケに覆われています。


秋のような彩りのモミジも。

飛天閣の入口左手には、大きなソテツもありました。

法堂の北側に回りました。法堂は、慶長10年(1605)、豊臣秀頼の寄進による
ものです。

法堂の東側にある鐘楼。

南側に並ぶ同志社大の、幾つかのレンガ造りの建物の間を南進し、京都御苑
に入ります。
京都御苑は、京都御所や、このあと拝観する仙洞御所を含む約65haの、緑が
いっぱいの国民公園。明治2年(1869)に御所が東京に移るまで、約200軒の
公家屋敷や宮家があったところです。

園内北側に、シダレザクラが咲き残っていました。
東の方に回ると、皇女和宮誕生の地といわれる橋本家跡の表示がありました。

和宮は、弘化3年(1846)にこの地で生まれ、14歳までここで育ったとか。
有栖川宮との婚約を破棄され、14代将軍・徳川家茂(いえもち)に降嫁したことは
よく知られたとおりです。
近くには、学習院跡の表示もあります。

学習院というと、東京・目白がすぐ浮かんできますが、この地は、安永8年(1779)
に皇位を継いだ光格天皇が公家の教育振興に取り組もうと考たのが発端で、弘化4
年(1847)に開講したとのことです。
京都御所の周囲は、高い土塀に囲まれていますが、ここは内部に入る門のひとつ。

普段は閉ざされたままのようです。
こちらは、このあと拝観する仙洞御所の長い土塀。

塀の中にある八重桜が、花を見せていました。