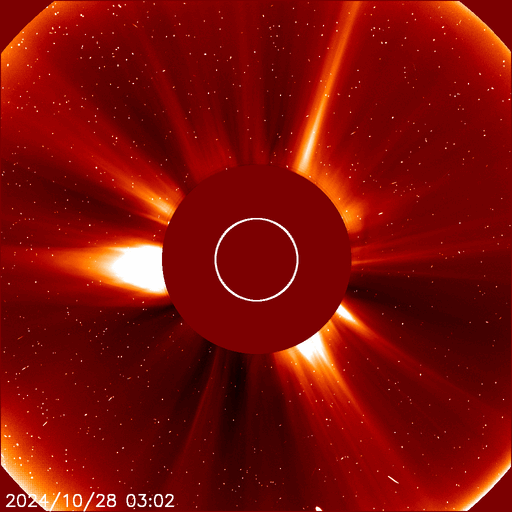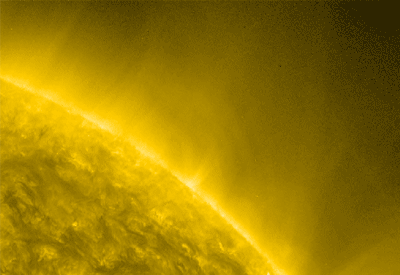紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)8回目の観望記録です。
10月20日は紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)が夕方の空で見えるようになってから、月明かりのない薄明終了後の夜空で初めて見ることができる日です。とはいっても薄明終了が18時18分で、月出が18時28分なので、薄明終了後の夜空は計算上は10分しかありません。
そこで今回は夜空が一番暗くなった時間はいつなのかを把握するためSQM(
スカイクオリティメーター )でソラノクラサを計測しながら紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)を撮影します。
観測地はなるべく空が暗いところがいいので10月2日に行った紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)3rd
観望場所 にしました。ここは数値上では蔵王よりも空が暗い場所です。
気になる天気ですが予報は快晴で、晴れガールの妻も同行しているので天気の心配はまったくありません。日没前は西空にわずかに雲がありましたが日没後は見事な快星になりました~。
日没時刻は16時50分です。1等星が見え始める時刻は17時40分頃ですが、なんと17時32分にはデジカメ上で彗星を
確認 することができました。さすが空が暗い場所は違います。
17時50分を過ぎる頃には肉眼でスッと伸びる尾がはっきり見えました。ここで車の中で待機している宙ガールさんに声を掛けてほうき星観望会の始まりです。
17時54分に撮影した紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)
2024/10/20 17h54m44s D810A Zoom-NIKKOR*ED 50-300mm F4.5 f300mm ISO3200 25sec ↑ 焦点距離300mm photo
まずチェアに座ってもらって双眼鏡で紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)を見つけてもらいます。上の方に伸びている尾も確認したところで双眼鏡から目を離して眼視で彗星を見てもらいます。
2024/10/20 17h56m28s D810A Zoom-NIKKOR*ED 50-300mm F4.5 f100mm ISO3200 60sec ↑ 焦点距離100mm photo
あ~、あれね、うん、見える。尾が伸びているのも分かる… これがほうき星なのね、初めて見た… とご満悦そうでした。尾が伸びている方を見上げると… ほほう、天の川が色濃く見えます。その中に明るい3つの1等星が見えます。そうです。夏の大三角です。
夏の大三角がわからなくなるほど色濃い天の川も凄かったのですが、その下にまっすぐ尾を伸ばしたほうき星があるなんて、これまで見たことがあっただろうか… と悦に浸ってる時間はありません! 月が昇ってきます!撮影を急ぎましょう。
こちらは尾の長さを実測するために感度を上げて撮影した紫金山・アトラス彗星です。なんと尾はあの死者をも蘇らせるへびつかい座の医神アスクレピオスの体を突っ切って右肩まで伸びています。
2024/10/20 18h05m31s D810A Zoom-NIKKOR*ED 50-300mm F4.5 f50mm ISO10000 20sec ↑ 焦点距離50mmです! photo
眼視で見えた尾の長さは約13°でしたが、この写真を使ってステラナビで計測すると尾の長さははっきり確認できるところで19°、ひいき目で見ると20°は伸びているかな…という感じです。(
photo )
2024/10/20 18h05m31s D810A Zoom-NIKKOR*ED 50-300mm F4.5 f50mm ISO10000 20sec モノクロ反転 ↑ 焦点距離50mm
空が最も暗い時間に撮影した紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)
*SQM測定値20.91 2024/10/20 18h12m52s D810A Zoom-NIKKOR*ED 50-300mm F4.5 f300mm ISO12800 15sec ↑ 焦点距離300mm photo
紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)と天の川
2024/10/20 18h26m26s D810A AS-F NIKKOR 24mm-70mm F2.8 ED f24mm F2.8 ISO6400 15sec ↑ 焦点距離24mm photo
月出の3分前ですが空はすでに月明かりの影響を受け始めました。
*SQM測定値20.72 2024/10/20 18h27m07s D810A AS-F NIKKOR 24mm-70mm F2.8 ED f70mm F2.8 ISO6400 15sec ↑ 焦点距離70mm
月出3分後には空が急速に明るくなって、彗星の姿が見る見るやせ細っていきました。天の川もすでに眼視では見えません。明るい空ではまるで別のほうき星を見ているかのように小さく感じます。
2024/10/20 18h31m46s D810A AS-F NIKKOR 24mm-70mm F2.8 ED f30mm F2.8 ISO6400 15sec ↑ 焦点距離30mm
東に見える山の端から強烈な月光を放って月が昇ってきました。まるで背後からスポットライトを浴びたかのように自分の影が伸びているその先で、月光に負けじと尾を伸ばしている紫金山・アトラス彗星が空に浮かんでいます… それは神々しささえ感じるすばらしい眺めでした~。
2024/10/20 18h49m12s D810A AS-F NIKKOR 24mm-70mm F2.8 ED f38mm F2.8 ISO6400 10sec ↑ 焦点距離38mm
本日のラストフォト
2024/10/20 19h25m54s D810A AS-F NIKKOR 24mm-70mm F2.8 ED f70mm F2.8 ISO3200 8sec ↑ 焦点距離70mm
*撮影時の月高度はすでに8°に達していて地上が月明かりで昼間のように写ってます。私の眼力ではこの時の彗星は見えませんでした。
*SQM測定値19.85 月齢17.7 輝面比0.87
さて、SQM(スカイクオリティメーター)によるソラノクラサですが、測定結果は下記のとおりでした
。
注:SQM測定はすべて天頂方向です。
時刻 彗星高度 SQM測定値 月高度
17:20 33° - -航海薄明開始-
17:30 31° 17.23
17:40 29° -
17:50 27° 19.61 -天文薄明開始-
18:00 25° 20.52
18:10 24°
20.91 SQM最高値
18:18 23° - -天文薄明終了-
18:25 21° 20.72
18:28 20° 20.71 -月出-
18:35 19° 20.54 1°
18:40 18° 20.47 2°
18:55 16° 20.28 3°
19:00 15° 20.20 4°
19:05 14° 20.20 5°
19:10 12° 19.94 6°
19:20 10° 19.98 7°
19:25 9° 19.95 8°
19:30 8° 19.85 8°
〈考察〉
予想どおり月明かりの影響は月出時刻より前に現れていた。空が最も暗かったのは天文薄明が終わる10分前から薄明終了時刻までだったと思われる。
撮影場所はLight pollution map上ではSQM値21.79となっている地点だが今回のベスト測定値が20.91だったのは天文薄明終了と同時に月齢18の月明かりの影響が出たからだと思われる。
月明かりがなくて生活光の影響も受けない場所であればさらに長い尾が撮影できていたかもしれない。とはいえ眼視で約13°、画像で19°の尾を伸ばした紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)は誰もが認める令和の大彗星だったと記憶されることだろう。
となると令和の大彗星論議の対象となるのが2020年(令和2年)7月に出現したネオワイズ彗星(C/2020 F3) だ。撮影画像はともかく眼視で見た(
ネオワイズ彗星は実測SQM値21.36mag の地点で観望 )感じでは、尾の派手さ(広がり)では明らかにネオワイズ彗星(C/2020 F3) が勝っていたと言える。
しかし、尾の長さと見た目のほうき星らしさ(容姿?)と天の川と一緒に見えたというロケーションを加味すると紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)に軍配が上がる感じがする。
(個人的な感想で~す)
〈観望中の空(ソラノクラサの変化)の様子〉
VIDEO
今後、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)は暗くなって尾の長さも短くなるが、高度が上がって月も細くなるので観望条件は良くなっていく。予報を見ると不安定な天気が続くようだが、晴れ間を見つけてもうしばらくウオッチングを続けることにしよう。
 午後から天気が良くなったので青空の中のアトラス彗星(C/2024 G3)を探してみました。
午後から天気が良くなったので青空の中のアトラス彗星(C/2024 G3)を探してみました。