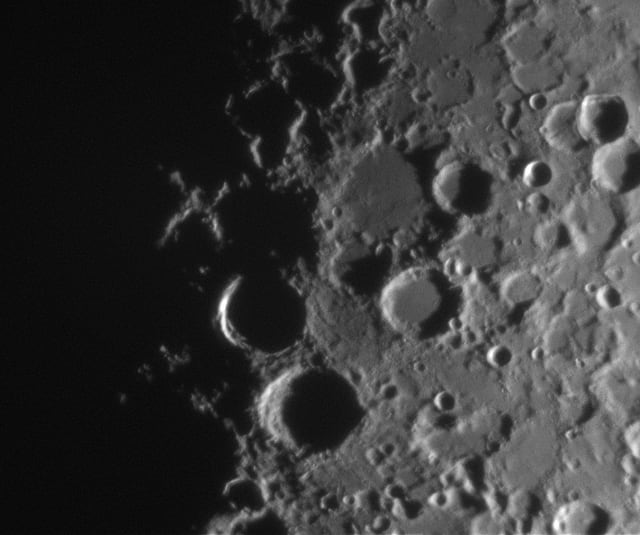1月11日に撮影した木星の記録です。

数日前からWindyの高層天気図で偏西風が南下する予報が出ていたので注視していたのですが、直前の予報では
250hPa(10km)が風速25m/sという冬ではあり得ない穏やかな風速になっていました。
まー、いくら風速25m/sといっても真夏の風速25m/sとはモノが違うよね~、とは思いましたがどんなもんか確かめるべく撮影を決行しました~。
本日の木星データは、光度 -2.5等級、視直径42.5"、地球からの距離は6億9450万kmです。11月3日の衝の時は、光度 -2.9等級、視直径49.5"、地球からの距離は5億9700万kmだったので1億kmも遠ざかっていたのですね。
で、撮影システムは、μ210+アイピースPL25mm+TCA-4+ASI290MC(UV/IRcut)にしてみました。ピント合わせはピント支援装置を使わずPC画面上の木星で判断しましたが、木星が小刻みに揺れているのでピンの追い込みはイマイチでした。
やはり、250hPa(10km)=風速25m/sといっても真夏とは大気の質が違います。期待するほどの解像度にはならないとは思いますが、この気流でどの程度写るかはやってみないと分からないので空の状態が悪くなる前に撮影を始めましょう。

こちらが本日のファーストショット、写っている衛星はイオです。17時52分、高度62°

2024/1/11 17h52m(JST)CMI=162.9° CMII=139.5° CMIII=195.5°
Duration=60s Shutter=6ms Gain=350 (58%) 50% of 9997frames ap27

17時53分、高度62°

2024/1/11 17h53mCMI=164.0° CMII=140.5° CMIII=196.5°
Duration=60s Shutter=6ms Gain=350 (58%) 50% of 9994frames ap27

17時55分、高度62°

2024/1/11 17h55m(JST)CMI=165.1° CMII=141.6° CMIII=197.6°
Duration=60s Shutter=10ms Gain=310 (51%) 50% of 5998frames ap29

18時03分、高度63°

2024/1/11 18h03m(JST)CMI=169.5° CMII=146.0° CMIII=202.0°
Duration=60s Shutter=7ms Gain=350 (58%) 50% of 8573frames ap31

18時04分、高度63°

2024/1/11 18h04m(JST)CMI=170.4° CMII=146.8° CMIII=202.9°
Duration=90s Shutter=7ms Gain=350 (58%) 50% of 12857frames ap31

18時06分、高度63°

2024/1/11 18h06m(JST)CMI=171.5° CMII=147.9° CMIII=204.0°
Duration=60s Shutter=13ms Gain=300 (50%) 50% of 18618frames ap31
う~む、どーもピントがイマイチなので、ここで望遠鏡をベテルギウスに向けて
バーティノフ・マスクを使ってピント合わせタイムです。ついでに拡大撮影アダプターTCA-4をちょっとだけ引き出して拡大率をアップしました!
惑星カメラのパラメータで確かめたところ合成焦点距離は5400mmから5450mmに… あれ?そんだけ? PC画面上ではいい感じに大きくなったのですが…
しか~し、それが奏効したのか、調整後の撮影で本日のベストフォトが出ました!(単に気流がよかっただけだとは思いますが…)

本日のベストフォト! 18時08分、高度63°

2024/1/11 18h08m(JST)CMI=172.7° CMII=149.1° CMIII=205.2°
Duration=60s Shutter=13ms Gain=300 (50%) 50% of 4616frames ap30
シーイングはこんな感じでした。↑ 18時08分の元動画です。

18時09分、高度63°

2024/1/11 18h09m(JST)CMI=173.5° CMII=149.9° CMIII=206.0°
Duration=90s Shutter=13ms Gain=300 (50%) 50% of 6922frames ap34

18時12分、高度63°

2024/1/11 18h12m(JST)CMI=175.0° CMII=151.4° CMIII=207.4°
Duration=60s Shutter=7ms Gain=350 (58%) 50% of 8572frames ap31

18時13分、高度63°

2024/1/11 18h13m(JST)CMI=175.9° CMII=152.3° CMIII=208.3°
Duration=90s Shutter=7ms Gain=350 (58%) 50% of 12856frames ap31
本日の結論として真冬のWINDY予報=250hPa(10km)風速25m/sは、真夏の好気流とは大気の質そのものが違いますが、この時期としては十分撮影に耐えられる気流の目安になることが分かりました。
今年は暖冬で寒さもそれほど厳しくないので、気流の具合を見ながら惑星の撮影をしてみることにしましょう。

 通信が確立して再観測を始めたSLIMですが、着陸地点はまもなく日没を迎えます。
通信が確立して再観測を始めたSLIMですが、着陸地点はまもなく日没を迎えます。