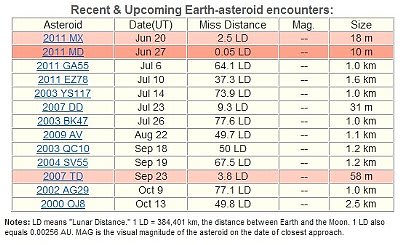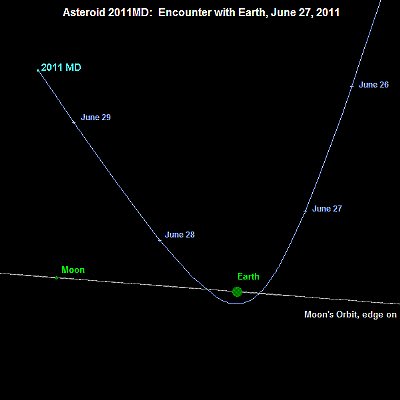暑い暑い…、今日の最高気温は34.4℃
なんでも6月の最高気温を更新したらしい。
6月の最高気温ランキング
(仙台)
第1位 34.4℃ 2011年6月30日
第2位 33.7℃ 1987年6月6日
第3位 33.6℃ 1941年6月25日
第4位 33.0℃ 1963年6月30日
第5位 32.8℃ 2009年6月27日
第6位 32.7℃ 2011年6月22日
第7位 32.6℃ 1991年6月12日
第8位 32.5℃ 1979年6月25日
第9位 32.1℃ 1979年6月21日
第10位 32.0℃ 2009年6月26日
我が家のウエザーステーションでも33℃越えを記録した。

湿球は24度、乾湿差は約9度…、あれ?換算表の示差は6度までしかないぞ~。
ふひゃ~、それでは湿度がわからないぞ~、と思いのあなた大丈夫です。
付属の別表があります。

まー、これも8.5度までなのですべてをカバーできるわけではありませんが、
今日の湿度は、おおよそ47%以下であることがわかります。
この気温に驚いたのか、気象棒が今まで見たことのないレベルで上昇しています。

早くも、梅雨明けか…、と思いたいところですが、仙台ではまだ
ニイニイゼミが鳴いていません。
ということで、仙台での梅雨明け発表は早くても7月12日以降…、のようですね。
なんでも6月の最高気温を更新したらしい。
6月の最高気温ランキング
(仙台)
第1位 34.4℃ 2011年6月30日
第2位 33.7℃ 1987年6月6日
第3位 33.6℃ 1941年6月25日
第4位 33.0℃ 1963年6月30日
第5位 32.8℃ 2009年6月27日
第6位 32.7℃ 2011年6月22日
第7位 32.6℃ 1991年6月12日
第8位 32.5℃ 1979年6月25日
第9位 32.1℃ 1979年6月21日
第10位 32.0℃ 2009年6月26日
我が家のウエザーステーションでも33℃越えを記録した。

湿球は24度、乾湿差は約9度…、あれ?換算表の示差は6度までしかないぞ~。
ふひゃ~、それでは湿度がわからないぞ~、と思いのあなた大丈夫です。
付属の別表があります。

まー、これも8.5度までなのですべてをカバーできるわけではありませんが、
今日の湿度は、おおよそ47%以下であることがわかります。
この気温に驚いたのか、気象棒が今まで見たことのないレベルで上昇しています。

早くも、梅雨明けか…、と思いたいところですが、仙台ではまだ
ニイニイゼミが鳴いていません。
ということで、仙台での梅雨明け発表は早くても7月12日以降…、のようですね。