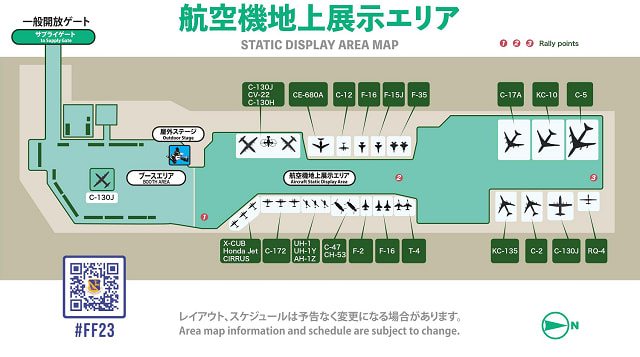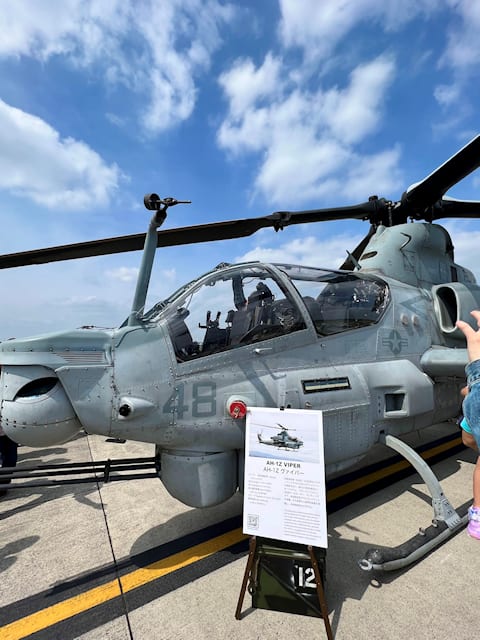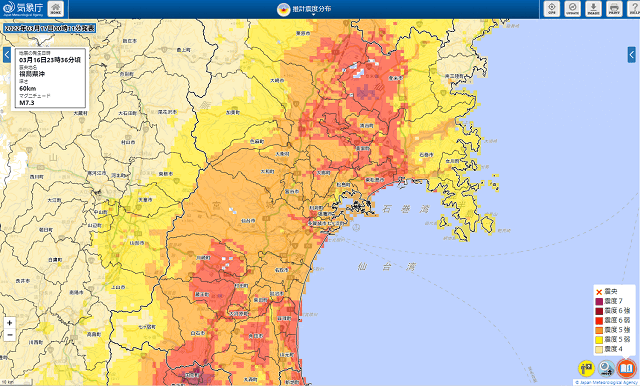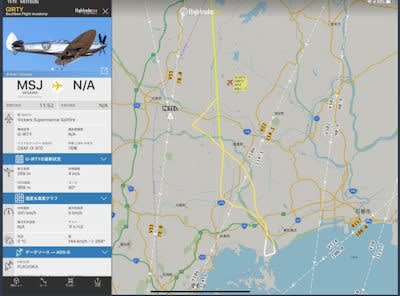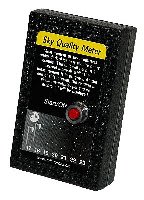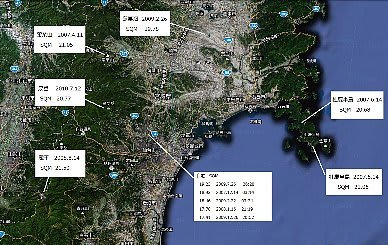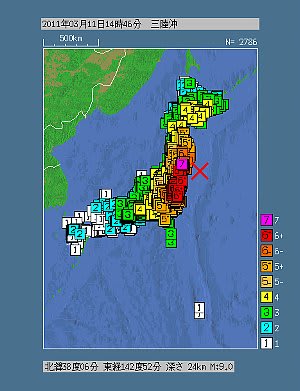ふ~む、どの天気予報を見ても雨ですね~。しかも強い雨の予報が出ています。まー、とりあえず行ってみて現地判断とすることにしましょう。現地の天気は行ってみないと分かりませんからね~。
なんと言っても今年の松島基地航空祭は4年ぶりの入場制限ナシだから行かない選択肢はないよね~と出かけたものの利府を過ぎて松島町に入ったところでバケツをひっくり返したような豪雨になりカーナビからは冠水警報が…
あわわ、この先大丈夫か~、と思ったのですが松島基地がある矢本に着くと水たまりはあるものの雨は降っていません。なんなら青空も見えてます。よし、これならOKです!
まずは駐車場探しですが…天気を気にして若干出遅れたので駐車場は駐車台数が400台と一番多い矢本東市民センターにしました。駐車場には難なく入れましたが駐車場係員がシーバーで「…あと10台です」と言ってたのでギリギリだったようです。→臨時駐車場情報、臨時駐車場案内経路、
ここから松島基地までは2.5kmもあるので臨時駐車場では遠い方ですが駐車できたので良しとしましょう。ここからてくてくと歩くこと約30分、行き着いたのは自衛隊基地の東門でした。やった~、久々の松島基地航空祭です。さて、現在時刻は8時30分、オープニングフライトまでには30分あるので基地内を探索しましょう。
とりあえずまっすぐ滑走路方向に進むと、ほひょ、ブルインパルスJrの走行展示が始まるところでした。オープニング前なので本番さながらの訓練走行?といったところでしょうか、オープニングフライトまで時間があるのでココで観覧タイムです。
お、始まりました。おおー、ブルーインパルスJrの演目を間近で見るのは初めてですが見事なフォーメーションです。しかも、カラースモーク… これはすご~い!
 タイトなフォーメーションを見せるブルーインパルスJr。ハイスピードで交差するスリリングな課目や途中で燃料を補給する空中給油タイム?などもあって見応え十分の展示走行です。
タイトなフォーメーションを見せるブルーインパルスJr。ハイスピードで交差するスリリングな課目や途中で燃料を補給する空中給油タイム?などもあって見応え十分の展示走行です。

そして、何と言っても圧巻の演目は「コークスクリュー」です。どうやって再現するのだろう?と思いましたが、これはお見事! 6番機のグリーンスモークが映える軽やかなコークスクリューでした~。→photo1、photo2
おっと、そろそろオープニングフライトの時刻です。急いで航空機展示エリアまで行くと、UH-60JとUH-125Aが通過したところでした。次に通過するオープニングフライト機はT-4とF-2ですが、おお~、スモークが出ています。ブルーインパルスの予備機とF-2Bの三機編隊飛行です!


さあ、いよいよ松島基地航空祭2023の開幕で~す。本日のイベントはこんな感じ…。

オープニングフライトの後はF-2B機動飛行です。

F-2Bの機動飛行は総合案内所付近に展示飛行の解説ボードがあるのでこれをスマホで撮影してから展示飛行を見るのがオススメです。
F-2B機動飛行のあとは午前中のメインイベント、ブルーインパルスの訓練飛行です!
滑走路に向かう1番機、お手ふりいただきました~。

リード・ソロ5番機によるローアングル・キューバン・テイクオフ

オポジング・ソロ6番機のロールオン・テイクオフ

φ(.. ) ミニ解説:「ローアングル・キューバン・テイクオフ」と「ロールオン・テイクオフ」は5番機と6番機が編隊離陸をして同時に行うダイナミックな課目ですが今回は天候状況で単機離陸になったようです。
約445kmまで加速した5番機が滑走路の終端付近でイッキに急上昇して宙返りをするローアングル・キューバン・テイクオフはT-4の高い運動性能ならではの課目です。→ド迫力の同時離陸動画はコチラ
さあ、次はお待ちかねのファン・ブレイクです。会場の斜め後方から機体間隔1mの密集隊形を維持したまま高度100mを時速720kmというハイスピードで観客の目の前を通過していきます。

ブルーインパルスが突如現れて至近距離を高速で通過するのでいつ見ても圧倒されます~。コックピットの中が見えるほどの低高度! スピードが速すぎていつもフレームアウトしてしまいます…

松島基地航空祭2023ブルーインパルス チェンジ・オーバー・ターンの後半部分
こちらはトレイル・トゥ・ダイヤモンド・ロール、雲が低くループ課目はナシでした~。


2~4番機が背面姿勢を維持したデルタ隊形、オポジット・トライアングル!

松島基地航空祭2023ブルインパルス ボントン・ロール
↑ スモーク・オフと同時に右へ360°ロールをして会場の右手後方に抜けていく課目、6機の息の合ったロール機動が見どころです。
最後の課目は5、6番機によるコークスクリューです。見事に決まりました~。

さて、ブルーインパルスの後は10時10分からUH-60LとU-125Aによる救難展示飛行が始まりますが、撮影はひとまず休憩として展示航空機を見ながらA格納庫まで移動です。
救難ヘリコプター UH-60J

US-2 救難機

V-22オスプレイ

P-1 哨戒機

こちらはエプロン内で展示しているF-15J、F-2B、T-4(ブルーインパルス)です。

さて、A格納庫前までやって来ました。10時50分から始まるF-2Bの訓練飛行まではまだ時間があるので、ここでA格納庫を見学することにしましょう。
A格納庫の中は航空機エンジンやF-2武装展示など盛りだくさんで見応えがありました~。

兵装展示、20mm機関砲弾、M61A2機関砲、AAM-3、AAM-3説明、チャフ/フレア、
ブルーインパルス関連の展示もありました。

射出座席、射出座席の仕組み、4番機の尾翼、
圧巻はF-2機搭載のエンジン F110-IHI-129Bの展示です。迫力ありました~。

さて、時刻は10時50分です。まもなく F-2B、2機による訓練飛行が始まります。
お、解説アナウンスが始まりました~。コンバットデバーチャーと呼ばれる2機同時の離陸で上昇したF-2Bが滑走路左側から進入してきました。松島基地を敵基地とみなして行う攻撃デモのスタートです! 解説はこちらを参照→21sq-F-2B
②エントリーパス(低高度、高速度で進入した2機がブレイクして爆撃パターンに入る瞬間)

③爆撃10°ダイブアングル

訓練は増装タンクを付けたまま…というのは当然のことですがそこが妙にリアルですね。

…と撮影に夢中になっていると滑走路からキーンというエンジン音が… わぉ、11時10分から始まるF-16デモフライトに向けてPACAFのF-16がタキシング体勢に入ってます。間髪入れずにデモフライトが始まるようです。うわ~、(嬉しい悲鳴~)

さあ、まもなくテイクオフです。アメリカ太平洋空軍PACAF F-16デモチームは松島基地でどのようなアクロバット飛行を見せてくれるのでしょうか? ワクワク… 期待に胸が膨らみます!
 PACAF F-16デモフライト アフターバーナー・テイクオフ→キューバン8
PACAF F-16デモフライト アフターバーナー・テイクオフ→キューバン8
↑ わずか300mの距離で離陸後、捻りを入れて低高度で観客前を通過!その直後に急上昇して八の字を描くキューバン8を行うF-16デモチームの名物アクロ!(太陽がまぶしくてスマホで追い切れません~)
天気が回復したのでヴェイパーはやや控えめです。それにしても日射しがキツイ!

グイーンと急上昇!翼面にモフモフが発生します!

イーサン”バンタム”スミス大尉は2023年6月からの新パイロット! ようこそ!松島基地へ。

これは背面ではありません。よく見るとコックピットが見えま~す。

で、本日のマイフェイバリットフォト! まるで空撮したかのようなフォトがありました~。

いや~、ナイスなアクロでしたね~ F-16デモチーム!松島でも堪能させてもらいました~。
さて午前のプログラムが終わったので、ここでぜひみたい展示コーナーのC格納庫に向かいましょう。そうです。C格納庫は知る人ぞ知るブルーインパルス専用の格納庫です。今日は開放してT-2ブル-インパルス機とF-2コックピットを展示しているようです。ですが、これが遠いのなんのって、途中日陰で休憩をしながらやっとの事で尽きました。早速入ってみましょう!

 おおー! 何ということでしょう! T-2ブルーインパルスの176号機です!
おおー! 何ということでしょう! T-2ブルーインパルスの176号機です!

176号機は1982年のT-2 Blueデビューから1995年のラストフライトまでリーダー機を務めた1番機です。決して順風満帆ではなかったT-2Blue時代を最後まで牽引してT-4へ引き継いだリーダー機としてブルーインパルス史を語る上では最も功績のあった機体だと言えるでしょう。

1984年7月29日松島基地航空祭で撮影した176号機(浜松事故後、展示飛行を再開したとき)の写真がありました。→photo1、photo2、phpto3(注:垂直尾翼のポジション・ナンバーは1987年夏から記入するようになったので当時はまだ無かった)

T-2 Blueは3機を事故で失ったため現存しているのは7機のみです。松島基地以外では浜松広報館、石川県立航空プラザ、岐阜かがみはら航空宇宙博物館、百里基地、三沢航空科学館、仙石線鹿妻駅前で保存されています。(浜松広報館 111号機、石川県立航空プラザ 163号機、岐阜かがみはら航空宇宙博物館 173号機、百里基地 175号機)

F-2のコックピット展示は長蛇の列だったので見学はパスしました~。ふう、これでお目当てのものは見たので、ここでエネルギー補給としましょう。
C格納庫を後にして露天通りに行くとお昼時なのでどの店も長蛇の列です。この炎天下で並ぶのはご免だな~と思って露天を見て回ると… ほひょ、誰も並んでない露店が1軒あります。
はて、この店舗は商売をやっているのだろうか。お店の看板を見ると売っているのは「ソーセージ4本400円」の1種類だけ…はて、買っていいのだろうか…と変なことを考えてしまいましたが、店名はなんと「牛タンの利休」です。な~ら安心!ということでソーセージをゲットです。
さて、ほかに長蛇の列ができていない店舗はないかなぁ~と探していたらありました!ケバブのお店です。ここでタンドリーチキンが入ったピタサンドをゲットして食べ物は確保!あとは飲み物ですが…どこのお店も、最後尾はココですプラカードが必要なほどの長~い列になってます。さすがにこの炎天下で待つのは危険なのでとりあえず日陰を探してエネルギー補給をすることにしました。それにしても今日の日射しは経験したことないほどの強烈さです。
ふう、皆さん考えることは同じで建物の日陰はどこもランチタイムの人でごった返しています。東門の方にしばらく歩いたところで誰もいない木陰を発見!やった~、ここで腰を下ろしてランチタイムにしましょう。利休のソーセージもケバブのピタサンドもとても美味でしたが食べ終わるとよけいに水分が欲しくなりました。
水筒に氷は入っていますが液体のH2Oは存在しない状態です。この氷が瞬時に溶ければいいのに…と思いながら水筒の底にたまっているH2Oを口に流し込んだ時、なんと、目の前にあるのにその姿が見えないステルス自販機を発見!
ほひょ~、これは天の恵みかミラクルか~、その自販機までは約20歩という近距離です…こ~れはオドロキです。行ってみるとたくさんの種類の飲料水があって、エナジードリンクもありました。ラッキー! さっそく購入したエナジードリンクが喉を通過した瞬間に、ひょっとしてこれ飲んだら千と千尋…のお父さんのように豚になるのでは? と思いましたが、そんなコトはありませんでした~。笑
さて、お腹もいっぱいになってエネルギー充填完了です。現在時刻は12時45分ですが、う~む、ブルーインパルスの展示飛行までは1時間以上ありますね~。気温は更に上昇、日射しも更に強くなっています。…う~む、午後のブルーを見たいけど、カラダが、おいおい大丈夫か~この炎天下を駐車場まで2.5kmも歩くんだぞ~体力のこってるか~と問いかけてきます。
たしかに基地内では隊員が担架をかかえて熱中症者のところへ駆けつける様子や救急車を誘導する隊員も見かけたので暑さが尋常ではないことが分かります。ということで午後はパスしてあっさり帰ることにしました~。帰路の2.5kmは果てしなく長く、駐車場に着いたときはヘロヘロでした。
臨時駐車場の矢本東市民センターに着くと何と職員がかき氷と冷たい飲み物の販売をしていました。かき氷は100円で練乳はサービス、飲み物は150円という大サービスです。こ~れは、ありがたい! メロンかき氷と柚子ソーダを頂いてほっと一息ついてから帰りました~。矢本東市民センターのみなさん、ありがとうございました~。
なんと言っても今年の松島基地航空祭は4年ぶりの入場制限ナシだから行かない選択肢はないよね~と出かけたものの利府を過ぎて松島町に入ったところでバケツをひっくり返したような豪雨になりカーナビからは冠水警報が…
あわわ、この先大丈夫か~、と思ったのですが松島基地がある矢本に着くと水たまりはあるものの雨は降っていません。なんなら青空も見えてます。よし、これならOKです!
まずは駐車場探しですが…天気を気にして若干出遅れたので駐車場は駐車台数が400台と一番多い矢本東市民センターにしました。駐車場には難なく入れましたが駐車場係員がシーバーで「…あと10台です」と言ってたのでギリギリだったようです。→臨時駐車場情報、臨時駐車場案内経路、
ここから松島基地までは2.5kmもあるので臨時駐車場では遠い方ですが駐車できたので良しとしましょう。ここからてくてくと歩くこと約30分、行き着いたのは自衛隊基地の東門でした。やった~、久々の松島基地航空祭です。さて、現在時刻は8時30分、オープニングフライトまでには30分あるので基地内を探索しましょう。
とりあえずまっすぐ滑走路方向に進むと、ほひょ、ブルインパルスJrの走行展示が始まるところでした。オープニング前なので本番さながらの訓練走行?といったところでしょうか、オープニングフライトまで時間があるのでココで観覧タイムです。
お、始まりました。おおー、ブルーインパルスJrの演目を間近で見るのは初めてですが見事なフォーメーションです。しかも、カラースモーク… これはすご~い!
 タイトなフォーメーションを見せるブルーインパルスJr。ハイスピードで交差するスリリングな課目や途中で燃料を補給する空中給油タイム?などもあって見応え十分の展示走行です。
タイトなフォーメーションを見せるブルーインパルスJr。ハイスピードで交差するスリリングな課目や途中で燃料を補給する空中給油タイム?などもあって見応え十分の展示走行です。
そして、何と言っても圧巻の演目は「コークスクリュー」です。どうやって再現するのだろう?と思いましたが、これはお見事! 6番機のグリーンスモークが映える軽やかなコークスクリューでした~。→photo1、photo2
おっと、そろそろオープニングフライトの時刻です。急いで航空機展示エリアまで行くと、UH-60JとUH-125Aが通過したところでした。次に通過するオープニングフライト機はT-4とF-2ですが、おお~、スモークが出ています。ブルーインパルスの予備機とF-2Bの三機編隊飛行です!


さあ、いよいよ松島基地航空祭2023の開幕で~す。本日のイベントはこんな感じ…。

オープニングフライトの後はF-2B機動飛行です。

F-2Bの機動飛行は総合案内所付近に展示飛行の解説ボードがあるのでこれをスマホで撮影してから展示飛行を見るのがオススメです。
F-2B機動飛行のあとは午前中のメインイベント、ブルーインパルスの訓練飛行です!
滑走路に向かう1番機、お手ふりいただきました~。

リード・ソロ5番機によるローアングル・キューバン・テイクオフ

オポジング・ソロ6番機のロールオン・テイクオフ

φ(.. ) ミニ解説:「ローアングル・キューバン・テイクオフ」と「ロールオン・テイクオフ」は5番機と6番機が編隊離陸をして同時に行うダイナミックな課目ですが今回は天候状況で単機離陸になったようです。
約445kmまで加速した5番機が滑走路の終端付近でイッキに急上昇して宙返りをするローアングル・キューバン・テイクオフはT-4の高い運動性能ならではの課目です。→ド迫力の同時離陸動画はコチラ
さあ、次はお待ちかねのファン・ブレイクです。会場の斜め後方から機体間隔1mの密集隊形を維持したまま高度100mを時速720kmというハイスピードで観客の目の前を通過していきます。

ブルーインパルスが突如現れて至近距離を高速で通過するのでいつ見ても圧倒されます~。コックピットの中が見えるほどの低高度! スピードが速すぎていつもフレームアウトしてしまいます…

松島基地航空祭2023ブルーインパルス チェンジ・オーバー・ターンの後半部分
こちらはトレイル・トゥ・ダイヤモンド・ロール、雲が低くループ課目はナシでした~。


2~4番機が背面姿勢を維持したデルタ隊形、オポジット・トライアングル!

松島基地航空祭2023ブルインパルス ボントン・ロール
↑ スモーク・オフと同時に右へ360°ロールをして会場の右手後方に抜けていく課目、6機の息の合ったロール機動が見どころです。
最後の課目は5、6番機によるコークスクリューです。見事に決まりました~。

さて、ブルーインパルスの後は10時10分からUH-60LとU-125Aによる救難展示飛行が始まりますが、撮影はひとまず休憩として展示航空機を見ながらA格納庫まで移動です。
救難ヘリコプター UH-60J

US-2 救難機

V-22オスプレイ

P-1 哨戒機

こちらはエプロン内で展示しているF-15J、F-2B、T-4(ブルーインパルス)です。

さて、A格納庫前までやって来ました。10時50分から始まるF-2Bの訓練飛行まではまだ時間があるので、ここでA格納庫を見学することにしましょう。
A格納庫の中は航空機エンジンやF-2武装展示など盛りだくさんで見応えがありました~。

兵装展示、20mm機関砲弾、M61A2機関砲、AAM-3、AAM-3説明、チャフ/フレア、
ブルーインパルス関連の展示もありました。

射出座席、射出座席の仕組み、4番機の尾翼、
圧巻はF-2機搭載のエンジン F110-IHI-129Bの展示です。迫力ありました~。

さて、時刻は10時50分です。まもなく F-2B、2機による訓練飛行が始まります。
お、解説アナウンスが始まりました~。コンバットデバーチャーと呼ばれる2機同時の離陸で上昇したF-2Bが滑走路左側から進入してきました。松島基地を敵基地とみなして行う攻撃デモのスタートです! 解説はこちらを参照→21sq-F-2B
②エントリーパス(低高度、高速度で進入した2機がブレイクして爆撃パターンに入る瞬間)

③爆撃10°ダイブアングル

訓練は増装タンクを付けたまま…というのは当然のことですがそこが妙にリアルですね。

…と撮影に夢中になっていると滑走路からキーンというエンジン音が… わぉ、11時10分から始まるF-16デモフライトに向けてPACAFのF-16がタキシング体勢に入ってます。間髪入れずにデモフライトが始まるようです。うわ~、(嬉しい悲鳴~)

さあ、まもなくテイクオフです。アメリカ太平洋空軍PACAF F-16デモチームは松島基地でどのようなアクロバット飛行を見せてくれるのでしょうか? ワクワク… 期待に胸が膨らみます!
 PACAF F-16デモフライト アフターバーナー・テイクオフ→キューバン8
PACAF F-16デモフライト アフターバーナー・テイクオフ→キューバン8↑ わずか300mの距離で離陸後、捻りを入れて低高度で観客前を通過!その直後に急上昇して八の字を描くキューバン8を行うF-16デモチームの名物アクロ!(太陽がまぶしくてスマホで追い切れません~)
天気が回復したのでヴェイパーはやや控えめです。それにしても日射しがキツイ!

グイーンと急上昇!翼面にモフモフが発生します!

イーサン”バンタム”スミス大尉は2023年6月からの新パイロット! ようこそ!松島基地へ。

これは背面ではありません。よく見るとコックピットが見えま~す。

で、本日のマイフェイバリットフォト! まるで空撮したかのようなフォトがありました~。

いや~、ナイスなアクロでしたね~ F-16デモチーム!松島でも堪能させてもらいました~。
さて午前のプログラムが終わったので、ここでぜひみたい展示コーナーのC格納庫に向かいましょう。そうです。C格納庫は知る人ぞ知るブルーインパルス専用の格納庫です。今日は開放してT-2ブル-インパルス機とF-2コックピットを展示しているようです。ですが、これが遠いのなんのって、途中日陰で休憩をしながらやっとの事で尽きました。早速入ってみましょう!

 おおー! 何ということでしょう! T-2ブルーインパルスの176号機です!
おおー! 何ということでしょう! T-2ブルーインパルスの176号機です!
176号機は1982年のT-2 Blueデビューから1995年のラストフライトまでリーダー機を務めた1番機です。決して順風満帆ではなかったT-2Blue時代を最後まで牽引してT-4へ引き継いだリーダー機としてブルーインパルス史を語る上では最も功績のあった機体だと言えるでしょう。

1984年7月29日松島基地航空祭で撮影した176号機(浜松事故後、展示飛行を再開したとき)の写真がありました。→photo1、photo2、phpto3(注:垂直尾翼のポジション・ナンバーは1987年夏から記入するようになったので当時はまだ無かった)

T-2 Blueは3機を事故で失ったため現存しているのは7機のみです。松島基地以外では浜松広報館、石川県立航空プラザ、岐阜かがみはら航空宇宙博物館、百里基地、三沢航空科学館、仙石線鹿妻駅前で保存されています。(浜松広報館 111号機、石川県立航空プラザ 163号機、岐阜かがみはら航空宇宙博物館 173号機、百里基地 175号機)

F-2のコックピット展示は長蛇の列だったので見学はパスしました~。ふう、これでお目当てのものは見たので、ここでエネルギー補給としましょう。
C格納庫を後にして露天通りに行くとお昼時なのでどの店も長蛇の列です。この炎天下で並ぶのはご免だな~と思って露天を見て回ると… ほひょ、誰も並んでない露店が1軒あります。
はて、この店舗は商売をやっているのだろうか。お店の看板を見ると売っているのは「ソーセージ4本400円」の1種類だけ…はて、買っていいのだろうか…と変なことを考えてしまいましたが、店名はなんと「牛タンの利休」です。な~ら安心!ということでソーセージをゲットです。
さて、ほかに長蛇の列ができていない店舗はないかなぁ~と探していたらありました!ケバブのお店です。ここでタンドリーチキンが入ったピタサンドをゲットして食べ物は確保!あとは飲み物ですが…どこのお店も、最後尾はココですプラカードが必要なほどの長~い列になってます。さすがにこの炎天下で待つのは危険なのでとりあえず日陰を探してエネルギー補給をすることにしました。それにしても今日の日射しは経験したことないほどの強烈さです。
ふう、皆さん考えることは同じで建物の日陰はどこもランチタイムの人でごった返しています。東門の方にしばらく歩いたところで誰もいない木陰を発見!やった~、ここで腰を下ろしてランチタイムにしましょう。利休のソーセージもケバブのピタサンドもとても美味でしたが食べ終わるとよけいに水分が欲しくなりました。
水筒に氷は入っていますが液体のH2Oは存在しない状態です。この氷が瞬時に溶ければいいのに…と思いながら水筒の底にたまっているH2Oを口に流し込んだ時、なんと、目の前にあるのにその姿が見えないステルス自販機を発見!
ほひょ~、これは天の恵みかミラクルか~、その自販機までは約20歩という近距離です…こ~れはオドロキです。行ってみるとたくさんの種類の飲料水があって、エナジードリンクもありました。ラッキー! さっそく購入したエナジードリンクが喉を通過した瞬間に、ひょっとしてこれ飲んだら千と千尋…のお父さんのように豚になるのでは? と思いましたが、そんなコトはありませんでした~。笑
さて、お腹もいっぱいになってエネルギー充填完了です。現在時刻は12時45分ですが、う~む、ブルーインパルスの展示飛行までは1時間以上ありますね~。気温は更に上昇、日射しも更に強くなっています。…う~む、午後のブルーを見たいけど、カラダが、おいおい大丈夫か~この炎天下を駐車場まで2.5kmも歩くんだぞ~体力のこってるか~と問いかけてきます。
たしかに基地内では隊員が担架をかかえて熱中症者のところへ駆けつける様子や救急車を誘導する隊員も見かけたので暑さが尋常ではないことが分かります。ということで午後はパスしてあっさり帰ることにしました~。帰路の2.5kmは果てしなく長く、駐車場に着いたときはヘロヘロでした。
臨時駐車場の矢本東市民センターに着くと何と職員がかき氷と冷たい飲み物の販売をしていました。かき氷は100円で練乳はサービス、飲み物は150円という大サービスです。こ~れは、ありがたい! メロンかき氷と柚子ソーダを頂いてほっと一息ついてから帰りました~。矢本東市民センターのみなさん、ありがとうございました~。