義援金の話である。
今回の震災に対し、世界各国から義援金や、
支援が寄せられている。
苦難を分かち合おうという国際社会の基本的な在り方は、
様々な国際間のしがらみや軋轢を越えて、誠に評価すべき
事と感じられる。
苦しむ人をそのままにしておけない。
その一個人の想いが、国家という大きな単位であっても
行動に移されるというのは、言わば理想である。
我々が思い描く平和理想に向けて行動するとき、
国家もその理想に向けて具体的に動くということではないか。
政府も各国に向けて謝辞広告を打ち出したが、
台湾に向けては、紙面掲載をしなかった。
中国との関係、台湾との国交関係上の措置であろうが、
ひとつ我々が認識しておかねばならないことがある。
台湾よりの義援金は、米国のそれを遥かに超え、
今では100億を超えている。
義援金の多寡を言っているのではなく、経済的に決して
豊かではない、わずか2300万人の人口の
自称独立国家が、大国を上回るほどの義援金を集めた
そのこと自体の意味を、我々は知るべきなのである。
その義援金の9割以上が民間から寄せられたものである。
もとより、義援金それ自体に価値の差はない。
いずれも日本人として心から感謝すべきことである。
だが、経済大国や、資産家による大きな義援金の
話題ばかりがニュースを賑わせている。
ともすれば、義援金の多寡で、その国なり、企業なり、
人なりの評価をしてしまうことになりかねない。
詳しくは述べないが、長者の万灯、貧者の一灯の話を
思い出した。
闇を払う灯りには何ら変わりはないが、その想いには
やはり違いがある。
まさしく身を削って、苦難に喘ぐ隣人の痛みを分かつ想いが、
台湾よりの義援金なのだと思う。
国家として認められていない彼らに対し、国家としての
謝辞広告を打ち出さなかったことについても、
「身内に礼状はいらない。」と、意にも介していないという。
過去の大きな震災の際に、日本が最も迅速な支援を
行ったことに対する恩返しと、台湾の誰もが言い切る。
日本と台湾の関係は深いものがあるが、それも世代交代に
よって変わってしまっただろうと考えていたが、
日本の美徳とされてきたものが、今も尚、台湾で
脈打っていることに反対に驚かされた。
イラン・イラク戦争の折の、トルコの人道的支援もまた、
日本より受けた遠い昔の恩返しであった。
この貧者の一灯の精神こそ、今回の震災を契機に
我々日本人が改めて取り戻さねばならないものでは
ないだろうか。
受けた恩は、身を持って返していく。
それは、共々に分かち合うということである。
そしてたとえ身を削って与えたとしても、そこになんら
見返りを望む心はない。
そういう人としての崇高な精神を、改めて思い出させて
頂いた気がする。
堂々たる国家である、台湾国民の皆様に、謹んで
お礼を申し上げたいと思うのである。
今回の震災に対し、世界各国から義援金や、
支援が寄せられている。
苦難を分かち合おうという国際社会の基本的な在り方は、
様々な国際間のしがらみや軋轢を越えて、誠に評価すべき
事と感じられる。
苦しむ人をそのままにしておけない。
その一個人の想いが、国家という大きな単位であっても
行動に移されるというのは、言わば理想である。
我々が思い描く平和理想に向けて行動するとき、
国家もその理想に向けて具体的に動くということではないか。
政府も各国に向けて謝辞広告を打ち出したが、
台湾に向けては、紙面掲載をしなかった。
中国との関係、台湾との国交関係上の措置であろうが、
ひとつ我々が認識しておかねばならないことがある。
台湾よりの義援金は、米国のそれを遥かに超え、
今では100億を超えている。
義援金の多寡を言っているのではなく、経済的に決して
豊かではない、わずか2300万人の人口の
自称独立国家が、大国を上回るほどの義援金を集めた
そのこと自体の意味を、我々は知るべきなのである。
その義援金の9割以上が民間から寄せられたものである。
もとより、義援金それ自体に価値の差はない。
いずれも日本人として心から感謝すべきことである。
だが、経済大国や、資産家による大きな義援金の
話題ばかりがニュースを賑わせている。
ともすれば、義援金の多寡で、その国なり、企業なり、
人なりの評価をしてしまうことになりかねない。
詳しくは述べないが、長者の万灯、貧者の一灯の話を
思い出した。
闇を払う灯りには何ら変わりはないが、その想いには
やはり違いがある。
まさしく身を削って、苦難に喘ぐ隣人の痛みを分かつ想いが、
台湾よりの義援金なのだと思う。
国家として認められていない彼らに対し、国家としての
謝辞広告を打ち出さなかったことについても、
「身内に礼状はいらない。」と、意にも介していないという。
過去の大きな震災の際に、日本が最も迅速な支援を
行ったことに対する恩返しと、台湾の誰もが言い切る。
日本と台湾の関係は深いものがあるが、それも世代交代に
よって変わってしまっただろうと考えていたが、
日本の美徳とされてきたものが、今も尚、台湾で
脈打っていることに反対に驚かされた。
イラン・イラク戦争の折の、トルコの人道的支援もまた、
日本より受けた遠い昔の恩返しであった。
この貧者の一灯の精神こそ、今回の震災を契機に
我々日本人が改めて取り戻さねばならないものでは
ないだろうか。
受けた恩は、身を持って返していく。
それは、共々に分かち合うということである。
そしてたとえ身を削って与えたとしても、そこになんら
見返りを望む心はない。
そういう人としての崇高な精神を、改めて思い出させて
頂いた気がする。
堂々たる国家である、台湾国民の皆様に、謹んで
お礼を申し上げたいと思うのである。

















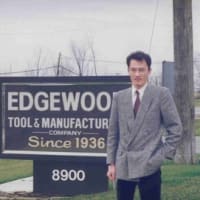


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます