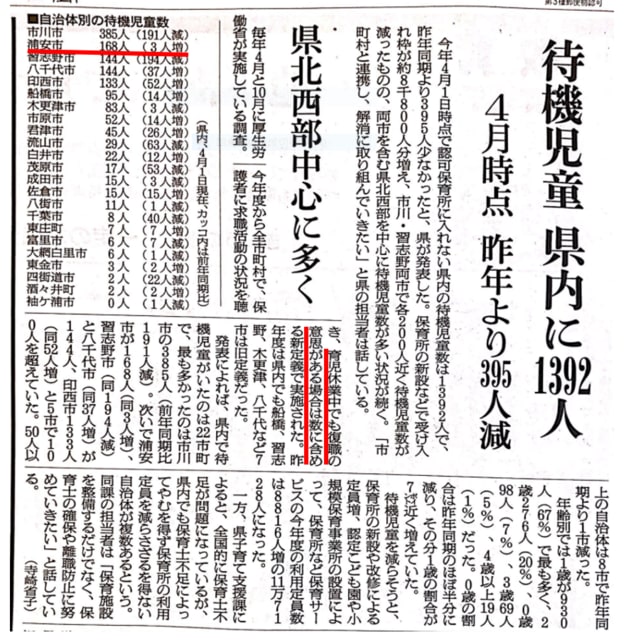本当にいつまで続くのでしょうか、このような不正請求は!
兵庫県西宮市のNPO法人「西宮がすきやねん」が障害者支援施設の運営補助金を不正に受け取っていた問題で、介護給付金の受給でも不正が分かり、同市が法人側に約8千万円の返還を求めたことが8日、同市への取材で分かった。
市の調査によると、法人は身体障害者が共同生活するグループホームを運営するが、2013~17年度、利用者を水増しする架空請求などを含めて、運営補助金約3900万円を不正受給した。
また、同ホームが営む介護サービスでも、本来は認められていないのに、施設での夜勤業務と夜間の重度訪問介護サービスを職員に兼務させ、給付金約3800万円を過大に受け取った。
さらに、要件を満たさなかった別施設のスプリンクラー設備への補助金約300万円の返還も求めた。
法人は、計約8千万円を15年以内に返済する計画を市に提出。法人の吉田知英理事長(70)は取材に「事業を回す中で金が足らず、水増しをやってしまった」と説明。市は調査の結果、「返済の意思があり、私的流用はなかった」として刑事告訴をしなかった。
一方、法人は10~12年度も施設運営補助金約2500万円を受給しているが、吉田理事長は不正を否定。市は、保管期限を過ぎて関係資料が廃棄されたため、「不正の有無は不明」としている。(初鹿野俊)
浦安市で働く半数以上が正規職員ではありません。市は、正規職員よりも人件費が安く、経費が節約できると考えているのかもしれませんが、以下の判決を読むと時代が変わりつつあることを実感できるはずです。
大阪医科大職員格差訴訟 2審支払い命じる
2019.2.15 23:00社会裁判
正職員と同じ業務内容なのに待遇に格差があるのは違法だとして、大阪医科大(大阪府高槻市)の研究室で秘書をしていた元アルバイト職員の50代女性が、手当の差額分など計約1270万円の支払いを大学側に求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は、賞与の不支給などを違法と判断。請求を棄却した昨年1月の1審大阪地裁判決を変更し、約110万円の支払いを命じる原告側逆転勝訴の判決を言い渡した。
江口裁判長は判決理由で、大学の賞与について、業績や年齢と関係なく基本給に連動して正職員に支給されていることから「賞与の算定期間に働いたことへの対価」と判断。フルタイムで働くアルバイト職員に全く支給しないのは不合理とした。額については、有期雇用の契約職員の額を踏まえ、60%を下回ると違法だとした。
また、夏期特別有給休暇の付与をめぐっては、同休暇は「心身のリフレッシュを図る必要から付与されている」と判示し、正職員と同様の日数を与えないのは不合理と認定した。
判決後に大阪市内で会見した弁護団の河村学弁護士は「非正規格差訴訟で、高裁段階で初めて賞与の支払いを認めた。画期的な判決だ」と評価。原告の女性は「判決をきっかけに非正規の人が働きやすくなれば」と話した。
同大運営法人は「判決文が届いていないので、コメントできない」とした。
・・・・・・・・・・・・・・・・
こちらの判決も無視できない
契約社員にも退職金認める 駅売店員の格差格差訴訟
2019/2/20 20:21
東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」とし、4人のうち2人に退職金45万~49万円を支払うよう命じた。
非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。
川神裁判長は、原告の2人が10年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額の「少なくとも4分の1」とした。
住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はないと指摘。3人への11万~55万円の支払いを命じた。一方、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や賞与などの格差は容認した。
一審・東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。
4人は64~71歳。2004~06年に採用され、3人は既に定年退職した。うち1人は、正社員と非正規との不合理な格差を禁じた改正労働契約法の施行前に定年で雇用形態が変わったため、高裁は一審同様に請求を退けた。
原告側は認められた支給額が低いとして上告する方針。
メトロコマースによると、1年ごとに契約する駅売店の販売員は2月1日時点で55人。同社は「判決文が届いておらず詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」としている。〔共同〕
介護保険運営協議会を傍聴しました。傍聴者への配布資料は有料でしたが、浦安市の実態を知るには大変役に立つものでしたので購入しました。カラー刷りでしたので1120円でした。 傍聴者三名、資料購入者は二名。
市民公募の委員さんはからは、積極的な発言があり、また、会場ではマイクが使われていたので声も良く聞こえました。
こんな厳しく(ある意味、当たり前)に対応している自治体がありました。「受検体制が整っていない」と言う理由で、県の監査を拒否した事例が過去にありましたが、こんな場合は札幌市はどのように対応するのか知りたいですね。
《行政処分の理由》(25年度から30年度)
・障害児支援利用計画を作成していないことを認識していたにも関わらず、障害児相談支援給付費を請求し、受領した
・平成26年12月から平成29年5月にかけて、大型連休(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始等)期間中の計15日間、事業所を営業していないにもかかわらず、「自習」と称して支援を行ったこととし、延べ745人分の訓練等給付費約384万円を架空請求した。
1. 人員配置の虚偽の届け出
平成29年4月1日以降のB型事業所の人員配置を同年4月12日付で札幌市に届け出ている。その際、勤務していない生活支援員3名について、勤務しているように見せかける虚偽の届出書を提出した。
2. 人員配置基準違反
就労継続支援A型事業所及びB型事業所において、平成29年4月から平成29年7月までの間、サービス管理責任者が常勤で勤務していない状態で事業を運営し続けた。
就労継続支援B型事業所において、平成24年12月から平成29年5月までの間、職業指導員1名及び生活支援員4名について、勤務実態がない若しくは勤務時間が届出より短い状態であり、人員配置基準が満たされていない状態で事業を運営し続けた。
3. 事業者が自己の利益を図るために行った基準違反
平成26年12月から平成29年5月にかけて、大型連休(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始等)期間中の計15日間において、利用者に対して障害福祉サービスを提供していないにかかわらず、サービスを提供したものとして、虚偽の内容に同意をさせ、同意をした利用者に対して給与を支給していた。
・訓練等給付費の不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号)
利用者の送迎加算について、実際に提供した送迎回数よりも多く、訓練等給付費を不正に請求した(水増し請求)。
(1) 障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたため。
(障害者総合支援法第50条第1項第10号に該当するため。)
1. 他の事業者と連絡調整等を行わずに、平成28年5月に事業所を突然閉鎖したことにより、利用者が必要なサービスを受けられなくなった。
2. 社会保険料が未納付であり事業運営費に流用した。
3. 平成28年5月に解雇した3事業所の従業者及び就労継続支援A型事業所の利用者について、30日前に予告しなかったことから、解雇予告手当の支払義務が発生しているが、未払いになっている。
4. 貸借対照表や損益計算書等の会計に関する書類を2年間作成していない。
5. 外部サーヒ゛ス利用型共同生活援助の世話人の1人について、勤務実態がないにもかかわらず、勤務しているとの虚偽の届け出を行った。
(2) 上記(1)1.の行為は、障がい者の人格を尊重するとともに、障がい者のため忠実にその職務を遂行していないため。
(障害者総合支援法第42条第3項、第50条第1項第2号に該当するため。)
(3) 平成28年5月に事業所が閉鎖され、事業の実態がないため。
(障害者総合支援法第50条第1項第3号、第4号に該当するため。)
・(1) 本市の再三にわたる帳簿書類の提出要求に対して、一切応じないまま帳簿書類を破棄し、監査を忌避したため。
(障害者総合支援法第50条第1項第7号、児童福祉法第21条の5の23第1項第7号、札幌市移動支援事業事業者登録要綱第8条第1項第7号に該当するため。)
(2) 実際のサービスの提供日数と請求内容に明らかな不一致があり、架空請求及び水増し請求の事実が認められたため。
(児童福祉法第21条の5の23第1項第5号、札幌市移動支援事業事業者登録要綱第8条第1項第5号に該当するため。)
(3) 平成27年10月から11月にかけて事業所が閉鎖され、事業の実態がないため。
(障害者総合支援法第50条第1項第3号、第4号、児童福祉法第21条の5の23第1項第3号、第4号、札幌市移動支援事業事業者登録要綱第8条第1項第3号、第4号に該当するため。)
・法人役員に欠格事由があるため。
(児童福祉法第21条の5の23第1項第1号及び第8号に該当するため。)
・介護給付費と移動支援費の請求書類を確認したところ、実際のサービスの提供時間と請求内容に明らかな不一致があり、架空請求及び水増し請求の事実が認められたため、指定取消し及び登録取消しを行った。
介護事業所による不正請求が後を絶たないのですが、厚生省の報告では過去最多になっています。制度の信頼を損なう事態です。国の不正統計問題が浮上し国への信頼が揺らいでいるのですが、何故こんな事態になっているのでしょうか。地元自治体は大丈夫でしょうか。
介護事業所の指定取消・停止処分、過去最多に 不正請求がトップ 厚労省
厚生労働省は6日の政策説明会で、何らかの不正によって指定の取り消しや効力の停止といった処分を受けた介護施設・事業所が、2016年度の1年間で244件にのぼったと明らかにした。227件だった前年度より17件多い。施設・事業所が増加していることなどを背景に過去最多を更新した。

指定の取り消しが141件、指定の効力停止が103件。処分を受けた法人の種類では、営利法人が206件と8割超を占めている。サービスの種類をみると、訪問介護が84件で最多。次いで、38件の居宅介護支援、34件の通所介護、13件のグループホームなどが多かった。
取り消しに至った理由(重複あり)では、「不正請求」が59.6%でトップ。「法令違反」と「虚偽報告」が25.5%で続いた。効力停止の理由でも、「不正請求(40.8%)」「法令違反(27.5%)」「虚偽報告(22.3%)」が上位だった。
不正があった際に法人全体で関与が無かったかなどを調べる「特別検査」は68件。このうち29件で改善勧告が、4件で改善命令が行われていた。
厚労省はこの日の政策説明会で、「事業者の不正は利用者に著しい不利益を与えるのみならず、制度全体の信頼を損なうもの」と改めて指摘。「疑わしいケースを把握したら速やかに監査を実施し、不正には厳正に対処してもらいたい」と指示した。加えて、「不正があった事業所の給付管理を行っていた居宅介護支援事業所に問題がないか、必要に応じて監査を行って欲しい」と求めた。
国がお手本を示さなければいけないのに、規定の半分の数字でした。国への信頼を失う事例です。
国の障がい者雇用率は1.22パーセント!
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181225-00000034-kyodonews-pol
昔子供たちが通っていた入船北小学校跡地にできた喫茶コーナー、少々場所が悪いのか、あるいは市民の間にまだ知れわたっていないからなのか、利用者が少ないようです。私が行ったときも私以外お客さんは誰もいませんでした。
でも、落ち着いた雰囲気でゆっくりとくつろげる場所です。穴場です。





ある意味、当たり前の判決ですが、でも、実態はなかなか難しいのが現実です。
(似たような事例が身近でも起きています。)
勤務する介護老人保健施設の違法行為を内部告発して不当解雇されたとして、施設に勤務していた男性が施設を運営する医療法人に解雇の無効確認などを求めた裁判の判決が30日、和歌山地裁であり、中山誠一裁判長は解雇無効を認める判決を言い渡した。
知的障害者に「うそつき」「泥棒」 三重の施設で虐待
提訴したのは、出口和広さん(42)=日高町。訴状によると、出口さんは、医療法人はしもと(美浜町)が運営する介護老人保健施設に理学療法士として勤務。施設が医師や職員を水増しして登録していること、入所者が虐待されていることなどを2014年に県などに通報したところ、15年12月に突然解雇された。出口さんは、解雇の無効確認や慰謝料などを求めて16年3月に提訴した。
被告側は、原告の行為は職場の秩序を混乱させるもので解雇は正当と主張したが、判決では、解雇を客観的に合理化できる理由ではないなどとし、解雇の無効を認めた。慰謝料の請求は棄却した。
判決を受けて出口さんは会見。通報者を守る公益通報者保護法には報復解雇した企業などへの罰則が無いことから、「法律に守られている実感は無かった。法律がもっと前面に出てきてもよいのではないか」と罰則などの導入を訴えた。原告側の代理人弁護士は「通報者が適正に保護されるように、法律の実効性を高める法改正を検討することも必要だ」と指摘した。
障がい者雇用水増しのマスコミ報道がなされた時、私は直ぐに担当課に電話を入れまして、浦安市の実態はどうなのかを質問しました。その時の回答は全く問題なしとのことでしたが・・・、実態は問題ありでした。
10月2日に市長からの報告
クリックすると拡大します。↓
市長部局が3人、教育委員会は2人も不足していました。
「本来含めるべき非常勤職員の数を算定基礎に含めたいなかったため」が理由でした。
浦安市は、非常勤職員を沢山抱えています。その数を除いて算定していたとのことです。
「新たな雇用の確保に全力で取り組んでいきたい」とのことですが、方法・時期等を明らかにして欲しいものです。
中日新聞が報じています障害児の放課後、地元はどうなっているのでしょうか。
|
多くの子どもの判定が覆った「わんぱくひろば」。手前は、判定を変更することを知らせる市からの通知=群馬県伊勢崎市で |
 |
障害のある子どもが放課後などを過ごす放課後等デイサービス(放課後デイ)が揺れている。四月の福祉サービス事業者への報酬改定以降、開所日を減らしたり、二施設を統合したり、経費節減を迫られた事例が相次ぐ。改定に伴って実施された子どもたちの障害の区分分けでも、反発や疑問の声が数多く上がり、国が自治体に判定のやり直しを通知する異例の事態となっている。戸惑う現場の様子を二回にわたって紹介する。
「これから土曜日は、閉所せざるを得ない」。四月中旬、群馬県伊勢崎市の放課後デイ「わんぱくひろば」に、長男の竜暉(りゅうき)さん(15)が通っているパートの小倉理代さん(39)は、放課後デイの職員からこう聞かされて絶句した。
放課後デイは、障害がある子どもたちが放課後や長期休暇などを過ごす施設。竜暉さんは高校一年で、発達障害や知的障害を伴う自閉症があり、意思疎通や読み書きがうまくできない。
土曜日の閉所は、報酬改定で受け取る基本報酬が減るのを受けての対応。国は市区町村に対して、まずは子どもたちの障害の重さを二つに分け、放課後デイは、障害が「重い」子が半数以上だと「区分1」、半数未満だと「区分2」とし、報酬に差をつけた。
わんぱくひろばは、小学一年から高校三年までの利用者十六人全員が「軽い」と判定され区分2に。報酬は区分1より低く、区分がなかった前年と比べると10~12%の減額。わんぱくひろばでは四月以降、月に約四十万円減った。
しかし、小倉さんは竜暉さんの障害の判定に疑問を感じた。竜暉さんは、重い障害がある人に交付される療育手帳「A」を持っている。判定の際、市からの聞き取りなどは何もなく、四月上旬に「指標該当 無」と書かれた通知が送られてきただけだった。わんぱくひろばの職員も、聞き取りは受けていなかった。「判定方法がおかしいのでは」と抗議した。
この問題は伊勢崎市議会六月定例会でも取り上げられ、市は判定のやり直しを決定。Aの療育手帳を持っている子どもは全員が「指標該当 有」とされ、竜暉さんも「重い」に覆った。わんぱくひろばでは十六人中十二人の判定が変更された。ただ、土曜日再開のめどは立っていない。
市によると、国から子どもの障害を判定するよう通知されたのは二月。四月の報酬改定に間に合わせるには新たな聞き取りを実施する時間がなかったため、以前から実施され、食事の介助が必要かなどを聞き取ってきた状況調査に基づいて判定したという。
全国の放課後デイなどでつくる「障害のある子どもの放課後保障全国連絡会」が二百十カ所を対象にしたアンケートによると、区分2になったのは回答を寄せたうちの八割。「廃止の危機」との声も二割から上がった。判定に際して、市区町村からの聞き取り調査がなかったというところは65%あった。こうした声を受け、厚生労働省は七月、書面のみで判定した場合などは、判定をやり直すよう自治体に通知した。
立正大社会福祉学部の中村尚子特任准教授は「子どもの実態が無視された制度改正だ。どんな支援が必要かという、子どもを第一に考えた視点が欠けている」と指摘する。
(細川暁子)
<放課後等デイサービス> 発達、知的などの障害がある6~18歳の子どもが放課後や長期休暇などを過ごす。2012年度に児童福祉法に位置付けられた。全国に約1万1000カ所あり、利用者は約18万人。生活に必要な力を伸ばす遊びや学習などをする。利用者は原則1割負担で、残りは国や自治体が負担する。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(下)
|
障害のある子どもたちが通う「あしたもえがお」。運営するNPO法人は報酬改定で減収となり、放課後デイ2カ所を統合した=名古屋市南区で |
 |
「二つが統合して通ってくる子が増えたことで、ストレスを感じている子は多い。友達の体を押したり、他の子の物を取ったり。いたずらして自分の存在を職員にアピールする子が増えた」。名古屋市南区の放課後等デイサービス(放課後デイ)「あしたもえがお」の管理者、仲松美咲さん(27)は声を落とす。放課後デイは、障害がある子どもたちが、活動しながら放課後や長期休暇などを過ごす施設だ。
通ってくるのは、特別支援学校などに通う小学二年から高校三年までの二十五人。しばらく前までは、中学生と高校生の計十一人だったが、運営主体のNPO法人「あした」が市内にもう一カ所開設していた放課後デイを七月に閉鎖。統合により、小学生ら十四人が移ってきた。
いずれの施設でも、子ども十人を職員七人で見る態勢を取ってきた。国が最低基準とする「十人に対して二人」を大幅に上回る。統合後も同じ態勢だが、それでも「どうしても小さい子に目がいってしまう。学年が上の子には、寂しい思いをさせてしまっている」と、仲松さんは表情を曇らせる。
統合の要因は、福祉サービス事業者宛ての国の基本報酬が四月に改定されたこと。通ってくる子どもの障害の重さに応じて報酬額が二つに分けられたが、閉鎖された放課後デイは報酬が低い区分となり、法人は年間約二百万円の赤字が見込まれた。職員を減らすことも検討されたが、「安全に見守れる態勢を維持するため、人件費を減らすのではなく二つを統合して家賃負担を減らすことを選んだ」と仲松さんは説明する。
経営悪化の背景には報酬改定の他、ここ数年、同様の施設が急に増え、競争が激しくなっていたこともある。厚生労働省によると、放課後デイは制度化された二〇一二年度は全国に約三千カ所だったのが、昨年四月時点では一万一千カ所と約四倍に。普及を図って報酬が高めに設定されたことや、利用者の負担が原則一割ですむため、安定的に利用者が見込めるとして、利益を求めて参入する事業者も少なからずいたためだ。
しかし、質の低下も問題視されるようになった。愛知県では昨年、管理者や保育士らを置かず、利用料の公的負担分や報酬を請求したとして、県内の運営企業が、六カ月間の新規利用者の受け入れ停止となり、約一億二千万円の返還を求められる事例もあった。
悪質業者も含む新規参入者の増加は、国や自治体の財政も圧迫。公費負担総額は、一二年度の四百七十六億円から一六年度は千九百四十億円に膨らんだ。
報酬改定で国は、こうしたことへの対応を図った。しかし、適正に運営し、子どもたちに放課後の居場所を提供してきた放課後デイが、あおりを食う状況に、不安を抱く人は多い。「うちの子は、部屋中を走り回って、じっとできない。小さな子にぶつかってけがをさせないかが、一番心配」。知的障害を伴う自閉症の高校二年生の長男(16)を通わせている母親(55)は統合の影響を懸念する。
「利益追求の事業所が増え、質を担保する必要があるのは分かる。でも放課後デイに支えてもらえなければ生きていけないほどお世話になってきた。安心して預けられるところまでが、追い込まれる状況はおかしいのではないか」と言う。
(細川暁子)
後を絶たないですね、不正受給。豊田市はきちんと行政処分をしています。
愛知県豊田市は7日、介護報酬約4730万円を不正受給したとして、同市の「医療法人寿光会 豊田老人保健施設」を半年間の新規利用者の受け入れ停止と、9カ月間の介護報酬3割減額の行政処分とした。
市によると、施設は2016年6月~18年1月に、月平均で定員を超えた状態が9カ月あった。定員超過の利用による減算を行わず、6回にわたって介護報酬を請求し受領。加算できない介護サービスへの報酬も受け取っていた。
同市に「定員を超過している」との情報が寄せられ、今年4月の調査で発覚した。施設の責任者は市の聞き取りに「稼働率を上げたかった」などと説明しているという。
これは便利になりました。
高齢者の運転免許返納 親族ら代行可能に 全署・幹部交番に窓口拡大
2018年9月5日
高齢者講習で指導員2人からアドバイスを受ける高齢ドライバー=千葉市花見川区の鷹ノ台ドライビングスクールで
写真
高齢ドライバーの運転免許の自主返納を促そうと、県警は親族や介護者などの代理人が、返納手続きを代行できる制度を始めた。病院に入院していたり、介護施設に入所しているなどやむを得ない事情がある場合が対象。免許課の担当者は「最寄りの警察署や幹部交番でも返納できるので、ぜひ利用してほしい」と呼び掛けている。
高齢者による事故が後を絶たないため、昨年三月に改正道交法が施行され、七十五歳以上のドライバーの認知機能検査などが強化された。県警は、運転に自信がなくなった人には、自主返納することを呼び掛けている。希望者には、身分証明書として使える運転経歴証明書を発行している。
これまで運転免許の返納手続きは、高齢者本人が千葉と流山の運転免許センターに訪れなければ認められていなかった。
新制度では、親族のほか、病院や介護施設の職員、ケアマネジャーなど福祉関係の有資格者、成年後見人が代理で申請できるようになった。本人が署名した「委任状兼承諾書」や、本人の運転免許証、代理人の身分証明書などを代理人が持参する。
申請窓口も千葉、流山両運転免許センターだけでなく、県内全三十九署と幹部交番全八カ所に広げた。
免許課によると、県内の六十五歳以上の免許の返納者は急増。二〇一三年に五千八百五十人だったのが、一七年は一万八千九百九十二人と三倍以上に増えている。
問い合わせは、千葉、流山両運転免許センターや最寄りの警察署・幹部交番へ。
◆認知機能検査、講習 待ち長期化
七十五歳以上の高齢ドライバーの認知機能検査で、今年三月末までの一年間に県内で検査を受けた九万八千九百三十四人のうち、二千三百九十三人(2・4%)が「認知症の恐れがある」と判定された。このうち十人が医師によって認知症と診断され、免許取り消しや停止処分となった。
県警免許課によると、「認知症の恐れがある」と判定された人のうち五百九十五人が自主返納した。
認知機能検査やその後に受ける「高齢者講習」では、予約待ちの長期化が課題となっている。
どちらも県内五十八カ所の自動車教習所で実施されている。検査は申し込みから受検まで平均五週間程度かかり、長い場合は三カ月待ちの教習所もある。高齢者講習は平均約三週間待ちで、最長で二カ月待ちとなる教習所もある。
検査では、指導員が対応できるのは一人当たり一度に十人まで、講習は三人までと道交法で定められており、一度に大勢を受け入れることができない。
受け入れ態勢の強化を図った教習所もある。鷹ノ台ドライビングスクール(千葉市花見川区)は検査や講習までの予約待ち期間は一週間ほど。新たに教習指導員を採用するなどしたという。
講習では、高齢者の事故の特徴や防ぎ方などを学ぶ。実際にコースを走行した後、ドライブレコーダーの映像で個別指導を受ける。千葉市美浜区から来た水口隆義さん(74)は「多少家から遠くても、検査と講習を早く終えたくて選んだ」と話した。
県警は、検査と講習の予約状況をホームページなどで紹介している。問い合わせは、県警免許課=電043(201)0110=へ。
(美細津仁志)