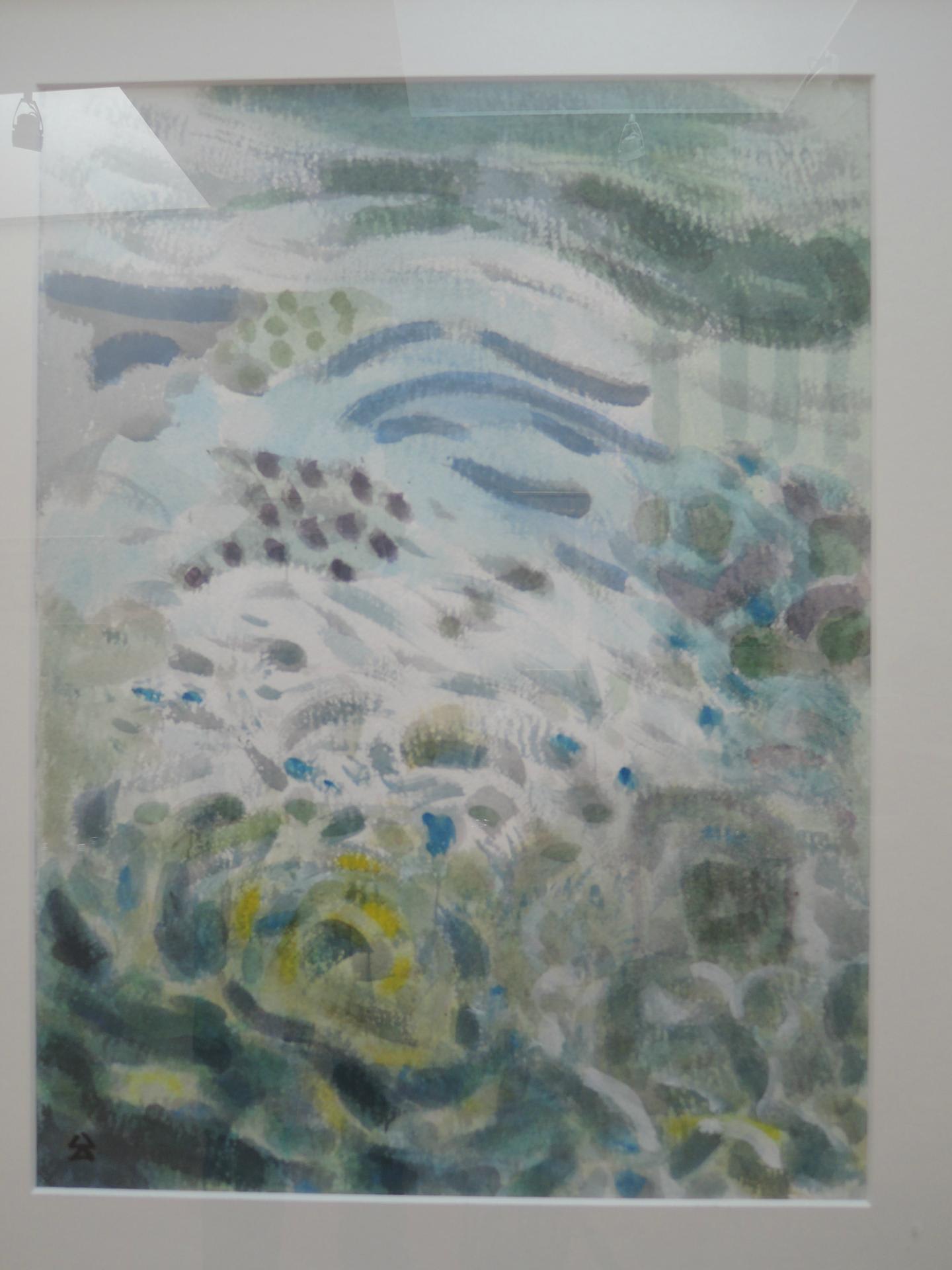日本精神史を読みながらの感想文の続きである。壁画であれ、仏像であれ、建築であれ、芸術、学問、宗教、法律までもが中国の最先端思想と技術によって、国の形が作られてきた国が日本である。その中心に存在し、中国文化に巻き込まれないような精神的安定を図った存在が天皇ではなかったのかという私の考え。天皇制は稲作文化に基づいた制度といえる。天皇家は水土の渡来技術を先進的に保持していた。稲作は水土技術がなければできない。しかも一定の権力の形成がなければ大きな土木工事は出来ない。水土を管理する技術は最先端技術であり、天皇家を中心とした集団が、管理運営をしていた。それ故に遣隋使遣唐使を含め、中国朝鮮からの渡来人が朝廷を技術者として支えていた。天皇という自然宗教神のような存在が、日本を維持するよすがであったのではなかろうか。最先端の技術を天皇を介して受け入れる様式の形成。
稲作を行う村々の鎮守に神社が作られはするが、あくまで、土俗的なアミニズム的な信仰が維持され、神道を宗教としてではなく、巨木信仰のように受け入れる。分かりやすく言えば、村の鎮守の大木への意識のようなものが、天皇という存在になる。身近な存在でもあり、永遠を思う遠い神が混同されていく。神社の巨木に戦争責任は問えない訳だ。ここにすり替えが起こり精神の安定が図られる。明治政府がこの天皇を、帝国主義の皇帝と位置付けたことで、天皇の意味が変質する。この天皇に対する見方は、堀田氏とも、阿満氏とも違う。正直私の考えている天皇像が正しい見方なのかどうかも自信がない。しかし、自分が田んぼをやってきた経験から、どうも技術というものはそういう事になるのではないかと考えるようになった。先端技術と宗教の関係を考えてみる必要がある。初期の宇宙飛行士が宗教家になるというようなことも、考える材料になるかもしれない。
日本人が豊かに心安寧に暮らすためには、最先端技術としての稲作を行う事が必要であった。その稲作技術が天皇家を介してもたらされることで、宗教にかかわり深い稲作が形成されていったのではないだろうか。現代でもMOAのように農業から宗教が生まれることがある。福岡氏や川口氏も極めて宗教的と言える。自然と一体化している農業が、日本人の生き方を支配していた時代があるのではないか。農業の中でも稲作は継続性という事が特に重要になる。3000年同じ場所で、自然耕作的に継続できる農業である。子孫に美田を残すために生きるという事になる。自分の田んぼを耕作してゆくという事は土を作っていることである。土は自分一代で結論が出ないようなものである。ご先祖様が土を作ってくれたから、今の自分が良い稲作ができるという実感の中で暮らすことができる。この舟原地区においても、1700年ごろに新田開発が行われ、人口が増加したとおもわれる。300年前の名前は知らないご先祖様が驚くべき程の努力の結果、作り出した田んぼを守り続けてきて今の自分の家族や暮らしがあるという意識が、日本人の村意識の根底にある。
それは近代日本国という国の成り立ちにも大きくかかわっている。問題になるのは明治期の日本が遅れた帝国主義国家として、必死近代国家を形成しようとしたときに、その日本人を天皇を中心とした、不思議な宗教国家ともいえるような不思議な形を作らされてしまったことになるのではなかろうか。日本の今の政治状況を考える上で、重要になる点はここにある。それまでの稲作神の様な天皇さんという村の鎮守の総まとめ的存在とは、隔絶する支配者としての帝王としての天皇の創出。これが現代の日本の保守思想を支配している。三島由紀夫氏、石原慎太郎氏ともに明治帝国主義の妄想家にしか見えない。安倍慎太郎氏は遅れてきた存在として、やはり同じに見える。こうした人たちに天皇家はゆがんだ明治期の天皇を期待されているのだ。日本人の精神史に大きな影響を与えてきた天皇の存在は、むしろ江戸時代の天皇家にあると考えるべきである。少なくとも、この2つの時代の天皇家を峻別して考えなければ、日本人の宗教は見えてこないように思う。(何かわけがわからないのだが、大切なことのようなので続ける。)