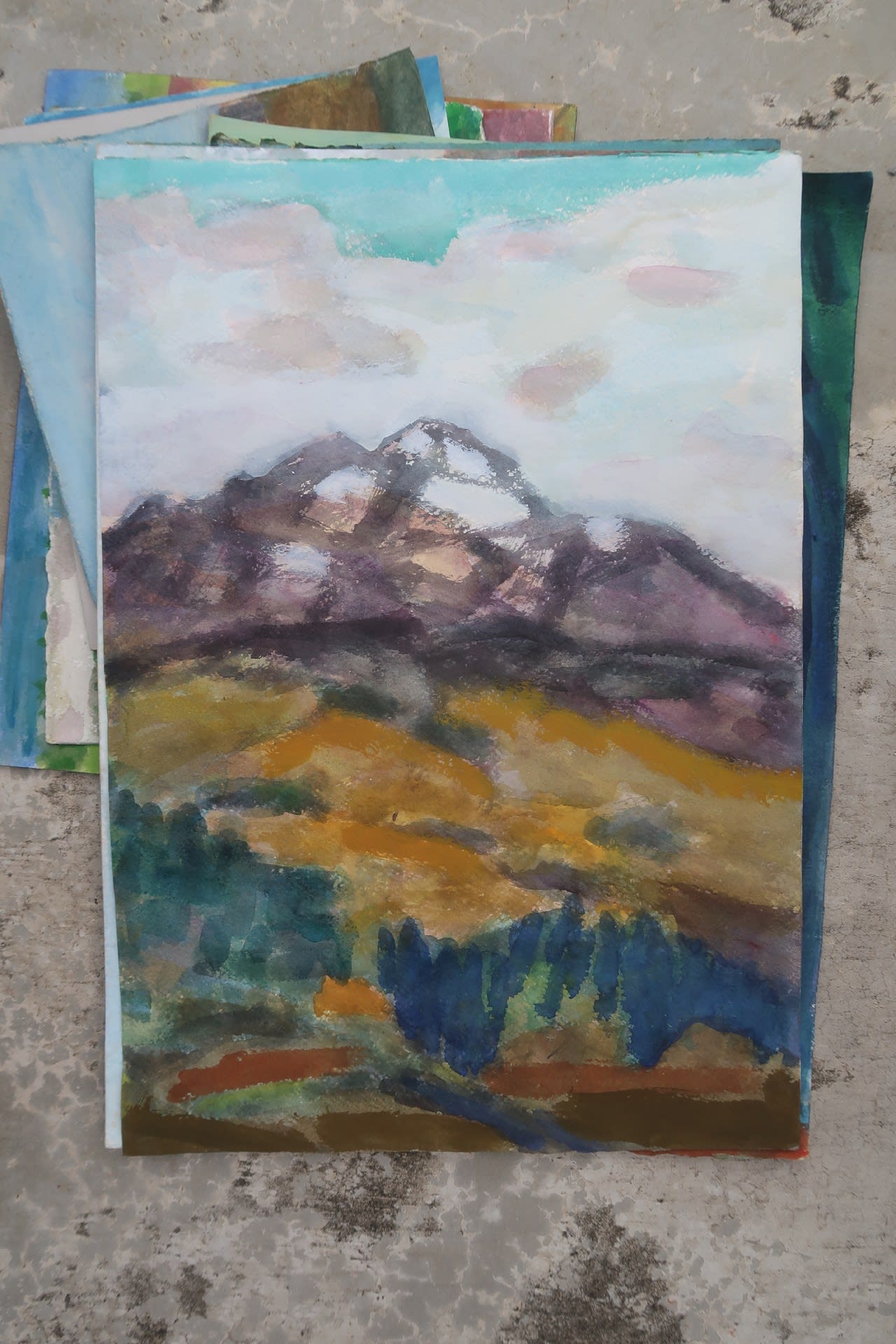絵を描いているときの状態を思い起こすのだが、訳の分からない状態。絵の世界に没入していると言うほどでもないのだが、何やらあやふやな感じなのだ。独特の状態なのだと思う。絵を描き出すと、大脳的には行き場を失い機能しなくなる。だから思い出す事ができない状態なのだ。
神がかりの人間ではない。ごく当たり前の普通の科学を重んじる人間である。だから絵を描いているときにはこんな感じで描いているなとは思うのだが、その感じを文章にしてみようと思い出すと、まったく言葉としては思い出せないのだ。何故なのだろうか。この状態がどういう状態か脳科学者に聞いてみたい。
ソンナエライ先生には縁もゆかりもないので、確かめる術もない。それでも良い絵を描こうとはしていないと言うことは確かだ。自由な状態で絵にしたがい、筆に従うようにしたい。そう考えているらしい。だから画面に反応しているだけなのだろう、こういう絵を描こうとかは思うことはない。
富士山を描いていたのが、何かのきっかけで菜の花畑の絵になるなど良くあることなのだ。たまたまそこに引かれた線から誘発されるように、絵が動き出す。動き出せば、その動きにできる限り邪魔をしないように、ついて行く。それだけなのだ。だからとんでもないことをしているに違いない。
やっと分かったところを全部描いてしまい。もう描けるような所はないなと言うところで、一段落で息をつく。その息を着いたときに絵を眺めている。ボーとして、半眠りで眺めている。突然その先のことが浮んでくる、すぐに飛び起きてまた描き始める。
描こうとすると、その気がついたこととは別のことをやり始めることが多い。どんどん壊し始めたりする。そこそこで来たのだから、何故メチャクチャのことをやってしまうのかは分からないが、どんどん潰していったりしている。描き継ぐ前には想像もしなかったような、とんでもないことになることが多い。
それはそれでいいと思いやっている。始まってしまえば、半眠りで見ていたときのことなど、飛んでしまう。しかし、その時ああそうだと思うから始めたにもかかわらず、画面の前に座るとまるで違うことをやる。これはほとんどの場合そうなのだ。これも何故なのかは分からないが、何でもやるが任せることがいいことにしている。
何が重要かは分からないが、ともかく絵を描く行為が重要なのであって、どんな絵を描くかは、ある意味たいしたことではないのだ。すべてを忘れて絵に没頭して絵を描く。それだけで良いと思っている。そうしていれば、いつかはきっと自分の絵という物が立ち現れるはずだと。これが悪い欲なのだ。
何故そう信じるかと言えば、前よりは自分の絵と言える絵に近づいている気がしているからだ。あれこれ頭を使って描いていたときはまったく自由という物ではなかった。自由に描く事を、大脳が制限を加えた。これでは自分が現われるはずがない。何からも自由でありながら、絵が描かれているとと言うところまで行くことが出来るのかである。
すこしづつだが、近づいているのではないかと、そういう希望的な気持ちがある。それは、このブログに載せている、日曜展示を見れば分かる。大半の人にはそうは見えないかも知れないが、肝心の私にはそう見えるのだから、問題は無い。了見違いであろうが、自分の方向に絵を描いて、努力していると思えるのだ。
これはそうありたいという欲かも知れないが、今はそれを信じて日々描いて行くほかない。どこまで行くものなのかこの方法を貫くつもりである。まあ実に曖昧で、デタラメなことだが、絵を描くというのはそんな物だ。どこにも確信できる物などない。
分かっているように描いている絵など大嫌いだし、くそ食らえである。りっぱにみえるような絵も嫌いだし、上手に見えるような絵は恥ずかしくて仕方がない。下手風に描くのもさらに嫌らしい。当たり前で、常識的な絵で良いと思っている。
特別気をてらうような必要も無い。平凡な絵で十分である。当たり前で常識的な絵が良いと思って描いている。ただ私の平凡に従おうというのだから、それは人とは違うかもしれない。絵はそれぞれの人間の中にあるのだ。その自らの当たり前の絵に至らなければならない。
一本の線を当たり前に引くことの難しさは限りない。上手そうな線は大嫌いだ。下手そうな線はわざとらしくて恥ずかしい。何が当たり前かは、これが当たり前の線だというように見えるまで、繰返し引く以外にない。繰り返している内に、意識しない当たり前の線になるだろう。
そうでありながら偶然引かれた線ののように見えるのも最悪だ。線ははっきりと自分の意志を反映していなければならない。私の考えが線を通して表明されている必要がある。意志があり、私であり、それがごく当たり前で無ければ嫌なのだ。そういう線がいつかは引けるのかと思いながら線を引く。
色もおなじだ、よさげな色は嫌だ。汚い色は尚嫌だ。ごく当たり前に、見える色を見えるように描きたい。それが難しくて困るだけなのだ。そうしたことがいつかは出来るはずだと思い、上手にならないように、下手にならないように、ただ当たり前に繰返し描く。
何とかこのように文章にしてみると、少し大げさになるが、こんな感じで絵を描いている。これを最善と思うわけでもないが、他にやりようもない。工夫はしない。頭は使わない。馬鹿になってやるほか無い。いや、それもダメだ。自分に近づこうとしてやるほか無い。
まだ、元気はある。過去一番気力を充実させて絵を描いている。あと20年あれば何とかなるかも知れない。遠回りをして、時間がかかることを恐れないでやりたい。慌てて結果を出そうとすれば、頭の制作になりかねない。手の制作にするには、時間を恐れないことだ。
いくらでも、無駄な時間を積み重ねてやるつもりだ。もし元気でこのまま絵を描き続ける事ができたら、何かは分かるはずだ。それでいいと思っている。結果をそれほど期待しているわけではない。今を充実して絵を描けることで十分満足なのだ。
ただその満足が将来の完成を目指している物でなければおかしいと言うことに過ぎない。本当はそうでなくても良いのかも知れない。いや、結論まで行かないことには今の意味が無い。そんな先のことは考えても無駄なことだ。今日も精一杯描いたし、明日も全力で描くと言うことだ。