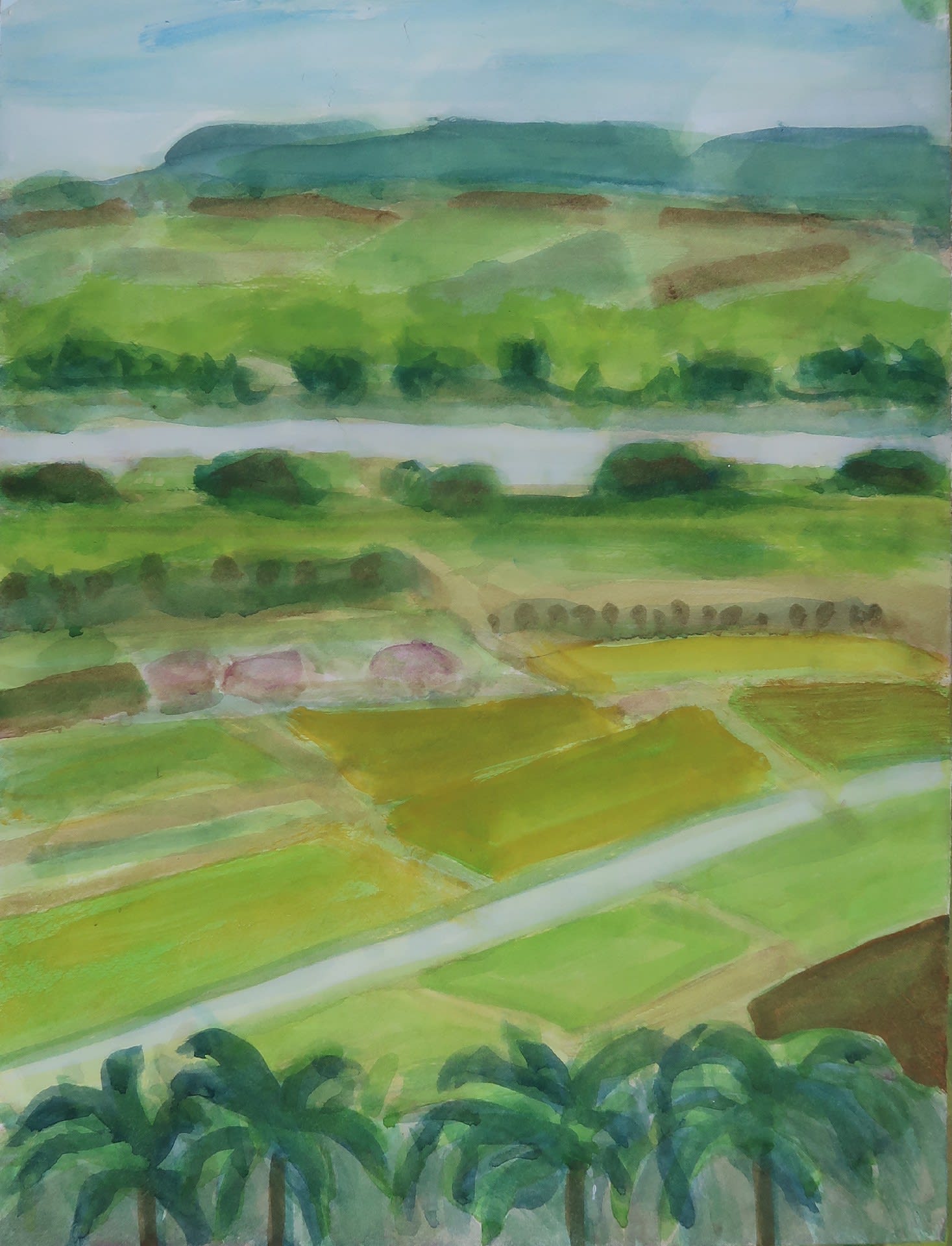水彩人は水彩画を探求する研究会として始まった。水彩という素材を生かした絵画を研究して行こうという組織だ。水彩人は装飾美術を目指すものではない。このことは何度でも言いたい。水彩画を人間を表現することの出来る藝術のための素材と考え、その奥深い表現方法を研究することが目的である。
芸術としての水彩画作品を描く事を目的と考えている。つまり、現代で言えば「私絵画」を描くために、最良の材料だと考えている。自分というもののを探り当てて行く上で、水彩という素材は、制作に自由に反応をしてくれる。これは誰にでもと言うより私にとってと言うことかも知れない。
水彩画には透明水彩というジャンルがある。水彩絵の具を薄く水で溶いて、透明性を生かして絵画を描くという方法である。水彩画の透明な美しさを生かして描く表現方法だ。英国から始まった方法のようだ。これは水彩画の一つの使い方で全体ではない。
この透明水彩の描き方の弱点は作者の意志の反映が弱くなると言うことである。対象を写実的に引き移すことに主眼が置かれ、描きながら作者の思想哲学を探求するという、芸術性はない場合が多い。そのことは逆から見れば、作品に作者の意志が画面に入らないので、安手の装飾品としては無難という意味でもある。
私の場合では、水彩画は絵の具を厚く塗り込めた部分もあったほうが良いと考えている。描いた線に筆触残る方が良いと考えている。その上で、水彩絵の具の透明性も利用した方が良いことは当たり前だ。つまりあらゆる方法で水彩絵の具を使えば良いと考えるのが「私絵画」だ。
日本透明水彩画会と言う水彩画のグループがある。この会の人で水彩人の同人という人も2人いる。だから決定的に何かが違うと言うことでも無いのだが、透明水彩とわざわざ会の名称にするくらいで、たぶんこの会には、不透明で色を塗り重ねるような水彩画はたぶん余りないのだろうかと思う。
水彩人は基本水彩絵の具を使うと言うことが条件で、どのような使い方をしようともかまわない。できる限り自由であることが大事だと考えている。何でもやれるのが水彩絵の具だと思う。やりたいようにやればいいのが水彩人である。だから水彩人には様々な絵があるのだとおもう。
水彩絵の具は子供にも取り組める材料である。紙に描くのが普通という意味でも、絵を描く材料としての手軽さは一番だろう。アクリル絵の具も便利なものではあるが、色が汚いのが弱点である。いわばプラステックの素材感は到底私には耐えられなかった。
水彩の透明性を生かして描くと、とても美しい表現になる。その表面的な素材の美しさのために、その美しさの奥にある世界に進みがたくなる。最初に塗った色の美しさに引っ張られてしまい、浅い通俗的な世界に留まる作品が多く成るのはその性である。
誰が描いたと言う事は無くなり、透明水彩画描法で描いたと言うことになっている作品になりがちだ。モミジを描くためにはこの手順で、薔薇を描くためにはこの手順で、こうした指導書が沢山でている。この考え方は、私絵画から言えば、絵を描く最も大切な部分を捨てていると言える。
商品絵画の分野では、透明水彩の作品が多いのだろう。そうした絵画はあるスタイルを踏襲したものになっている。誰が描いたかよりも、装飾品としての意味が重視されている。巧みな手順で、巧みに描かれて居ればそのスタイルが絵画の意味になる。
水彩人ではそうした描法で描く絵を水彩画の中心には置かない。水彩人は下手は絵の内と考えている。上手いは絵の外と考えている。上手そうに見えると言うことはむしろ恥ずべき事だと考えている。「なんだこりゃー」と言うのが芸術だ岡本太郎が叫んでいたが、その通りである。
岡本太郎の作品はその主張とは裏腹にあまりに慎重で、様式で作られていると見えるが、書いている本は正しい芸術論に満ちている。「芸術は爆発だ」これもなかなかいい。縄文土器を見て「なんだこりゃー」と叫んだのだ。今縄文はブームであるが、岡本太郎に始まっているのだ。
未だかつてないものに挑戦して行くことが芸術的行為である。ありがちな絵をなぞらえるようなものは、芸術作品とは言わない。この点を間違えてしまうと、違うところにはまり込んでしまう。だから水彩人は下手くそだというのは、素晴らしい褒め言葉だと考えている。
お上手ですねでは、芸術にはならない。この点水彩画に対する世間の評価がおかしいのであえて書いてみた。プレパトというテレビ番組が悪いらしい。番組は見たことがないので分からないのだが、その問題点がウエッブで見てみてよく分かる。
絵は人と競べるようなものではない。誰が一番上手い、などと言うことは無い。どこまでもその人であればそれでいい。その人の世界がどこまで深いかが問題なのだ。絵で見たいのはその人の世界なのだ。見たいほどの人間は滅多にいないわけだが。よく出来た水彩画が見たいわけではないのだ。
プレパトのウエッブを見た範囲では、そこにあるのは技術だけである。写真を見て上手に移すことを基準にしている。こうした制作方法はマチガテもやらない方が良いことである。肝に銘じておかなければならない。絵を描くと言うことで一番大切な物が失われる。
見て感動するという原点である。描きたいという思いの原点は、自分という人間が見て感動したものを、画面に表現すると言うことにある。見た対象を説明するのではなく、その場で起きた感動を表さなければならない。感動も何もない写真を見せられてこれを絵にしろというようなことは、絵を描く上で害になる。
しかし、水彩画の異端は私の方であろう。わたしがおかしいと言うのが世間の見方なのだろう。そんなことはどうでも良いが、水彩画が誤解されて行くのは寂しい。水彩人にそうした絵が現われてきているのは残念である。水彩人は上手な絵を良い絵とはしていない。
水彩画の探求をいよいよ真剣にやらなければならない。絵を描きたいのであれば、自分の世界観を持たなければならない。絵が悪いのはその人間が浅はかだからだ。これは自戒である。以前他の人にこのことを言って、この歳になって人間が悪いなどと言われるとは思わなかったと言われた。
やはり本音で言えばそういうことにならざる得ない。中川一政の書は見たいが、代書屋の書いたものを見たいとは思わない。見たい水彩画は、みたい人間が描いた絵だ。まだまだである。