黄色の大地の岩山に巨大な石仏が彫られているのが中国三大石窟の一つの雲崗石窟でしたが、黄色の砂漠の岩山に巨大な王の像が彫られているのがアブシンベル神殿です。アブシンベル神殿は、アスワン・ハイ・ダムに水没してしまう可能性がありましたが、UNESCOによって移築され保存されました。このプロジェクトが世界遺産の創設のきっかけとなりました。今回の写真は、現地でカメラが壊れ、8mmビデオの映像から取り込んだため、不鮮明な画像になっています。
アブシンベル神殿は、エジプトの最南端のスーダン国境に近いところにあります。観光客は、通常は200km程離れたアスワンを経由して、飛行機でアブシンベル空港まで行き、そこからバスに乗り継いで神殿まで行くことになります。さすが世界的な観光地だけあって、3,000m級の滑走路を持ち大型機も離発着できる空港になっています。ただ、空港の周りは茶色の砂漠が広がるだけで、滑走路を作る土地はいくらでもありそうですが。時間に余裕のある人は、アスワンから3~4泊のクルーズ船が出ているようで、アブシンベル神殿以外の遺跡も眺めることができて、なかなか好評なのだそうです。



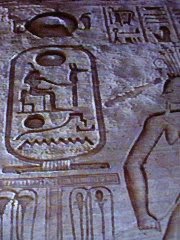
 アブシンベル神殿は紀元前13世紀頃にラムセスⅡによって作られたもので、大神殿と小神殿とからできています。このラムセスⅡはよほど自己顕示欲が強かったらしく、神殿を飾る巨像のほとんどが本人の像です。大神殿正面の4体の巨像は当然ながらラムセス本人で、妻にささげたといわれる小神殿の6体の像も、4体までがラムセスとされています。大神殿の中央の入り口から入っていくと、壁には数多くの壁画や像があり、最奥の4体の像には年に2回太陽の光が届くのだそうです。本来はラムセスⅡの誕生日の2月22日と即位した10月22日でしたが、移築によって日にちがずれてしまったのだそうです。それにしても、3,000年以上も前に、あの巨大な神殿をそれだけ正確に作るという技術の高さには改めて驚かされます。
アブシンベル神殿は紀元前13世紀頃にラムセスⅡによって作られたもので、大神殿と小神殿とからできています。このラムセスⅡはよほど自己顕示欲が強かったらしく、神殿を飾る巨像のほとんどが本人の像です。大神殿正面の4体の巨像は当然ながらラムセス本人で、妻にささげたといわれる小神殿の6体の像も、4体までがラムセスとされています。大神殿の中央の入り口から入っていくと、壁には数多くの壁画や像があり、最奥の4体の像には年に2回太陽の光が届くのだそうです。本来はラムセスⅡの誕生日の2月22日と即位した10月22日でしたが、移築によって日にちがずれてしまったのだそうです。それにしても、3,000年以上も前に、あの巨大な神殿をそれだけ正確に作るという技術の高さには改めて驚かされます。
 アブシンベル神殿のUNESCOによる移築は、1964年から4年間を要して行われ、標高にして60mほど上部に移動しました。移築したのは巨像のある前面だけで、後方の丘はコンクリート製のドームに砂をかぶせたもの。中に入ると巨大なプラネタリュウムかドーム球場の感じで、とても遺跡の雰囲気はありません。それでも、移築費用は当時のお金で8千万ドル以上もかかったのだそうです。移築する前の神殿の写真を見ると、ナイル川の川原から岩山が立ち上がっていますが、移築後の現在は、砂漠の大地がナセル湖に向かってテラス状に伸びている途中に、岩山が忽然と現れるといった感じです。どうしても不自然な感じがするのは、無理からぬことかもしれません。このナセル湖は当然淡水で灌漑用にも使われていると思うのですが、湖岸には木一本生えていないのが不思議でした。気温が高すぎるのでしょうか、緯度的には香港と変わらないのですが。
アブシンベル神殿のUNESCOによる移築は、1964年から4年間を要して行われ、標高にして60mほど上部に移動しました。移築したのは巨像のある前面だけで、後方の丘はコンクリート製のドームに砂をかぶせたもの。中に入ると巨大なプラネタリュウムかドーム球場の感じで、とても遺跡の雰囲気はありません。それでも、移築費用は当時のお金で8千万ドル以上もかかったのだそうです。移築する前の神殿の写真を見ると、ナイル川の川原から岩山が立ち上がっていますが、移築後の現在は、砂漠の大地がナセル湖に向かってテラス状に伸びている途中に、岩山が忽然と現れるといった感じです。どうしても不自然な感じがするのは、無理からぬことかもしれません。このナセル湖は当然淡水で灌漑用にも使われていると思うのですが、湖岸には木一本生えていないのが不思議でした。気温が高すぎるのでしょうか、緯度的には香港と変わらないのですが。
エジプトやヨーロッパに行くと、千年二千年、またはそれ以上の年月を経た遺跡が残っています。石で作られた建物は、火災に遭っても躯体は残るし、壊すのも大変です。ただ、新しい建物に使うために古い神殿などの石を流用したという話しはよく聞きますが。一方、東洋の建物は木で作られ、火災にはひとたまりもなく、虫に食われたり自然に朽ちたりで、世界一古い木造建築の法隆寺でさえ、やっと1400年です。朽ち易い有機物と、いつまでも残る無機物の差が文化の差にもなっているかもしれません。現在のコンピュータは無機物のシリコン結晶に依存していますが、有機物半導体の研究も盛んに行われています。この有機物は朽ちないで後世に残されるでしょうか。
アブシンベル神殿は、エジプトの最南端のスーダン国境に近いところにあります。観光客は、通常は200km程離れたアスワンを経由して、飛行機でアブシンベル空港まで行き、そこからバスに乗り継いで神殿まで行くことになります。さすが世界的な観光地だけあって、3,000m級の滑走路を持ち大型機も離発着できる空港になっています。ただ、空港の周りは茶色の砂漠が広がるだけで、滑走路を作る土地はいくらでもありそうですが。時間に余裕のある人は、アスワンから3~4泊のクルーズ船が出ているようで、アブシンベル神殿以外の遺跡も眺めることができて、なかなか好評なのだそうです。



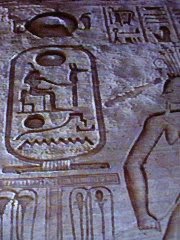
 アブシンベル神殿は紀元前13世紀頃にラムセスⅡによって作られたもので、大神殿と小神殿とからできています。このラムセスⅡはよほど自己顕示欲が強かったらしく、神殿を飾る巨像のほとんどが本人の像です。大神殿正面の4体の巨像は当然ながらラムセス本人で、妻にささげたといわれる小神殿の6体の像も、4体までがラムセスとされています。大神殿の中央の入り口から入っていくと、壁には数多くの壁画や像があり、最奥の4体の像には年に2回太陽の光が届くのだそうです。本来はラムセスⅡの誕生日の2月22日と即位した10月22日でしたが、移築によって日にちがずれてしまったのだそうです。それにしても、3,000年以上も前に、あの巨大な神殿をそれだけ正確に作るという技術の高さには改めて驚かされます。
アブシンベル神殿は紀元前13世紀頃にラムセスⅡによって作られたもので、大神殿と小神殿とからできています。このラムセスⅡはよほど自己顕示欲が強かったらしく、神殿を飾る巨像のほとんどが本人の像です。大神殿正面の4体の巨像は当然ながらラムセス本人で、妻にささげたといわれる小神殿の6体の像も、4体までがラムセスとされています。大神殿の中央の入り口から入っていくと、壁には数多くの壁画や像があり、最奥の4体の像には年に2回太陽の光が届くのだそうです。本来はラムセスⅡの誕生日の2月22日と即位した10月22日でしたが、移築によって日にちがずれてしまったのだそうです。それにしても、3,000年以上も前に、あの巨大な神殿をそれだけ正確に作るという技術の高さには改めて驚かされます。 アブシンベル神殿のUNESCOによる移築は、1964年から4年間を要して行われ、標高にして60mほど上部に移動しました。移築したのは巨像のある前面だけで、後方の丘はコンクリート製のドームに砂をかぶせたもの。中に入ると巨大なプラネタリュウムかドーム球場の感じで、とても遺跡の雰囲気はありません。それでも、移築費用は当時のお金で8千万ドル以上もかかったのだそうです。移築する前の神殿の写真を見ると、ナイル川の川原から岩山が立ち上がっていますが、移築後の現在は、砂漠の大地がナセル湖に向かってテラス状に伸びている途中に、岩山が忽然と現れるといった感じです。どうしても不自然な感じがするのは、無理からぬことかもしれません。このナセル湖は当然淡水で灌漑用にも使われていると思うのですが、湖岸には木一本生えていないのが不思議でした。気温が高すぎるのでしょうか、緯度的には香港と変わらないのですが。
アブシンベル神殿のUNESCOによる移築は、1964年から4年間を要して行われ、標高にして60mほど上部に移動しました。移築したのは巨像のある前面だけで、後方の丘はコンクリート製のドームに砂をかぶせたもの。中に入ると巨大なプラネタリュウムかドーム球場の感じで、とても遺跡の雰囲気はありません。それでも、移築費用は当時のお金で8千万ドル以上もかかったのだそうです。移築する前の神殿の写真を見ると、ナイル川の川原から岩山が立ち上がっていますが、移築後の現在は、砂漠の大地がナセル湖に向かってテラス状に伸びている途中に、岩山が忽然と現れるといった感じです。どうしても不自然な感じがするのは、無理からぬことかもしれません。このナセル湖は当然淡水で灌漑用にも使われていると思うのですが、湖岸には木一本生えていないのが不思議でした。気温が高すぎるのでしょうか、緯度的には香港と変わらないのですが。エジプトやヨーロッパに行くと、千年二千年、またはそれ以上の年月を経た遺跡が残っています。石で作られた建物は、火災に遭っても躯体は残るし、壊すのも大変です。ただ、新しい建物に使うために古い神殿などの石を流用したという話しはよく聞きますが。一方、東洋の建物は木で作られ、火災にはひとたまりもなく、虫に食われたり自然に朽ちたりで、世界一古い木造建築の法隆寺でさえ、やっと1400年です。朽ち易い有機物と、いつまでも残る無機物の差が文化の差にもなっているかもしれません。現在のコンピュータは無機物のシリコン結晶に依存していますが、有機物半導体の研究も盛んに行われています。この有機物は朽ちないで後世に残されるでしょうか。



















