長谷寺は山の南斜面を這い上がっるようにお寺の伽藍が建っていました。長谷寺の前に紹介した室生寺も傾斜はなだらかですが室生川に向けてのなだらかな南斜面に伽藍が立ち並んでいます。一方、住宅地も横浜や神戸などの山の手は傾斜地に住宅街が伸びっています。斜面の場合には南側に家が建っても日陰になりにくいというメリットがあるかもしれませんが、日常生活では坂の上り下りで大変かと思います。坂の町の住宅街は数多くありますが、土蔵造りの古民家が軒を連ねるところはさほど多くはないかと思います。今回は、大阪から室生寺や長谷寺に向かう近鉄大阪線のずっと大阪よりの安堂駅からほど近い柏原(かしわら)市の太平寺地区を紹介します。








太平寺地区は、生駒山系から大和川に向かって伸びた扇状地で、地名の由来は続日本紀に記載のあるお寺の子院の一つである太平寺があったため推定されています。江戸時代には大和川の右岸にあたる柏原や八尾は河内木綿の産地としての豪農や、大和川を使って南河内の農産物を大阪に運んだ豪商などの家が立ち並んだものと言われています。また、明治期以降は、傾斜地を利用したブドウの栽培で潤ったようです。ただ、東高野街道や鉄道は、太平寺地区の西側を南北に貫いており、太平寺地区は近代の交通のルートから外れてしまったため、古い町並みが冷凍保存されて残されたのかもしれません。地区内の道路は軽自動車がやっと通れ、対向車とはすれ違えないほど狭く、この不便さも町並みが残る要因の一つだったかもしれません。










冷凍保存といっても、古民家群は真新しく見え、常に手入れが行われていることを感じさせます。また、他ではよく見かける、古民家のそばに景観を損ねる家や商店を見かけないのも太平寺地区の良さかもしれません。とにかく、例外なく土蔵と羽目板張りの民家が続きます。漆喰部分は城が目立ちますが、黒漆喰で塗られた民家もあって、重々しさを感じます。高知県で見かけた水切り瓦と思しきつくりのある民家も見かけました。大阪の市街地の南東10km、近鉄で40分足らずのところに、こんな町並みが残っていたというの奇跡みたいです。
この地区で育ったブドウを原料に大正時代にワインの醸造が始まり、現存のワイナリーとしては西日本最古だそうです。町内にあるワインの貯蔵庫は登録文化財にも指定されています。ワインというと、熟成が必要なお酒ですが、この熟成によって化学的にどのような変化が起こるのか、これまでいろいろな研究が行われ、諸説があるようです。一説には水の分子構造が変化して、アルコールの刺激がまろやかに鳴門とのことで、通常は熟成をしない日本酒では、熟成しなくても美味しいのは原料の水自体が「美味しい水」だからかもしれません。熟成には温度や湿度など貯蔵環境がい大きく影響し、ワインの愛好家によってはコンピュータ管理をした地下貯蔵庫を持っている方もいらっしゃるようですね。








太平寺地区は、生駒山系から大和川に向かって伸びた扇状地で、地名の由来は続日本紀に記載のあるお寺の子院の一つである太平寺があったため推定されています。江戸時代には大和川の右岸にあたる柏原や八尾は河内木綿の産地としての豪農や、大和川を使って南河内の農産物を大阪に運んだ豪商などの家が立ち並んだものと言われています。また、明治期以降は、傾斜地を利用したブドウの栽培で潤ったようです。ただ、東高野街道や鉄道は、太平寺地区の西側を南北に貫いており、太平寺地区は近代の交通のルートから外れてしまったため、古い町並みが冷凍保存されて残されたのかもしれません。地区内の道路は軽自動車がやっと通れ、対向車とはすれ違えないほど狭く、この不便さも町並みが残る要因の一つだったかもしれません。










冷凍保存といっても、古民家群は真新しく見え、常に手入れが行われていることを感じさせます。また、他ではよく見かける、古民家のそばに景観を損ねる家や商店を見かけないのも太平寺地区の良さかもしれません。とにかく、例外なく土蔵と羽目板張りの民家が続きます。漆喰部分は城が目立ちますが、黒漆喰で塗られた民家もあって、重々しさを感じます。高知県で見かけた水切り瓦と思しきつくりのある民家も見かけました。大阪の市街地の南東10km、近鉄で40分足らずのところに、こんな町並みが残っていたというの奇跡みたいです。
この地区で育ったブドウを原料に大正時代にワインの醸造が始まり、現存のワイナリーとしては西日本最古だそうです。町内にあるワインの貯蔵庫は登録文化財にも指定されています。ワインというと、熟成が必要なお酒ですが、この熟成によって化学的にどのような変化が起こるのか、これまでいろいろな研究が行われ、諸説があるようです。一説には水の分子構造が変化して、アルコールの刺激がまろやかに鳴門とのことで、通常は熟成をしない日本酒では、熟成しなくても美味しいのは原料の水自体が「美味しい水」だからかもしれません。熟成には温度や湿度など貯蔵環境がい大きく影響し、ワインの愛好家によってはコンピュータ管理をした地下貯蔵庫を持っている方もいらっしゃるようですね。






























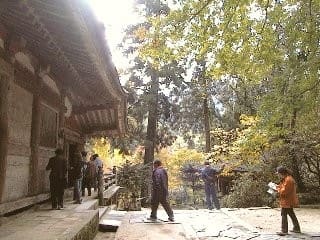













































































































































 南に行くと油津港で、南国の宮崎らしいパッっと明るい景色が広がります。その景色の中に直方体に赤い屋根が乗り窓のない石倉倉庫の建物が、ちょっと異質にぽつんと建っていました。
南に行くと油津港で、南国の宮崎らしいパッっと明るい景色が広がります。その景色の中に直方体に赤い屋根が乗り窓のない石倉倉庫の建物が、ちょっと異質にぽつんと建っていました。














