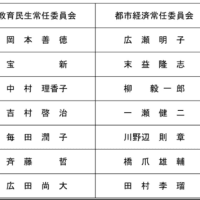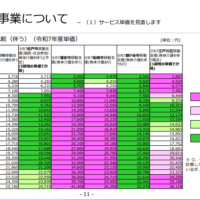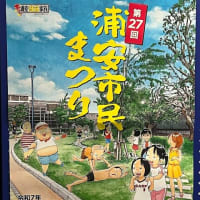昨年の第一回議会で浦安市は「浦安市まちづくり基本条例」を制定しました。(4月1日施行)
条例の内容はこちらです。↓
外国人に参政権を認めることを容認する箇所など全くないのに、当時、何故か全国から私にも(多分、他の市議にも)沢山のメールや電話が届きました。採決時に賛成しないで下さいとの内容でした。
浦安市の条例は、外国人の参政権には全く触れていないのですが、第3条の「市民」の定義が気になったようです。
※(用語の定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいいます。
この条文からすると、「外国人」も当然ふくまれ、外国人に参政権の道を開く危険性があるとの主張のようでした。
条例には当然「用語の定義」が必要です。定義がないと条例が対象としている範囲が決まりません。解釈者の恣意性を排除できなくなります。その意味で、私は全くこの条文には問題がないと今でも考えていますので、当時全国から送られてきたメールや電話には与することが出来ませんでした。
ところで、熊本市で自治基本条例の改正を巡り、「参政権」との誤解がSNSの世界で広まっているとのことですが、一年前の浦安市と同じような現象が起きているのでしょうか。
第2条の「市民」に「外国の国籍を有する者を含む」を加えることで誤解が広がっているようです。
(一部抜粋)
熊本市によると、現行条例で定める「市民」にも外国人が含まれるという認識だった。しかし、条例改正の内容を審議した自治推進委員会のメンバーから「きちんと書いていないと分かりにくい」「外国人も市民として明記すべきだ」といった声が出たという。
市はこうした指摘を踏まえて昨年12月7日に改正素案をまとめ、今年1月18日まで1カ月間を意見公募の期間に設定。その声も踏まえ、2月定例市議会に改正案を提出し、4月1日に施行する日程を描く。
SNSに詳しい熊本学園大商学部の堤豊教授(63)は「ネット上では極端な意見や主張が支持され、発信力のある人が書き込むと一気に広がることがある。見る側には、何が事実なのかを冷静に見極めるリテラシー(知識や判断力)が求められる」と指摘した。