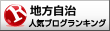24時間対応の定期巡回・随時対応サービスモデル事業、年間151回しか利用がなかったわけですが、ではその利用実績は・・・。
以下の表にまとめてみました。
クリックすると拡大します。↓

7月は26日からスタートしたので、利用者ゼロ、8月は定期利用者1名×2回利用、随時利用者2名がそれぞれ1回利用、合計4回利用でした。
9月は定期利用者1名が7回利用、随時利用は3名が合計7回利用しています。
・
・
・
こんな感じで、3月までに合計151回の利用がありました。
1回、約20分の介護の仕事です。
●随時対応の為なのでしょう、7月26日から翌3月31まで、朝6時から夜10時まで常時人を3名配置して出動要請を待っていました。
結局随時利用回数は89回だけでした。
この89回の為だけに、朝6時から夜10時まで常時3名の職員を待機させていたことになります。
(定期利用は、事前にわかるわけですから、人を待機させる意味はありません。)
「非効率」なんて言うものではありません!言葉がありません。
●定期利用者はモデル事業期間を通しての利用者はたったの1名のみでした。
しかもこの定期利用者は火曜日と土曜日のみ利用していたようで、「定期利用」の用語として正しいのかどうか私は疑問を抱いています。
浦安市24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業実施要項(23年7月5日)第4条事業の内容では、
(1)定期巡回訪問サービス事業
利用者に対し、予め作成された計画に基づき、日常生活上の介助を必要に応じて1日数回程度提供する事業。原則として、そのサービス内容を行うのに標準的な時間は1回あたり概ね20分未満のものとする。
と定められています。
1週間にたったの2回だけの利用を、このモデル事業が予測していた定期利用と言ってよいのでしょうか?
毎日の利用は全期間通じて一度もありませんでした。
要綱で厳格に定期巡回訪問サービス事業につてい規定をしておきながら、それに沿わない利用形態を「定期利用」として国に報告で上げているわけです。何か釈然としません。
そもそもこの法人には、要綱が求めていた定期利用者はいたのでしょうか?あるいは集める能力があったのでしょうか?
もし、ないのであれば、市内の他の事業者と連携して、本来の意味での定期利用者を募れば良かったのです。
事業は再委託というものも認めていましたので、その気があればできたはずです。
この事業は1回100円でサービスが受けられるように市は設定していました。(自治体でこの金額は異なります。)
介護保険の自分の持ち点を使い切って介護保険を利用できない人、あるいは、1回100円なら利用しやすいのでたとえモデル事業期間だけでも利用してみたいと考えていた市民はいたはずです。
既存のサービスを利用していても、このサービスは利用可能でしたから。
滋賀県草津市では広報(8月1日号)で広く市民にこのサービスの実施を知らせています。
浦安市ではこのような宣伝はゼロ。
市内該当事業者へのこの事業への協力要請も、皆無に等しかったのです。(事業を始める時の事業者への案内・公募方法からしておかしかったのです。これにつていは、後に書きます。)
草津市の広報 ↓

浦安市の場合、広報等で市民に広く宣伝し、潜在的利用者を掘り起こす努力をした跡も見れません。
市は事業者の努力を期待していたのかもしれませんが、朝6時から夜10時まで職員を配置さえしていれば、利用者獲得のための惜しみない努力はしなくても国からお金が入る仕組みになっていたので、事業者の努力は最初から期待することが無理な話だったのではないでしょうか。
こんなに利用者がいなくても、実際お金は動きました。
既に払い込みは終わっています。(昨年10月7日…7、579、000円…と12月20日…11、871、000円…の二度にわたって支払いが行われています。)
以下の表にまとめてみました。
クリックすると拡大します。↓

7月は26日からスタートしたので、利用者ゼロ、8月は定期利用者1名×2回利用、随時利用者2名がそれぞれ1回利用、合計4回利用でした。
9月は定期利用者1名が7回利用、随時利用は3名が合計7回利用しています。
・
・
・
こんな感じで、3月までに合計151回の利用がありました。
1回、約20分の介護の仕事です。
●随時対応の為なのでしょう、7月26日から翌3月31まで、朝6時から夜10時まで常時人を3名配置して出動要請を待っていました。
結局随時利用回数は89回だけでした。
この89回の為だけに、朝6時から夜10時まで常時3名の職員を待機させていたことになります。
(定期利用は、事前にわかるわけですから、人を待機させる意味はありません。)
「非効率」なんて言うものではありません!言葉がありません。
●定期利用者はモデル事業期間を通しての利用者はたったの1名のみでした。
しかもこの定期利用者は火曜日と土曜日のみ利用していたようで、「定期利用」の用語として正しいのかどうか私は疑問を抱いています。
浦安市24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業実施要項(23年7月5日)第4条事業の内容では、
(1)定期巡回訪問サービス事業
利用者に対し、予め作成された計画に基づき、日常生活上の介助を必要に応じて1日数回程度提供する事業。原則として、そのサービス内容を行うのに標準的な時間は1回あたり概ね20分未満のものとする。
と定められています。
1週間にたったの2回だけの利用を、このモデル事業が予測していた定期利用と言ってよいのでしょうか?
毎日の利用は全期間通じて一度もありませんでした。
要綱で厳格に定期巡回訪問サービス事業につてい規定をしておきながら、それに沿わない利用形態を「定期利用」として国に報告で上げているわけです。何か釈然としません。
そもそもこの法人には、要綱が求めていた定期利用者はいたのでしょうか?あるいは集める能力があったのでしょうか?
もし、ないのであれば、市内の他の事業者と連携して、本来の意味での定期利用者を募れば良かったのです。
事業は再委託というものも認めていましたので、その気があればできたはずです。
この事業は1回100円でサービスが受けられるように市は設定していました。(自治体でこの金額は異なります。)
介護保険の自分の持ち点を使い切って介護保険を利用できない人、あるいは、1回100円なら利用しやすいのでたとえモデル事業期間だけでも利用してみたいと考えていた市民はいたはずです。
既存のサービスを利用していても、このサービスは利用可能でしたから。
滋賀県草津市では広報(8月1日号)で広く市民にこのサービスの実施を知らせています。
浦安市ではこのような宣伝はゼロ。
市内該当事業者へのこの事業への協力要請も、皆無に等しかったのです。(事業を始める時の事業者への案内・公募方法からしておかしかったのです。これにつていは、後に書きます。)
草津市の広報 ↓

浦安市の場合、広報等で市民に広く宣伝し、潜在的利用者を掘り起こす努力をした跡も見れません。
市は事業者の努力を期待していたのかもしれませんが、朝6時から夜10時まで職員を配置さえしていれば、利用者獲得のための惜しみない努力はしなくても国からお金が入る仕組みになっていたので、事業者の努力は最初から期待することが無理な話だったのではないでしょうか。
こんなに利用者がいなくても、実際お金は動きました。
既に払い込みは終わっています。(昨年10月7日…7、579、000円…と12月20日…11、871、000円…の二度にわたって支払いが行われています。)