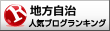千鳥に障がい者就労を目的とした野菜工場を作る予定ですが、野菜工場そのものの運営は大変なようです。この事業は、現在事業者選定に入っているようですが、以下の記事を読むと、可成りの専門的技術を持った事業者でないと難しそうです。市は、こんな困難さが伴う事業を敢えて事業化したわけですが、大丈夫でしょうか?
補助金漬け「植物工場」の不毛~どうなる?日本の次世代農業
2つの象徴的な倒産
1980年代後半の第1次、90年代後半の第2次を経て、農水・経産両省連携の国家プロジェクトとして2009年に始まった植物工場の第3次ブームが今なお続いている。しかし、植物工場の多くは(1)コストが高い(2)栽培法・経営ノウハウが未熟(3)露地野菜との差別化ができない――の三重苦に喘(あえ)ぎ、赤字経営に陥って撤退・倒産するケースも珍しくはない。
15年前半に象徴的な植物工場の倒産が2件相次いだ。1月初旬、東日本大震災の復興モデルとして注目された宮城県名取市の「さんいちファーム」(11年11月設立)が、約1億3200万円の負債を抱えて倒産した。
仙台市の被災農家3人が、資金約3億5000万円(うち国・宮城県・名取市の補助金が8割)で植物工場を建設。ベビーリーフなどの葉物野菜を土壌の代わりに養分を溶かした水を使う水耕栽培で生産し、スーパーなどに販売していた。
しかし、彼らには畑での露地栽培の経験はあるが、水耕栽培は初めてだ。その上、メーカーの技術指導が不十分なため、発育障害が多く売上高が落ち込んだ。その一方で、電気代や人件費などコストがかかって赤字が累積し、再建を断念した。
2件目は15年6月末、04年9月に設立された大学発ベンチャー「みらい」(東京都中央区)が負債額約10億9200万円で倒産した。
創業者の嶋村茂治氏は第3次植物工場ブームに火をつけた農水・経産両省連携プロジェクト推進の拠点、千葉大学大学院で蔬菜(そさい)園芸学を専攻。設立後、水耕栽培装置を全国12か所に導入したほか、南極昭和基地への栽培技術システム提供やモンゴルでの植物工場稼働など、先駆的かつ業界の広告塔的役割を果たしてきた。
同社は14年、経産省補助事業「みやぎ復興パーク」(宮城県多賀城市)に世界最大規模の施設、千葉大学近くにも大型工場を建設した。
しかし、レタスなどの生産が当初の予定通りには安定せず、逆にその設備投資資金などの返済に窮して経営が追い込まれた。本来「起こるはずのない」倒産であり、業界に大きな衝撃を与えた。
赤字が普通
09年、農水・経産両省が巨額の植物工場関連予算(農水省97億円、経産省50億2000万円)を付けたのを機に、企業などの参入が相次ぎ、現在約420社の植物工場が稼働中だ。
日本で植物工場とは、栽培施設内で光や温度などの環境条件を制御し、作物を安定的に生産するシステムを指す。植物工場は、閉鎖された環境で太陽光を一切利用せずに蛍光灯や発光ダイオード(LED)などを使う「人工光型」と、補助的に人工光を使う併用型を含めて基本的に太陽光だけの「太陽光型」の2つのタイプに大別される。
双方とも水耕栽培だが、環境条件をほぼ完全に制御しなくてはならず、難度が高いことから、天候や昼夜に左右される太陽光型ではなく、人工光型が植物工場の主流となっている。
約420社のうち人工光型の約200社について、植物工場研究の第一人者、古在豊樹・千葉大学名誉教授は、「全体のうち15%は黒字だが、単年度では黒字でも工場建設費の減価償却がまだなのは10%。残りの75%は赤字」と指摘した。太陽光型はというと、さまざまな報告で40~50%は赤字と指摘されており、たとえ難度は低くても、環境制御は難しいようだ。
結局、01年に撤退したオムロンに始まり、居酒屋チェーンを運営する親会社を持つエコファーム・マルシェは10年に解散。産業用LED照明のシーシーエスは12年に撤退するなど、撤退・倒産が珍しいものではない。
オランダからどのくらい学べるのか
13~14年、安倍首相や当時の林農相、根本復興相、甘利経済再生相などが続々とオランダの施設園芸(ガラス温室)を視察した。
オランダは九州程度の狭い国土と冷涼な気候で農業不適地だが、それをバネに世界第2位の農産物輸出国になり、強い農業を目指す日本には垂涎(すいぜん)のマトだ。
オランダは広い農地が必要な小麦など穀類を輸入し、独仏などに需要の多い野菜などを輸出する戦略だ。それも選択と集中と称して、施設園芸ではトマトやパプリカなどの少品種に絞り、効率良く生産。80年代に温室内の温湿度、光、炭酸ガスなどの環境制御システムを実用化した。
さらに温室の大型化や環境制御のコンピューター化などを進め、日本施設園芸協会の「次世代施設園芸の全国展開~攻めの農業の旗艦~」(16年6月)によると、トマトの平均収量は10アール当たり50トン以上と日本(同11トン)の4・5倍以上の高い生産性を誇る。
ただ、オランダの栽培施設はグリーンハウス、温室であり、植物工場とは呼ばれない。日本はそれを太陽光型に分類しているが、温湿度や光などを統合的に制御するためのデータ化、精密農業化、さらに作業の自動化や労務管理にIT技術を活用するなど、日本の太陽光型に比べて植物工場に近い。
フェンロー型と呼ばれる温室も、間口(3~4メートル)が狭くて背(5~7メートル)が高い、簡単な構造のユニットをつなぐ多連棟式で、大型化が可能だ。日本に多い大屋根型などに比べて建設コストも安いなど、日本が学べる点も多い。
一方で、例えばトマトでは品種を絞る極端な選択・集中の結果、過剰生産で価格が低迷し、スペインやポーランドなど他の生産国との競争が激化した。このオランダの経験を踏まえて、日本は収量を高め、味や品質などにこだわりつつ品種の多様化を図る道がある。
とは言え、目の前の現実は厳しい。
立ちはだかる高い壁
人工光型は施設が光を通さない断熱材で覆われ、密閉性と断熱性が極めて高い。昼夜と季節の違いをなくし、農業を自然環境の制約条件から解放することによって、工業的に食料資源生産を可能にする。工業的農業のユートピアだが、そこに至る道筋が現状では見えていない。
一番目の問題は、人工光型の栽培法と経営ノウハウが未熟な点だ。作物は生き物で、環境の変化の中で成長する。露地栽培では、農家は自らの技術、勘と経験で柔軟に対応してきた。
ところが、植物工場では環境を完全に制御するとしながら、それに必要なデータ・知見がまだまだ不十分だ。例えばレタスを40日間で栽培するには、最適なLED光度や室内温度、養液濃度(水耕栽培)が、発育段階でそれぞれ微妙に違う。
二番目の問題は、植物工場経営のコストの高さだ。09年4月の農水、経産両省共同の「植物工場ワーキンググループ報告書」によれば、10アール当たりの設置(建設)コストは施設生産(ビニールハウスでのホウレンソウなどの水耕栽培)の1800万円に対し、植物工場が約17倍の3億1000万円。同運営コスト(光熱費)は施設生産の40万円に対し、植物工場が約47倍の1860万円である。
また別の報告書では、人工光型の設置コストは太陽光型の約4倍だが、運営コストは太陽光型の約11倍で、人工光型がエネルギー多消費型の金食い虫であることがわかる。
野菜のマーケティングと販路の拡大が三番目の問題で、特に一般野菜への差別化がポイントだ。ところが、植物工場事業者や小売りなどの調査報告書によると、「味や食感ではまだまだ露地野菜に負ける」「(露地野菜の)あくまでも副次的な野菜」などの評価があり、“植物工場産野菜”の身の置き所のない心細さが伝わってくる。
農商工連携のお膳立て
それでは、農業に無縁な企業が植物工場ビジネスに乗り出すのはなぜか。第3次ブームが始まった「2009年」が、一つの答えだ。09年の農地法改正で、企業も最長50年の農地借用が可能になり、農業参入に弾みがついた。
戦後、農地取得(借用、所有)は耕作農家に限られてきたが、日本がコメなど農産物の大幅な輸入自由化を迫られたガット・ウルグアイラウンド合意(93年)が近づく中で、経済界が農業参入と農地取得を強く要求。その後、段階的に企業の農業参入への道が開かれてきていた。
09年農地法改正の流れの中で、農水・経産(通産)両省が農商工連携のシンボルとして植物工場の普及・拡大に乗り出し、補助金も付けた。それ以降、これまで両省合わせて総額500億円の補助金が投じられた。
ただ近年、農水省は太陽光型、経産省は人工光型へと、それぞれ政策の中心軸を移し、農水省は強い農業作り交付金で、地域エネルギーと先端技術を活用した太陽光型植物工場など次世代型の大規模な高度環境制御型栽培施設の整備を支援中だ。
片や、経産省は植物工場を、LEDやICT(情報通信技術)、各種センサーなどの工業分野の先端的技術を駆使した農産物の「高度生産管理システム」と位置づけ、企業の発展と共に、農業の成長産業化に取り組むという。企業の中には、半導体事業低迷などで遊休化したクリーンルームの転用の例も珍しくない。いずれにせよ、政策的なお膳立てがあればこその企業参入例が多いようだ。
特殊用途に特化すべき
植物工場産野菜が一般の野菜ビジネスに馴染(なじ)みにくいならば、特殊用途に特化すべきだろう。低カリウムレタスが一例で、現在生産・販売共に好調だ。これはカリウムが多い生野菜摂取を制限される透析・腎臓病患者向けのもので、富士通系の会津富士加工がカリウム含有量を5分の1に減らしたレタスの量産化に成功した。
また、甘草(かんぞう)など漢方薬原料の薬用植物なども有望だという。漢方薬の生薬の約7割に用いられる甘草の場合、国内の使用分のほとんどが中国からの輸入だが、栽培されたものではなく野生のものだ。

福島県川内村の植物工場で栽培されるレタス
近年、乱獲から採取・輸出規制が強化された結果、レアアース(希土類)ならぬレアプラント(希少植物)とも呼ばれ、国内での栽培が急務となっていた。こうした中、三菱樹脂は昨年、苗を人工光型植物工場で生産し、その後、露地に植え替える栽培法を開発した。
国内での植物工場の運営がコスト高なので難しいなら、技術そのものの農業不適地への輸出は有望なのかもしれない。砂漠や冷涼地、高地、災害被災地、巡視船など大型船舶、宇宙空間などの農業不適地だ。こういう場所なら、多少のコスト高も許容される可能性がある。
その点で注目されるのが、経産省のグローバル農商工連携推進事業だ。これは海外需要創出に向け、植物工場などの先端的な生産システムを構築し、3年以内に事業化を目指す実証事業を支援するプロジェクトだ。15年度の場合、超省エネLED採用の人工光型植物工場自体のフィンランドへの輸出ビジネスや、植物工場産野菜をシンガポールに、また他の企業のハワイ、グアムなどへ輸出する事業も採択された。
国や自治体の補助金にぶら下がらず、様々なニーズを汲(く)み上げてこそ、日本の植物工場や運営企業はこれからの農業の希望の星となっていくだろう。