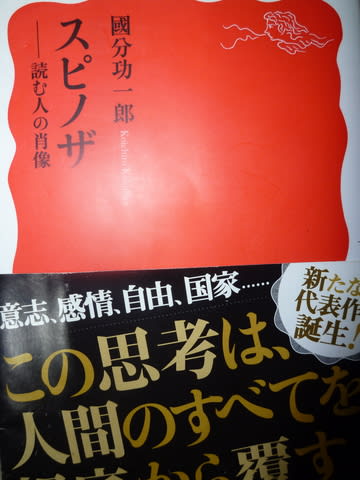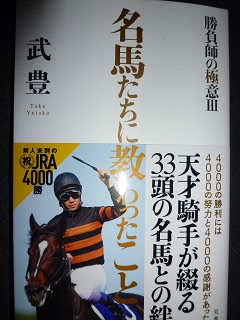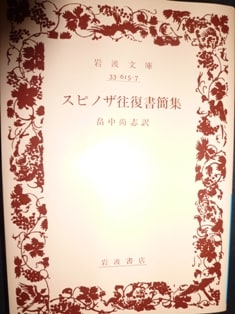スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
メイセイオペラ記念の第28回マーキュリーカップ 。クラウンプライド はコリアカップ 以来の優勝で重賞3勝目。国内の重賞は初制覇となりました。実績と近況を踏まえると負けられないといっていいくらいのメンバー構成。超ハイペースを2番手で追走し,最終コーナーで先頭に立って追い上げを凌いだという内容は強かったですが,2着馬も3着馬も上昇馬だったことを考えると,斤量差があったとはいえあまり着差をつけられなかったことをむしろ不満に感じます。たぶんもう少し短い距離の方が本質的には適しているのだろうとは思うのですが,今日の内容では大レースに手が届くところまでいくのは難しいかもしれないと思わされました。父は2009年のきさらぎ賞と2010年のマイラーズカップを勝ったリーチザクラウン でその父がスペシャルウィーク 。母の父はキングカメハメハ 。祖母の父はアグネスタキオン 。母の3つ上の半姉が2012年にロジータ記念 を勝ったエミーズパラダイス で5つ下の半妹が昨年の福島記念を勝ったホウオウエミーズ 。第三部定理九備考 では,僕たちは善bonumであるがゆえにそのものに衝動appetitusを有するのではなく,あるものに対して衝動を有するがゆえにそのものを善と判断するといわれています。國分は衝動についてはこのことによって理解し,第四部定義七 でいわれているのは,衝動によって善と判断されるものが目的finisとして意識されるということだといっています。僕たちが個々の衝動を感じるのは,何らかの原因causaに依拠するわけですが,それがどのようなものであれ,諸々の原因によって僕たちのうちに何らかの事物を希求する衝動が現れると,そのように希求された事物が自分自身にとって善なる目的として意識されるようになるというのが國分の見解opinioということです。したがって,第四部定義七というのは,衝動についての定義Definitioといわなければならないのですが,國分にとっては衝動の定義というよりは目的の定義なのであって,実際に國分はこの定義のことを,目的の定義であるといっています。書簡九 でいっているところによれば,十分に理解することができればよい定義といわれる意味で,事物のよい定義ということになるでしょう。そしてこの定義で解するといわれているのは衝動なのですから,この定義は衝動の定義というほかないと僕は考えます。知性 intellectusのうちに目的という概念notioがいかにして発生するのかということを意味で目的の定義であるということが,絶対にできないというようには僕は考えません。
昨晩の第14回優駿スプリント 。トーセンヴィオラは町田騎手から藤本騎手に変更。張田昂騎手は手足口病を罹患したためスマイルナウは内田博幸騎手に変更。ティントレット は南関東重賞初制覇。昨年5月に北海道でデビュー。シーズン一杯を北海道で走り,休む間もなく南関東に転入。今春はクラシックを走りました。北海道でのデビューから一貫して1700m以上を走っていた馬で,1200mに対応できるかどうかが心配だったのですが,結果をみるとむしろスプリントの適性が高かったようです。タイムも優秀なので,この距離であれば古馬が相手でもすぐに通用しそうです。父がホッコータルマエ で母の父がゼンノロブロイ 。母は2011年に東京プリンセス賞 を勝ったマニエリスム 。Tintorettoはイタリアの画家。フジノウェーブ記念 以来の南関東重賞39勝目。第6回 以来8年ぶりの優駿スプリント2勝目。管理している大井の荒山勝徳調教師は南関東重賞27勝目。第13回 に続く連覇で優駿スプリント2勝目。第四部定理三七備考一 を,神 Deusを認識するcognoscere限りにおける我々から起こる欲望cupiditasを良心conscientiaに関係させ,その欲望から生じる行動を良心的行動に関係させると訳すのは,ひとつの方法であると僕は思います。少なくともここでいわれている宗教心religioは,僕たちが使用している語でいえば宗教心よりも良心に近いですから,この部分だけでいえば,このように訳すことは適切であると思われるからです。第二部公理三 からして,スピノザは感情 affectusを伴わない観念idea,とりわけ喜びlaetitiaへの方向性も悲しみtristitiaへの方向性も伴わない観念があるということを認めていたと思われるので,それを強く自覚していたかどうかは別として,意識を観念の観念idea ideaeとみる限り,意識は良心よりも広くわたるということには気付いていたと僕は解します。いい換えれば意識という概念notioと良心という概念を分けなければならないということには気付いていたと思います。それでも,良心を意識とは別の思惟の様態cogitandi modi,意識された喜びおよび意識された悲しみと関連付けずに理解していたということはあり得ないと思います。したがって,『エチカ』の中では良心について積極的に言及している部分は存在しませんが,もしも良心という概念を『エチカ』の中に発見しようとするならば,國分もそうしているように第四部定理八 をまずは参照しなければならないと思います。なのでそのような意識化された喜びおよび意識化された悲しみというのを,神を認識する限りにおいて僕たちから生じる欲望と同列に論じることはできません。なので,宗教心と訳されているその語を,良心と意訳することは,たとえその方が僕たちが使用している語のニュアンスには近いのだとしても,不適切であるということになるのです。
ホクトベガメモリアルの昨晩の第28回スパーキングレディーカップ 。アーテルアストレア はクイーン賞 以来の勝利で重賞3勝目。このレースは今年に入って重賞を勝っているアーテルアストレアとライオットガール,この2頭と勝ったり負けたりを繰り消しているキャリックアリードが3強。神奈川記念でキャリックアリードを負かし,今年はまだ1戦のヴィブラフォンが3強に続くという勢力図。スピーディキックも昨年のこのレースで2着になっていて,復調すれば勝負圏内という馬ですから,かなり順当な結果になったといえそうです。アーテルアストレアはこのように後方から差し脚を繰り出す方が持ち味が生き,また距離も1800mより長くなるよりは短くなった方がいいというタイプなのでしょう。上位勢は突き抜けた能力には欠けるもののいずれも安定勢力なので,今後も勝ったり負けたりを繰り返していくことになりそうです。父は2009年のきさらぎ賞と2010年のマイラーズカップを勝ったリーチザクラウン でその父がスペシャルウィーク 。セレタ 系ダイナエイコーン の分枝で母の2つ上の半兄に2018年のマーチステークスを勝ったセンチュリオン 。Aterはラテン語で黒い。Astraeaはギリシア神話の女神。
昨晩の第47回帝王賞 。マースインディは藤田凌騎手から笹川騎手に変更。キングズソード はJBCクラシック 以来の勝利で大レース2勝目。そのときは重賞未勝利での優勝。その後の3戦は5着,5着,4着でしたが,大きく離されていたわけではありませんので,巻き返しは可能と思われました。思いのほかペースが上がらなかったので,先行したこの馬に有利になった面はあったと思います。距離も本来はもっとあってもいいというタイプなのかもしれません。母の父はキングヘイロー 。アストニシメント 系エベレスト の分枝で8つ上の全兄に2017年のプロキオンステークスを勝ったキングズガード 。フェブラリーステークス 以来の大レース5勝目。帝王賞は初勝利。管理している寺島良調教師はJBCクラシック以来の大レース2勝目。書簡五十 でいっていることであり,スピノザはそこで間違ったことを伝えているわけではありません。しかし自然権が放棄できないものであるとすれば,社会というのは.その諸個人の権利をまとめて所持する人びとの集合体を意味し,かつ人びとはその権利の執行を社会に一任することになるのですから,その社会の権力はどのような法lexにも縛られないし,人びとはその権力に従わなければならないということになるでしょう。つまり出現する社会,これは国家Imperiumといってもいいですが,その現実は,ホッブズが示しているものとそう大差はない,もっといえばほぼ同じであることになります。国家論 Tractatus Politicus 』では,社会契約論をまったく使用せずに国家を説明していますが,それは,社会契約論を用いた説明の必然的な帰結を避けるためではなかったかと僕は考えています。
第28回さきたま杯 。レモンポップ はチャンピオンズカップ 以来の勝利で大レース4勝目。メンバーの中では実力最上位。1400mのレースが久々だったことを懸念しましたが,元来はスピードタイプということもあり,2番手につけることが叶いました。その時点でこの馬の優勝は決定づけられたといっていいでしょう。コーナー4回の1400m戦でも快勝できたのは収穫だったと思います。高松宮記念 以来の大レース9勝目。さきたま杯は初勝利。管理している田中博康調教師はチャンピオンズカップ以来の大レース4勝目。さきたま杯は初勝利。Leviathan 』では,法と権利を混同するのが常であるけれど,両者は区別されなければならないと主張されています。
昨晩の第60回関東オークス 。アンデスビエント は重賞初挑戦での優勝。前走の1勝クラスを3馬身半差で快勝していた馬で,例年のこのレースでは優勝候補。ほかにもJRAの2勝馬がいましたが,メイショウヨシノは短距離を使っていて,クリスマスパレードはダートが初めて。イゾラフェリーチェは未勝利はダートで勝ったものの1勝クラスは芝で勝ったということもあり,それぞれ対応できなかったためアンデスビエントの圧勝となりました。現状は逃げるレースがベストですが,タイムは優秀なので,古馬相手でも通用する要素はありそうです。祖母の父はキングカメハメハ 。母は2019年にブリーダーズゴールドカップ とレディスプレリュード ,2020年にエンプレス杯 を勝ったアンデスクイーン で7代母がレディチャッター 。Vientoはスペイン語で風。不安 metusに苛まれるよりは希望spesに胸を膨らませる方がましですから,強い不安に襲われている人には,僕はこの種の助言をします。しかし,それが社会的な意味において,つまり人間が協働して生きていくものであるということまで考慮に入れたときに,よい助言であると一般的にいえるわけではありません。少なくとも僕は,これが一般的に優れたアドバイスであるというように考えているわけではありません。スピノザがどのようにいっているのかを確認します。第四部定理四七 です。ここでは,希望も不安もそれ自体では善bonumではあり得ないといわれています。第四部定理八 により,現実的に存在する各々の人間にとっての善というのは,その人間による自身の意識化された喜び laetitiaにほかならないのですが,第三部諸感情の定義一二 により,希望というのは喜びにほかならないからです。したがって現実的に存在する人間は,自身の希望を意識したならそれを善と認識するcognoscereことになります。これは明らかに第四部定理四七でいわれていることと反することになるでしょう。一方,第三部諸感情の定義一三 により,不安は悲しみtristitiaの一種ですから,現実的に存在する人間は自身の不安を意識するときにはそれを悪malumと認識するでしょう。つまりこちらの方は第四部定理四七でいわれている通りです。第三部諸感情の定義一三説明 にあるように,希望は不安なしにはあり得ないからです。つまり不安は悲しみであり,不安なしにはあり得ない希望は,悲しみなしにはあり得ない感情ということになるから,それ自体では善ではあり得ないとスピノザはいっているのです。これが,第四部定理四七の証明Demonstratioの全体像になります。ただしこれらの感情は,もしも受動的な喜びが過度になるのを抑制し得るのであれば善であるとスピノザはつけ加えています。
習志野きらっとスプリントトライアルの昨晩の第4回川崎スパーキングスプリント 。プライルード は前々走のオープン以来の勝利。南関東重賞は一昨年のアフター5スター賞 以来の3勝目。出走メンバーの中では実績は上位。900mに出走するのが初めてだったのですが,問題とはなりませんでした。現状は1200mよりも1000mの方がよいというタイプになっているのかもしれません。タイムは上々だったと思います。父はラブリーデイ 。母の父はサクラバクシンオー 。ふたつ上の半姉が2019年のローレル賞 を勝ったブロンディーヴァ でひとつ上の半姉が一昨年の福島牝馬ステークスを勝ったアナザーリリック 。Praeludeはプレリュード。東京湾カップ 以来の南関東重賞18勝目。川崎スパーキングスプリントは初勝利。管理している大井の藤田輝信調教師は南関東重賞27勝目。川崎スパーキングスプリントは初勝利。第四部定理五七 で,高慢な人間が寛仁 generositasの人を憎むといわれているのは,ひとつのキーポイントです。第三部定理五九備考 でいわれているように,寛仁というのは感情 affectusのひとつであって,これは人間が理性 ratioに従うときにのみ生じる欲望cupiditasのひとつです。したがって人間は高慢superbiaである限りは理性に従っている人を憎むのです。このことが,高慢は狂気であるとスピノザがいう理由のひとつとなっています。憎しみodiumというのは第四部定理四五 および第四部定理四五系二 から分かるように,スピノザが全面的に否定するnegare感情のひとつです。つまり高慢な人間は単に理性に従うことに反するという点で狂気といわれるわけではなく,理性に従っている人を憎むという点で狂気といわれているのです。第四部定理二五 というのは,自己満足 acquiescentia in se ipsoあるいは自己愛philautiaだけを射程に入れたような定理Propositioではなく,ごく一般的な定理です。ですからこうしたことは自己満足だけに適用されるわけではなくて,受動的な喜びlaetitiaのすべてに妥当するといわれなければなりません。喜びはより小なる完全性perfectioからより大なる完全性への移行transitioであり,悲しみtristitiaはより大なる完全性からより小なる完全性への移行ですから,ある特定の人間だけを抽出すれば,悲しんでいるよりも喜んだ方がよいということになります。しかし人間が共同で生活するという点に着目すると,喜びはかえって迷惑を及ぼすので,悲しみを感じていた方が人びとの和合には有益であるという場合も生じるのです。
昨晩の第70回東京ダービー 。ラムジェット はユニコーンステークスからの重賞連勝で大レース制覇。デビュー戦でまったく走る気を見せず,離された最後尾から直線だけで前をいく馬すべてを差し切った馬で,その時点でスター候補生になりました。2勝目をあげるのに3戦を要しましたが,それ以降は負け知らずでここまで来ました。反応は鈍いけれども脚は長続きするという内容での重賞連勝ですから,もっと強くなる余地があるように思えます。現状は距離が長い方がレースはしやすいのではないでしょうか。母の父はゴールドアリュール 。祖母が2009年に関東オークス とスパーキングレディーカップ ,2010年に名古屋大賞典 とスパーキングレディーカップ ,2011年にTCK女王盃 とエンプレス杯 とスパーキングレディーカップ を勝ったラヴェリータ 。Ramjetはジェットエンジンの一種。JBCスプリント 以来となる大レース3勝目。管理している佐々木晶三調教師は2015年の中山大障害 以来となる大レース制覇。このレースは今年から重賞になりましたので,両者ともに初勝利です。第三部定理五五 を,ひとつのクライマックスといっていました。もっともそれは,具体的な感情論の最後の部分に当たるという意味合いでしかないのですが,だからといって,第三部定理五三 で自己の能力potentiamを観想するといわれるとき,それを第三部定理五五の前振り,つまり能力は観想されるが無能力impotentiaは表象されるということだけの意味として理解するわけにはいかないといっています。人間が自己の能力を観想することは,第四部以降にも重要な場面で『エチカ』の中に登場します。現実的に存在する人間が自己の能力を観想することによって生じる喜びlaetitiaは,第三部諸感情の定義二五 にあるように,自己満足Acquiescentia in se ipsoといわれるのですが,第四部定理五二 は,理性rationeから生じる自己満足は最高の満足であるといっていますし,第五部定理二七 では,第三種の認識 cognitio tertii generisから自己満足が生じ,これが精神mensの最高の満足であるという意味のことがいわれています。ですから,現実的に存在する人間が,自身の能力を観想することが,スピノザの哲学において重要な思惟作用であるということは疑い得ません。
昨晩の第4回若潮スプリント 。沢田騎手が4レースで落馬し,腸骨骨折などの傷を負ったためモノノフブラックは野畑騎手に変更。ギガース はネクストスター東日本 以来の勝利で南関東重賞3勝目。距離が短縮して苦しんだ感はありましたが,速力を生かして軽快に逃げたオーソレリカを,58キロを背負いながら捻じ伏せたのは底力の証明で,この距離でもこのメンバーなら力が抜けていたということでしょう。レースのしやすさという観点からは,もう少し距離があった方がいいのではないでしょうか。母の父はジャングルポケット 。祖母がダイヤモンドビコー で3代母がステラマドリッド 。Gigasはギリシア神話の巨人族のひとつ。複数形はギガンテス。森泰斗騎手 はプラチナカップ 以来の南関東重賞61勝目。若潮スプリントは初勝利。管理している船橋の佐藤裕太調教師は南関東重賞13勝目。若潮スプリントは初勝利。フロム Erich Seligmann Frommが『愛するということ The Art of Loving 』において,スピノザの哲学について指摘していたことです。フロムはそこで,自分の外部にある目標に向かって邁進する人は,活発に活動しているようにみえ,椅子に座って沈思黙考する人は逆に不活発にみえるけれど,スピノザの哲学においては前者が受動passioであり,後者が能動actioであるという意味のことをいっていました。ここでも活発にみえるかそうでないかということは,その人が能動状態にあるか受動状態にあるかということと無関係であるということがいわれているのであり,これは國分がこの部分で指摘していることと同じであるといえるでしょう。第四部定理四系 でいわれているように,現実的に存在する人間は常に何らかの受動に隷属しています。國分が,その力を表示しているといわずに,より多く表示しているといっているのは,このことと関連しています。すなわち,現実的に存在している人間は,自分の力だけを表示するということはありません。ただ,外部の力よりも自分の力をより多く表示するということはあるのであって,その場合はその人間の能動といわれるのです。逆にいえば,たとえねたみや金銭欲によって活発に活動するときも,活発している当人の力がまったく表示されていないというわけではありません。
第7回プラチナカップ 。アマネラクーン は南関東重賞初制覇。浦和の1400mを中心に走ってきた馬で,これまで24戦して16勝。南関東重賞では勝てていなかったのですが,この条件であればいつ勝ってもおかしくないと思っていました。今日は前の2頭の競り合いに乗じたところはありますが,この条件であればこれからも大きく崩れることはないと思います。ただ,年齢的にこれ以上の上積みは難しいでしょう。祖母は2001年にさきたま杯と兵庫ゴールドトロフィーを勝ったゲイリーイグリット 。森泰斗騎手 はクラウンカップ 以来の南関東重賞60勝目。第1回 ,3回 に続いて4年ぶりのプラチナカップ3勝目。管理している浦和の小久保智調教師は南関東重賞66勝目。第2回 以来となる5年ぶりのプラチナカップ2勝目。第三部諸感情の定義一 のように,与えられたその各々の変状affectioによってあることをなすように決定されると考えられる限りにおいて,ということをつけ加えれば,精神mensが自身の欲望cupiditasないしは衝動appetitusを意識し得るということが出てくるのです。第三部定理九備考 でいわれている,意識される限りでの衝動であるという欲望の定義は,発生的定義に対していえば,名目的定義なのです。つまりそれは,欲望という語をこのような意味で用いますという宣言にすぎないのであって,その宣言が,第三部諸感情の定義一において,発生的定義あるいは実在的定義に書き換えられているのです。國分はこの定義は,『エチカ』の中にあるいくつかのターニングポイントのひとつであるといっていたわけですが,これがターニングポイントであると國分がいうことの具体的な意味になります。
昨晩の第69回大井記念 。ナンセイホワイトは腹痛のために出走取消となり9頭。サヨノネイチヤ はここがブリリアントカップ 以来のレース。連勝を7まで伸ばし,南関東重賞3連勝。ここまで勝っていた勝島王冠,ブリリアントカップに比べると大井記念は同じ南関東重賞でも格式が高く,メンバーも強化されていましたし,これまでの2戦より距離も伸びていました。そうした点を突破しての優勝で,それだけの価値があるといえるでしょう。ペースの関係もあり,タイムが平凡なのですぐに重賞で通用というわけにはいかないと思いますが,まだ底を見せていないのも事実で,そういう可能性を秘めた馬なのは間違いないでしょう。父はダノンレジェンド 。母の父はオレハマッテルゼ 。祖母の13歳上の半兄が1991年に小倉記念と京都新聞杯と鳴尾記念,1994年に高松宮杯を勝ったナイスネイチャ 。東京スプリント も勝っています。大井記念は初勝利。管理している大井の坂井英光調教師は南関東重賞5勝目。大井記念は初勝利。したがって衝動とは人間の本質そのもの,ー自己の維持に役立つすべてのことがそれから必然的に出て来て結局人間にそれを行なわせるようにさせる人間の本質そのもの,にほかならない 」。第三部定理六 から帰結していると考えられます。備考では自己の維持に役立つといわれていて,第三部定理六では自己の有に固執するsuo esse perseverareといわれていますが,このふたつは同じことを意味していると考えられるからです。前もっていっておいたように,第三部定理六は現実的に存在するすべての個物 res singularisに妥当する本性ですが,人間もまた現実的に存在する個物なのですから,それが人間にも適用されるのです。ただ備考の冒頭でいわれているように,衝動は精神 mensと身体corpusの両方に関係するといわれていて,これは当然ながら人間の身体humanum corpus,ほかの個物とは異なった人間の身体と,同じようにほかのものの精神とは異なった人間の精神mens humanaを意味しますから,それを踏まえて人間の本性といわれているのです。第三部諸感情の定義一 でいわれていることと内容が一致するといえます。備考ではそれを人間に行うようにさせるといわれていて,第三部諸感情の定義一ではあることをなすように決定されるといわれていますが,これらは両方とも現実的に存在する人間が働きを受けるpatiことを示しているといえるからです。要するにこれらは両方とも人間の受動passioについての言及なのです。いい換えれば備考でいわれている衝動および諸感情の定義でいわれている欲望cupiditasは,受動状態における人間の本性を示しているといえると僕は考えます。よって,第三部定理九備考でスピノザが主眼としていることは,人間を突き動かすような力potentiaのことであるよりは,人間が働きを受けることについてであると僕は解します。この備考が付せられている第三部定理九 は,人間は混乱した観念idea inadaequataを有する限りにおいても自己の有に固執し,それを意識するといわれているのです。
キヨフジ記念の昨晩の第70回エンプレス杯 。オーサムリザルト は重賞初挑戦での制覇。ここはすでに重賞で実績をあげている馬たちと,ここまで5連勝中のオーサムリザルトという構図。オーサムリザルトは前走で牡馬相手のオープンを勝っているので,能力が通用するのは疑い得ませんでした。途中からの逃げでついてきた馬たちを突き離し,好位からの差しを凌いでの優勝なので,着差は少なくても内容は充実していたと思います。まだ遊びながら走っているようなところが見受けられるので,そのあたりは改善の余地があるでしょう。牝馬重賞ではまだ勝っていけるでしょうし,牡馬相手の重賞でも通用するのではないかと思います。Awesome Resultは素晴らしい結果。武豊騎手 は第50回,56回 ,57回 ,62回 に続き8年ぶりのエンプレス杯5勝目。管理している池江泰寿調教師はエンプレス杯初勝利。デカルト René DescartesやホッブズThomas Hobbesを理解する際にも必要とされる注意です。僕はこのような理由もあって,スピノザの哲学における意識とは何かということを日本語で考えるときには,意識というのを良心とは異なった独立したものとして把握するために,それを無意識との対比で解するという立場を採用します。スピノザは無意識という概念notioをおそらくは有していなかったのですから,スピノザ自身がこのように意識を理解していたということはあり得ません。その意味でいえば,僕のような解釈は,スピノザの思想の理解のためには正当性を欠くといわれても仕方がないと思います。ただ現代の日本人である僕が,日本語でスピノザの思想を現代的に理解しようとするなら,僕のような方法を採用する方がよいのではないかと思います。
昨日の第24回名古屋グランプリ 。ノットゥルノ は佐賀記念 以来の勝利で重賞3勝目。このレースはノットゥルノとディクテオンの力量が他より上で,優勝争いとみていました。ところがノットゥルノが速力で圧倒し,ディクテオンは道中で差を詰めていくことさえできませんでした。僕の見立てが大きく誤っていて,このメンバーではノットゥルノの力量が断然であったということでしょう。佐賀記念の回顧でもいったように,大井で特異に力を発揮していた馬ですが,佐賀に続いて名古屋でも結果を出したことで,その評価は覆したといっていいでしょう。左回りにはまだ課題が残っていますが,この勝ち方なら,トップクラスに追いついてきているとみていいのではないかと思います。父はハーツクライ 。Notturnoはイタリア語で夜想曲。武豊騎手 は第2回以来22年ぶりの名古屋グランプリ2勝目。管理している音無秀孝調教師は名古屋グランプリ初勝利。第二部自然学②要請三 から理解できるように,人間の身体は多種の外部の物体から多様な仕方で刺激されるので,逐一その状態を意識していたら,ほかのことに対する意識が希薄になってしまうでしょう。それはもしそのようなことがあれば人間は現実的に生き続けていくことができないという意味です。他面からいえば,人間の身体は多種の物体から多様な仕方で刺激されるがゆえに,意識化されない無意識が存在する余地もそれだけ大きくなっているといえるのです。僕は,僕たちの意識というのは僕たちの無意識のごく一部であって,僕たちの無意識というのはほとんどが意識されずに僕たちの精神のうちで観念を形成しているのだと考えます。概念 notioがなかったのであって,だからスピノザも意識とは何か,そして無意識とは何かということは少しも考えていなかったであろうと思います。しかしそれでも,確かにスピノザの哲学は無意識の理論を含んでいます。このことは,自然科学として無意識という概念を確立し,その理論を構成したフロイトSigmund Freudが,スピノザの哲学の影響を受けているということを明言していることから明白だといえるでしょう。そして僕はこの観点から,観念の観念が意識であるとすれば,観念とは無意識であるというように解するのです。つまりこれは自然科学的な見解opinioです。
第38回東京湾カップ 。マコトロクサノホコ は南関東重賞初挑戦での制覇。北海道デビュー馬で昨年は8戦して1勝。今年から南関東で走り始めると4戦して2勝,2着2回と堅実に走っていました。このレースはクラウンカップの上位馬がそのまま好走するという傾向があり,今年もクラウンカップを勝ったシシュフォスが2着。ペースに恵まれた面はあったと思いますが,差をつけて勝ちましたので,少なくともクラウンカップ組と同等の力量はあったとみてよいでしょう。レースぶりからはもっと距離が延びた方がよいように思えます。父は2014年の弥生賞を勝ったトゥザワールド でその父がキングカメハメハ で母がトゥザヴィクトリー 。母の父はフジキセキ 。母の8つ下の半妹に2016年の福島牝馬ステークスとクイーンステークスを勝ったマコトブリジャール 。六叉の鉾は鉄剣の名称。ユングフラウ賞 以来の南関東重賞17勝目。東京湾カップは初勝利。管理している船橋の川島正一調教師は南関東重賞34勝目。東京湾カップは初勝利。チルンハウス Ehrenfried Walther von Tschirnhausがカトリックあるいはキリスト教にとって好ましくないものを所持しているからステノ Nicola Stenoはそれを入手しようと試みたという説は,可能性という面からいえば,そうでなかった場合と比較したときに,より高いものとなるように僕には思えます。
昨晩の第36回かしわ記念 。シャマル は黒船賞 から連勝。重賞6勝目で大レースは初制覇。これまでの重賞5勝は1200mと1400mのもの。ここは速力が生きる馬場になったので,短い距離で結果を出していたこの馬に向いたということでしょう。そういう馬場になればこの距離でこの相手でも速力で圧倒することができるということが分かったのは大きな収穫でしょう。ただこの馬はこのレースも含めて重賞6勝がすべて重馬場か不良馬場でのものとなっていますので,良馬場であったらこのレースの結果も違ったものになっていたのではないでしょうか。馬場が悪くなった場合には相手が強くても対抗できるという馬なのだと思います。父はスマートファルコン 。母の父はアグネスデジタル 。祖母の父はダンスインザダーク 。母の従妹に2022年のローズステークスと2023年の愛知杯を勝ったアートハウス 。Shamalはペルシャ湾岸に吹く風。阪神ジュベナイルフィリーズ 以来の大レース2勝目。チルンハウス Ehrenfried Walther von Tschirnhausが『エチカ』の手稿を所持しているということをホイヘンス Christiaan Huygensに教えなかったということは,書簡七十 から確定できます。ナドラーSteven Nadlerはチルンハウスはライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibnizにはそのことを伝え,単に伝えただけではなくそれを読ませたとみていますが,それと同時にそうしたことはなかったとするフリードマンGeorges Friedmannの見解opinioにも触れていて,僕はフリードマンの見解の方に同意します。ただしこのことは史実として確定できる要素を有しているわけではないので,少なくともホイヘンスには教えなかったという点をここでは強調します。神学・政治論 Tractatus Theologico-Politicus 』を読んでいたこと,そしておそらくそれを所有していたであろうことは書簡六十七の二 の冒頭部分から確定できます。しかしそのことは,だからステノは信頼するに値する人物であって,自身が『エチカ』の草稿を所有していることを教えてもよいとチルンハウスに思わせる事象にはなり得ません。ホイヘンスもまたおそらく『神学・政治論』を所有しまた読んでいたであろうことは書簡七十からはっきりしていますから,この条件はホイヘンスにあってもステノにあっても同一だからです。してみれば,ホイヘンスには教えなかったようなことを,ステノにチルンハウスが伝えるとは考えにくいといわなければなりません。ホイヘンスは学者であるのに対し,ステノは司祭になるような,あるいはすでに司祭になっていたかもしれないカトリックの布教者なのであって,自身が『エチカ』の草稿を所持していることを伝えることの危険性は,ホイヘンスに伝えるよりもステノに伝える方がずっと高いということくらいはチルンハウスにも理解できると思われるからです。