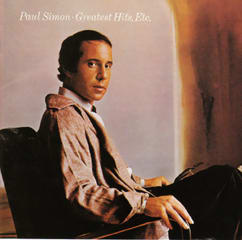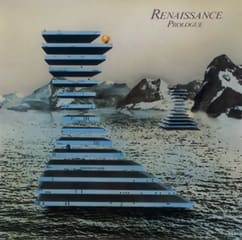私がこの4月に転勤して新しい職場で働き始めてもう半年以上が経った。私は音楽の話が出来る人としか友達にならないので職場環境が変わるといつも虎視眈々とロック/ポップス・ファンを探すのだが、ロックンロール偏重主義の自分とテイストが似通った人に出会える確率は極端に低い。少なくとも今の職場にそういう人はいないように思えたし、無理して音楽以外の話題に付き合いぐらいなら独りでいる方がマシ、とばかりに “男は黙ってサッポロビール” (←懐かしい!)を決め込んでいた。
しかし世の中どこに縁が転がっているかわからない。私は週一でウチへ派遣されてくるサマンサというオーストラリア人女性とペアで仕事をすることになったのだ。 “英語なんか喋れるかよ...” と不安に思いながら彼女に会ってみると実に気さくで楽しそうな感じの人だ。そこで “オーストラリア” を突破口にしたれと一計を案じた私は、“I love AC/DC. Do you like them?” と訊いてみた。初対面でいきなり “AC/DC 好きか?” と訊いてくる日本人なんて私ぐらいのモンだろうが、敵もさるものひっかくもの。何とこの3月のAC/DC 京セラドーム大阪公演に行ってきたというからオドロキだ(゜o゜)
“おぉ、こいつ、バリバリのロック・ファンやんけ!” とすっかり嬉しくなった私は仕事そっちのけで音楽談義に突入!もちろんルー大柴みたいに英語と日本語のチャンポンだが...(笑) 彼女は外国人とは思えないぐらいに関西人のノリでツッコミを入れてくるのでめちゃくちゃ面白い。もうコテコテである。それから半年、今では何でも話せる無二の親友... ケンシロウ流に言えば我が朋友だ。
先週の火曜日のこと、いつものように仕事の打ち合わせのふりをしながらロックの話をしていて話題がイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」になった時、彼女が “例のイントロに入る前にスパニッシュ・ギターっぽいソロがあるライヴ・ヴァージョンが最高!” と言った。私の知っている「ホテル・カリフォルニア」のライヴは確か「ロング・ラン」の後に出た例の2枚組ライヴ「イーグルス・ライヴ」だけだが、 “スパニッシュ・ギターっぽいソロ” なんてあったっけ???
私がそんなん知らんでぇ~と言うと、彼女は今週、そのテイクの入った CD-R を持ってきた。友人が焼いてくれたというコンピ CD-R だ。早速聴いてみると初めて耳にするアコースティック・アレンジ・ヴァージョンだ。しかもそれが又めちゃくちゃ心に響いてくるのである。コレは何としても出自を突き止めなければならない!こういう時は Amazon と YouTube で検索するに限るが、私はものの5分と経たないうちに同じヴァージョンを見つけ出した。それがこの「ヘル・フリージズ・オーヴァー」収録のニュー・アコースティック・アレンジ・ヴァージョンというわけ。この「ホテ・カリ」1曲だけでも十分価値があると思った私はその日のうちにアマゾンでこの盤を注文した。ということで、今日は “ラモーンズ祭り” (←まだまだ続くよ...たぶん)をお休みして “朋友に捧げる緊急特別企画(?)” のイーグルス、届いたばかりのホヤホヤ盤だ。
このアルバムは1994年にリリースされたもので、彼らにとっては14年ぶりの再結成ということになる。94年と言えば私はグランジ、オルタナ、ラップまみれの洋楽シーンとは絶縁していたのでこの盤の存在を知らなかったのも無理はない。以前取り上げたフリートウッド・マックといい、このイーグルスといい、70年代に一世を風靡した大物が揃って90年代に再結成して素晴らしいライヴ盤を残しているというのも面白い偶然だ。
「ヘル・フリージズ・オーヴァー」というのは、80年代初めにバンドが崩壊した時に再結成の可能性について訊かれたドン・ヘンリーが答えた言葉 “When Hell freezes over” (←“地獄が凍てついたらね”... 地獄の炎は永遠に燃え続けるとされるから、要するに“再結成なんて絶対にありえないよ!” という意味)で、それをこの再結成アルバムのタイトルに使うとは中々洒落たことをしてくれる。こういうユーモアのセンス、好っきゃわぁ...(^_^)
アルバムの構成は前半4曲が新曲で、残りの11曲は「MTV アンプラグド」の模様を収録。私としてはソロ作品とあまり変わり映えのしない新曲群よりも中盤以降の “アンプラグド・ライヴ” 音源に魅かれてしまう。①②③④と聴いてきてライヴの1曲目⑤「テキーラ・サンライズ」が始まると、何か目の前がパァ~っと開けたような感じがするのは私だけだろうか?
この盤を知るきっかけとなった⑥「ホテル・カリフォルニア」は “オレ達は解散したんじゃなくて、14年間のヴァケーションを取ってただけさ...” というグレン・フライの前ふりに続いてラテンっぽいアレンジの物憂げなガット・ギター・ソロで始まり、やがてそこにパーカッションが合流、一瞬 “何の曲やろ?” と思わせておいて絶妙のタイミングであの必殺のイントロが現れる瞬間が鳥肌モノだ。あの屈指の名曲が20年近い時を経て熟成され、実に渋くてカッコ良いヴァージョンに仕上がっている。この1曲だけでも “買って良かった!” と思えるキラー・チューンだ。
ドン・ヘンリーのやるせないヴォーカルがクセになる⑦「ウエステッド・タイム」、昔と全然変わらないティモシー・シュミットのハイトーン・ヴォイスとそれに絡む美しいコーラス・ハーモニーに涙ちょちょぎれる⑨「アイ・キャント・テル・ユー・ホワイ」、ドン・ヘンリーの “声” が持つ吸引力の凄さに平伏してしまう⑪「ラスト・リゾート」と、心が洗われるようなバラッドの名演が続く。イーグルスって高い演奏後術もさることながら、やはりヴォーカル/コーラスが最大の武器なんだと再認識させられた。そんな彼らの魅力ここに極まれりと言える⑫「テイク・イット・イージー」は数あるイーグルス曲の中で理屈抜きに一番好きなナンバーだ。
ラストの⑮「デスペラード」のオーケストラ・アレンジも曲の魅力を引き出す見事なもので、ドン・ヘンリーの艶のあるヴォーカルを更に際立たせている。誰にも真似のできない彼の歌声はまさに人間国宝級で、聴く者の心に沁みわたる。私の知る限りでは、この曲のベスト・ヴァージョンと言っていいだろう。やっぱりイーグルスはエエなぁ...(≧▽≦)
この素晴らしい盤との出会いのきっかけを作ってくれて私の音楽遍歴のミッシング・リンクを埋めてくれたサムに大感謝、やはり持つべきものは音楽の話ができる朋友だ。Thank you, Sam!!!
EAGLES hell freezes over
Eagles -Hell Freezes Over- Tequila sunrise (live)
Milenium en Concierto - Eagles - I can´t tell you why
しかし世の中どこに縁が転がっているかわからない。私は週一でウチへ派遣されてくるサマンサというオーストラリア人女性とペアで仕事をすることになったのだ。 “英語なんか喋れるかよ...” と不安に思いながら彼女に会ってみると実に気さくで楽しそうな感じの人だ。そこで “オーストラリア” を突破口にしたれと一計を案じた私は、“I love AC/DC. Do you like them?” と訊いてみた。初対面でいきなり “AC/DC 好きか?” と訊いてくる日本人なんて私ぐらいのモンだろうが、敵もさるものひっかくもの。何とこの3月のAC/DC 京セラドーム大阪公演に行ってきたというからオドロキだ(゜o゜)
“おぉ、こいつ、バリバリのロック・ファンやんけ!” とすっかり嬉しくなった私は仕事そっちのけで音楽談義に突入!もちろんルー大柴みたいに英語と日本語のチャンポンだが...(笑) 彼女は外国人とは思えないぐらいに関西人のノリでツッコミを入れてくるのでめちゃくちゃ面白い。もうコテコテである。それから半年、今では何でも話せる無二の親友... ケンシロウ流に言えば我が朋友だ。
先週の火曜日のこと、いつものように仕事の打ち合わせのふりをしながらロックの話をしていて話題がイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」になった時、彼女が “例のイントロに入る前にスパニッシュ・ギターっぽいソロがあるライヴ・ヴァージョンが最高!” と言った。私の知っている「ホテル・カリフォルニア」のライヴは確か「ロング・ラン」の後に出た例の2枚組ライヴ「イーグルス・ライヴ」だけだが、 “スパニッシュ・ギターっぽいソロ” なんてあったっけ???
私がそんなん知らんでぇ~と言うと、彼女は今週、そのテイクの入った CD-R を持ってきた。友人が焼いてくれたというコンピ CD-R だ。早速聴いてみると初めて耳にするアコースティック・アレンジ・ヴァージョンだ。しかもそれが又めちゃくちゃ心に響いてくるのである。コレは何としても出自を突き止めなければならない!こういう時は Amazon と YouTube で検索するに限るが、私はものの5分と経たないうちに同じヴァージョンを見つけ出した。それがこの「ヘル・フリージズ・オーヴァー」収録のニュー・アコースティック・アレンジ・ヴァージョンというわけ。この「ホテ・カリ」1曲だけでも十分価値があると思った私はその日のうちにアマゾンでこの盤を注文した。ということで、今日は “ラモーンズ祭り” (←まだまだ続くよ...たぶん)をお休みして “朋友に捧げる緊急特別企画(?)” のイーグルス、届いたばかりのホヤホヤ盤だ。
このアルバムは1994年にリリースされたもので、彼らにとっては14年ぶりの再結成ということになる。94年と言えば私はグランジ、オルタナ、ラップまみれの洋楽シーンとは絶縁していたのでこの盤の存在を知らなかったのも無理はない。以前取り上げたフリートウッド・マックといい、このイーグルスといい、70年代に一世を風靡した大物が揃って90年代に再結成して素晴らしいライヴ盤を残しているというのも面白い偶然だ。
「ヘル・フリージズ・オーヴァー」というのは、80年代初めにバンドが崩壊した時に再結成の可能性について訊かれたドン・ヘンリーが答えた言葉 “When Hell freezes over” (←“地獄が凍てついたらね”... 地獄の炎は永遠に燃え続けるとされるから、要するに“再結成なんて絶対にありえないよ!” という意味)で、それをこの再結成アルバムのタイトルに使うとは中々洒落たことをしてくれる。こういうユーモアのセンス、好っきゃわぁ...(^_^)
アルバムの構成は前半4曲が新曲で、残りの11曲は「MTV アンプラグド」の模様を収録。私としてはソロ作品とあまり変わり映えのしない新曲群よりも中盤以降の “アンプラグド・ライヴ” 音源に魅かれてしまう。①②③④と聴いてきてライヴの1曲目⑤「テキーラ・サンライズ」が始まると、何か目の前がパァ~っと開けたような感じがするのは私だけだろうか?
この盤を知るきっかけとなった⑥「ホテル・カリフォルニア」は “オレ達は解散したんじゃなくて、14年間のヴァケーションを取ってただけさ...” というグレン・フライの前ふりに続いてラテンっぽいアレンジの物憂げなガット・ギター・ソロで始まり、やがてそこにパーカッションが合流、一瞬 “何の曲やろ?” と思わせておいて絶妙のタイミングであの必殺のイントロが現れる瞬間が鳥肌モノだ。あの屈指の名曲が20年近い時を経て熟成され、実に渋くてカッコ良いヴァージョンに仕上がっている。この1曲だけでも “買って良かった!” と思えるキラー・チューンだ。
ドン・ヘンリーのやるせないヴォーカルがクセになる⑦「ウエステッド・タイム」、昔と全然変わらないティモシー・シュミットのハイトーン・ヴォイスとそれに絡む美しいコーラス・ハーモニーに涙ちょちょぎれる⑨「アイ・キャント・テル・ユー・ホワイ」、ドン・ヘンリーの “声” が持つ吸引力の凄さに平伏してしまう⑪「ラスト・リゾート」と、心が洗われるようなバラッドの名演が続く。イーグルスって高い演奏後術もさることながら、やはりヴォーカル/コーラスが最大の武器なんだと再認識させられた。そんな彼らの魅力ここに極まれりと言える⑫「テイク・イット・イージー」は数あるイーグルス曲の中で理屈抜きに一番好きなナンバーだ。
ラストの⑮「デスペラード」のオーケストラ・アレンジも曲の魅力を引き出す見事なもので、ドン・ヘンリーの艶のあるヴォーカルを更に際立たせている。誰にも真似のできない彼の歌声はまさに人間国宝級で、聴く者の心に沁みわたる。私の知る限りでは、この曲のベスト・ヴァージョンと言っていいだろう。やっぱりイーグルスはエエなぁ...(≧▽≦)
この素晴らしい盤との出会いのきっかけを作ってくれて私の音楽遍歴のミッシング・リンクを埋めてくれたサムに大感謝、やはり持つべきものは音楽の話ができる朋友だ。Thank you, Sam!!!
EAGLES hell freezes over
Eagles -Hell Freezes Over- Tequila sunrise (live)
Milenium en Concierto - Eagles - I can´t tell you why