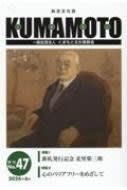熊本史談会の先輩・福田晴男氏の「くまもとお大師廻り」(自家版・73頁)御労作だが、久しぶりに取り出して読んでみた。
慶八成る人物が熊本城下のお寺その他88ヶ所を巡る話を51話に纏められている。その27話に次のようにあった。
「蓙打町の法雲院 かつてとまハれハ大師堂 布屋の裏の東岸寺 堀の外端廻れども 尋ねて聞けば内坪井・・・」
ここに東岸寺というお寺の名前が出てきたが、このお寺は明治28年、天草の御所浦島に御寺がないという事で、島の有志によって移転している。
この無くなったお寺の目の前にラフカディオ・ハーンが熊本での二軒目の住まいがあった。
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と節子夫人が、熊本大学の前身である第五高等中学校(のちの第五高等学校)の英語教師として島根の松江中学校から赴任したのは明治24年(1891)11月であり、明治27年10月までの3年間を熊本で暮らした。
最初に住んだ家が当時手取本町34番地にあったが、現在は鶴屋百貨店裏の蓮政寺公園の中に移転されている。
その後熊本市坪井西堀端町(現・坪井1丁目九)の東岸寺前の住まいに移転しているが、「八雲通り」の名前と、その跡地(A生命社宅用地)にその旨が立派な石碑として建てられておりその痕跡を残すのみである。
明治26年(1893)11月17日、この屋敷でのことである。ハーンと夫人節子の間に長男・一雄が生まれたとき、節子の祖父の稲垣万右衛門が喜びの声を上げ「フェロン公!天晴だ!生まれますたで(ママ)/\」(井上智重著・漱石とハーンが愛した熊本)とその出生を知らせたという。
節子は稲垣家から小泉家の養女となっていて、小泉の両親、稲垣の両親と祖父・万右衛門たちを帯同して熊本に入っている。
この東岸寺、井上智重氏は「廃寺の跡だった。そこには小さなお堂だけが残り、お地蔵さまが祀られていた。」と記しているが、28年御所浦に移転したというお寺の沿革からすると、一雄が生まれたころのこのお寺の状況はすでに解体されて材木などは運び去られていたという事だろうか?
そしてハーンゆかりの「東岸寺跡のお地蔵さん」のお堂は、近年その誼をもって、御所浦東岸寺に移されたとは福田氏のお話である。