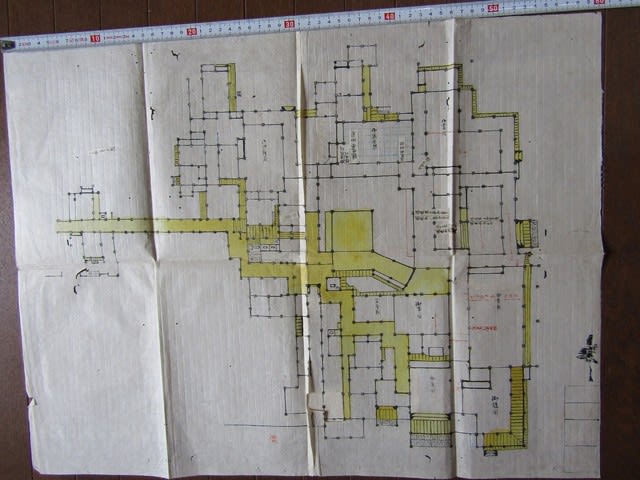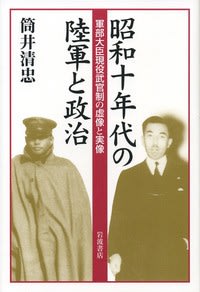一連の京都シリーズ「京都ぎらい・京都ぎらい官能編etc」の著者で私が敬愛する井上章一先生は、国際日本文化研究センター(日文研)の所長であられる。
この日文研には、年に2回発行される学術雑誌「日本研究」がある。現在69号が既刊となっているが、私は時折その内容をチェックしている。
そんな中に、2021年には日文研の教授となられた歴史家・磯田道史氏の論考「藩政改革の伝搬-熊本藩宝暦改革と水戸藩寛政改革」が、2009年(当時は客員准教授)の『日本研究』40号に掲載されているのを発見した。
検索してみるとこの論考はWEBで公開されている。 nk40001.pdf (896.3 kB)
40ページに及ぶものだが、プリントアウトして精読している。熊本藩の宝暦の改革がこのように評価されることは誇らしいことである。
藩主細川重賢を大奉行・堀平太左衛門が補佐して実行された熊本藩における宝暦の改革とは、次の如くである。
1、行政改革 大奉行・堀平太左衛門の任用、六奉行・十二分職とする機構改革、(2~5の改革の下準備)
人材登用のための「足し高制」の採り入れ
2、法制改革 刑法改革-懲役刑の採り入れ、「御刑法草書」の編纂、穿鑿役を設け行政と司法を分離、
衣服令の施行(封建的身分制の強化につながった)
3、文教政策 藩校・時習館の設立と朱子学による教育、再春館(医学)、蕃滋園(薬園)の設立
4、財政改革 世減の規矩(新知知行者の減知)ーーーーーーーーーーーーーーーーーー(旧知知行者の保護)
5、農業改革 地引合せ(いわゆる検地による隠田畑700町歩の摘発)
私は「財政改革」についてはいささかの異論がある。
いわゆる「世減の規矩(新知知行の減知)」と呼ばれるものは、「新知」の者だけに限定されたことである。(約17万石)
「旧知」の者は既得権益が残されて、まったく痛みを感ずることなく明治に至っている。保守温存政策ともいえる。
「新知」同様とはいかないまでも、例えば5%ほどでも減知を行い、痛みを共有すべきではなかったのか。
先に■宝暦の改革の限界を書いたが、旧知のお宅の知行の合計は432千石程になる。5%減ずれば2万石ほど削減できたはずだ。
藩主・重賢と大奉行・堀平太左衛門の願いは、100%完成には至らず、二人の存命の内にまた財政は悪化の途をたどり始める。
つまるところ、開明的な藩主重賢や堀の死去後、執政の権力は家老の元へ帰し、誠に保守的な路線へと逆行を始めたというべきであろう。