●ヨーロッパ諸国のインド進出
15世紀末から、ヨーロッパ諸国のインド亜大陸への進出が始まった。
最初は、ポルトガルである。ヴァスコ・ダ・ガマがアフリカ南端の喜望峰を回って、1498年にインド西岸のカリカットに到達し、インド航路の開拓に成功した。次に、カブラルがブラジル領有のきっかけを作った後にインドに向かい、武力でゴアに貿易拠点を築いて利益を独占した。ポルトガル人は、インドのヴァルナとジャーティによる社会制度を「カスター(血統・家柄)」と呼んだ。それがカースト制という名称の由来となった。
ムガル帝国の時代に、ポルトガルに続いて、オランダがインドに進出した。17世紀はじめ、オランダとイギリスの東インド会社は、インドネシアの香料貿易の主導権を得ようと争った。1623年のアンボイナ事件で勝ったオランダがモルッカ諸島における優位を確立した。敗れたイギリスは東南アジアから撤退し、インドに活動の場を求めた。フランスも負けじとインドに進出した。
イギリスとフランスは、アウラングゼーブ帝の時代に、交易の利権を拡大し、利益の独占を追及した。17世紀後半から海外植民地の支配権をめぐって各地で戦争を繰り返した両国は、インドでも激突した。1757年のプラッシーの戦いでイギリスが勝利し、フランス勢力を駆逐した。以後、イギリスはインドの諸国を次々に征服した。1840年代後半にはスィク戦争に勝って、パンジャーブ地方を併合し、インド征服をほぼ完成した。イギリスは、東インド会社をインド植民地の統治機関とし、これを通じて植民地支配を進めた。
イギリスによるインドの植民地化は、インド文明の西洋文明への従属であり、宗教的にはキリスト教徒によるヒンドゥー教徒・イスラーム教徒らへの支配だった。また、これは白人種による有色人種の搾取でもあった。
●イギリスのインド植民地支配
イギリスによるインドの植民地化の過程は、産業の発展と結びついたものだった。イギリスがインドで交易の利権を拡大していた17世紀半ば、イギリスで薄地で軽やかな織物を着る流行が始まった。そうしたところに、1660年頃からインド木綿が流れ込んできた。インド木綿は、流行に乗って急速に普及した。同世紀末までにインド木綿は、他の衣料と比べ物にならない人気を獲得した。着心地よく、美しく、しかも安かった。当時ムガル帝国は、この製品によって、圧倒的な輸出力を誇っていた。
イギリスでは、毛織物工業でマニュファクチュアが発達し、技術的分業が進んでいた。分業化された生産は、工程の一部を機械に置き換えることができる。機械化は1760年代に、まず毛織物工業で始まった。機械化はまもなく、新興の綿工業で急速に進んだ。まさに革命的な変化だった。この機械化の過程が、イギリス産業革命にほかならない。
イギリス綿工業は、ほぼ1世紀の年月をかけてインド木綿の模倣に成功した。輸入代替化に成功したイギリスは、今度はもとの供給国インドに輸出し始めた。イギリス木綿は、1820年代前後から、怒涛のごとくインドに流入した。それまでヨーロッパへの輸出に依存していたインド綿業は壊滅的な打撃を受けた。これがムガル帝国の経済的基盤を掘り崩した。イギリスから機械生産による綿布がインドに大量に流入すると、インドの手工業者は圧迫され、インド経済は打撃を受けた。インド人の不満は高まり、1857年セポイの反乱(インド大反乱)が勃発した。セポイとは、東インド会社が雇ってインド征服の手足としていた傭兵である。
直接的な原因は、当時の新式銃に装填する弾丸の薬莢の端に牛と豚の脂を混ぜたものが使われていることに、ヒンドゥー教徒またはイスラーム教徒であるセポイたちが激怒したためである。それゆえ、この反乱は、民族間闘争であるとともに、宗教間闘争でもあった。
反乱は大規模化したが、1859年イギリス軍はこれを鎮圧した。この間、イギリス政府は、1858年にインド統治改善法を制定し、東インド会社の機能を停止して、直接統治に切り替えた。内閣に新設されたインド担当国務大臣が、現地のインド総督を指揮した。イギリス人インド総督は、インド帝国における国王の代理として副王の称号を与えられた。
イギリスは、カースト制度における身分・職業等による諸集団の対立や、ヒンドゥー教とイスラーム教の対立を分割統治に利用した。ヒンドゥー教に対しては、その信仰に基づく嬰児殺し、幼児婚、寡婦の殉死等を禁止した。これらの禁止はキリスト教の布教を目的とするものだったが、インドの民衆は容易に従わなかった。
イギリスは、インドで徴税や行政、治安維持等を行なうため、インド人を官吏や軍人に採用することにし、1835年より、教育をすべて英語で行うことにした。また、公文書は英語で作成することを命じた。これによって、英語が急速に普及した。インドは多言語社会であり、共通言語が発達していなかったことも英語普及の要因である。やがて英語教育を受けた若い世代の中から、西洋の政治思想を学んで、民族意識を持ち、インド社会の変革を志す者や、ヒンドゥー教の改革に取り組む者が現れるようになる。
インドの直接統治体制を確立したイギリスは、ムガル皇帝を廃して帝国を滅亡させ、1877年にヴィクトリア女王が皇帝を兼ねるインド帝国を創建した。こうしてインドは、完全に植民地にされた。
イギリスは、19世紀末から帝国主義政策を進め、植民地支配をさらに強化した。反発するインド民衆を弾圧するため、インド人の出版・言論を制限する法律やインド人の武器所持を禁じる法律等を制定した。こうした差別的な統治法に対して、インド人から激しい反対の声が上がった。それが、インドの反英闘争の始まりとなった。
次回に続く。
************* 著書のご案内 ****************
『人類を導く日本精神~新しい文明への飛躍』(星雲社)
https://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/cc682724c63c58d608c99ea4ddca44e0
『超宗教の時代の宗教概論』(星雲社)
https://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/d4dac1aadbac9b22a290a449a4adb3a1
************************************
15世紀末から、ヨーロッパ諸国のインド亜大陸への進出が始まった。
最初は、ポルトガルである。ヴァスコ・ダ・ガマがアフリカ南端の喜望峰を回って、1498年にインド西岸のカリカットに到達し、インド航路の開拓に成功した。次に、カブラルがブラジル領有のきっかけを作った後にインドに向かい、武力でゴアに貿易拠点を築いて利益を独占した。ポルトガル人は、インドのヴァルナとジャーティによる社会制度を「カスター(血統・家柄)」と呼んだ。それがカースト制という名称の由来となった。
ムガル帝国の時代に、ポルトガルに続いて、オランダがインドに進出した。17世紀はじめ、オランダとイギリスの東インド会社は、インドネシアの香料貿易の主導権を得ようと争った。1623年のアンボイナ事件で勝ったオランダがモルッカ諸島における優位を確立した。敗れたイギリスは東南アジアから撤退し、インドに活動の場を求めた。フランスも負けじとインドに進出した。
イギリスとフランスは、アウラングゼーブ帝の時代に、交易の利権を拡大し、利益の独占を追及した。17世紀後半から海外植民地の支配権をめぐって各地で戦争を繰り返した両国は、インドでも激突した。1757年のプラッシーの戦いでイギリスが勝利し、フランス勢力を駆逐した。以後、イギリスはインドの諸国を次々に征服した。1840年代後半にはスィク戦争に勝って、パンジャーブ地方を併合し、インド征服をほぼ完成した。イギリスは、東インド会社をインド植民地の統治機関とし、これを通じて植民地支配を進めた。
イギリスによるインドの植民地化は、インド文明の西洋文明への従属であり、宗教的にはキリスト教徒によるヒンドゥー教徒・イスラーム教徒らへの支配だった。また、これは白人種による有色人種の搾取でもあった。
●イギリスのインド植民地支配
イギリスによるインドの植民地化の過程は、産業の発展と結びついたものだった。イギリスがインドで交易の利権を拡大していた17世紀半ば、イギリスで薄地で軽やかな織物を着る流行が始まった。そうしたところに、1660年頃からインド木綿が流れ込んできた。インド木綿は、流行に乗って急速に普及した。同世紀末までにインド木綿は、他の衣料と比べ物にならない人気を獲得した。着心地よく、美しく、しかも安かった。当時ムガル帝国は、この製品によって、圧倒的な輸出力を誇っていた。
イギリスでは、毛織物工業でマニュファクチュアが発達し、技術的分業が進んでいた。分業化された生産は、工程の一部を機械に置き換えることができる。機械化は1760年代に、まず毛織物工業で始まった。機械化はまもなく、新興の綿工業で急速に進んだ。まさに革命的な変化だった。この機械化の過程が、イギリス産業革命にほかならない。
イギリス綿工業は、ほぼ1世紀の年月をかけてインド木綿の模倣に成功した。輸入代替化に成功したイギリスは、今度はもとの供給国インドに輸出し始めた。イギリス木綿は、1820年代前後から、怒涛のごとくインドに流入した。それまでヨーロッパへの輸出に依存していたインド綿業は壊滅的な打撃を受けた。これがムガル帝国の経済的基盤を掘り崩した。イギリスから機械生産による綿布がインドに大量に流入すると、インドの手工業者は圧迫され、インド経済は打撃を受けた。インド人の不満は高まり、1857年セポイの反乱(インド大反乱)が勃発した。セポイとは、東インド会社が雇ってインド征服の手足としていた傭兵である。
直接的な原因は、当時の新式銃に装填する弾丸の薬莢の端に牛と豚の脂を混ぜたものが使われていることに、ヒンドゥー教徒またはイスラーム教徒であるセポイたちが激怒したためである。それゆえ、この反乱は、民族間闘争であるとともに、宗教間闘争でもあった。
反乱は大規模化したが、1859年イギリス軍はこれを鎮圧した。この間、イギリス政府は、1858年にインド統治改善法を制定し、東インド会社の機能を停止して、直接統治に切り替えた。内閣に新設されたインド担当国務大臣が、現地のインド総督を指揮した。イギリス人インド総督は、インド帝国における国王の代理として副王の称号を与えられた。
イギリスは、カースト制度における身分・職業等による諸集団の対立や、ヒンドゥー教とイスラーム教の対立を分割統治に利用した。ヒンドゥー教に対しては、その信仰に基づく嬰児殺し、幼児婚、寡婦の殉死等を禁止した。これらの禁止はキリスト教の布教を目的とするものだったが、インドの民衆は容易に従わなかった。
イギリスは、インドで徴税や行政、治安維持等を行なうため、インド人を官吏や軍人に採用することにし、1835年より、教育をすべて英語で行うことにした。また、公文書は英語で作成することを命じた。これによって、英語が急速に普及した。インドは多言語社会であり、共通言語が発達していなかったことも英語普及の要因である。やがて英語教育を受けた若い世代の中から、西洋の政治思想を学んで、民族意識を持ち、インド社会の変革を志す者や、ヒンドゥー教の改革に取り組む者が現れるようになる。
インドの直接統治体制を確立したイギリスは、ムガル皇帝を廃して帝国を滅亡させ、1877年にヴィクトリア女王が皇帝を兼ねるインド帝国を創建した。こうしてインドは、完全に植民地にされた。
イギリスは、19世紀末から帝国主義政策を進め、植民地支配をさらに強化した。反発するインド民衆を弾圧するため、インド人の出版・言論を制限する法律やインド人の武器所持を禁じる法律等を制定した。こうした差別的な統治法に対して、インド人から激しい反対の声が上がった。それが、インドの反英闘争の始まりとなった。
次回に続く。
************* 著書のご案内 ****************
『人類を導く日本精神~新しい文明への飛躍』(星雲社)
https://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/cc682724c63c58d608c99ea4ddca44e0
『超宗教の時代の宗教概論』(星雲社)
https://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/d4dac1aadbac9b22a290a449a4adb3a1
************************************










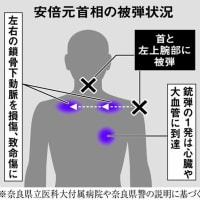









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます