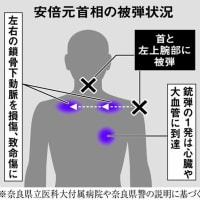●宗教と哲学及び科学
原初宗教から高度宗教への発達過程では、象徴的な思考から概念的な思考への変化が現れた。ここで象徴的な思考とは、例えば善悪について善の神と悪の神の物語を語るような思考の仕方である。概念的思考とは人格化された神々の話ではなく、善悪という概念を以て思考するものである。前者にも一定の論理があるが、通常その論理は明確に意識されずに物語として理解される。後で者は概念的な思考に伴う形で論理が発達する。
神話に基づく古代的な宗教は、象徴的思考のなかに概念的思考を併せ持っている。しかし、その思考は神話を完全に脱却したものではない。そこから概念的思考がさらに発達したところに、哲学が出現した。
哲学とは、古代ギリシャで、紀元前6世紀ころに発生した知的な活動である。英語のphilosophy等は、「知を愛すること」を原義とする。イオニア学派のヘラクレイトスやエレア学派のパルメニデス等は、神話的信仰を基盤としつつ、概念的思考を展開した。万物の始源(アルケー)を追求して、「永遠に生ける火」「存在(ト・エオン)」などの概念で表した。また物事の法則や論理に当たる「ロゴス」を論じた。プラトンは「イデア(形相)」の概念を用いて、物事の合理的認識を進めるとともに、「善(アガトン)」の概念をもって人間の徳の追及を行った。これらの哲学者は、当時の古代的な宗教を否定したものではなく、例えばプラトンはオリュンポス神殿の神々やダイモンと呼ばれる守護霊を仰いだ。また輪廻転生を説くオルフェウス教や数の理法を説くピュタゴラス教団の影響が指摘されている。彼の弟子アリストテレスは、形相―質料、類―種―個等の概念を用いた哲学を説いた。彼の思想においては、プラトンより神話的信仰は薄くなっているが、その哲学の中心には神があり、神を「質料を持たない純粋形相」であり、「不動の動者」等ととらえている。
哲学は、古代ギリシャで発生し、ローマ帝国を経て、ヨーロッパで発達した。その意味では、西洋文明に固有の知の形態である。だが、哲学を概念的思考によって物事の合理的認識や人間の徳の追及を行う学問と規定するならば、西洋文明に限らず、他の文明でも発生し発達したものと考えることができる。
例えば、古代シナでは、天地・宇宙・万物を創造し支配する神を天帝とする天命思想があり、それを背景として、紀元前5~6世紀から儒教・道教が発達した。これらは、仏教に対比されて「教」の文字をつけて呼ばれるように、古代的な宗教である。例えば、孔子は葬礼を行う巫術者の集団の指導者だったと考えられ、老子は神仙伝説と結び付けられる伝説的な存在である。そうした宗教的な思想の中で、古代ギリシャの哲学と比較し得るような概念的な思考が行われた。孔子の「仁」「忠」「孝」「礼」等の徳目や老子の「道」、易経の「陰陽」等は、その概念的思考の産物である。
また、古代インドでは、神話的信仰を背景として、紀元前13世紀からバラモン教が発達した。バラモン教は、ベーダという根本聖典を持ち、その奥義書にウパニシャッドがある。ウパニシャッドは、宇宙の本体としてのブラフマン(梵)と人間の本質としてのアートマン(我)が同一であるという梵我一如を中心思想とする。ここでも古代ギリシャの哲学と比較し得るような概念的な思考が行われた。バラモン教は、そうした合理的認識を含みつつ、輪廻転生の世界からの解脱を説き、ヒンドゥー教の基礎となった。
こうした例を見るならば、哲学は西洋文明に限らず、シナ文明、インド文明等においても発生し発達したということができる。また、様々な宗教において、その宗教には哲学的な側面があり、哲学には宗教的な側面があって、これらを原理的に区別してとらえることは、実態を損ねるものとなる。
近代西欧では、哲学はキリスト教の神学から自立したものと考え、近代西欧哲学を哲学の純粋形態とみなす。しかし、ヨーロッパにおいても、キリスト教の神学は、キリスト教の教義をギリシャ哲学を応用して整備する取り組みから発達したものだった。特に12世紀以降は、アリストテレスの理論に負うところが大きい。古代ギリシャの多神教の社会で発達した哲学を、ユダヤ民族が生み出した天地・人間を創造したとされる唯一神、カトリック教会が樹立した神と子と聖霊の三位一体の信仰に応用したものである。
近代西欧においても、キリスト教と哲学の関係は続いている。物心二元論・主客二元図式・要素還元主義等によって近代哲学の祖とされるデカルトは、キリスト教の神への信仰を否定しておらず、神の存在証明を行っている。また、自由主義・民主主義・資本主義等の基礎理論を打ち立てたロックは、キリスト教の神への信仰に基づく政治社会理論を展開した。18世紀啓蒙主義の代表的存在であるカントは、人間の認識能力を根本的に検討した批判哲学を、キリスト教の信仰による心霊論的信条の上に構築している。19世紀以降の科学的合理主義を経た20世紀以降においても、欧米を中心にキリスト教の信仰に基づく哲学が脈々と受け継がれており、神学的哲学、哲学的神学が展開されている。
近代化の進む非西洋社会においても、宗教と哲学の関係は続いている。イスラーム教にも神学と哲学があり、キリスト教文化圏における以上にそれらの結びつきは深い。仏教には、仏教の教学とそれに基づく哲学があり、同様のことが言える。
宗教と哲学を比較すると、宗教は何らかの体験に基づいている。祈り、瞑想、祭儀、修行等の実践を通じて得た体験が、宗教における不可欠の要素である。これに比し、哲学は経験一般に基づくことなく、純粋な思考によって真理の認識に到達しようとする思弁的な傾向がある。宗教の認識は直観的・体得的であり、その表現は象徴的であることが多く、しばしば非言語的である。これに対して、哲学の認識は論理的・対象的であり、表現は概念的であり、常に言語的である。こうした特徴を持つ宗教と哲学は、ともに真理の探究をするものとして、相補的な関係にある。
ところで、宗教・哲学と対比されるものに、科学がある。科学は体系的で、経験的に実証可能な知識を言う。古代から近代の初期までの長い歴史において、科学は宗教と不可分であり、また哲学とも不可分だった。宗教から哲学が分かれ、またそこから科学が発達した。科学もまた古代ギリシャに限るものではなく、シナ、インド、イスラーム等の諸文明においても発達した。
近代西欧科学は、それらの諸文明で発達した前近代的な科学を土台として発生したものである。近代西欧科学は、自然の研究において、客観性・再現性のある現象を対象とし、数学と実験を用いて法則を見出す点に特徴がある。その根本にあるのは、観察と分析であり、仮説を立てて証明を行いながら、理論を構築する。社会に関しても、観察と分析を行い、仮説を立てて論理的に説明を行う方法によって、経験的に実証可能な知識を体系化することが可能であり、自然科学に対して社会科学が発達した。
こうした科学と宗教は相いれないものではなく、自然科学及び社会科学の理論と方法を以て、宗教の研究を行うことは可能である。今日はその研究によって、精神を対象とする科学、すなわち精神科学が発達することが求められている。特に宗教に不可欠である体験の研究が重要となる。宗教における体験については、後に別の項目に書く。
次回に続く。
原初宗教から高度宗教への発達過程では、象徴的な思考から概念的な思考への変化が現れた。ここで象徴的な思考とは、例えば善悪について善の神と悪の神の物語を語るような思考の仕方である。概念的思考とは人格化された神々の話ではなく、善悪という概念を以て思考するものである。前者にも一定の論理があるが、通常その論理は明確に意識されずに物語として理解される。後で者は概念的な思考に伴う形で論理が発達する。
神話に基づく古代的な宗教は、象徴的思考のなかに概念的思考を併せ持っている。しかし、その思考は神話を完全に脱却したものではない。そこから概念的思考がさらに発達したところに、哲学が出現した。
哲学とは、古代ギリシャで、紀元前6世紀ころに発生した知的な活動である。英語のphilosophy等は、「知を愛すること」を原義とする。イオニア学派のヘラクレイトスやエレア学派のパルメニデス等は、神話的信仰を基盤としつつ、概念的思考を展開した。万物の始源(アルケー)を追求して、「永遠に生ける火」「存在(ト・エオン)」などの概念で表した。また物事の法則や論理に当たる「ロゴス」を論じた。プラトンは「イデア(形相)」の概念を用いて、物事の合理的認識を進めるとともに、「善(アガトン)」の概念をもって人間の徳の追及を行った。これらの哲学者は、当時の古代的な宗教を否定したものではなく、例えばプラトンはオリュンポス神殿の神々やダイモンと呼ばれる守護霊を仰いだ。また輪廻転生を説くオルフェウス教や数の理法を説くピュタゴラス教団の影響が指摘されている。彼の弟子アリストテレスは、形相―質料、類―種―個等の概念を用いた哲学を説いた。彼の思想においては、プラトンより神話的信仰は薄くなっているが、その哲学の中心には神があり、神を「質料を持たない純粋形相」であり、「不動の動者」等ととらえている。
哲学は、古代ギリシャで発生し、ローマ帝国を経て、ヨーロッパで発達した。その意味では、西洋文明に固有の知の形態である。だが、哲学を概念的思考によって物事の合理的認識や人間の徳の追及を行う学問と規定するならば、西洋文明に限らず、他の文明でも発生し発達したものと考えることができる。
例えば、古代シナでは、天地・宇宙・万物を創造し支配する神を天帝とする天命思想があり、それを背景として、紀元前5~6世紀から儒教・道教が発達した。これらは、仏教に対比されて「教」の文字をつけて呼ばれるように、古代的な宗教である。例えば、孔子は葬礼を行う巫術者の集団の指導者だったと考えられ、老子は神仙伝説と結び付けられる伝説的な存在である。そうした宗教的な思想の中で、古代ギリシャの哲学と比較し得るような概念的な思考が行われた。孔子の「仁」「忠」「孝」「礼」等の徳目や老子の「道」、易経の「陰陽」等は、その概念的思考の産物である。
また、古代インドでは、神話的信仰を背景として、紀元前13世紀からバラモン教が発達した。バラモン教は、ベーダという根本聖典を持ち、その奥義書にウパニシャッドがある。ウパニシャッドは、宇宙の本体としてのブラフマン(梵)と人間の本質としてのアートマン(我)が同一であるという梵我一如を中心思想とする。ここでも古代ギリシャの哲学と比較し得るような概念的な思考が行われた。バラモン教は、そうした合理的認識を含みつつ、輪廻転生の世界からの解脱を説き、ヒンドゥー教の基礎となった。
こうした例を見るならば、哲学は西洋文明に限らず、シナ文明、インド文明等においても発生し発達したということができる。また、様々な宗教において、その宗教には哲学的な側面があり、哲学には宗教的な側面があって、これらを原理的に区別してとらえることは、実態を損ねるものとなる。
近代西欧では、哲学はキリスト教の神学から自立したものと考え、近代西欧哲学を哲学の純粋形態とみなす。しかし、ヨーロッパにおいても、キリスト教の神学は、キリスト教の教義をギリシャ哲学を応用して整備する取り組みから発達したものだった。特に12世紀以降は、アリストテレスの理論に負うところが大きい。古代ギリシャの多神教の社会で発達した哲学を、ユダヤ民族が生み出した天地・人間を創造したとされる唯一神、カトリック教会が樹立した神と子と聖霊の三位一体の信仰に応用したものである。
近代西欧においても、キリスト教と哲学の関係は続いている。物心二元論・主客二元図式・要素還元主義等によって近代哲学の祖とされるデカルトは、キリスト教の神への信仰を否定しておらず、神の存在証明を行っている。また、自由主義・民主主義・資本主義等の基礎理論を打ち立てたロックは、キリスト教の神への信仰に基づく政治社会理論を展開した。18世紀啓蒙主義の代表的存在であるカントは、人間の認識能力を根本的に検討した批判哲学を、キリスト教の信仰による心霊論的信条の上に構築している。19世紀以降の科学的合理主義を経た20世紀以降においても、欧米を中心にキリスト教の信仰に基づく哲学が脈々と受け継がれており、神学的哲学、哲学的神学が展開されている。
近代化の進む非西洋社会においても、宗教と哲学の関係は続いている。イスラーム教にも神学と哲学があり、キリスト教文化圏における以上にそれらの結びつきは深い。仏教には、仏教の教学とそれに基づく哲学があり、同様のことが言える。
宗教と哲学を比較すると、宗教は何らかの体験に基づいている。祈り、瞑想、祭儀、修行等の実践を通じて得た体験が、宗教における不可欠の要素である。これに比し、哲学は経験一般に基づくことなく、純粋な思考によって真理の認識に到達しようとする思弁的な傾向がある。宗教の認識は直観的・体得的であり、その表現は象徴的であることが多く、しばしば非言語的である。これに対して、哲学の認識は論理的・対象的であり、表現は概念的であり、常に言語的である。こうした特徴を持つ宗教と哲学は、ともに真理の探究をするものとして、相補的な関係にある。
ところで、宗教・哲学と対比されるものに、科学がある。科学は体系的で、経験的に実証可能な知識を言う。古代から近代の初期までの長い歴史において、科学は宗教と不可分であり、また哲学とも不可分だった。宗教から哲学が分かれ、またそこから科学が発達した。科学もまた古代ギリシャに限るものではなく、シナ、インド、イスラーム等の諸文明においても発達した。
近代西欧科学は、それらの諸文明で発達した前近代的な科学を土台として発生したものである。近代西欧科学は、自然の研究において、客観性・再現性のある現象を対象とし、数学と実験を用いて法則を見出す点に特徴がある。その根本にあるのは、観察と分析であり、仮説を立てて証明を行いながら、理論を構築する。社会に関しても、観察と分析を行い、仮説を立てて論理的に説明を行う方法によって、経験的に実証可能な知識を体系化することが可能であり、自然科学に対して社会科学が発達した。
こうした科学と宗教は相いれないものではなく、自然科学及び社会科学の理論と方法を以て、宗教の研究を行うことは可能である。今日はその研究によって、精神を対象とする科学、すなわち精神科学が発達することが求められている。特に宗教に不可欠である体験の研究が重要となる。宗教における体験については、後に別の項目に書く。
次回に続く。