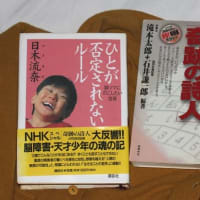商店街に通じる街道の桜並木がそろって散り終わる頃、PTA総会の出欠票及び委任状が息子の級友によってわが家に届けられた。息子は中学一年生の初めから学校へは行っていない。四月から二年生に進級し組替えされた結果、新しいクラスと担任を得てはいたのだが、やはり登校できないでいるのであった。新学年当初ということで何かとプリント類が多いらしく毎日のように近隣の級友が下校時に届けてくれる。
総会の日付を見れば私が呼びかけて地域に作った、「不登校の親の会」第一回の例会の三日前だった。それで、同校の父母たちや教師などにも息子たちの置かれている不登校についての状況や私たちの会の紹介をしておこうと思い、この度の総会にはぜひ出席しようと決め、次の日新しい担任の先生への顔つなぎということも兼ね、出欠票を提出してきたのである。半年前から私は失業中のことであり時間はあった。
二人の息子が六歳違いなものだから、彼らの小学校時代から数えれば計十八年ほど義務教育就学者の親として過ごしてきているわけで、PTA会員としても十八年の大ベテランということになる。だが夫婦して常勤で勤めてきたことで、役員を引き受けたことは一度もなければ、時間が合わずほとんどその活動に参加したこともない。
PTAは意志的に忌避しない限りは入学時に自動的に会員となってしまうので、脱会するにもなかなかエネルギーを必要とするのであった。会費だけは着々と預金口座から引き落とされているからでもあるのだが、会員としての権利と義務については訳のわからぬまま、ともかく会員であり続け会費もとどこおりなく支払っては来ていた。だが息子たちが登校しなくなって以来PTA会員であることはほとんど無為で意味のないものだ、という気持が強くなってきてもいた。実際脱会しようかと考えたことも何度かあった。
学校のPTA総会に出席したのは十八年間で初めてのことなので、今さらのように批判がましく偉そうなことは言えないのだが、会長を始め役員を決めるさいには自らの指針をもって出馬するような父母は皆無らしい。あらかじめアミダくじが用意されているような学校もあると聞いている。
この日は木曜日の十五時半から教室の一つを使って開催されたのだが、週日の昼間開かれるのはどこの学校でもそうらしい。校長・教頭の勤務時間内に済ますべきものとしてこうした時間が選ばれるという声を聞いたことがある。だから常勤で勤めている親は総会ばかりでなくPTAの集まりには、よほどでないかぎり出席はできない。
共働きの私たちからすればPTA活動からシャットアウトされていると不満を抱きがちなのだが、仕方なく役員を引き受けている父母から見れば、反対に私たちのような親は非協力的だと写ってしまう。会長は父母の中から選ばれてはいるのだが、これは表面だけのことで、学校側の強力な院政の元に活動しているというのが実態なのだ。防犯上の理由からということで、数年前から生徒名簿が作成されなくなっているため、会員の一覧名簿すら存在しないまま運営されている。正確な会員の把握は学校でしてくれているという訳だ。
せっかく週日の午後開かれるというのに、教師側から出席したのは校長、教頭の二人だけだった。一般に小学校の場合は教師の多くが列席するらしいが、中学校となるとこれが常なのだと後に事情通の父母から聞いた。だがこれは随分父母を馬鹿にした話ではないか。民主主義を教えるべき教師が当の現場でそれを否定しているのである。教師はすべてPTA会員である。
実際に総会に出席したのは初めてだったが、出席しようとしたことはあった。息子が小学生の五年生のときだった。休みがちになり、このままでは完全不登校になると予感した私は、学校への疑問をそこでぶつけてみたかった。だが、やはり総会は勤務中のそれも週の中で仕事が一番忙しくなる金曜日の午後ということで怒りを持ちつつあきらめた。あきらめた変わりにPTA会則を仔細に点検して、会長あてに手紙を出した。会則では慶弔金についての規定が変だった。同じ会員でありながら教師に厚く、父母に薄いのである。総会において会則の是正を求めた。手紙を出してから一週間ほどして会長から電話があった。「そうは言っても○○さん。私はただ頼まれて会長をひきうけているだけでして。すいませんがこれは議題にできません」と言い訳してきた。
そう言えば会則の中の特記項目に「校長はすべてのPTAの会合に出席できる」とあった。院政システムの法的根拠がここにある。逆に言えば校長の認可しない父母だけの会議は認められないという意味にもなる。
さて父母側は男の性である私を除けばすべて女性、すなわち母親ばかりだった。見知った人は校長を除けば一人もいなかった。校長、教頭が着席するとすぐ、反対側の席に座っていた司会者が立ち上がり開会を宣した。続いて四五〇名の会員のうち出席者は二三名、三百四十通の委任状によって総会は規約通り成立していると報告があった。それにしても会員の五%しか出席しないとは驚きだった。それが毎年の通例で当たり前のことらしく、校長も着席したときから満足気に笑みを絶やさず、父母たちへの顔面サービスを振りまいている。すでに年度末に新しく選出された今年度の会長が「よろしくご審議のほどを」と一言述べ、続いて一会員であるべきはずの校長によって越権とも思え、かつ冒頭にしては長すぎる発言があった。
「昨日、区の校長会がありまして今年度の教育財政についても相変わらず厳しい状況であることが伝えられました。その中でも喜ばしいことに区内の全中学校に新しいパソコンが配置されることになりました。ご存じの通りパソコンは一年たてば使いものにならないと言われており、やっとわが校でも新しいパソコンが設置されることになったわけです」と、校長の話の中で私が気になったのはそれだけだった。一年で使いものにならなくなるパソコンを区内の全中学校に配備して、それで来年はどうするのかという疑問が湧いてくる。
つまるところ校長としては「財政難の中、私たちとしても懸命に教育環境を良くしようとして努力はしています」と言いたかったのだろうが、私には何か弁明しているようにも聞こえたのである。校長会という会議の性格もほのかに見えてくる。区内の校長らが一堂に会して、学校教育論に花が咲くというのでは全くなく、そこでは予算とか、与えられる物資の目録に目を通すとかの、いわば報告・通達の類を「お上」から承ってくるために列席するという意味しかもっていないらしい。
さて議題は昨年度決算の承認、今年度予算の承認とすすみ、その度に議長がなにか質問はありませんかと聞くのだが、だれ一人手を挙げる者もなくここまで十分とかからず終了してしまった。次は今年度の活動予定の説明があり、これも五分ほどで終わってしまった。最後に用意されていた「その他」という議題になったので、私は手を挙げ発言したのである。私の上着の内ポケットには昨夜ほとんど徹夜で仕上げた自分の発言のための草稿が隠されていた。以下がその文面である。
-★-★-
十三才になる息子は当学校に学籍はもっているのですが、一年生の時からほとんど登校していません。現在十九歳になる上の子の場合も六年前この中学校に在籍していたのですが同じような状態でした。十年近くも二人の息子たちの不登校と付き合ってきたのですが、昨年夏、私は長く勤めてきた会社を退職し、少しはゆっくり物事を考える時間ができましたので、登校拒否という現象について同じような親御さんたちとしっかり話し合ってみたいと考えました。
そこで「不登校の親の会」という会を作り、懇談会を企画したのです。チラシなどをつくり区内の全小・中学校へ案内文を配布したり、また多少ともつながっている地域の親御さんたちに呼びかけました。三月の初めに一回目の懇談会をこの近くの地区会館で開催したのです。当日何人来てくれるか心配だったのですが、十七名もの父母が参加してくれました。悩みあり、模索あり、はたまた自信ありの自由討議でしたが、参加されたみなさんが一様に「悩んでいるのは私だけではなかった」と感想を述べてくれました。
みなさんもご存じとは思いますが、現在日本中で十万人近くの小・中学生が登校していません。区内でも合計すれば四百人前後の子どもたちが登校できないで苦しんでいるということなのです。この数字には改めて驚いてしまうのですが、今後ますます増えていくと予想する人はいても減るから大丈夫という関係者は皆無です。すっかり「いじめ」「不登校」という問題は社会的な話題となって新聞でも毎日の記事にことかかない有様です。有効な手だてもほとんど見つかっていません。
あと何年かしたら、教室の三分の一の机には生徒はいないと言った光景はどこの学校でもみられるというふうになってしまうのではないでしょうか。実際に高校ではこうした光景が日常的に見られるようになってきました。たいした理由もないのに学校を休む、遅刻する、早退する、登校しているのに授業には出ないという生徒が溢れています。このままでは日本の学校が崩壊するのは時間の問題といってもいいでしょう。いったいどうしてこんなことになってしまったのでしょう。高校の場合は子どもたちが志願して入学したという前提があるので、私にとっては対岸の火事ぐらいにしか思っていませんが、義務教育最中の小・中学校の場合は親の悩みも想像以上に深刻なものがあるのです。
一週間ほど前に学校信仰や教師聖職論の発祥の根がここらへんにあるのではないかと常々訝(いぶか)しく思っていたこともあり、しっかり批判してみるつもりで壺井栄の小説『二十四の瞳』読んでみたのです。これは一九五二年に出版されました。作者が五三歳の時でした。二年後に作られた木下恵介監督の同名の映画も名作でしたが、私はこの映画を何度か見たことがありますが、まじめに原作を読んだのははじめてだったです。
みなさんもその内容はご存じのように物語は戦前から戦争を挟んで敗戦直後までの二十年間の瀬戸内海の小豆島という小さな島の分校の物語です。昭和四年に新任で十二名の生徒しかいない分校に配属されてきた女性教師・大石先生と子どもたちの厚い友情の物語なのですが、当初の私の意に反してとても感動してしまいました。先生も子どもたちも、心の持ちようといったものが今の学校とはまったく違うのです。何が違うのかこの一週間の間ずっと考え続けているのですが、少しだけですが分かったことがありました。
息子が一年生の最後の日、私は一年間ほとんど欠席したままで心配ばかりかけた担任の先生への挨拶のため学校にきました。職員室の前の廊下で少しの間でしたが、なかなか手のあかない先生を待っていたのです。そこに予定表などを書き込む大きなボードが掲げられています。右側第一行目に大きくこう書かれてありました。
「テストが終わっても気をゆるめずに」と、そしてたしか文末にはびっくりマークが添えられてあったはずです。その横には各部活の春休みのスケジュールが、これまたびっしりと書き込まれてあったのです。私にはこの一文のいわんとしているところが理解できませんでした。家にいる息子がそれを見ても多分理解できないでしょう。テストが終わったら、なぜ「お疲れさま、ゆっくり春休みを過ごしてくれ」と言ってやることができないのでしょう。
ここに書かれてあったテストとは学年末三学期の期末テストのことなのでしょうが、テストが始まるまで子どもたちは回りのすべての大人たちから一点でも良い成績をとるように尻を叩かれてきたのではないのでしょうか。そのテストが終了し春休みを前にしても相変わらず「気をゆるめてはならない」と子どもたちは迫られているのです。子どもたちにこうした言葉しかかけてやることができないのかと、大人の一員として実に寂しい気持ちを味わいました。
けれどよく考えて見ればこの一文は子ども達に伝わっているのでしょうか。この標語通りに実践する子どもがもしいたとしたら、いまごろ病気になってしまっているのではないでしょうか。つまり子どもたちに、この日本語はほとんど伝わっていないというのが実際のような気がするのです。そう気が付いて再度見てみると、「あの人は要領がいいね」というその要領を教えるための標語のような気もしてきたのです。先生方もちゃんと分かっているのです。むしろまじめに取ってしまわれては先生方の方が困ってしまうという類の言葉なのではないのでしょうか。
これは単に努力目標だからまじめに受け取らなくてもいいのだと分かっていながら、なぜ無意味とも思われるようなこうした標語を掲げなければいけないのか。家庭でも同じようなことが言えるのです。「ベンキョしなさい」「早くしなさい」と繰り返し繰り返し大人たちから連発され、子どもたちはこうした口先だけの大人たちの言葉が無意味で空疎なものでしかないと感じ始めています。子どもたちは大人たちから毎日毎日競走馬のように鞭を入れられ、心を痛めているのです。
『二十四の瞳』の大石先生は少なくとも本の中では、こうした意味不明な言葉は決して発していません。家の仕事が忙しいからと言って学校へこれない子どものことを自分の職業的存在をかけて心配しています。子ども達の髪の毛が汚れているからなんとかしなければとバリカンやシラミ退治の薬の算段を真剣に考えているのです。毎日毎日を全体として見れば貧しい家庭のそれぞれの子どもたちの健康と将来を真剣に思いやっているのです。
ベンキョができるできないはまったく子どもの個性であると確信をもっていますから彼女が発することばは全て子ども個人との生活的な対話から成り立っているため、先生の全ての言葉が子どもたちの胸に響いてくるようです。集団としての子どもたちに号令をかけたり命令したりする場面は少なくとも本のなかでは一切ありません。戦争をはさんだ時代ですから、国の方から出されてくる標語が腐るほどあるのですが、大石先生はそれを嫌います。要領だけを教えるような標語的言葉を彼女はけっして子どもたちの前で口にしなかったのです。戦争遂行への先生の不信感はやがて村や学校の中で知られることになり、このことが原因で大石先生は教職を離れなければならなくなりました。
作者の壺井栄自身は高等小学校しか卒業していません。今の中学校です。その彼女が戦争遂行中の時勢という反面を除けば、幼年期に受けた学校教育を素材としてこれほどまでに教師と子どもたちの交流を肯定し賛歌しているということは、当時の学校教育が子どもたちの実感上、かけがえのない大切なものとして受容されていたことを示しているのです。この作品をもう少し深く読み込んでいけば標語的なものと生活的なものとの教育上の対立なども見えてきます。それはとりもなおさず大人と子ども、あるいは戦争と生活という対立であり、国家と庶民という対立でもありました。子どもの立場にたつか、大人の立場にたつのかという二分された苦悩を自覚する教師の物語であったと私は理解したのでした。壺井栄は主人公の教師を時勢に流される大人たちから、あくまで子どもを守る立場にたたせています。それを作品の中で一貫させていたのでした。
言葉が伝わるか伝わらないかという問題では木下順二さんの戯曲『夕鶴』の中に好例があります。いつか助けてやった鶴が恩返しをしようと、美しい女性「つう」に化身して「与ひょう」の元にやってきます。二人は夫婦となり、鶴の化身「つう」は自らの羽を引き抜いては布をおり生活を助けます。ある日、その反物が評判となり「与ひょう」のところに出入りしている仲買人がもっと沢山織れば、えらい金儲けができるぞと素朴な「与ひょう」にたらし込みます。「与ひょう」は「つう」にもっとたくさん布を織ってくれと頼みます。金を儲けて都に遊びにいくんだ、と言います。
けれど金の話になると「つう」にはその「与ひょう」の言葉がまったく通じなくなってしまうのです。知らない外国語でもきいているようにチンプンカンプンとなってしまいます。けれど「つう」は「与ひょう」が自分を好いてくれていることだけは確認できましたから、最後の愛をしめし、決して仕事をしているところを覗いていけないと言い置いてから自分の羽を引き抜いていきます。「つう」の存在を、もはやそのままのものとして受け取れなくなっている、いわば知恵という雑念を得た人間となってしまっていた「与ひょう」は「つう」との約束を破り障子を開け覗いてしまいました。こうして反物が織り上がると「つう」は元の鶴となって、約束を破った「与ひょう」から去っていってしまうのです。
職員室の前の廊下に書かれてあった一文は『夕鶴』の「つう」に伝わるでしょうか。残念ながら通じないでしょう。大石先生ならば決して口にしなかったろうと思うのです。こうした公式標語は子どもたちに届かないばかりでなく大人たちとの間のいっそうの断絶を予告しているようにしか思えないのです。先生方には酷な言い方かもしれませんが、私には戦争中に流された幾種類ものまがまがしいスローガンを読んでいるような気さえしたのでした。それらの標語は国家から庶民へという伝達システムの元に掲げられてはいたものの、実際に作用した事実では大人たちから子どもたちへと伝わったのであり、また男たちが女たちへ一方的に押しつけようとしていたものであったことは半世紀後の今日から見れば余りにあきらかです。
話がとても長くなりました。私は当学校のやはり登校できないでいるお子さまを持つ父母と連絡をとってみた結果、それぞれに情報を交換し励まし合うことができるならばと「親の会」を作りました。それで初の会合を三日後の日曜日に、この近くの会館で開きます。こうした問題で困っている方がありましたら是非ご参加ください。また皆さんの回りにそのような方がいらっしゃいましたら、チラシを持ってきておりますので知らせてあげてください。
-★-★-
だが私はこの草稿をついに内ポケットから取り出さなかった。当日そのまま読むことをしなかったのは深夜に書いた恋文のように、思いこみが一面的に過ぎ学校批判のみが主題となってしまっていたからである。また余りに長すぎてこの場にふさわしくなく、このままでは招かれざる講演者か演説家になってしまい父母にさえも嫌われそうな心配が出てきた。加えて重大な勘違いをしているらしいと気付いたからだ。草稿の中で鬼の首を取ったかのように指摘している職員室の廊下のボードは生徒会が使用するものとしてそこにあり、標語のように書かれていた一文は教師が書いたものではなく、生徒自身が書いたものではなかったかという疑問がわいてきたからだった。そう言えば大人の書いた字とは思えないような気もしてきたのである。
総会の後、それとなく確かめてみるとやはりそうだった。子どもが子どもに競争をあおっている内情が浮かんでくる。背後から子どもにそれを書かせているのは誰なのか。気をゆるめっぱなしのわが息子などは、学校の中では級友たちからでさえ排斥されかねないという思いが湧いてきて、いっそう背筋が寒くなるのであった。この日実際に私が発言したことは、不登校児童の全国的加速度的な増加は学校存在の危機・公教育の危機であり、とりもなおさず子どもたちの学習権の危機であること。不登校のこどもたちが毎日をどのように過ごしているか。大部分の子どもたちは家に閉じこもりがちでマンガやテレビゲームで時を過ごしていること。将来の見えない子どもを前にしての家族の混迷。一部の子どもは親たちによって運営されているフリースクール、フリースペースなどに通っているけれど、公的助成が全くなされていないため個人的負担が大変であること。最後に日時の差し迫っている私たちの会の宣伝を言うにとどめた。
さらに「校長先生の話では、一年で古くなるパソコンを今年度一新するとのことですが、私の息子はこうした恩恵にも全く無縁なのです」と釘をさしてもみた。だが「不登校の問題は単に学校や先生方を批判するだけではなんら解決の方向を示してはいないのです」と学校に対するゴマすりのようなことも付け加えてしまい、草稿の主題とは随分違った内容になってしまったのであった。三分ほどのスピーチだったが、私が着席するとすぐ補足しなければ立場がないと言わんばかりに校長が議長を無視して立ち上がった。
「○○さんが言うように」などと私の言葉を引用して追従し「不登校のこどもたちは一人一人その原因も状態も違い、学校としましても対応に苦慮しているところです。他の中学校ではだいたい十人以上の子どもが登校していないという状況ですが、幸いわが校は現在三人しかいません」と、予想に反して柔らかかった私の話に安心したのか、「わが校は周囲の学校に比べてみても、落ち着いたよい環境が出来上がりつつあると思われます」と締めくくった。だがそれは冒頭でのパソコン発言よりもさらに弁明的だった。私の上着の内ポケットには草稿とともに「不登校の親の会」の案内チラシが十枚ほどあったので、その一枚を隣の母親に「これです」と渡すと、前から後ろからと母親たちの手が伸びてきた。チラシは校長が話している間のうちになくなった。校長の頭上あたりに掲げてあった大きな丸い時計を見ると十五時五十五分だった。始まってから二十五分しか経っていない。こうして年一度の総会は閉じられた。意見を持って発言した者は校長の他には私だけだった。(記:1997/04/19)<9024字>
総会の日付を見れば私が呼びかけて地域に作った、「不登校の親の会」第一回の例会の三日前だった。それで、同校の父母たちや教師などにも息子たちの置かれている不登校についての状況や私たちの会の紹介をしておこうと思い、この度の総会にはぜひ出席しようと決め、次の日新しい担任の先生への顔つなぎということも兼ね、出欠票を提出してきたのである。半年前から私は失業中のことであり時間はあった。
二人の息子が六歳違いなものだから、彼らの小学校時代から数えれば計十八年ほど義務教育就学者の親として過ごしてきているわけで、PTA会員としても十八年の大ベテランということになる。だが夫婦して常勤で勤めてきたことで、役員を引き受けたことは一度もなければ、時間が合わずほとんどその活動に参加したこともない。
PTAは意志的に忌避しない限りは入学時に自動的に会員となってしまうので、脱会するにもなかなかエネルギーを必要とするのであった。会費だけは着々と預金口座から引き落とされているからでもあるのだが、会員としての権利と義務については訳のわからぬまま、ともかく会員であり続け会費もとどこおりなく支払っては来ていた。だが息子たちが登校しなくなって以来PTA会員であることはほとんど無為で意味のないものだ、という気持が強くなってきてもいた。実際脱会しようかと考えたことも何度かあった。
学校のPTA総会に出席したのは十八年間で初めてのことなので、今さらのように批判がましく偉そうなことは言えないのだが、会長を始め役員を決めるさいには自らの指針をもって出馬するような父母は皆無らしい。あらかじめアミダくじが用意されているような学校もあると聞いている。
この日は木曜日の十五時半から教室の一つを使って開催されたのだが、週日の昼間開かれるのはどこの学校でもそうらしい。校長・教頭の勤務時間内に済ますべきものとしてこうした時間が選ばれるという声を聞いたことがある。だから常勤で勤めている親は総会ばかりでなくPTAの集まりには、よほどでないかぎり出席はできない。
共働きの私たちからすればPTA活動からシャットアウトされていると不満を抱きがちなのだが、仕方なく役員を引き受けている父母から見れば、反対に私たちのような親は非協力的だと写ってしまう。会長は父母の中から選ばれてはいるのだが、これは表面だけのことで、学校側の強力な院政の元に活動しているというのが実態なのだ。防犯上の理由からということで、数年前から生徒名簿が作成されなくなっているため、会員の一覧名簿すら存在しないまま運営されている。正確な会員の把握は学校でしてくれているという訳だ。
せっかく週日の午後開かれるというのに、教師側から出席したのは校長、教頭の二人だけだった。一般に小学校の場合は教師の多くが列席するらしいが、中学校となるとこれが常なのだと後に事情通の父母から聞いた。だがこれは随分父母を馬鹿にした話ではないか。民主主義を教えるべき教師が当の現場でそれを否定しているのである。教師はすべてPTA会員である。
実際に総会に出席したのは初めてだったが、出席しようとしたことはあった。息子が小学生の五年生のときだった。休みがちになり、このままでは完全不登校になると予感した私は、学校への疑問をそこでぶつけてみたかった。だが、やはり総会は勤務中のそれも週の中で仕事が一番忙しくなる金曜日の午後ということで怒りを持ちつつあきらめた。あきらめた変わりにPTA会則を仔細に点検して、会長あてに手紙を出した。会則では慶弔金についての規定が変だった。同じ会員でありながら教師に厚く、父母に薄いのである。総会において会則の是正を求めた。手紙を出してから一週間ほどして会長から電話があった。「そうは言っても○○さん。私はただ頼まれて会長をひきうけているだけでして。すいませんがこれは議題にできません」と言い訳してきた。
そう言えば会則の中の特記項目に「校長はすべてのPTAの会合に出席できる」とあった。院政システムの法的根拠がここにある。逆に言えば校長の認可しない父母だけの会議は認められないという意味にもなる。
さて父母側は男の性である私を除けばすべて女性、すなわち母親ばかりだった。見知った人は校長を除けば一人もいなかった。校長、教頭が着席するとすぐ、反対側の席に座っていた司会者が立ち上がり開会を宣した。続いて四五〇名の会員のうち出席者は二三名、三百四十通の委任状によって総会は規約通り成立していると報告があった。それにしても会員の五%しか出席しないとは驚きだった。それが毎年の通例で当たり前のことらしく、校長も着席したときから満足気に笑みを絶やさず、父母たちへの顔面サービスを振りまいている。すでに年度末に新しく選出された今年度の会長が「よろしくご審議のほどを」と一言述べ、続いて一会員であるべきはずの校長によって越権とも思え、かつ冒頭にしては長すぎる発言があった。
「昨日、区の校長会がありまして今年度の教育財政についても相変わらず厳しい状況であることが伝えられました。その中でも喜ばしいことに区内の全中学校に新しいパソコンが配置されることになりました。ご存じの通りパソコンは一年たてば使いものにならないと言われており、やっとわが校でも新しいパソコンが設置されることになったわけです」と、校長の話の中で私が気になったのはそれだけだった。一年で使いものにならなくなるパソコンを区内の全中学校に配備して、それで来年はどうするのかという疑問が湧いてくる。
つまるところ校長としては「財政難の中、私たちとしても懸命に教育環境を良くしようとして努力はしています」と言いたかったのだろうが、私には何か弁明しているようにも聞こえたのである。校長会という会議の性格もほのかに見えてくる。区内の校長らが一堂に会して、学校教育論に花が咲くというのでは全くなく、そこでは予算とか、与えられる物資の目録に目を通すとかの、いわば報告・通達の類を「お上」から承ってくるために列席するという意味しかもっていないらしい。
さて議題は昨年度決算の承認、今年度予算の承認とすすみ、その度に議長がなにか質問はありませんかと聞くのだが、だれ一人手を挙げる者もなくここまで十分とかからず終了してしまった。次は今年度の活動予定の説明があり、これも五分ほどで終わってしまった。最後に用意されていた「その他」という議題になったので、私は手を挙げ発言したのである。私の上着の内ポケットには昨夜ほとんど徹夜で仕上げた自分の発言のための草稿が隠されていた。以下がその文面である。
-★-★-
十三才になる息子は当学校に学籍はもっているのですが、一年生の時からほとんど登校していません。現在十九歳になる上の子の場合も六年前この中学校に在籍していたのですが同じような状態でした。十年近くも二人の息子たちの不登校と付き合ってきたのですが、昨年夏、私は長く勤めてきた会社を退職し、少しはゆっくり物事を考える時間ができましたので、登校拒否という現象について同じような親御さんたちとしっかり話し合ってみたいと考えました。
そこで「不登校の親の会」という会を作り、懇談会を企画したのです。チラシなどをつくり区内の全小・中学校へ案内文を配布したり、また多少ともつながっている地域の親御さんたちに呼びかけました。三月の初めに一回目の懇談会をこの近くの地区会館で開催したのです。当日何人来てくれるか心配だったのですが、十七名もの父母が参加してくれました。悩みあり、模索あり、はたまた自信ありの自由討議でしたが、参加されたみなさんが一様に「悩んでいるのは私だけではなかった」と感想を述べてくれました。
みなさんもご存じとは思いますが、現在日本中で十万人近くの小・中学生が登校していません。区内でも合計すれば四百人前後の子どもたちが登校できないで苦しんでいるということなのです。この数字には改めて驚いてしまうのですが、今後ますます増えていくと予想する人はいても減るから大丈夫という関係者は皆無です。すっかり「いじめ」「不登校」という問題は社会的な話題となって新聞でも毎日の記事にことかかない有様です。有効な手だてもほとんど見つかっていません。
あと何年かしたら、教室の三分の一の机には生徒はいないと言った光景はどこの学校でもみられるというふうになってしまうのではないでしょうか。実際に高校ではこうした光景が日常的に見られるようになってきました。たいした理由もないのに学校を休む、遅刻する、早退する、登校しているのに授業には出ないという生徒が溢れています。このままでは日本の学校が崩壊するのは時間の問題といってもいいでしょう。いったいどうしてこんなことになってしまったのでしょう。高校の場合は子どもたちが志願して入学したという前提があるので、私にとっては対岸の火事ぐらいにしか思っていませんが、義務教育最中の小・中学校の場合は親の悩みも想像以上に深刻なものがあるのです。
一週間ほど前に学校信仰や教師聖職論の発祥の根がここらへんにあるのではないかと常々訝(いぶか)しく思っていたこともあり、しっかり批判してみるつもりで壺井栄の小説『二十四の瞳』読んでみたのです。これは一九五二年に出版されました。作者が五三歳の時でした。二年後に作られた木下恵介監督の同名の映画も名作でしたが、私はこの映画を何度か見たことがありますが、まじめに原作を読んだのははじめてだったです。
みなさんもその内容はご存じのように物語は戦前から戦争を挟んで敗戦直後までの二十年間の瀬戸内海の小豆島という小さな島の分校の物語です。昭和四年に新任で十二名の生徒しかいない分校に配属されてきた女性教師・大石先生と子どもたちの厚い友情の物語なのですが、当初の私の意に反してとても感動してしまいました。先生も子どもたちも、心の持ちようといったものが今の学校とはまったく違うのです。何が違うのかこの一週間の間ずっと考え続けているのですが、少しだけですが分かったことがありました。
息子が一年生の最後の日、私は一年間ほとんど欠席したままで心配ばかりかけた担任の先生への挨拶のため学校にきました。職員室の前の廊下で少しの間でしたが、なかなか手のあかない先生を待っていたのです。そこに予定表などを書き込む大きなボードが掲げられています。右側第一行目に大きくこう書かれてありました。
「テストが終わっても気をゆるめずに」と、そしてたしか文末にはびっくりマークが添えられてあったはずです。その横には各部活の春休みのスケジュールが、これまたびっしりと書き込まれてあったのです。私にはこの一文のいわんとしているところが理解できませんでした。家にいる息子がそれを見ても多分理解できないでしょう。テストが終わったら、なぜ「お疲れさま、ゆっくり春休みを過ごしてくれ」と言ってやることができないのでしょう。
ここに書かれてあったテストとは学年末三学期の期末テストのことなのでしょうが、テストが始まるまで子どもたちは回りのすべての大人たちから一点でも良い成績をとるように尻を叩かれてきたのではないのでしょうか。そのテストが終了し春休みを前にしても相変わらず「気をゆるめてはならない」と子どもたちは迫られているのです。子どもたちにこうした言葉しかかけてやることができないのかと、大人の一員として実に寂しい気持ちを味わいました。
けれどよく考えて見ればこの一文は子ども達に伝わっているのでしょうか。この標語通りに実践する子どもがもしいたとしたら、いまごろ病気になってしまっているのではないでしょうか。つまり子どもたちに、この日本語はほとんど伝わっていないというのが実際のような気がするのです。そう気が付いて再度見てみると、「あの人は要領がいいね」というその要領を教えるための標語のような気もしてきたのです。先生方もちゃんと分かっているのです。むしろまじめに取ってしまわれては先生方の方が困ってしまうという類の言葉なのではないのでしょうか。
これは単に努力目標だからまじめに受け取らなくてもいいのだと分かっていながら、なぜ無意味とも思われるようなこうした標語を掲げなければいけないのか。家庭でも同じようなことが言えるのです。「ベンキョしなさい」「早くしなさい」と繰り返し繰り返し大人たちから連発され、子どもたちはこうした口先だけの大人たちの言葉が無意味で空疎なものでしかないと感じ始めています。子どもたちは大人たちから毎日毎日競走馬のように鞭を入れられ、心を痛めているのです。
『二十四の瞳』の大石先生は少なくとも本の中では、こうした意味不明な言葉は決して発していません。家の仕事が忙しいからと言って学校へこれない子どものことを自分の職業的存在をかけて心配しています。子ども達の髪の毛が汚れているからなんとかしなければとバリカンやシラミ退治の薬の算段を真剣に考えているのです。毎日毎日を全体として見れば貧しい家庭のそれぞれの子どもたちの健康と将来を真剣に思いやっているのです。
ベンキョができるできないはまったく子どもの個性であると確信をもっていますから彼女が発することばは全て子ども個人との生活的な対話から成り立っているため、先生の全ての言葉が子どもたちの胸に響いてくるようです。集団としての子どもたちに号令をかけたり命令したりする場面は少なくとも本のなかでは一切ありません。戦争をはさんだ時代ですから、国の方から出されてくる標語が腐るほどあるのですが、大石先生はそれを嫌います。要領だけを教えるような標語的言葉を彼女はけっして子どもたちの前で口にしなかったのです。戦争遂行への先生の不信感はやがて村や学校の中で知られることになり、このことが原因で大石先生は教職を離れなければならなくなりました。
作者の壺井栄自身は高等小学校しか卒業していません。今の中学校です。その彼女が戦争遂行中の時勢という反面を除けば、幼年期に受けた学校教育を素材としてこれほどまでに教師と子どもたちの交流を肯定し賛歌しているということは、当時の学校教育が子どもたちの実感上、かけがえのない大切なものとして受容されていたことを示しているのです。この作品をもう少し深く読み込んでいけば標語的なものと生活的なものとの教育上の対立なども見えてきます。それはとりもなおさず大人と子ども、あるいは戦争と生活という対立であり、国家と庶民という対立でもありました。子どもの立場にたつか、大人の立場にたつのかという二分された苦悩を自覚する教師の物語であったと私は理解したのでした。壺井栄は主人公の教師を時勢に流される大人たちから、あくまで子どもを守る立場にたたせています。それを作品の中で一貫させていたのでした。
言葉が伝わるか伝わらないかという問題では木下順二さんの戯曲『夕鶴』の中に好例があります。いつか助けてやった鶴が恩返しをしようと、美しい女性「つう」に化身して「与ひょう」の元にやってきます。二人は夫婦となり、鶴の化身「つう」は自らの羽を引き抜いては布をおり生活を助けます。ある日、その反物が評判となり「与ひょう」のところに出入りしている仲買人がもっと沢山織れば、えらい金儲けができるぞと素朴な「与ひょう」にたらし込みます。「与ひょう」は「つう」にもっとたくさん布を織ってくれと頼みます。金を儲けて都に遊びにいくんだ、と言います。
けれど金の話になると「つう」にはその「与ひょう」の言葉がまったく通じなくなってしまうのです。知らない外国語でもきいているようにチンプンカンプンとなってしまいます。けれど「つう」は「与ひょう」が自分を好いてくれていることだけは確認できましたから、最後の愛をしめし、決して仕事をしているところを覗いていけないと言い置いてから自分の羽を引き抜いていきます。「つう」の存在を、もはやそのままのものとして受け取れなくなっている、いわば知恵という雑念を得た人間となってしまっていた「与ひょう」は「つう」との約束を破り障子を開け覗いてしまいました。こうして反物が織り上がると「つう」は元の鶴となって、約束を破った「与ひょう」から去っていってしまうのです。
職員室の前の廊下に書かれてあった一文は『夕鶴』の「つう」に伝わるでしょうか。残念ながら通じないでしょう。大石先生ならば決して口にしなかったろうと思うのです。こうした公式標語は子どもたちに届かないばかりでなく大人たちとの間のいっそうの断絶を予告しているようにしか思えないのです。先生方には酷な言い方かもしれませんが、私には戦争中に流された幾種類ものまがまがしいスローガンを読んでいるような気さえしたのでした。それらの標語は国家から庶民へという伝達システムの元に掲げられてはいたものの、実際に作用した事実では大人たちから子どもたちへと伝わったのであり、また男たちが女たちへ一方的に押しつけようとしていたものであったことは半世紀後の今日から見れば余りにあきらかです。
話がとても長くなりました。私は当学校のやはり登校できないでいるお子さまを持つ父母と連絡をとってみた結果、それぞれに情報を交換し励まし合うことができるならばと「親の会」を作りました。それで初の会合を三日後の日曜日に、この近くの会館で開きます。こうした問題で困っている方がありましたら是非ご参加ください。また皆さんの回りにそのような方がいらっしゃいましたら、チラシを持ってきておりますので知らせてあげてください。
-★-★-
だが私はこの草稿をついに内ポケットから取り出さなかった。当日そのまま読むことをしなかったのは深夜に書いた恋文のように、思いこみが一面的に過ぎ学校批判のみが主題となってしまっていたからである。また余りに長すぎてこの場にふさわしくなく、このままでは招かれざる講演者か演説家になってしまい父母にさえも嫌われそうな心配が出てきた。加えて重大な勘違いをしているらしいと気付いたからだ。草稿の中で鬼の首を取ったかのように指摘している職員室の廊下のボードは生徒会が使用するものとしてそこにあり、標語のように書かれていた一文は教師が書いたものではなく、生徒自身が書いたものではなかったかという疑問がわいてきたからだった。そう言えば大人の書いた字とは思えないような気もしてきたのである。
総会の後、それとなく確かめてみるとやはりそうだった。子どもが子どもに競争をあおっている内情が浮かんでくる。背後から子どもにそれを書かせているのは誰なのか。気をゆるめっぱなしのわが息子などは、学校の中では級友たちからでさえ排斥されかねないという思いが湧いてきて、いっそう背筋が寒くなるのであった。この日実際に私が発言したことは、不登校児童の全国的加速度的な増加は学校存在の危機・公教育の危機であり、とりもなおさず子どもたちの学習権の危機であること。不登校のこどもたちが毎日をどのように過ごしているか。大部分の子どもたちは家に閉じこもりがちでマンガやテレビゲームで時を過ごしていること。将来の見えない子どもを前にしての家族の混迷。一部の子どもは親たちによって運営されているフリースクール、フリースペースなどに通っているけれど、公的助成が全くなされていないため個人的負担が大変であること。最後に日時の差し迫っている私たちの会の宣伝を言うにとどめた。
さらに「校長先生の話では、一年で古くなるパソコンを今年度一新するとのことですが、私の息子はこうした恩恵にも全く無縁なのです」と釘をさしてもみた。だが「不登校の問題は単に学校や先生方を批判するだけではなんら解決の方向を示してはいないのです」と学校に対するゴマすりのようなことも付け加えてしまい、草稿の主題とは随分違った内容になってしまったのであった。三分ほどのスピーチだったが、私が着席するとすぐ補足しなければ立場がないと言わんばかりに校長が議長を無視して立ち上がった。
「○○さんが言うように」などと私の言葉を引用して追従し「不登校のこどもたちは一人一人その原因も状態も違い、学校としましても対応に苦慮しているところです。他の中学校ではだいたい十人以上の子どもが登校していないという状況ですが、幸いわが校は現在三人しかいません」と、予想に反して柔らかかった私の話に安心したのか、「わが校は周囲の学校に比べてみても、落ち着いたよい環境が出来上がりつつあると思われます」と締めくくった。だがそれは冒頭でのパソコン発言よりもさらに弁明的だった。私の上着の内ポケットには草稿とともに「不登校の親の会」の案内チラシが十枚ほどあったので、その一枚を隣の母親に「これです」と渡すと、前から後ろからと母親たちの手が伸びてきた。チラシは校長が話している間のうちになくなった。校長の頭上あたりに掲げてあった大きな丸い時計を見ると十五時五十五分だった。始まってから二十五分しか経っていない。こうして年一度の総会は閉じられた。意見を持って発言した者は校長の他には私だけだった。(記:1997/04/19)<9024字>