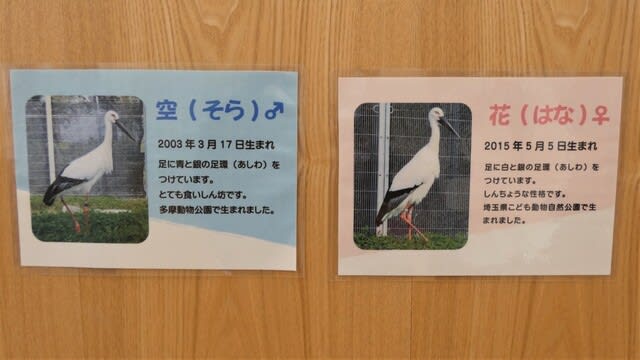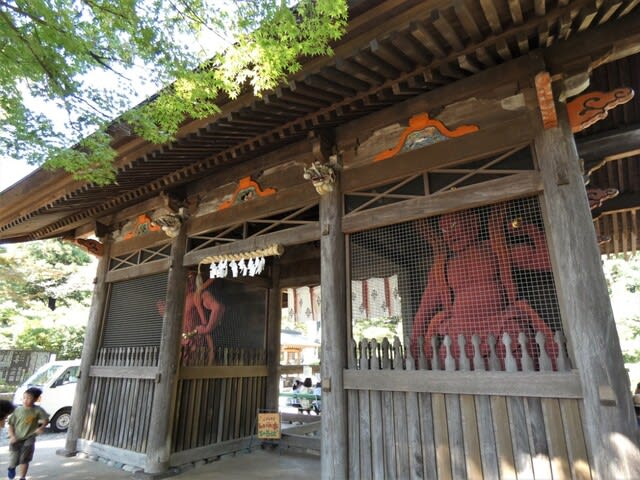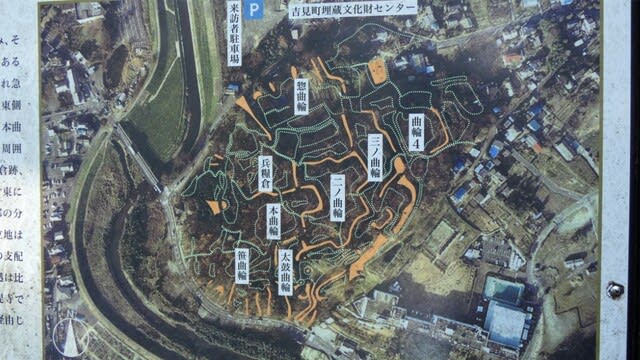10月28日(金)、埼玉県比企郡ときがわ町の「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」へ行く前に、同町の「雀川砂防ダム公園」と「三波渓谷」を見に行った。
◆雀川砂防ダム公園
雀川砂防ダムは、昭和63年(1998年)度に完成した重力式砂防ダム。完成後、ときがわ町(旧玉川村)により、雀川砂防ダム公園が整備された。公園は、周辺の自然環境に恵まれた緑豊かな山並みと雀川の清らかな水を生かし、かつ、その自然環境を保全することを目的として整備され、憩いの場として親しまれている。(埼玉県Webサイトより)
ここは初めて訪れる。川沿いの駐車場に着き、ダムに向かって歩いて進むと、広場があり、野外ステージもある。

右手には東屋、左手は川に降りる階段があり、親水公園の趣き。小さい子供でも川遊びができそう。

橋の上から上流をみると、砂防ダムの堤体が正面に。

近くまで行ってみる。どっしりとした大きいダム。高さは17mとのこと。

ダムの上にも駐車場があるというので車で移動する。天端は一人が歩ける程度の巾はある。

土砂がどれほど溜まっているのかは分からないが、水は満ちていた。遠く稜線の上にさいたま市のビル群が見えた。

ダムの下側を見降ろす。このダムのおかげで、相当な量の土砂を留めてくれそうだ。

“ダム”でイメージする貯水ダムは、全国で約3千基あるらしい。それに対して砂防ダムは約9万基あるとか。
砂防ダムは、山地の多い日本では、地方の川沿い・沢沿いに行けばけっこう見る機会はあるはずだが、多くは規模が小さいし気にも留めないだろうと思う。
雀川砂防ダムは、比較的街中に近いところにあるし、公園も併設しているので行きやすいスポットだ。せっかくなので、砂防ダム自体の事が解るような説明等があってほしいとも思う。
◆三波渓谷(さんばけいこく)
三波渓谷は「御荷鉾緑色岩」(みかぶりょくしょくがん)と呼ばれる緑色をした岩石からできている。この緑色の石が、群馬県藤岡市を流れる三波川付近で採掘される緑色の石(三波石)に似ている事から、この渓谷の名がついた。(町のWebサイト参照)
子供が幼い頃は、都幾川には何度も川遊びに行ったり川釣りもしていたので、当地にも一度立ち寄ったはずだが、あまり覚えてない。ただ、当時に比べると駐車場が広くなったことは間違いない。
駐車料金は環境整備費として料金ボックスに入れるようになっていたが、通年なのか時季によるのか分かり難かった。
駐車場の案内板では、渓谷に降りる階段が2か所示されていた。下りれば河原でつながっているのだろうと思い、近くの下流側の階段から下りる。階段・坂道はそれほど整備されていない。
狭い河原に降り立つ。川下の様子。

川上の様子。上流の方が川に起伏がある。階段と手すりがわずかに見えるが、あそこまで行けるのか?

水の流れはキレイだ。深いところは緑がかって見える。

途中、岩のトンネルをしゃがみながら通る。しかし、その先からは歩けるスペースが無かった。夏だったら、水の中に入るという選択も考えるだろうけど・・・。

仕方がないので、一旦戻って上流側の階段から再度下る。階段は整備されていた。河原は少し広い。

川下の様子。一人のライダーが、ティータイムを過ごしていた。

川上の様子。岩が張り出してよく見えない。夏だったら、ジャブジャブとさらに歩いて行くところだ。でも、夏は人が多いらしい・・・。

ひっそりと三波渓谷を楽しめた。