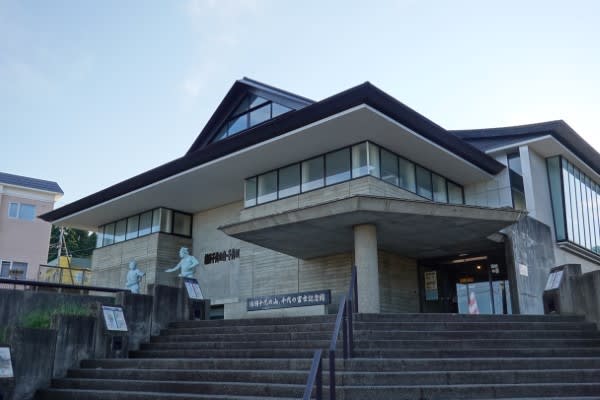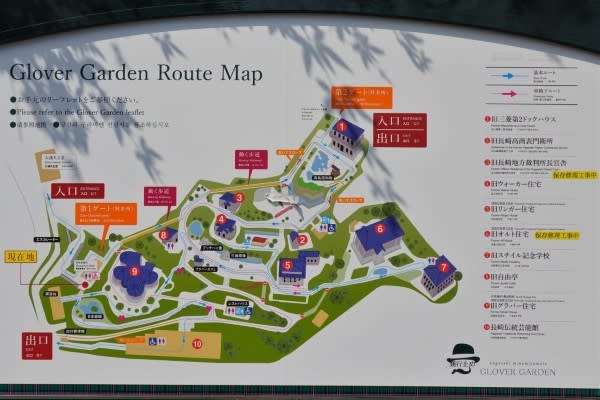〔前回からのつづき〕福山城(松前城)の他、北側の神社・お寺の方にも行ってみた。後日調べた事も含め記録しておく。
江戸時代、福山城の背後(北側)に位置する土地に15余の寺社が建ち並び寺町を形成していましたが、箱館戦争の戦火による焼失やその後の火災等によりその多くは現存しておらず、現在は、龍雲寺、阿吽寺、光善寺、法幢寺、法源寺のほか松前藩主松前家墓所が残り当時の面影を伝えています。(出典:函館・みなみ北海道観光ガイド)
福山城(松前城)の広場を挟んだ北側に松前神社があった。

松前藩の始祖である武田信廣公を祀る神社。明治14年に造られ、現在の神明造りの社殿は大正12年総ヒノキ造りで再建されたもの。

法源寺は1469年創建。本堂及び庫裡は、明治元年(1868)の箱館戦争で焼失したが(その後再建)、山門は戦火を免れた。

山門(国指定重要文化財)は江戸時代中期の建立とされ、道内最古の建造物の一つ。こけら葺の四脚門。

法幢寺は1490年創建。松前藩主の菩提寺。松前藩主松前家墓所が隣接する。

松前藩主松前家墓所は、松前藩の歴代藩主やその家族など55基のお墓がある。

石造りの霊廟が多く、北前船交易等により北陸地方からもたらされた笏谷石や御影石などが使われている。(国指定史跡)

龍雲院(国指定重要文化財)は1625年創建。箱館戦争で焼失を免れた唯一のお寺。

海上航行の安全を司る龍神を祀る龍神堂があるようだ。惣門にも龍がいた。

光善寺は1533年創建。後水尾天皇から山号と法衣を賜ったとされる。

境内には松前桜三大名木の1つで、桜の木の精にまつわる伝説が残る「血脈桜(けちみゃくざくら)」がある。栽培品種「マツマエハヤザキ(松前早咲)」、別名「ナデン(南殿)」の原木とのこと。

阿吽寺は少し離れているので諦め、福山城(松前城)を見た後は海に向かう。
なお、江戸時代末期に築城された松前城とその北側に広がる寺町は、明治以前の北海道の歴史を物語る文化財として、2004年に「福山城(松前城)と寺町」として北海道遺産に選定されている。“北海道”と聞いて思い浮かべることのない光景だけど、北海道の歴史の一端を担う貴重な処に思えた。
道の駅「北前船 松前」のテラスに「北前船と福山波止場」の案内があった。福山波止場は、もともと北前船が発着していた海岸に。松前城が解体された際の石垣を利用して1875(明治8)年までに造られた。

福山波止場は、東側の大松前波止場と西側の小松前波止場があり、岸から突堤が伸びている。下の画は、小松前波止場。遠くに津軽半島が見える。

日没となる頃合い。店の看板に照明。ふと見ればセイコーマートと趣きのある北洋銀行。これは北海道らしい光景だ。

そこそこ歩いて汗ばんだ。約1時間強の散歩は有意義だった。