英語の詩を日本語で
English Poetry in Japanese
Wordsworth, ("My heart leaps up . . . ")
ウィリアム・ワーズワース(1770-1850)
(「心が飛びあがる」)
心が飛びあがる、
空に虹を見ると。
そうだった、人生がはじまったときから。
そうである、大人になった今も。
そうあってほしい、年をとっても。
そうでなければ死んでもいい!
子どもは大人の父である。
わたしの日々が、過去から未来まで、
一日一日、自然を敬う心でつながることを切に願う。
* * *
William Wordsworth
("My heart leaps up. . . ")
My heart leaps up when I behold
A Rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a Man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die!
The Child is Father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.
* * *

By Takkk
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Rainbow_in_Budapest.jpg
* * *
以下、解釈例。
2 Rainbow
虹は、創世記9章(ノアの方舟のところ)では、神と人間の
和解と契約のシンボル。これが、あえてキリスト教的な
文脈から切り離されているところがポイント。

Joseph Anton Koch (1768–1839)
"Landschaft mit dem Dankopfer Noahs"
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Anton_Koch_006.jpg>
The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.
DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.
Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.
真ん中で虹を見あげているのがノア。動物たちが
みなオス/メスのペアになっていることに注目。
また、いちばん前で、子羊をいけにえにする準備を
していることに注目。(たぶん、その左の羊の
オスとメスの子。)
7 The Child is Father of the Man
人の生涯において、子どもの時期が大人の時期に
先行するということ。つまり、人は、自分より先に
生きてきた親やその他多くの人々から学ぶと同時に、
子どもの頃の自分の経験や感受性からも、
さまざまなことを学ぶ(べき)、ということ。
8 I could wish
もともとwishということばには、「見苦しいほど、
はしたないほど、強く望む、ほしがる」という
ニュアンスがあり、それを仮定法のcould(・・・・・・と
いっちゃっていいかも、くらいの意味)で弱めている
(OED 1)。
9 natural
下のような意味が混在していることば。
(さらにほかの意味の可能性も。上の訳では、
下のdを前面に出しています。)
a.
自然の状態(教育や宗教によって啓蒙されていないかたち)で
存在する (OED 4)
b.
自然によって形成される(OED 6)
c.
人/ものに本来備わっている(OED 8)
d.
自然に関係する/自然を対象とする(OED 18)
("Natural philosophy" というときなど)
8-9 my days to be / Bound each to each by natural piety
通常神に関して使う「敬虔」ということばを、
ここではあえて自然に対して用いている。
(7行目の "Father of the Man" ということばも、
「父なる神」などを連想させるが、それが神でなく
「子ども」というところも、ちょっとした逆説。)
「自然を敬う心で日々がつながる」、というのは、たとえば、
糸でビーズがつながるようなイメージ。
(キリスト教のロザリオが連想される。)
小さい頃、虹を見た時の感動を、今も、そして年老いてからも、
もちつづけていたい、幼少時から老年まで、心はずっと同じで
ありたい、ということ。

By Ricce
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosari_2.jpg>
ロザリオを使ってのお祈りは、カトリック的なものの
はずだが(正直よく知りません)、プロテスタント国
イギリスの詩にも、よくこれが登場する。たとえば
キーツの「憂鬱についてのオード」など。なぜ?
いずれにせよ、以上のように、この詩は、キリスト教的な
語彙やイメージを用いて、キリスト教的ではない内容を
語る作品であると思われる。
(ここから、下記のような議論がいろいろ出てくると
思いますが、作品そのものの楽しみとは無関係と
思われるので深入りしません。
a.
この詩においてワーズワースは、キリスト教ではなく
自然のほうがよい教え、といっている
b.
いや、実はaのように自然宗教的に見えて、実はキリスト教的
思考から逃れることができていない
c.
aとbの中間、あるいは両方、その他いろいろ)
* * *
以下、リズムの解釈例。

---
/: ストレスのある音節
x: ストレスのない音節
音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)
(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)
B: ビート、拍
(特にストレス・ミーターの詩において、ここで拍子をとると
四拍子のリズムに言葉がスムーズにのる、というところ。)
(B): 言葉をともなわないビート、拍
言葉(音節)はのっていないが、息継ぎの間のようなかたちで
ビートがあるところ。
---
基調はストレス・ミーター、四拍子にのるリズム。
B(ビート)のところで手をたたいたり、机をコツコツしながら、
声に出して読んでみてください。
この詩では、基調の四拍子に、さらにいくつか工夫が
重ねられています。
1-2
My heart leaps upとwhenからはじまる従属節の
あいだに自然に入る小休止を意識して読むと、次のように、
強音節のleapsにもビートがあるように感じられ、この四語が
本当に飛び跳ねているような雰囲気になるかと。
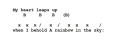
残されるwhenからskyまでは十音節、いわゆる弱強五歩格。
(厳密に x / x / x / x / x / となってなくても気にしない。
"x/" 5回というルールを厳密に守ってまともな詩を
書くことは無理。たとえば、Popeでも、そのようなことは
していない。)
つまり、My heart leaps upのところは、いわば
タテノリのパンクのようにジャンプするようなリズムで
(大げさですが)、when以降は、普通に語るような雰囲気。
(四拍子にのらない弱強五歩格は、歌と散文の中間のリズム。
この点でまさに「詩」のリズムといえるかも。)
6
人生半ばで死ぬ、という内容にあわせて、行が途中で
プツッと切られている。
8-9
四拍子2行が9行目のBoundで、つまり、まさに
「つなげられて」という意味のことばでつながっている。
加えて、この二行は行またがりによってもつなげられている。
(8行目末にコンマなどのパンクチュエーションが、つまり
音読時の息継ぎがない。)
さらに、この二行はbeとBoundの子音 /b/ に
よってもつなげられている。
つまり、「わたしの日々が、一日一日、自然を敬う心で
つながるように」という内容が、音の連続や行の組み方に
よって多重的に補強されている。
(Be動詞には通常ストレスがないので、beとBoundは、
厳密には頭韻alliterationをなしているとはいえない、
とか、修辞学的/詩作法的に面倒な議論になりますので、
頭韻などの用語は使いません。)
(上のスキャンジョンでは、beにビートを見る場合と
見ない場合を併記しました。前者の場合、この二行は
4ビート + Bound + 4ビート、後者の場合は
4ビート + 4ビート、となります。)
9
Bound以降、リズムが強調的で遅い下降調
(強弱格/強弱弱)に変化している。特に、natural
piety(強弱弱/強弱弱)のエンディングには、ゆっくり、
静かに、ある意味、思いに浸るような雰囲気で
終わるような印象があるかと。
* * *
詩のリズムについては、以下がおすすめです。
ストレス・ミーターについて
Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)
古典韻律系
Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.
(New York, 1979)
その他
Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays
(Princeton, 1957) 251ff.
(後日ページを追記します。和訳もあります。)
Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"
Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):
580-94
The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics
(Princeton, 1993)
(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも
古典韻律系の解説があります。)
* * *
英文テクストは、William Wordsworth, Poems,
in Two Volumes, vol. 2 (1807) より
<http://www.gutenberg.org/ebooks/8824>
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
(「心が飛びあがる」)
心が飛びあがる、
空に虹を見ると。
そうだった、人生がはじまったときから。
そうである、大人になった今も。
そうあってほしい、年をとっても。
そうでなければ死んでもいい!
子どもは大人の父である。
わたしの日々が、過去から未来まで、
一日一日、自然を敬う心でつながることを切に願う。
* * *
William Wordsworth
("My heart leaps up. . . ")
My heart leaps up when I behold
A Rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a Man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die!
The Child is Father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.
* * *

By Takkk
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Rainbow_in_Budapest.jpg
* * *
以下、解釈例。
2 Rainbow
虹は、創世記9章(ノアの方舟のところ)では、神と人間の
和解と契約のシンボル。これが、あえてキリスト教的な
文脈から切り離されているところがポイント。

Joseph Anton Koch (1768–1839)
"Landschaft mit dem Dankopfer Noahs"
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Anton_Koch_006.jpg>
The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.
DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.
Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.
真ん中で虹を見あげているのがノア。動物たちが
みなオス/メスのペアになっていることに注目。
また、いちばん前で、子羊をいけにえにする準備を
していることに注目。(たぶん、その左の羊の
オスとメスの子。)
7 The Child is Father of the Man
人の生涯において、子どもの時期が大人の時期に
先行するということ。つまり、人は、自分より先に
生きてきた親やその他多くの人々から学ぶと同時に、
子どもの頃の自分の経験や感受性からも、
さまざまなことを学ぶ(べき)、ということ。
8 I could wish
もともとwishということばには、「見苦しいほど、
はしたないほど、強く望む、ほしがる」という
ニュアンスがあり、それを仮定法のcould(・・・・・・と
いっちゃっていいかも、くらいの意味)で弱めている
(OED 1)。
9 natural
下のような意味が混在していることば。
(さらにほかの意味の可能性も。上の訳では、
下のdを前面に出しています。)
a.
自然の状態(教育や宗教によって啓蒙されていないかたち)で
存在する (OED 4)
b.
自然によって形成される(OED 6)
c.
人/ものに本来備わっている(OED 8)
d.
自然に関係する/自然を対象とする(OED 18)
("Natural philosophy" というときなど)
8-9 my days to be / Bound each to each by natural piety
通常神に関して使う「敬虔」ということばを、
ここではあえて自然に対して用いている。
(7行目の "Father of the Man" ということばも、
「父なる神」などを連想させるが、それが神でなく
「子ども」というところも、ちょっとした逆説。)
「自然を敬う心で日々がつながる」、というのは、たとえば、
糸でビーズがつながるようなイメージ。
(キリスト教のロザリオが連想される。)
小さい頃、虹を見た時の感動を、今も、そして年老いてからも、
もちつづけていたい、幼少時から老年まで、心はずっと同じで
ありたい、ということ。

By Ricce
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosari_2.jpg>
ロザリオを使ってのお祈りは、カトリック的なものの
はずだが(正直よく知りません)、プロテスタント国
イギリスの詩にも、よくこれが登場する。たとえば
キーツの「憂鬱についてのオード」など。なぜ?
いずれにせよ、以上のように、この詩は、キリスト教的な
語彙やイメージを用いて、キリスト教的ではない内容を
語る作品であると思われる。
(ここから、下記のような議論がいろいろ出てくると
思いますが、作品そのものの楽しみとは無関係と
思われるので深入りしません。
a.
この詩においてワーズワースは、キリスト教ではなく
自然のほうがよい教え、といっている
b.
いや、実はaのように自然宗教的に見えて、実はキリスト教的
思考から逃れることができていない
c.
aとbの中間、あるいは両方、その他いろいろ)
* * *
以下、リズムの解釈例。

---
/: ストレスのある音節
x: ストレスのない音節
音節: 母音ひとつ + 前後に付随する子音(群)
(長母音、二重母音も基本的に母音ひとつと数える。)
B: ビート、拍
(特にストレス・ミーターの詩において、ここで拍子をとると
四拍子のリズムに言葉がスムーズにのる、というところ。)
(B): 言葉をともなわないビート、拍
言葉(音節)はのっていないが、息継ぎの間のようなかたちで
ビートがあるところ。
---
基調はストレス・ミーター、四拍子にのるリズム。
B(ビート)のところで手をたたいたり、机をコツコツしながら、
声に出して読んでみてください。
この詩では、基調の四拍子に、さらにいくつか工夫が
重ねられています。
1-2
My heart leaps upとwhenからはじまる従属節の
あいだに自然に入る小休止を意識して読むと、次のように、
強音節のleapsにもビートがあるように感じられ、この四語が
本当に飛び跳ねているような雰囲気になるかと。
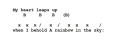
残されるwhenからskyまでは十音節、いわゆる弱強五歩格。
(厳密に x / x / x / x / x / となってなくても気にしない。
"x/" 5回というルールを厳密に守ってまともな詩を
書くことは無理。たとえば、Popeでも、そのようなことは
していない。)
つまり、My heart leaps upのところは、いわば
タテノリのパンクのようにジャンプするようなリズムで
(大げさですが)、when以降は、普通に語るような雰囲気。
(四拍子にのらない弱強五歩格は、歌と散文の中間のリズム。
この点でまさに「詩」のリズムといえるかも。)
6
人生半ばで死ぬ、という内容にあわせて、行が途中で
プツッと切られている。
8-9
四拍子2行が9行目のBoundで、つまり、まさに
「つなげられて」という意味のことばでつながっている。
加えて、この二行は行またがりによってもつなげられている。
(8行目末にコンマなどのパンクチュエーションが、つまり
音読時の息継ぎがない。)
さらに、この二行はbeとBoundの子音 /b/ に
よってもつなげられている。
つまり、「わたしの日々が、一日一日、自然を敬う心で
つながるように」という内容が、音の連続や行の組み方に
よって多重的に補強されている。
(Be動詞には通常ストレスがないので、beとBoundは、
厳密には頭韻alliterationをなしているとはいえない、
とか、修辞学的/詩作法的に面倒な議論になりますので、
頭韻などの用語は使いません。)
(上のスキャンジョンでは、beにビートを見る場合と
見ない場合を併記しました。前者の場合、この二行は
4ビート + Bound + 4ビート、後者の場合は
4ビート + 4ビート、となります。)
9
Bound以降、リズムが強調的で遅い下降調
(強弱格/強弱弱)に変化している。特に、natural
piety(強弱弱/強弱弱)のエンディングには、ゆっくり、
静かに、ある意味、思いに浸るような雰囲気で
終わるような印象があるかと。
* * *
詩のリズムについては、以下がおすすめです。
ストレス・ミーターについて
Derek Attridge, Poetic Rhythm (Cambridge, 1995)
古典韻律系
Paul Fussell, Poetic Meter and Poetic Form, Rev. ed.
(New York, 1979)
その他
Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays
(Princeton, 1957) 251ff.
(後日ページを追記します。和訳もあります。)
Joseph Malof, "The Native Rhythm of English Meters,"
Texas Studies in Literature and Language 5 (1964):
580-94
The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics
(Princeton, 1993)
(日本語で書かれたイギリス詩の入門書、解説書の多くにも
古典韻律系の解説があります。)
* * *
英文テクストは、William Wordsworth, Poems,
in Two Volumes, vol. 2 (1807) より
<http://www.gutenberg.org/ebooks/8824>
* * *
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を参照する際には、
このサイトのタイトル、URL, 閲覧日など必要な事項を必ず記し、
剽窃行為のないようにしてください。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « Waller, "Go, ... | Eliot, TS, "L... » |