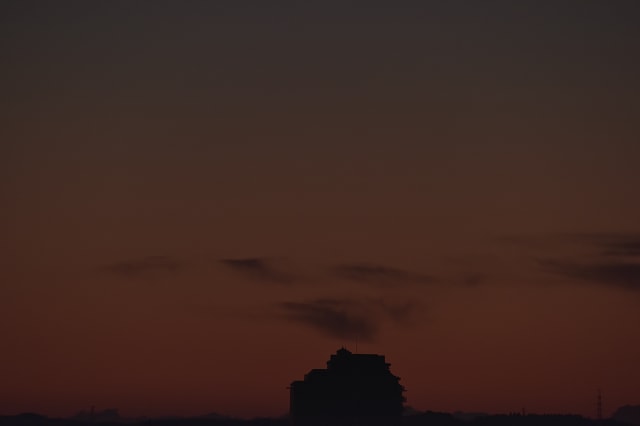1月9日は2024年最初の月と惑星の接近「有明の月と水星、金星、アンタレスの競演」が見られる日なので気合いを入れて早起き観望をしてきました~。今朝は寒かった~。マイナス5度でした。
1月9日は2024年最初の月と惑星の接近「有明の月と水星、金星、アンタレスの競演」が見られる日なので気合いを入れて早起き観望をしてきました~。今朝は寒かった~。マイナス5度でした。
本日の月出時刻は04時40分、金星出が4時13分です。観望地に着くとすでに月が昇っていましたが、あらら~、雲がありますね。金星もにじんでいて、アンタレスは眼視では…う~む、見えませんね。
本日のファーストショット!(写真ではアンタレスが写っていました~)

2024/1/9 05h07m27s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 f150mm ISO1600 F5 1/2sec
水星が昇ってくるのを待って撮影した写真がこちら… 全体的に雲だらけです。

2024/1/9 05h17m41s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO1600 f58mm F4.5 2.5sec
水星出の時刻は05時11分ですがカメラが水星を捉えたのは15分過ぎ(高度0.4°)でした。

2024/1/9 05h17m53s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO1600 f46mm F4.5 2.5sec
空が晴れることを期待したのですが低層の雲は厚くなる一方です。トホホ…

2024/1/9 05h36m45s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO1600 f50mm F7.1 1.6sec
さそり座のあたまは見えているのですが、水星はついに姿を消しました!

2024/1/9 05h42m45s D810A NIKON VR24-70mm f/2.8 ISO1600 f38mm F7.1 1sec
ということでレンズを望遠にして金星と月とアンタレスのスリーショットを撮ろうとしばらく待ったのですが、アンタレスを隠している帯状の雲が動かなくて結局撮影できませんでした。

2024/1/9 05h55m10s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 ISO1600 f150mm F7.1 1/4sec
おっと、ここで撮影対象を火星にチェン~ジです。明日は「新月前日の月と水星、火星の接近」が見られる日ですが、東空の明るさを見ると光度1.4等の火星を目視するのはやはりムリのようです。
明日のシミュレーションとして火星が写るのかテスト撮影をしてみましょう。すでに時刻は火星出の時刻(05時57分)を過ぎています。急ぎましょう!
で、何枚か撮影したのですが写っていたのはファーストショットのこちらだけでした。ほかの写真は雲で減光されてかすかに位置が分かる程度のものでした。こちらの画像の火星高度は0.9°です。

2024/1/9 06h06m33s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 ISO1600 f220mm F7.1 1/3sec
雲さえ無ければ火星は写るようですね。このあとも雲が切れることはなく、月も見えなくなったので撮影会は終了~、機材を撤収して帰宅しました。
こちらは帰宅後に撮影した月(月齢26.9)と金星です。

2024/1/9 06h37m10s D810A SIGMA150-600mm f5-6.3 ISO400 f210mm F5.6 1/80sec
さ~て、明日は「新月前日の月と水星、火星の接近」です。仙台では月出が05時49分、火星出が05時56分です。透明度が良ければ撮影はできると思うのですが、天気はあまり良くないようです。
空の透明度が良ければ撮影は十分可能ですが、空の明るさを考えると撮影可能時間は火星出から10分程度です。かなり難易度の高いイベントですが天気の具合を見てチャレンジすることにしましょう。

 1月10日「新月前日の月と水星、火星の接近」〈2023年12月1日のブログより再掲〉
1月10日「新月前日の月と水星、火星の接近」〈2023年12月1日のブログより再掲〉
1月10日は新月前日の月と水星、火星が薄明の空でトライアングルを描く。新月前日だが輝面比が0.04あるので見つけるのは思ったほど難しくない。水星もマイナス等級なので問題ないが火星を眼視で見つけるのはほぼムリだろう。双眼鏡または撮影画像で検出できればラッキーと言ったところだ。2024年の火星は2025年1月の小接近(-1.4等)に向けて明るくなっていくのでその変化を楽しみたい。