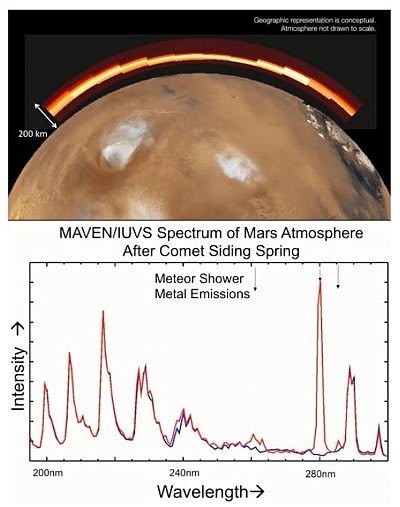昨日の月齢1.0の月撮影ミッション終了後…、
12月31日に近日点を通過する45P/本田・ムルコス・パジュサコバ周期彗星の撮影にもチャレンジしてみました。本日の薄明終了時刻は18時00分、その時点での45P周期彗星の高度はわずかに8.7°です。か~なり厳しい条件です。
ただいまの時刻は17時30分、空はまだ青みが残っていますが撮影してみましょう。
45Pはやぎ座のど真ん中にいます。金星からファインダーで星を辿って導入することにしましょう。
45Pファーストショット

2016.12.30 17:26-28(4枚コンポジット 露出55sec) SE200N D90 ISO1000
ふ~む、尾が画角からはみ出しています。写っている尾は20分程度ですがかなり伸びているようです。
上記写真を撮影した範囲はこちら(ステラナビゲーター10)
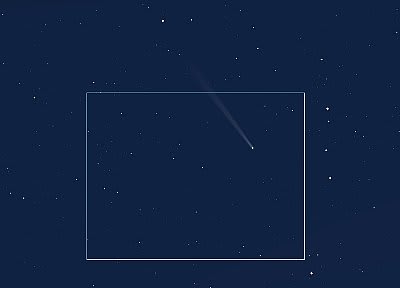
月撮影の直後なので北極星での極軸合わせをまだしていません。ピントも目分量だったのですが、
ピントだけは上記写真撮影後にバーティノフマスクであわせました。時間の都合上、極軸はそのままです。
近日点通過1日前の45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星

2016.12.30 17:47(2枚コンポジット 露出40sec) SE200N D90 ISO1600 トリミング
日心距離 0.53291 au、地心距離 0.72918 au
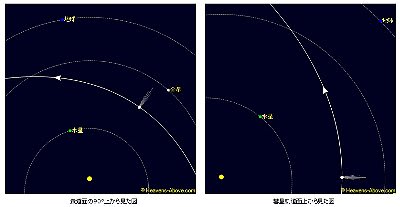
雲が流れてくるようになり、撮影は何度も中断です。ふう~。
彗星の高度も10°を切ったので、そろそろ本日の撮影会は終了のようです。
本日のラストショット

2016.12.30 17:50&17:59(2枚コンポジット 露出50sec) SE200N D90 ISO1600
45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星は近日点通過後、2月上旬に明け方の空に戻ってきます。
日心距離は 1auほどに遠ざかりますが、地心距離は 0.08auまで近づきます。撮影好期は
2月8日~13日ごろかな。肉眼彗星になるほど明るくはありませんが、7等級まで明るくなる
予想も出ていますので期待しましょう。
さ~て、今年もあと5時間となりました。来年はどんな天体現象が見られるでしょうか。
来年もたま~にアップしていきますので、時間があるときにお寄りいただければ幸いです。
今年も、このブログを見てくださった みなさん、本当にありがとうございました。
それでは皆さん、よいお年を~!
12月31日に近日点を通過する45P/本田・ムルコス・パジュサコバ周期彗星の撮影にもチャレンジしてみました。本日の薄明終了時刻は18時00分、その時点での45P周期彗星の高度はわずかに8.7°です。か~なり厳しい条件です。
ただいまの時刻は17時30分、空はまだ青みが残っていますが撮影してみましょう。
45Pはやぎ座のど真ん中にいます。金星からファインダーで星を辿って導入することにしましょう。
45Pファーストショット

2016.12.30 17:26-28(4枚コンポジット 露出55sec) SE200N D90 ISO1000
ふ~む、尾が画角からはみ出しています。写っている尾は20分程度ですがかなり伸びているようです。
上記写真を撮影した範囲はこちら(ステラナビゲーター10)
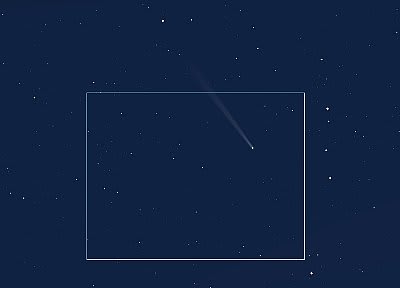
月撮影の直後なので北極星での極軸合わせをまだしていません。ピントも目分量だったのですが、
ピントだけは上記写真撮影後にバーティノフマスクであわせました。時間の都合上、極軸はそのままです。
近日点通過1日前の45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星

2016.12.30 17:47(2枚コンポジット 露出40sec) SE200N D90 ISO1600 トリミング
日心距離 0.53291 au、地心距離 0.72918 au
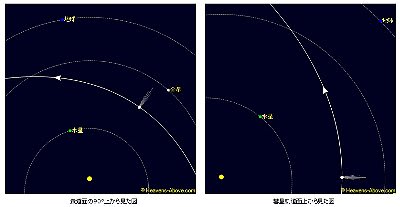
雲が流れてくるようになり、撮影は何度も中断です。ふう~。
彗星の高度も10°を切ったので、そろそろ本日の撮影会は終了のようです。
本日のラストショット

2016.12.30 17:50&17:59(2枚コンポジット 露出50sec) SE200N D90 ISO1600
45P/本田・ムルコス・パジュサコバ彗星は近日点通過後、2月上旬に明け方の空に戻ってきます。
日心距離は 1auほどに遠ざかりますが、地心距離は 0.08auまで近づきます。撮影好期は
2月8日~13日ごろかな。肉眼彗星になるほど明るくはありませんが、7等級まで明るくなる
予想も出ていますので期待しましょう。
さ~て、今年もあと5時間となりました。来年はどんな天体現象が見られるでしょうか。
来年もたま~にアップしていきますので、時間があるときにお寄りいただければ幸いです。
今年も、このブログを見てくださった みなさん、本当にありがとうございました。
それでは皆さん、よいお年を~!












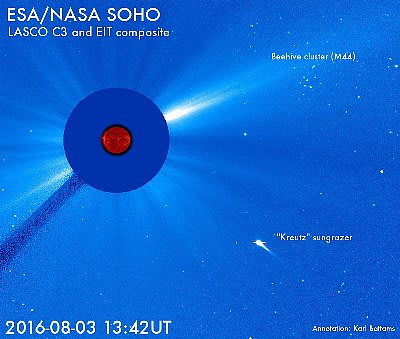
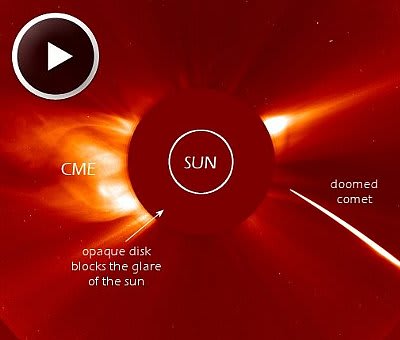






































 ~
~