 金星が最大光度(-4.9等)に達した2月15日に白昼の金星が見えるかウオッチングしてみました~。
金星が最大光度(-4.9等)に達した2月15日に白昼の金星が見えるかウオッチングしてみました~。
気になる天気ですが… 県内の鉄道網の多くを計画運休にさせた二日連続の強風もおさまって朝から雲ひとつ無い快晴になりました。気温も上昇して春のような体感です。
ファースト観望タイムは12時を少し過ぎた頃… この時の金星は南東の空、高度50°付近にあります。まずは双眼鏡で捜索です。ふむ、ありました。さすが最大光度です。クッキリ見えます。
しか~し、肉眼では目をこらしてもまったく見えません。ま、これは想定内です。肉眼で見える金星チャレンジは金星が南中する14時13分以降とふんでいるので、ここでは昼間の金星拡大撮影です。
惑星カメラを装着したμ210を自動導入で金星に向けてファインダーで微調整をして PCモニター見ると… ほひょ、金星がいません。ファインダーの十字線の中心に金星はいるのですが… なぜ?
しかたないので25mm十字線入りアイピースに交換して金星を導入です。ずいぶんズレたところにいるなぁ~と不思議に思いながらファインダーを覗くと… え!? ファインダーが大きくズレてます!
なぜだ?… あ、あれだ… 先日、望遠鏡撤去の時にファインダーをコツンとぶつけたのですが、μ210のファインダーは望遠鏡の把手にもなっているので少々ぶつけたくらいではズレるはずないよね~という正常バイアスが働いてそのままにしていたやつだ。ガックリです。
結局、ファインダー修正に1時間ちょっとかかりました。トホホです。 そんなこんなでやっとPCモニターに映った金星は、なんとブルブル震えていて最悪の気流です。まさに踏んだり蹴ったりです。
 最大光度の金星(-4.9等、輝面比0.271、視直径39".3)
最大光度の金星(-4.9等、輝面比0.271、視直径39".3)
2025/2/15 14h01m μ210+WREYMER PLAN 5×+TCA-4+Apollo-C(UV/IRcut) FocalLength=7000mm (F/30)
Shutter=0.401ms Gain=350 (72%) Duration=20s AS!3.25% of 6545frames
ふう、ここは気を取り直して肉眼で青空の中の金星が見えるかチャレンジしましょう。2回目の観望タイムは金星が南中した直後で日没2時間前の14時15分と思っていたのでちょうどいい時間です。
まず、双眼鏡で金星の位置を確かめて、そこから双眼鏡をそっとずらして肉眼で青空の中の金星を探します… う~む、見えません。あの場所にあるはずですが… 何度やっても見えません。
ここで双眼鏡を7×50から3×50にチェンジです。ふむ、3倍でもしっかり見えます。ここで双眼鏡から目をはずして青空を見ると… あれ~、やっぱり見えません。なぜ~? 透明度が悪い?
たしかに、いわゆる抜けの悪い空ではあります… 14時35分まで粘りましたが肉眼では見えませんでした。仕方ないです。日没1時間前の3rd観望時刻16時15分に賭けましょう!
で、時刻はあっという間に16時15分です。双眼鏡で見るこの時間の金星はギラギラしてます。太陽高度は10°です。さっそく双眼鏡から視線を外すと… あら、くっきりはっきり金星が見えます。
青空の中に白い点像の星がポツンと浮いている姿は何度見ても不思議な感じがします。それにしてもこの40分間でこうも変わるかね~と思えるクリアな見え方です。
 焦点距離600mmの望遠で撮った金星は五日月のような形で写っていました。
焦点距離600mmの望遠で撮った金星は五日月のような形で写っていました。
現在宵の明星として輝いている金星は、3月21日に内合を迎えたあと3月末頃から明けの明星として東の空で輝き始めます。それから1か月後の4月27日に明けの明星としての最大光度(-4.8等)を迎えます。
日の出時の高度は20°ほどで、南中時でも52°とやや低めですが青空の中で見えるのか再度チャレンジしてみることにしましょう!













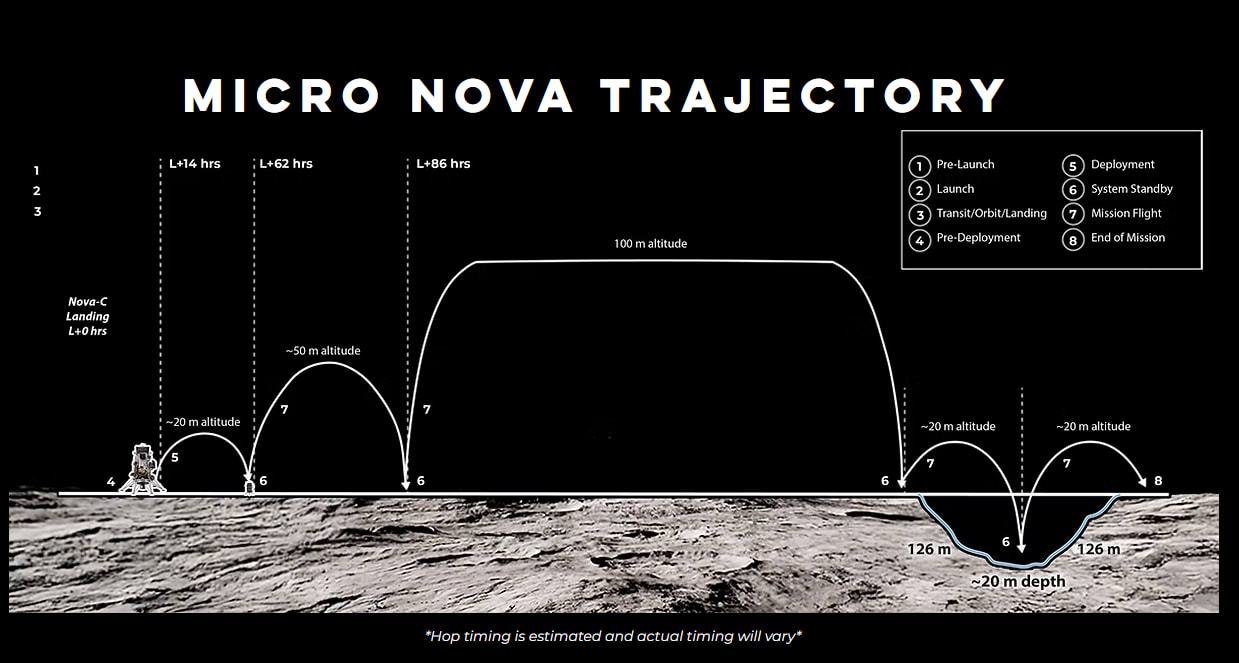


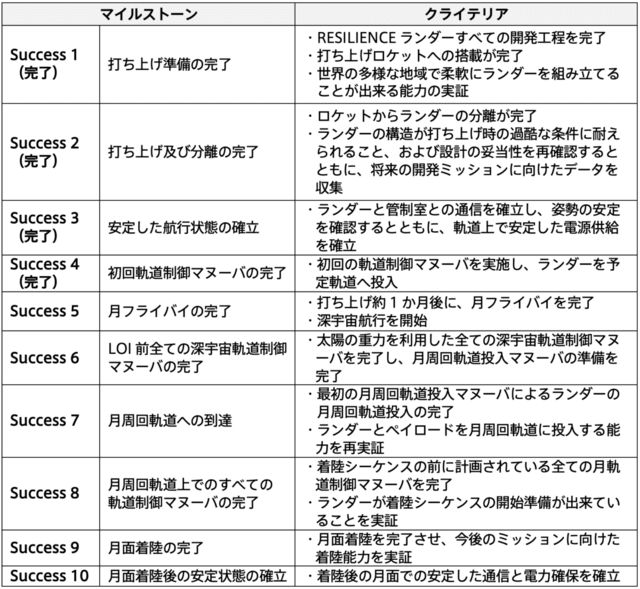

































 こちらはオリジナル1枚元画像です。撮影時の火星暦は4月22日なのでまだまだ北極冠(北極フード)が大きいですね。北極の雲が消えて小さくなった北極が見えるのは火星の夏至(2025/5/30)の頃ですがその時の視直径は5".6です。気流はいい時期なので天気次第では撮影できそうですね
こちらはオリジナル1枚元画像です。撮影時の火星暦は4月22日なのでまだまだ北極冠(北極フード)が大きいですね。北極の雲が消えて小さくなった北極が見えるのは火星の夏至(2025/5/30)の頃ですがその時の視直径は5".6です。気流はいい時期なので天気次第では撮影できそうですね 



