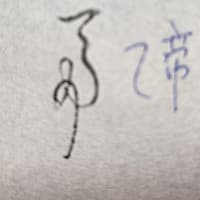昨日は水曜稽古だがブログも書けず
ねてしまった
木曜稽古
松波資之のほととぎすの和歌を掛ける
湖遠郭公
遊山
から崎の
まつとはなしに
ほととぎす
ききつるばかり
うれしきはなし
松波資之マツナミスケユキ
1831*-1906
幕末-明治時代の歌人。
天保元年12月19日生まれ。
安芸広島の商人岡田集介の次男。
京都徳大寺家につかえ,
のち北面の武士松波家の養子となる。
香川景樹にまなび,
景樹没後はその子の景恒をたすけて
東塢塾を主宰。
維新後は皇太后宮の内舎人ウドネリ,
雑掌をつとめた。
明治39年9月13日死去。
77歳。
通称は直三郎,大学大允。
号は遊山,随所。
歌集に「花仙堂家集」。
(日本人名大辞典ヨリ)
唐崎というと
近江八景の「唐崎夜雨」を思い浮かべる
唐崎は
『万葉集』の
「さざなみの志賀の辛崎幸あれど大宮人の船待ちかねつ」
『蜻蛉日記』では
都人が唐崎へ祓ハライに向かう様子が描かれている。
『枕草子』では
「崎は唐崎、三保が崎」
近江八景では唐崎夜雨といわれる
芭蕉の俳句に
「唐崎の松は花より朧にて」
唐崎は松が有名とか
唐崎のまつとはなしに
と
掛詞になっている
近江八景を読みこんだ
という大田南畝の狂歌があった
乗セタ カラ サキはアワズ カ タダの駕籠 ヒラ イシヤマ ヤ ハセらしてミイ
勢多夕照 -唐崎夜雨 -粟津晴嵐 -堅田落雁 - 比良暮雪 -石山秋月 -矢橋帰帆 - 三井晩鐘 -
だとか
覚えられるか