●人間の尊厳
世界人権宣言は、第1条に「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と記す。また「宣言」を具体化した国際人権規約は、人権を「人間の固有の尊厳」に由来するものとしている。自由権規約は次のように始まる。
「この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、……」
この項で言及したいのは、人間の「尊厳」についてである。「尊厳」は、英語dignityの訳語である。dignity の原義は「価値のあること」。そこから「尊さ、尊厳、価値、貴重さ」などを意味する。「尊厳」という漢語については、「広辞苑」は「とうとくおごそかで、おかしがたいこと」と解説している。
では、なぜ人間には尊厳、言い換えれば価値があるのか。実は、世界人権宣言は、人間の尊厳を謳いながら、その尊厳について具体的に書いていない。それ以降の国際人権規約や各種国際人権条約も、同様である。その状態で、国際人権文書は、人間の尊厳という価値観の上に、人権の体系を組み立てている。そして、世界の大多数の国々がその文書に賛同し、参加している。これは奇妙な状態である、と言わねばならない。
世界人権宣言や国際人権規約は、現在世界的に広く受け入れられている文書である。その文書に人間の尊厳について具体的に書かれていない。そのため、人類は、なぜ人間は尊厳を持つのか、その価値の根拠は何か、という問いに対し、まだ文化・文明・宗教・思想の違いを超えて広く受け入れられる回答を持つに至っていない。哲学、法学、政治学、人類学等において、さまざまな議論がされてきたが、まだ世界的な定説はない。世界共通の認識を確立できていないのである。
私は、人間の尊厳という観念の背景には、キリスト教及びカントの哲学があると思う。近代西欧から世界に広がった人権の観念のもとにあるのは、ユダヤ=キリスト教の教義である。ユダヤ民族が生み出した宗教では、人間は神(ヤーウェ)が創造したものであると教える。神が偉大であるゆえに、神の被造物である人間は尊厳を持つ。しかも、人間は神の似姿として造られたとされる。人間は他の生物とは異なる存在であり、地上のすべてを支配すべきものとされる。
ユダヤ教から生まれたキリスト教は、ローマ帝国の国教となり、近代西洋文明の一要素となった。人間の尊厳という観念は、キリスト教の神学に、受け継がれてきた。教父アウグスティヌスやトマス・アクイナスは、著書に人間の尊厳という観念を表している。彼らの思想は、古いようでいて、決して過去の遺物ではない。21世紀の現代においても、カトリックを中心として、信心深いキリスト教徒に、基本的な世界観・価値観を与えているからである。そこでは、人間の理性は、キリスト教的な全知全能の神の英知を、不完全な形で分有したものとされる。この観念がキリスト教神学にとまるものであったなら、非キリスト教社会に広がることはなかっただろう。キリスト教を信じない者には、そもそも人間は神(ヤーウェ)の被造物という考えは認められない。私は、人間の尊厳という観念が非キリスト教社会に受け入れられるものとなったのは、カントの哲学によるところが大きいと考える。
私は先に、ロックの思想は17世紀以降、この21世紀まで、世界に甚大な影響を与えており、その重要性は、マルクスやニーチェやフロイトの比ではないと書いた。ロックの思想が世界に広まり、そのうえにカントの哲学が浸透している。象徴的に言えば、ロック=カント的な人間観が今日の世界に普及した人間観のもとにあると見ることができる。ロック=カント的な人間観とは、人間は、生まれながらに自由かつ平等であり、個人の意識とともに、理性に従って道徳的な実践を行う自律的な人格を持つ、という人間観である。
カントは、18世紀西欧の「啓蒙の世紀」を代表する哲学者であり、アメリカ独立戦争やフランス革命を同時代として生きた。西欧では、天動説から地動説への転回をきっかけに、中世的な世界観が大きく揺らいだ。カントは、科学と道徳の両立を図って、宗教の独自性を認め、科学的理性的な認識の範囲と限界を定めつつ、神・霊魂・来世という形而上的なものを志向する人間の人間性を肯定し、理性に従って道徳的な実践を行う自由で自律的な人格を持つ者としての人間の尊厳を説いた。
このようにカントは、人間の尊厳を伝統的なキリスト教の教義から離れて、近代的な哲学によって意味づけ直した。それによって、人間の尊厳という観念は、世俗化の進む西欧社会でも維持され、同時に非キリスト教社会にも伝播し得るものとなった。その観念は、今も世界に広まりつつある。
ところが、その一方、大元の欧米では、19世紀半ば、ダーウィンの進化論が登場し、人間は神が創造したものではなく、猿から進化したものだという理論が広まった。また、西洋とキリスト教の歴史と現状を考察したニーチェが、「神は死んだ」と言い、ニヒリズムの到来を予言した。こうして、キリスト教的な神の存在を疑ったり、否定したりする思想が社会に影響を及ぼすようになった。ここで、仮に神という超越的な観念を排除すれば、そこには、人間の尊厳という観念のみが残ることになる。
近代西欧には、科学技術の発達によって、人間は宇宙のすべてを知り、自然を支配することが可能だという考えが、早くから存在した。16世紀後半のフランシス・ベーコンに始まって、ホッブス、サン・シモン、コント等が主張してきた。18世紀以降、こうした科学万能の思想が影響力を強めていった。19世紀後半から20世紀へと進むに従って、欧米では人間の理性への過信や傲りが高じた。とりわけ二度にわたる世界大戦、そして核兵器の登場は、科学と理性について、深刻な反省を要する出来事だった。
だが、非キリスト教社会は、近代西洋文明が直面している根本問題を徹底的に議論することなく、人間の尊厳という観念を受け入れ、国連憲章や世界人権宣言に賛同・参加してきている。世界の大多数の国々が西欧における近代化の成果、すなわち科学技術や資本主義、主権国家や合理主義等を摂取するのと同時に、人権という観念を輸入したのである。そして、人間の尊厳という観念は、深く検討されることなく、21世紀においても時が経過し続けているのである。
次回に続く。
世界人権宣言は、第1条に「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と記す。また「宣言」を具体化した国際人権規約は、人権を「人間の固有の尊厳」に由来するものとしている。自由権規約は次のように始まる。
「この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、……」
この項で言及したいのは、人間の「尊厳」についてである。「尊厳」は、英語dignityの訳語である。dignity の原義は「価値のあること」。そこから「尊さ、尊厳、価値、貴重さ」などを意味する。「尊厳」という漢語については、「広辞苑」は「とうとくおごそかで、おかしがたいこと」と解説している。
では、なぜ人間には尊厳、言い換えれば価値があるのか。実は、世界人権宣言は、人間の尊厳を謳いながら、その尊厳について具体的に書いていない。それ以降の国際人権規約や各種国際人権条約も、同様である。その状態で、国際人権文書は、人間の尊厳という価値観の上に、人権の体系を組み立てている。そして、世界の大多数の国々がその文書に賛同し、参加している。これは奇妙な状態である、と言わねばならない。
世界人権宣言や国際人権規約は、現在世界的に広く受け入れられている文書である。その文書に人間の尊厳について具体的に書かれていない。そのため、人類は、なぜ人間は尊厳を持つのか、その価値の根拠は何か、という問いに対し、まだ文化・文明・宗教・思想の違いを超えて広く受け入れられる回答を持つに至っていない。哲学、法学、政治学、人類学等において、さまざまな議論がされてきたが、まだ世界的な定説はない。世界共通の認識を確立できていないのである。
私は、人間の尊厳という観念の背景には、キリスト教及びカントの哲学があると思う。近代西欧から世界に広がった人権の観念のもとにあるのは、ユダヤ=キリスト教の教義である。ユダヤ民族が生み出した宗教では、人間は神(ヤーウェ)が創造したものであると教える。神が偉大であるゆえに、神の被造物である人間は尊厳を持つ。しかも、人間は神の似姿として造られたとされる。人間は他の生物とは異なる存在であり、地上のすべてを支配すべきものとされる。
ユダヤ教から生まれたキリスト教は、ローマ帝国の国教となり、近代西洋文明の一要素となった。人間の尊厳という観念は、キリスト教の神学に、受け継がれてきた。教父アウグスティヌスやトマス・アクイナスは、著書に人間の尊厳という観念を表している。彼らの思想は、古いようでいて、決して過去の遺物ではない。21世紀の現代においても、カトリックを中心として、信心深いキリスト教徒に、基本的な世界観・価値観を与えているからである。そこでは、人間の理性は、キリスト教的な全知全能の神の英知を、不完全な形で分有したものとされる。この観念がキリスト教神学にとまるものであったなら、非キリスト教社会に広がることはなかっただろう。キリスト教を信じない者には、そもそも人間は神(ヤーウェ)の被造物という考えは認められない。私は、人間の尊厳という観念が非キリスト教社会に受け入れられるものとなったのは、カントの哲学によるところが大きいと考える。
私は先に、ロックの思想は17世紀以降、この21世紀まで、世界に甚大な影響を与えており、その重要性は、マルクスやニーチェやフロイトの比ではないと書いた。ロックの思想が世界に広まり、そのうえにカントの哲学が浸透している。象徴的に言えば、ロック=カント的な人間観が今日の世界に普及した人間観のもとにあると見ることができる。ロック=カント的な人間観とは、人間は、生まれながらに自由かつ平等であり、個人の意識とともに、理性に従って道徳的な実践を行う自律的な人格を持つ、という人間観である。
カントは、18世紀西欧の「啓蒙の世紀」を代表する哲学者であり、アメリカ独立戦争やフランス革命を同時代として生きた。西欧では、天動説から地動説への転回をきっかけに、中世的な世界観が大きく揺らいだ。カントは、科学と道徳の両立を図って、宗教の独自性を認め、科学的理性的な認識の範囲と限界を定めつつ、神・霊魂・来世という形而上的なものを志向する人間の人間性を肯定し、理性に従って道徳的な実践を行う自由で自律的な人格を持つ者としての人間の尊厳を説いた。
このようにカントは、人間の尊厳を伝統的なキリスト教の教義から離れて、近代的な哲学によって意味づけ直した。それによって、人間の尊厳という観念は、世俗化の進む西欧社会でも維持され、同時に非キリスト教社会にも伝播し得るものとなった。その観念は、今も世界に広まりつつある。
ところが、その一方、大元の欧米では、19世紀半ば、ダーウィンの進化論が登場し、人間は神が創造したものではなく、猿から進化したものだという理論が広まった。また、西洋とキリスト教の歴史と現状を考察したニーチェが、「神は死んだ」と言い、ニヒリズムの到来を予言した。こうして、キリスト教的な神の存在を疑ったり、否定したりする思想が社会に影響を及ぼすようになった。ここで、仮に神という超越的な観念を排除すれば、そこには、人間の尊厳という観念のみが残ることになる。
近代西欧には、科学技術の発達によって、人間は宇宙のすべてを知り、自然を支配することが可能だという考えが、早くから存在した。16世紀後半のフランシス・ベーコンに始まって、ホッブス、サン・シモン、コント等が主張してきた。18世紀以降、こうした科学万能の思想が影響力を強めていった。19世紀後半から20世紀へと進むに従って、欧米では人間の理性への過信や傲りが高じた。とりわけ二度にわたる世界大戦、そして核兵器の登場は、科学と理性について、深刻な反省を要する出来事だった。
だが、非キリスト教社会は、近代西洋文明が直面している根本問題を徹底的に議論することなく、人間の尊厳という観念を受け入れ、国連憲章や世界人権宣言に賛同・参加してきている。世界の大多数の国々が西欧における近代化の成果、すなわち科学技術や資本主義、主権国家や合理主義等を摂取するのと同時に、人権という観念を輸入したのである。そして、人間の尊厳という観念は、深く検討されることなく、21世紀においても時が経過し続けているのである。
次回に続く。










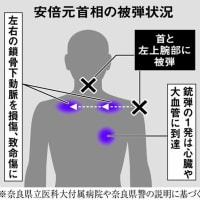









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます